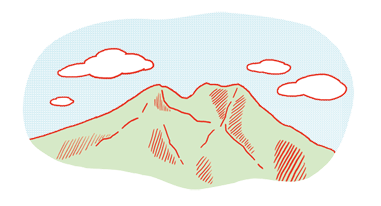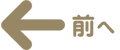2-2.通院治療に向けた準備と実際
2-2-1.治療が始まる前に ~医療者とのコミュニケーション~
![]() がんと診断されてから、すごく目まぐるしく毎日が過ぎていきましたが、「がん情報サービス」(「8-4.信頼できる情報源」参照)などの信頼できるウェブサイトの情報をじっくり読んで病気のことを学び、夫や担当医、医療スタッフの方たちとよく話して治療方針が決まったら、少し気持ちが落ち着いてきました。
がんと診断されてから、すごく目まぐるしく毎日が過ぎていきましたが、「がん情報サービス」(「8-4.信頼できる情報源」参照)などの信頼できるウェブサイトの情報をじっくり読んで病気のことを学び、夫や担当医、医療スタッフの方たちとよく話して治療方針が決まったら、少し気持ちが落ち着いてきました。
![]() 不安な気持ちはあっても、納得して治療方針を決められたのですね。
不安な気持ちはあっても、納得して治療方針を決められたのですね。
![]() はい、ただ、この先実際に治療が始まったら、自分の体や、毎日の生活がどんなふうになっていくのか、想像ができなくて……。診察のときには「ほかにお聞きになりたいことはありますか」と声をかけられるのですが、担当医の先生もお忙しそうで、あれこれ聞きすぎるのもよくないかなぁと。
はい、ただ、この先実際に治療が始まったら、自分の体や、毎日の生活がどんなふうになっていくのか、想像ができなくて……。診察のときには「ほかにお聞きになりたいことはありますか」と声をかけられるのですが、担当医の先生もお忙しそうで、あれこれ聞きすぎるのもよくないかなぁと。
![]() まだ担当医ともやりとりが始まったばかりなので、「聞きにくいな」「こんなこと聞いてもいいのかな」と思うことがあるかもしれませんね。けれど、T さんの病状や治療内容について最もよく知っているのは担当医です。聞きたいことや心配なことなどは、率直に伝えていくことで、徐々に信頼関係を築いて、やがてなんでも相談できる間柄になっていけると思いますよ。
まだ担当医ともやりとりが始まったばかりなので、「聞きにくいな」「こんなこと聞いてもいいのかな」と思うことがあるかもしれませんね。けれど、T さんの病状や治療内容について最もよく知っているのは担当医です。聞きたいことや心配なことなどは、率直に伝えていくことで、徐々に信頼関係を築いて、やがてなんでも相談できる間柄になっていけると思いますよ。
![]() 聞こう聞こうと思っていても、いざ診察室に入ると、頭から抜けてしまうこともあって……。
聞こう聞こうと思っていても、いざ診察室に入ると、頭から抜けてしまうこともあって……。
![]() 日頃から、不安なことや聞きたいこと、気になっていることをメモしておくと、聞き忘れを減らしたり、限られた診察時間のなかでも要領よく質問できるのでお勧めです。けれど、日頃書き溜めた疑問を1回の診察の間に全部尋ねるというのはやはり難しいので、なかでも絶対にこれは聞いておきたい、と思うものを2つ3つほど、診察前に絞っておくと、無理なく聞けると思います。
日頃から、不安なことや聞きたいこと、気になっていることをメモしておくと、聞き忘れを減らしたり、限られた診察時間のなかでも要領よく質問できるのでお勧めです。けれど、日頃書き溜めた疑問を1回の診察の間に全部尋ねるというのはやはり難しいので、なかでも絶対にこれは聞いておきたい、と思うものを2つ3つほど、診察前に絞っておくと、無理なく聞けると思います。
![]() なるほど、そうですね。優先順位をつければ自分のなかでも何が一番気になっているかの整理ができそうです。
なるほど、そうですね。優先順位をつければ自分のなかでも何が一番気になっているかの整理ができそうです。
![]() 特に通院での治療となると、入院と違っていつでも周囲に医療者がいるわけではないので、機会を逃さずに不安や疑問を解消したいですよね。診察には、ご主人や信頼できる人に付き添ってもらい、一緒に話を聞いてもらうと、聞き漏らしを減らしたり、医師の説明をあとで再確認したりするのにも役立ちます。信頼する人がそばにいてくれることで、精神的にも安心して、落ち着いて対話ができると思いますよ。また最近は、治療の方針や入院前の説明など、重要事項の説明や面談には、担当医に加えて看護師が同席できるようになっています。診察のあとに、看護師と、わからないことがないかとか、不安やつらさがないかなどのやりとりができることがあります。
特に通院での治療となると、入院と違っていつでも周囲に医療者がいるわけではないので、機会を逃さずに不安や疑問を解消したいですよね。診察には、ご主人や信頼できる人に付き添ってもらい、一緒に話を聞いてもらうと、聞き漏らしを減らしたり、医師の説明をあとで再確認したりするのにも役立ちます。信頼する人がそばにいてくれることで、精神的にも安心して、落ち着いて対話ができると思いますよ。また最近は、治療の方針や入院前の説明など、重要事項の説明や面談には、担当医に加えて看護師が同席できるようになっています。診察のあとに、看護師と、わからないことがないかとか、不安やつらさがないかなどのやりとりができることがあります。
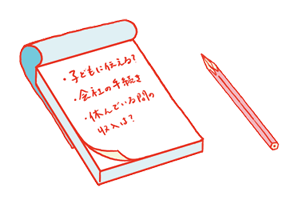
医療者との上手なコミュニケーションのコツ
- 心配ごとや、確認しておきたいことは、遠慮せずに率直に伝えましょう。
- 普通の人間関係と同じで、医療者とも一朝一夕に信頼関係を築くのは難しいものです。今後の療養のなかで、少しずつ良好な関係づくりをしていくつもりで、その日の体調や自分の希望、不安に思っていることなどを都度伝えていきましょう。
- 診察の際には、できるだけ家族や信頼できる人に付き添ってもらいましょう。聞きたいことをあらかじめメモして持っていくと、聞き漏らしを防ぐことができます。
- 医師に聞きにくいと思うことは、看護師に相談したり、「がん相談支援センター」などの相談窓口(第1章「1-3.在宅療養に関する、信頼できる情報源」参照)を活用することもできます。
2-2-2.治療が始まる前に ~家族とのコミュニケーション~
![]() そうですね……。ですが、病気がわかったときから、夫には何かと仕事を休んでサポートしてもらったりなど、これ以上迷惑はかけられないと思い、お願いするのをためらってしまって。子どもたちの世話も、これまでより夫に負担がかかっているので、できることは自分でなんとかしなくてはと……。
そうですね……。ですが、病気がわかったときから、夫には何かと仕事を休んでサポートしてもらったりなど、これ以上迷惑はかけられないと思い、お願いするのをためらってしまって。子どもたちの世話も、これまでより夫に負担がかかっているので、できることは自分でなんとかしなくてはと……。
![]() お気持ちはとてもよくわかります。でも、もしTさんが反対の立場だったら、「なんでも話してほしい」「こんなときこそ力になりたい」と思うのではないでしょうか。
お気持ちはとてもよくわかります。でも、もしTさんが反対の立場だったら、「なんでも話してほしい」「こんなときこそ力になりたい」と思うのではないでしょうか。
![]() 確かにそうです。
確かにそうです。
![]() これから治療が始まるにあたって、Tさんはもちろんご家族も、一時的とはいえ、これまでどおりのリズムやペースで生活することが難しくなる場面が出てくるはずです。こうしたとき、身近なご家族と情報を共有し、状況に合わせて臨機応変に対応していくためにも、家族や身近な人に頼ることを遠慮せずに、現在の状況や今後の見通し、自分の希望などを、少しずつでも伝え、話し合っていくことがとても大切になります。「迷惑をかけたくないから」「どうせ言っても変わらないから」などと思わずに、その時々で率直な気持ちや身体の状況、希望を伝えてみましょう。「言葉にすることで整理できることがある」「口に出すことで相手に伝わる」ということを、ぜひ心に留めておいてください。
これから治療が始まるにあたって、Tさんはもちろんご家族も、一時的とはいえ、これまでどおりのリズムやペースで生活することが難しくなる場面が出てくるはずです。こうしたとき、身近なご家族と情報を共有し、状況に合わせて臨機応変に対応していくためにも、家族や身近な人に頼ることを遠慮せずに、現在の状況や今後の見通し、自分の希望などを、少しずつでも伝え、話し合っていくことがとても大切になります。「迷惑をかけたくないから」「どうせ言っても変わらないから」などと思わずに、その時々で率直な気持ちや身体の状況、希望を伝えてみましょう。「言葉にすることで整理できることがある」「口に出すことで相手に伝わる」ということを、ぜひ心に留めておいてください。
2-2-3.子どもや離れて暮らす家族にどう伝えるか
![]() わかりました。実は、病気のことを、子どもたちや離れて暮らす両親には、まだ伝えていないのです。伝えるタイミングや、どのように伝えたらよいのかがわからなくて。
わかりました。実は、病気のことを、子どもたちや離れて暮らす両親には、まだ伝えていないのです。伝えるタイミングや、どのように伝えたらよいのかがわからなくて。
![]() ご家族間の関係性は、ご家庭により本当にさまざまなので、絶対にこうすべき、とは言えないのですが、基本的には時機をみて、なんらかのかたちで伝えるほうがよいと思います。
ご家族間の関係性は、ご家庭により本当にさまざまなので、絶対にこうすべき、とは言えないのですが、基本的には時機をみて、なんらかのかたちで伝えるほうがよいと思います。
![]() やはり、そうですよね。
やはり、そうですよね。
![]() 隠しておくことで、今後、さまざまな場面で取り繕ったり、嘘をついたりしなくてはならなくなると、何より Tさんご自身の負担になり、そのことで疲弊してしまうこともあります。本音を話せず、後ろめたい気持ちをもったままでいるのは重荷ですよね。それに、相手が Tさんの言動を不審に思ったり、別の人から真実が伝わってしまったりすると「どうしてもっと早く話してくれなかったの」「なぜ直接言ってくれなかったの」と責められたり、これまでの関係性に亀裂が生じてしまうこともあります。
隠しておくことで、今後、さまざまな場面で取り繕ったり、嘘をついたりしなくてはならなくなると、何より Tさんご自身の負担になり、そのことで疲弊してしまうこともあります。本音を話せず、後ろめたい気持ちをもったままでいるのは重荷ですよね。それに、相手が Tさんの言動を不審に思ったり、別の人から真実が伝わってしまったりすると「どうしてもっと早く話してくれなかったの」「なぜ直接言ってくれなかったの」と責められたり、これまでの関係性に亀裂が生じてしまうこともあります。
![]() 先ほどの話と同じですね。もし自分が反対の立場で、知らされなかったらどう思うか……。
先ほどの話と同じですね。もし自分が反対の立場で、知らされなかったらどう思うか……。
![]() そうですね。ですから、「伝えるか・伝えないか」ではなく、「どのように伝えるか」ということを考えたほうがよいかもしれません。「これからどう関わっていきたいか」ということでもよいですね。医学的な診断名や病状、治療の内容などを詳しく説明するというよりは、病気や治療に伴って生じる生活への影響や、その後の見通しなどを伝えるほうが、理解やサポートを得やすく、今後の生活に対する共通のイメージをもちやすくなるでしょう。
そうですね。ですから、「伝えるか・伝えないか」ではなく、「どのように伝えるか」ということを考えたほうがよいかもしれません。「これからどう関わっていきたいか」ということでもよいですね。医学的な診断名や病状、治療の内容などを詳しく説明するというよりは、病気や治療に伴って生じる生活への影響や、その後の見通しなどを伝えるほうが、理解やサポートを得やすく、今後の生活に対する共通のイメージをもちやすくなるでしょう。
![]() 自分が大切に思う人ほど、隠さずに伝えておいたほうがよいのかもしれないですね。
自分が大切に思う人ほど、隠さずに伝えておいたほうがよいのかもしれないですね。
![]() そうですね。反対に、普段から付き合いの少ない親戚や知人などに療養のことを伝えると、時に病気のことを根掘り葉掘り聞かれたり、療養に対する無理解な言葉を投げかけられることもあるかもしれません。理解してほしいと思う人には必要なことを丁寧に少しずつでも説明していくことが大切ですが、そうでない場合には、あえて伝えないということも、ご自分が疲弊しないためには大切かもしれません。
そうですね。反対に、普段から付き合いの少ない親戚や知人などに療養のことを伝えると、時に病気のことを根掘り葉掘り聞かれたり、療養に対する無理解な言葉を投げかけられることもあるかもしれません。理解してほしいと思う人には必要なことを丁寧に少しずつでも説明していくことが大切ですが、そうでない場合には、あえて伝えないということも、ご自分が疲弊しないためには大切かもしれません。
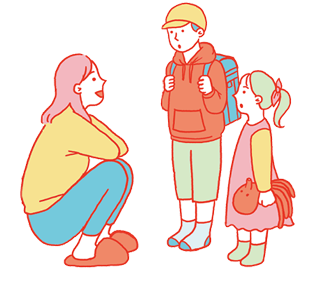
![]() わかりました。子どもにはどのように伝えたらよいのでしょうか。2人ともまだ幼く、病気のことをわかるとは思えません。
わかりました。子どもにはどのように伝えたらよいのでしょうか。2人ともまだ幼く、病気のことをわかるとは思えません。
![]() お子さんに伝えるときも、病気自体のことを詳しく伝えるというよりも、お子さんの日々の生活にどのような変化が起こるか、についてだけでも伝えておくと、お子さんの年齢なりの理解で、その後に起こることへの心の備えができます。話すのがつらかったり、難しく感じるときには、あらかじめ手紙にまとめてみたり、普段からお子さんとのコミュニケーションツールとして使用している手段――たとえば、親子交換日記や、年齢が少し大きければSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などでしょうか――があれば、そういったツールを使って伝えてもよいと思いますよ。
お子さんに伝えるときも、病気自体のことを詳しく伝えるというよりも、お子さんの日々の生活にどのような変化が起こるか、についてだけでも伝えておくと、お子さんの年齢なりの理解で、その後に起こることへの心の備えができます。話すのがつらかったり、難しく感じるときには、あらかじめ手紙にまとめてみたり、普段からお子さんとのコミュニケーションツールとして使用している手段――たとえば、親子交換日記や、年齢が少し大きければSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などでしょうか――があれば、そういったツールを使って伝えてもよいと思いますよ。
2-2-4.治療開始前に確認しておきたいこと
![]() いよいよ来週から治療が始まると思うと緊張します。治療が始まるまでにやっておくべきことで忘れていることがないか心配です。
いよいよ来週から治療が始まると思うと緊張します。治療が始まるまでにやっておくべきことで忘れていることがないか心配です。
![]() 治療に直接関連したことでは、事前に担当医をはじめ医療者から説明のあった内容をもう一度よく確認し、準備しておくように言われたことを見直しておきましょう。それ以外には、特別に何かをしておかねばならない、してはいけない、といったことはありませんから、体調を整えて日々を過ごしましょう。
治療に直接関連したことでは、事前に担当医をはじめ医療者から説明のあった内容をもう一度よく確認し、準備しておくように言われたことを見直しておきましょう。それ以外には、特別に何かをしておかねばならない、してはいけない、といったことはありませんから、体調を整えて日々を過ごしましょう。
![]() 医師には、はじめの診察のときに「たばこはやめておこうね」と言われました。子どもを授かってからはずっとやめていたのですが、1年くらい前から、仕事が忙しいときなどに1日数本だけ吸ってしまうことがあって……。今は完全にやめています。
医師には、はじめの診察のときに「たばこはやめておこうね」と言われました。子どもを授かってからはずっとやめていたのですが、1年くらい前から、仕事が忙しいときなどに1日数本だけ吸ってしまうことがあって……。今は完全にやめています。
![]() そうですね。喫煙習慣があると、術後肺炎などの合併症が起こりやすくなったり、薬物療法や放射線療法の効果が弱まってしまうことが知られていますので、禁煙を心がけるのはよい準備だと思います。ほかに心配なことはありますか?
そうですね。喫煙習慣があると、術後肺炎などの合併症が起こりやすくなったり、薬物療法や放射線療法の効果が弱まってしまうことが知られていますので、禁煙を心がけるのはよい準備だと思います。ほかに心配なことはありますか?
![]() そうですね、やはり通院で治療を受けるので、家にいるときに副作用が強く出たらどうしようとか、体調が悪くなったときはすぐに病院に連絡してもよいのか、それから、ひとまず職場には、様子をみながら働き続けたいと伝えていますが、仕事に穴を開けないか、夫や子どもたちに迷惑をかけないか……など、考えると心配なことはいろいろあります。
そうですね、やはり通院で治療を受けるので、家にいるときに副作用が強く出たらどうしようとか、体調が悪くなったときはすぐに病院に連絡してもよいのか、それから、ひとまず職場には、様子をみながら働き続けたいと伝えていますが、仕事に穴を開けないか、夫や子どもたちに迷惑をかけないか……など、考えると心配なことはいろいろあります。
![]() 今心配なことを書き出してみて、それに対してどんな備えができるか、どんな対応が必要か、という視点で確認してみると、漠然とした不安を軽減できる場合があります。また、今は心配でも、治療が進んでいく間に、大した問題ではなかったと思えることもありますから、今できることをできる範囲で備えておく、ということでよいと思います。
今心配なことを書き出してみて、それに対してどんな備えができるか、どんな対応が必要か、という視点で確認してみると、漠然とした不安を軽減できる場合があります。また、今は心配でも、治療が進んでいく間に、大した問題ではなかったと思えることもありますから、今できることをできる範囲で備えておく、ということでよいと思います。
![]() わかりました。治療が始まる前に、担当医から説明してもらった治療内容やその後の見通しを思い出しながら、もう一度家族でよく確認し合っておこうと思います。
わかりました。治療が始まる前に、担当医から説明してもらった治療内容やその後の見通しを思い出しながら、もう一度家族でよく確認し合っておこうと思います。
![]() 一人で抱え込まず、周りに頼りながら進めていくので大丈夫ですよ。それから、通院治療に向けた心配ごととその対応策としては、次のようなことが参考になるかもしれません(下記参照)。
一人で抱え込まず、周りに頼りながら進めていくので大丈夫ですよ。それから、通院治療に向けた心配ごととその対応策としては、次のようなことが参考になるかもしれません(下記参照)。
通院治療に向けた準備と対策
1 医療費や生活費についての心配がある
院内に常駐する医療ソーシャルワーカー(社会福祉の専門家)に相談ができます。また、自身で加入している民間のがん保険などがあれば、給付対象や必要な手続きについて忘れずに確認してみましょう。第3章「3-5.経済的な側面への支援制度」参照
2 家庭内での役割を担えなくなる心配がある
通院治療であっても、体調が優れない日などには、今まで担っていた家事や役割が行えないこともあります。実際に治療が始まってみないとわからない部分もありますが、事前に想定できる範囲で、家族で分担するのか、親やきょうだいなどにサポートを頼むのか、外部のサービスなどを利用するのか、など家族や親しい人の間で相談しておくとよいでしょう。第3章3-4-2.参照
3 職場での役割を担えなくなる心配がある
治療を受けながら仕事を続けている方が増えています。しかし、職場に伝えずに治療を開始してしまうと、後々のトラブルや予定外の状況が生じた際に対応が難しくなります。職場のしかるべき立場の人に病状や今後の見通しを伝え、理解と協力を得ておくことが大切です。第3章「3-2.職場への伝え方とコミュニケーション」参照
4 自宅での生活に手助け(介護)が必要になる可能性がある
65歳以上の人、または 40~64歳で医師ががんと診断し病状の基準を満たした人では、介護保険制度による訪問介護などを利用することができます。利用にはお住まいの市区町村への申請と審査・認定が必要になるため、早めに情報収集や手続きを開始しておきましょう。第4章4-2-2.参照
5 治療や副作用・後遺症についての心配がある
受ける治療の内容や目的、起こる可能性のある副作用や後遺症について、担当医や看護師、薬剤師などに十分確認し、納得して治療に臨むことが大切です。また、「がん情報サービス」などのウェブサイトで情報を集めたり、患者会・患者支援団体、ピアサポートなど、がんの経験者のアドバイスが参考になることもあります。第2章「2-3.通院での治療と副作用・後遺症への対応」、「8-4.信頼できる情報源」参照
 告知からの心の変化 そして検査と治療へ(2)
告知からの心の変化 そして検査と治療へ(2)
((1) より続き)
前立腺がんと診断されて検査から治療へ。点滴や尿道への管( これがまたまた痛い!!)、オムツ、転倒落下センサー、食事はお粥、ベッドサイドには簡易トイレ。起きることさえ無理な状態になっていました。
初めての入院。一人になるとさまざまなことが頭を巡り、死への不安と恐怖、転移による骨折で痛くて起き上がることもできず、手足も自由に動かず、情けなくて涙は止まりませんでした。
明け方になり、空が白んで明るくなった病棟の窓から、うっすらと見え出した右田ケ岳を眺めながら、なぜか心のなかでは力が湧いてきて、「こんなことで、がんなんかでこのまま泣きながら死ねない」と思いだしました。リングに向かう老いたボクサーのような気持ちが沸々と湧いてきました。
それからは、まるでサーキットトレーニングのように多くの検査を受け、なかでも骨髄採取や前立腺生検は痛く、歯を喰いしばり耐えました。数々の検査を経て、冷静で穏やかな笑顔の医師から「前立腺がんでステージは4です。直ちに薬物療法(ホルモン療法) に入りましょう」との提案でした。入院は2週間、職場復帰し通院という長い戦いの始まり。私は負けません。「BEAT CANCER(がんを克服するぞ) !」