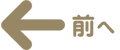2-8.がんのリハビリテーション
がんの療養においては、さまざまな場面でリハビリテーション(リハビリ)も行われます。「がんのリハビリ」と聞いても、すぐにはピンとこないかもしれませんが、がん療養におけるリハビリは、がんと診断されたあとの早い時期、場合によっては治療が始まる前から行われます。
![]() リハビリというと、脳卒中や事故などで体になんらかの障害を負った人が、リハビリ室などで専任のスタッフの方と一緒に行うようなイメージがあるのですが……。がんのリハビリとは、それらとは違うものなのですか?
リハビリというと、脳卒中や事故などで体になんらかの障害を負った人が、リハビリ室などで専任のスタッフの方と一緒に行うようなイメージがあるのですが……。がんのリハビリとは、それらとは違うものなのですか?
![]() がんのリハビリは、がんそのものや、がん治療で生じる体への影響を最小限にして、治療後の回復をスムーズにしたり、残っている体の機能を維持・向上させたりするために行われるはたらきかけのことです。たとえば Tさんが前に、「手術後はなるべく早く体を動かしたほうがよいのですよね?」とおっしゃっていましたね。これも、治療によって生じたダメージから早期に回復を図るために行われるもので、リハビリの一環です。
がんのリハビリは、がんそのものや、がん治療で生じる体への影響を最小限にして、治療後の回復をスムーズにしたり、残っている体の機能を維持・向上させたりするために行われるはたらきかけのことです。たとえば Tさんが前に、「手術後はなるべく早く体を動かしたほうがよいのですよね?」とおっしゃっていましたね。これも、治療によって生じたダメージから早期に回復を図るために行われるもので、リハビリの一環です。
![]() では、手術の前に、体力を落とさないように軽い運動を……というのも、リハビリということですか?
では、手術の前に、体力を落とさないように軽い運動を……というのも、リハビリということですか?
![]() そうです。術後の合併症などを減らすために行われる「予防的リハビリテーション」に当たります。
そうです。術後の合併症などを減らすために行われる「予防的リハビリテーション」に当たります。
![]() そうだったのですね。
そうだったのですね。
![]() がんのリハビリは、下表のように、必要に応じてがんの治療開始前から始まり、治療中はもちろん、積極的な治療を終えたあとを含めて、あらゆる状況に応じて、治療や療養と並行して行われます。
がんのリハビリは、下表のように、必要に応じてがんの治療開始前から始まり、治療中はもちろん、積極的な治療を終えたあとを含めて、あらゆる状況に応じて、治療や療養と並行して行われます。
がんのリハビリテーション 病期別の目的
| 病期 | リハビリテーションの分類 | リハビリテーションの目的 |
| がん発見~ | 予防的 リハビリテーション |
身体機能の障害を予防する目的で、がんの診断後の早期(治療開始の前)から始めるリハビリテーション |
| 治療開始~ | 回復的 リハビリテーション |
病気や治療によって生じた身体機能や日常生活に必要な動作の障害に対し、最大限の機能回復を図ることを目的に行われるリハビリテーション |
| 再発や転移の発見~ | 維持的 リハビリテーション |
がんが増大し、機能障害が進行しつつある場合に、身体機能や日常生活に必要な動作の維持・改善を目的として行われるリハビリテーション |
| 積極的治療後~ | 緩和的 リハビリテーション |
緩和ケアが主体となる時期に、ご本人の希望や要望を尊重しながら、身体的・精神的・社会的に質の高い生活が送れるようにすることを目的に行われるリハビリテーション |
![]() がんのリハビリは、基本的には自分一人で行うものなのですか?
がんのリハビリは、基本的には自分一人で行うものなのですか?
![]() いいえ、そうとは限りません。ほかの領域のリハビリと同じように、リハビリ科医や専門のスタッフ(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など)、看護師などが関わって、その患者さんに必要なリハビリをともに検討し、計画を立てて機能の改善や回復の促進を図っていくこともあります。
いいえ、そうとは限りません。ほかの領域のリハビリと同じように、リハビリ科医や専門のスタッフ(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など)、看護師などが関わって、その患者さんに必要なリハビリをともに検討し、計画を立てて機能の改善や回復の促進を図っていくこともあります。
![]() 回復をさまざまなかたちでサポートしてくれる人がいるのは心強いですね。
回復をさまざまなかたちでサポートしてくれる人がいるのは心強いですね。
![]() Tさんの場合は、乳がん術後に起こりやすい上腕の筋力低下や動かしにくさ、あるいはリンパ浮腫の予防を目的として、治療後のリハビリ(運動療法など)が計画されるかもしれません。具体的にどんなことをするかなど、気になる点があれば、担当医や看護師に尋ねてみましょう。そのほかにも、ご自宅で自分でできるリハビリはないか、などを確認してみるとよいかもしれませんね。
Tさんの場合は、乳がん術後に起こりやすい上腕の筋力低下や動かしにくさ、あるいはリンパ浮腫の予防を目的として、治療後のリハビリ(運動療法など)が計画されるかもしれません。具体的にどんなことをするかなど、気になる点があれば、担当医や看護師に尋ねてみましょう。そのほかにも、ご自宅で自分でできるリハビリはないか、などを確認してみるとよいかもしれませんね。
![]() なるほど、わかりました。
なるほど、わかりました。

がんのリハビリテーション医療の対象となるおもな症状や障害
がんそのものによるもの
- 骨への転移による痛みや骨折
- がんが中枢神経を圧迫したりすることで現れる麻痺や言語障害、嚥下障害、排尿・排便機能の障害
- がんが末梢神経を巻き込んだりすることで現れるしびれや筋力の低下
- がんが体内の栄養を奪ってしまうことによる身体の衰弱(悪液質)
手術療法によるもの
- 胸やお腹のがん手術後に起こる肺炎
- 乳がんや子宮がん手術後のリンパ浮腫、関節機能の障害など
- 頭部や首周囲の手術による嚥下障害や発声障害
- 骨盤周囲のがん手術後の排尿・排便機能の障害
- 四肢(腕や脚)の手術によって生じる動作機能の障害
薬物療法や放射線療法によるもの
- だるさ・倦怠感
- しびれや筋力・体力の低下
通院で治療を始めるうえで、参考になる情報があったでしょうか?
Tさんはその後、実家のご両親に病気のこと、これからの治療のこと、今後の予定などについて話し、協力を仰ぎました。抗がん剤治療が始まるタイミングで、Tさんのお母さんが家に来てくれることになり、家族の食事や家事全般、子どもの面倒をサポートしてくれることになりました。妹さんやママ友さんも、買い物や子どもの送迎などに協力してくれるそうです。 Tさん自身は、早速ご主人にアピアランスケアセンターのことを話し、一緒に相談に出かけました。脱毛に備えてさまざまなアドバイスを受け、自分らしさを大切にしながら、治療に臨む準備が整いました。
新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどの流行が長引いているときに通院や療養生活を継続することがあるかもしれません。在宅療養を続けていくにあたって、以下に留意点をまとめました。
感染対策について
一般的な対策を守りましょう。マスクの着用、こまめな手洗いや手指消毒、3密(密集・密接・密閉)の回避、咳エチケットを守る、なるべく手を顔に触れないようにする、などです。患者さん本人だけでなく、ご家族や親しい周囲の人も十分な対策を心がけましょう。
発熱などの症状に備えて
発熱や咳、呼吸が苦しいなど、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどを疑う症状がみられたときの対応や連絡先について、あらかじめ医療機関に確認しておきましょう。家族や親しい人に体調不良がみられたときの対応についても併せて確認しておきましょう。
流行期の治療
一般的には、流行の状況にかかわらず、必要性が高いと判断されるがん治療は予定どおりに行うことが勧められます。自己判断で受診を控えず、必要な治療を適切なタイミングで受けられるよう、担当医や医療機関と相談しましょう。
受診日に発熱などの症状がある場合には、直接受診しないで、あらかじめ医療機関に連絡し、受診してよいかどうか、また受診方法などについて相談しましょう。
ワクチンの接種
がん治療中や経過観察中の方も、感染症対策のためにワクチンを接種することには安全上の問題はなく、多くの場合特に問題なく接種が可能です。ただし、接種に伴う副反応が、がん治療のスケジュールなどに影響を及ぼすこともあるので、接種のタイミングについては担当医と相談するのがよいでしょう。
信頼できる情報源
感染症に関する情勢は日々変化しています。信頼できる情報源の情報を参照しましょう。
日本臨床腫瘍学会:新型コロナウイルス感染症関連情報(一般の方向け)
https://www.jsmo.or.jp/general/coronavirus-information/ ![]()
厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html ![]()