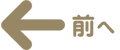第6章 人生の最期をともに生きる
この章では、在宅で人生の最期のときを過ごすご本人に寄り添いながら生活を送るときの心構えや、関わるスタッフとの対話のコツについてまとめています。ご家族や支える方が疲弊することなく穏やかに過ごすためには、ご本人の希望や想いを大切にしながら、どのような不安や心配ごとでもなるべく共有しておくことが重要です。
しっかりと緩和ケアを受けることで痛みや不安のない生活を維持することができます。介助やケアについても専門のスタッフの助けやアドバイスを受けながら、無理のない範囲で家族が行うこともできます。
- 最期まで“自分らしく”過ごせるように、ご本人とご家族の希望や願いを共有することが大切です。
- 無理のない範囲で、ご家族が日常的なケアや介助を行うことができます。
- ご本人にとってもご家族にとっても、心のケアが大切な時期です。心身ともに疲れたり、ストレスが溜まってつらくなりすぎたりしないように、周囲に相談したり、気持ちを聞いてもらう機会をつくるようにしましょう。
6-1.身体的な変化に寄り添う
第4章で、在宅支援チームのサポートを受けながら在宅療養を始めることに決めた「Sさん」とご家族は、さまざまな不安を抱きつつも、相談員「Nさん」の助言を得ながら在宅での療養をスタートさせ、しばらくが経ちました。引き続きSさんご家族とNさんとのやりとりから、在宅療養の実際をみていきましょう。
6-1-1.今後起こりうる変化について確認しておきましょう
![]() 夫が家で過ごしていることに慣れてはきましたが、私や娘は、これまでと違う生活に少し気疲れを感じることもあります。なるべく夫の希望に沿うかたちで自宅での時間を過ごしてもらえればと思ってはいますが、私たち家族はどんなことを心がけていけばよいのでしょう。
夫が家で過ごしていることに慣れてはきましたが、私や娘は、これまでと違う生活に少し気疲れを感じることもあります。なるべく夫の希望に沿うかたちで自宅での時間を過ごしてもらえればと思ってはいますが、私たち家族はどんなことを心がけていけばよいのでしょう。
![]() そうですね。以前にもお伝えしたように、一番大切にしたいのはご本人の想いです。人生の質・生活の質(クオリティ・オブ・ライフ:QOL)という言葉がありますが、QOLのなかには、自分の意向が周囲に尊重されていることや、できることは自分でできる、自分で決められるという「自立・自律」が保たれていることも含まれます。周囲が何もかもやってあげるよりも、時間がかかっても自身でやり遂げるのを見守ったり、ほんの少し手助けしたりして達成感をサポートするように心がけるのもよいかもしれませんね。
そうですね。以前にもお伝えしたように、一番大切にしたいのはご本人の想いです。人生の質・生活の質(クオリティ・オブ・ライフ:QOL)という言葉がありますが、QOLのなかには、自分の意向が周囲に尊重されていることや、できることは自分でできる、自分で決められるという「自立・自律」が保たれていることも含まれます。周囲が何もかもやってあげるよりも、時間がかかっても自身でやり遂げるのを見守ったり、ほんの少し手助けしたりして達成感をサポートするように心がけるのもよいかもしれませんね。
![]() なんでもやってあげようとしすぎるのもよくないのですね。
なんでもやってあげようとしすぎるのもよくないのですね。
![]() ご家族のQOLも大切なポイントです。支える方も、疲弊しないで介護を続けられるように、必要に応じて在宅支援チームの力を取り入れ、活用しながら態勢を整えていくことも大切ですね。
ご家族のQOLも大切なポイントです。支える方も、疲弊しないで介護を続けられるように、必要に応じて在宅支援チームの力を取り入れ、活用しながら態勢を整えていくことも大切ですね。
![]() 今の夫は、外見からは健康な人のように見えます。昨日は部屋の片付けを手伝ってくれました。数か月後に最期を迎えるかもしれないなんて、信じられない思いです。
今の夫は、外見からは健康な人のように見えます。昨日は部屋の片付けを手伝ってくれました。数か月後に最期を迎えるかもしれないなんて、信じられない思いです。
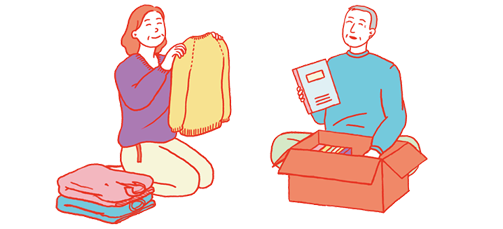
![]() そうですね。今のご様子からは信じられないかもしれませんね。ただ、痛みが増す、食事ができなくなる、立ち上がるときに介助が必要になるなどの身体的な変化が急激に訪れる患者さんは少なくありません。また、身体が弱っていくのに伴って、ご自分の意思を明確に伝えることが困難になっていくこともあります。
そうですね。今のご様子からは信じられないかもしれませんね。ただ、痛みが増す、食事ができなくなる、立ち上がるときに介助が必要になるなどの身体的な変化が急激に訪れる患者さんは少なくありません。また、身体が弱っていくのに伴って、ご自分の意思を明確に伝えることが困難になっていくこともあります。
![]() ……想像するだけで、どうにかなりそうです。でも今から私がグラついていては駄目ですね。
……想像するだけで、どうにかなりそうです。でも今から私がグラついていては駄目ですね。
![]() お気持ちが揺れるのは無理もありません。ご家族は、ご本人を介護する立場ではありますが、大切な人を近い将来に失ってしまう立場でもあります。悲しみや葛藤、不安でいっぱいになるのは当然です。また、今の時代、介護の経験は初めて、という方がほとんどです。介助の必要な場面が徐々に増えていくと思いますが、Sさんご本人の心身の状態について、不安な点や疑問点は訪問看護師やケアマネジャーに伝え、ご家族の負担が重くなりすぎないようにサービスの内容を手厚くしていくことなども相談していくのがよいと思います。
お気持ちが揺れるのは無理もありません。ご家族は、ご本人を介護する立場ではありますが、大切な人を近い将来に失ってしまう立場でもあります。悲しみや葛藤、不安でいっぱいになるのは当然です。また、今の時代、介護の経験は初めて、という方がほとんどです。介助の必要な場面が徐々に増えていくと思いますが、Sさんご本人の心身の状態について、不安な点や疑問点は訪問看護師やケアマネジャーに伝え、ご家族の負担が重くなりすぎないようにサービスの内容を手厚くしていくことなども相談していくのがよいと思います。
![]() はい……。
はい……。
![]() また、今後どのような症状が生じる可能性があるか、急に容態が変化したときの対処法や連絡先についても確認しておくことが大切です。なるべく早い段階で確認しておけば、いざというときの安心につながるはずです。在宅支援チームは、患者さんだけでなく、ご家族の心と体も心配しています。不安な気持ちを伝え、遠慮なく相談してみてください。
また、今後どのような症状が生じる可能性があるか、急に容態が変化したときの対処法や連絡先についても確認しておくことが大切です。なるべく早い段階で確認しておけば、いざというときの安心につながるはずです。在宅支援チームは、患者さんだけでなく、ご家族の心と体も心配しています。不安な気持ちを伝え、遠慮なく相談してみてください。
6-1-2.本人の意思を大切に、過ごし方を考えましょう
![]() 夫は、苦痛をできる限り減らしてほしい、延命のための治療は一切受けたくないと言っています。私たち家族もその意思を尊重したいと思っていますが、本人や家族の希望はどこまで聞いてもらえるものなのでしょう?
夫は、苦痛をできる限り減らしてほしい、延命のための治療は一切受けたくないと言っています。私たち家族もその意思を尊重したいと思っていますが、本人や家族の希望はどこまで聞いてもらえるものなのでしょう?
![]() 在宅支援チームは、ご本人とご家族の希望を最大限尊重した医療やケアを提供することを大事にしています。そのためにも、治療の方針について具体的なご希望がある場合には、あらかじめご本人、ご家族と在宅支援チームとでよく話し合っておくことが大切です。急変したときの対応方針や、胃ろう(手術で腹部に小さな孔を開けチューブを通し、直接胃に栄養を注入する医療処置)や点滴などの具体的な医療処置について、もしかしたらご本人が文書にまとめられているかもしれませんね。そんな意向も聞きながら、みんなで話し合えるとよいですね。
在宅支援チームは、ご本人とご家族の希望を最大限尊重した医療やケアを提供することを大事にしています。そのためにも、治療の方針について具体的なご希望がある場合には、あらかじめご本人、ご家族と在宅支援チームとでよく話し合っておくことが大切です。急変したときの対応方針や、胃ろう(手術で腹部に小さな孔を開けチューブを通し、直接胃に栄養を注入する医療処置)や点滴などの具体的な医療処置について、もしかしたらご本人が文書にまとめられているかもしれませんね。そんな意向も聞きながら、みんなで話し合えるとよいですね。
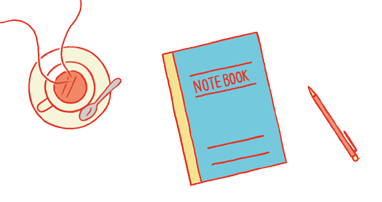
![]() 確かに、夫は何かノートのようなものによく書き物をしているので、自分の希望などもまとめているかもしれません。
確かに、夫は何かノートのようなものによく書き物をしているので、自分の希望などもまとめているかもしれません。
![]() ご本人のお気持ちや意思を大切にしていきたいですね。ただ、今後病状が進行していくなかで、ご本人やご家族の考え方も揺れ動くかもしれません。こうしたときには、その時々で話し合いをもてるようにしておくとよいでしょう。考えが変わっていくのは悪いことでも、いけないことでもなく、自然なことです。ただ、ご本人が明確な意思を示すことができなくなったときには、話し合いをもつことは難しいですから、そのときにはどうするかも事前に考えておきましょう。
ご本人のお気持ちや意思を大切にしていきたいですね。ただ、今後病状が進行していくなかで、ご本人やご家族の考え方も揺れ動くかもしれません。こうしたときには、その時々で話し合いをもてるようにしておくとよいでしょう。考えが変わっていくのは悪いことでも、いけないことでもなく、自然なことです。ただ、ご本人が明確な意思を示すことができなくなったときには、話し合いをもつことは難しいですから、そのときにはどうするかも事前に考えておきましょう。
![]() キーパーソン(第4章4-1-2.参照)である私がしっかりせねばなりませんね。
キーパーソン(第4章4-1-2.参照)である私がしっかりせねばなりませんね。
![]() ご本人がそれまで大事にされてきたことや、ご本人だったらどうしていただろうかという視点で、その都度、ご家族と在宅支援チームで医療やケアの方針を決めていきたいですね。事前にご本人とご家族が話し合った内容は、ご本人の意思を尊重したケアを最期まで行うのにきっと役に立ちます(第1章1-2-2.参照)。
ご本人がそれまで大事にされてきたことや、ご本人だったらどうしていただろうかという視点で、その都度、ご家族と在宅支援チームで医療やケアの方針を決めていきたいですね。事前にご本人とご家族が話し合った内容は、ご本人の意思を尊重したケアを最期まで行うのにきっと役に立ちます(第1章1-2-2.参照)。
![]() はい。夫はあまり口数の多いほうではないので、今のうちから私のほうで意識して声をかけていきたいと思います。
はい。夫はあまり口数の多いほうではないので、今のうちから私のほうで意識して声をかけていきたいと思います。
![]() そうですね。身体的な変化に伴って、周囲に反応する力も低下していくことが多いので、ご本人が意思をしっかり伝えられるうちに、これからの日々の過ごし方を話し合っておきたいですね。
そうですね。身体的な変化に伴って、周囲に反応する力も低下していくことが多いので、ご本人が意思をしっかり伝えられるうちに、これからの日々の過ごし方を話し合っておきたいですね。
![]() わかりました。
わかりました。
![]() 「こうしてほしい」という意思や希望をはっきりとおっしゃらない方もいます。その場合、「これだけはやめてほしい」「やってほしくない」ということを確認したり、書き留めておいて一緒に確認しておくのもよいと思います。
「こうしてほしい」という意思や希望をはっきりとおっしゃらない方もいます。その場合、「これだけはやめてほしい」「やってほしくない」ということを確認したり、書き留めておいて一緒に確認しておくのもよいと思います。
在宅での療養に限らず、人生の残り少ない日々のケアでは、ご本人が最後まで“自分らしく”過ごせることが理想です。症状が進行したり、また痛みやつらさが強くなったりしたときは、その影響で明確な意思表示が難しくなります。そのような状況でも、事前にご本人や在宅支援チームと話し合っておくことで、ご本人の希望を可能な限り反映させることができるかもしれません。
また、症状が進行すると、食事や排泄、体を動かすときなど、日常のさまざまな場面で介助が必要になることが増えていきます。精神的な側面も含めて、ご家族の負担も徐々に増していくことが多くなりますが、在宅支援チームの力を借りて無理をしすぎないようにしましょう。