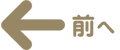1-2.ご本人とご家族の心構え
ここまで見てきたように、「在宅療養」にはさまざまなかたちがあります。患者さん本人・ご家族の状況や生活スタイルに合った在宅療養がよりよいものになるよう、まずはご本人とご家族の心構えについて、一緒に考えてみましょう。
1-2-1.これまでのこと、これからのことをともに考える
在宅療養を始めるにあたっては、考えたり、決めたりしなければならないことがたくさんあり、何から手をつけてよいのか混乱したり、不安になってしまうことがあると思います。
その混乱や不安の背景には、「今後の生活がうまくイメージできない」ことが大きく影響している場合があります。生活していくうえで、「これまで」と比べて「これから」どのような変化が起こるのか、あらかじめ担当医や看護師などのほかに、がん相談支援センターの相談員や、同じがんの経験者などから話を聞いたり、病院や地域で行われている「がんサロン」などに参加するなど、「これから」に役立つ情報を積極的に集め、患者さん本人・ご家族でその情報を共有し、ある程度の「今後の見通し」を立てておくことが、在宅療養を始めるうえでの大切な準備になります。
生活にどのような変化が起こるかは、がんの種類や治療内容などによって異なりますが、たとえば次のようなことがあるかもしれません。
「これまで」との生活の変化(例)
- 定期的な通院や検査・治療が必要になる(時間の確保が必要になる)
- 継続的な薬の服用・注射・点滴が必要になる/副作用への対策が必要になる
- 病気による症状や、治療に伴う後遺症・合併症への対応が必要になる
- 体調が優れない日があったり、これまでのようには無理がきかないことがある
- 急な体調変化が起こりうる
- 病気の進行や再発に対する不安や心理的なストレスを抱える
- 家族や地域内での役割分担に変更が必要になる場合がある
- 仕事の内容や就労・就学環境の調整が必要になることがある
こうした生活上の変化は、ご自身の工夫や、公的な支援制度の利用、家族や周囲の人、医療者などからのサポートによって解消・軽減できることもあります。一方で、受け入れていかざるを得ない変化もありますが、在宅療養生活を、想定できる範囲でイメージしておくこと、イメージしたうえで、心配な事柄に対してあらかじめ打てる対策や手立てを考えたり、関係する人に相談しておくことで、少しずつ不安や混乱が解消され、新しい生活のかたちがみえてくるでしょう。
なお、これらすべてのことを患者さんご本人やご家族だけで抱え込もうとすると、とてもつらくなってしまうことがあります。ご本人・ご家族だけでなく、周囲の信頼できる人や医療者との間で状況や情報を共有することで、困難や不安に対し、ともに悩み考え、解決していくことができます。周囲に伝えることや頼ることに対して遠慮しすぎずに、頼れるものには時に頼って、あなたらしい、そのご家庭らしい新しい日常生活を少しずつ築いていきましょう。
1-2-2.アドバンス・ケア・プランニングとは?
「アドバンス・ケア・プランニング」(advance care planning:ACP)という言葉を聞いたことがあるでしょうか。目の前の「これから」のことを考える延長として、さらにその先の「人生の最終段階」が訪れたときに、どのように過ごしたいか、何を大切にして生きたいかについて、患者さん本人・ご家族(親しい人や友人なども含みます)・医療者(介護従事者も含みます)の間で話し合いを重ねる過程(プロセス)のことを言います。
当たり前のことですが、がんという病気の有無にかかわらず、命あるものには必ず「最期のとき」が訪れます。しかし、考えてみると、いつ、どんな状況で「そのとき」が訪れ、「どのようにしたいのか」を事前に想定しておくことは、自分のこととはいえ、大変難しいものです。また、ご家族にとっても、たとえば急にご本人の体調が変化したときや、十分な意思疎通ができなくなったときなどに、ご本人が何を望んでいるのかがわからないままに代理で意思決定をしなければならない場面が生じ、大きな苦悩を抱えることがあります。ご本人やご家族の意思決定に基づいて治療やケアを行う医療者にとっても、時に葛藤が生じます。
こうしたことから、現在の病状や今後予想される病気の経過を関係者が共有し、今だけでなく将来的な治療・ケアの目標や方向性について、折に触れて話し合っておくこと(ACP)の重要性が注目されるようになってきました。

厚生労働省では ACPを「人生会議」と呼ぶことも提案しています。「会議」と聞くと堅苦しく感じられるかもしれませんが、 ACPや人生会議に「正解」はありません。何度繰り返してもいいし、なんらかの明確な結論を出す必要もありません。「最期のとき」を想像することは誰にとっても難しいもので、気持ちが揺れたり、途中で意見が変わったりするのはごく当たり前のことです。だからこそ、具体的な結論を出すことよりも、何度も繰り返し、お互いの気持ちを寄せて話し合い、どんなことを大切にしたいのか、どんなことがうれしいか・嫌いなのか、などの価値観や考え方をご本人・ご家族・医療者で共有しておくことが大切です。
何度も話し合うことで、ご本人もご家族も、人生において大切にしたいことがより明確になったり、限られた貴重な時間をどう過ごしたいかを考えたりする機会になります。ご家族や医療者にとっては、仮にご本人が意思決定することが難しい状況になったときでも、ご本人の価値観を尊重し、「本人ならきっとこう考えるだろう」と納得して医療・ケアの継続や差し控えを含めて今後の方針を考えることができ、最期のときを穏やかに受けとめやすくなります。
「人生の最期」なんて考えたくない、という方もいるでしょう。しかし、誰もが「限られた生」を生きるなかで、病気や治療に対する思いや、どう過ごしていきたいかなどについて、日頃から話せる範囲で家族間で話したり、伝え合ったりすることを、ぜひ大切にしましょう。こうした対話をしておくことは、「これから」を生きるうえで、ご本人とご家族の安心や希望につながっていきます。
1-2-3.ご本人とご家族のコミュニケーションのコツ
(ご家族へ)ご本人の希望を知るためのコミュニケーション法
前述のとおり、今後の療養の方針を決めるためには、当然のことですが、ご本人の気持ちを知ることが何よりも大切です。ご本人の思いや希望を共有することは、在宅療養の基本的な方針や方法を決定していくうえで、なくてはならないものです。とはいえ、気恥ずかしさや照れが先に立ち、改まって率直な対話をするのが難しいこともあるかもしれません。
患者さんによっては、自らあれこれと今後の計画を練ったり、関心のある情報を集め、積極的にこれからのライフプランを考える方もいますが、一方で、考えがまとまらなかったり、考えをもっていても言葉にしてうまく伝えられなかったりすることもあります。こうした場合でも、在宅を療養の場として選んだ背景には、「家族や大切な人(親しい人)とできるだけ一緒にいる時間をもちたい」とか、「自宅のお気に入りの場所でゆっくり過ごしたい」、「早く職場に復帰したい」、「子どもたちに食事を作ってあげたい」など、在宅での療養生活で一番大切にしたいことを、漠然とでももっているはずです。
家族としてともに経験してきた過去の苦労話や思い出話などをしながら、そうした思いを少しずつ引き出し、何を大切にしていきたいのかを共有できるとよいでしょう。また、具体的なコミュニケーションのとり方として、以下のいくつかの項目が参考になるかもしれません。
(ご家族や支援者の方へ)効果的なコミュニケーションのために
- 会話を始めるときは、話の切り出し方を工夫してみましょう。たとえば、患者さんご本人が自分から話したいと思われる話題を、先に質問してみるのもよいかもしれません。
- ご本人の話していることが、たとえご家族の考えと違っていても、まずはしっかり耳を傾けましょう。
- 聞いたふり、わかったふりはしないで、わからないことはしっかりと聞き返しましょう。
- ご本人の話を受けとめたうえで、ご家族の認識や気持ちも伝えてみましょう。ただ、大切なことは、ご家族の考えをご本人に知ってもらうことです。無理に説得したり、同意を強要したりしないようにしましょう。
- ご本人が何を一番伝えたいかを知るために、話している内容だけでなく、声の調子、身振り、言葉そのものについても注意を払いましょう。
- ご本人が話しているときには、言葉の一つひとつに反応するのではなく、なるべく冷静に聞くようにしましょう。
- ご本人が話したことを復唱し、話を理解したことを示しましょう。ご本人も安心するはずです。
ご本人の話に注意深く耳を傾け、また表情やちょっとしたしぐさをよく観察することによって、本当に伝えたいことを見いだせる場合もあります。このとき、ご家族が会話をリードするのではなく、ご本人が話したい話題を、ありのままに受けとめる姿勢を大切にしたいですね。
答えにくいことを聞かれたときには…
たとえば対話のなかで「私、いつまで体が自由に動くんだろう」など、まだ先の話と思えるようなことや、答えに困ることを聞かれたときにも、「そんな話しないでよ」とか、「そんな弱気なこと言わないで」などと否定したり言葉を遮ったりせずに、「どうしてそう思うの」と尋ね、静かにご本人の言葉に耳を傾けるのがよいと思います。「今の時点では、将来何が起こるか、私にもわからない」と正直に伝えたり、「今度、診察のときに一緒に聞いてみよう」と提案してみるのもよいかもしれません。ご本人の不安な気持ちに寄り添いながら、時につらい感情も共有し、不安を分かち合っていくような姿勢でやりとりができるとよいですね。
言葉をかけにくいときには…
何か言葉をかけたくても、思いをうまく言葉にできなかったり、なんと声をかけてよいのかわからなくなってしまうときもあるでしょう。そんなとき、「何か言葉を見つけなくては」と思うばかりに、ご家族のほうがつらくなってしまったり、不安になってしまったりすることがあるかもしれません。
こうしたとき、無理に言葉を見つける必要はありません。話すことや聞くことだけでなく、ご家族が「そばにいること」に十分に大きな意味があります。思いを伝えたいけれどもうまく伝えられない様子や、慣れない在宅療養に家族も戸惑ったり不安を抱えたりしていることも、コミュニケーションの一つのかたちとして、ご本人に伝わります。「何を言うか」「何をするか」よりも、ただ「本人を思い寄り添ってそばにいること」「一緒に同じときを過ごしていること」に大きな意味があると言えます。「うまく話そう」とか「本人を不安にさせないように」とか、あれこれ考えすぎなくても大丈夫です。言葉で表現できないときは、体に触れたり、さすったり、抱きしめたりすることもよいかもしれません。ご家族がご本人を気遣い、受け入れていることは、言葉を超えて伝わることでしょう。
病気のことばかりでなく、天気やテレビ番組について他愛もない会話をするなど、これまでと同じように接してもらうことが、一番自然で安らげると話す方も多くいます。
参考までに、相手への気遣いを示すコミュニケーションのヒントを以下にご紹介します。
(ご家族へ)どのように気遣いをあらわすか
- あまり堅苦しくならず、普段の何気ない会話や冗談をやりとりするだけでよいのです。きっとそれが一番長続きするでしょう。
- 照れたり恥ずかしがったりしないで、手を握ったり、さすったり、抱擁をしてみましょう。一緒に座っているだけでも、多くの会話を交わしたように支えになるでしょう。
- 生活のなかに積極的にちょっとした笑いやユーモアを取り入れ、ほほえみを絶やさないようにしたいものです。笑いは、私たちをリラックスさせ、気持ちを前向きにさせてくれます。どんなに困難な状況でも、小さな笑いが心をほぐし、助けになってくれることがあります。
- 昔の旅行のこと、畑仕事や庭の草花のこと、音楽の好み、最近のスポーツや映画、本の話題など、気さくに語り合うのもよいですね。
- ご本人が友人と連絡をとったり、訪問したり、外出したりなど、気分転換ができるようサポートするのもよいでしょう。
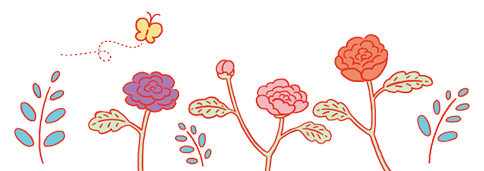
1-2-4.相談できる話し相手を見つけておきましょう
(患者さんへ)「がんばりすぎない日々」を大切に
在宅療養を始める患者さんの状況は人それぞれではありますが、在宅療養のうえでは、「がんばりすぎない」こともぜひ大切にしてください。住み慣れた環境で生活していると、どうしても、これまで自分が担ってきた役割を果たそうと、「早く体力を戻さなきゃ」とか「家族に世話をかけるわけにはいかない」「これ以上職場に迷惑をかけられない」などと、つらくてもつい無理をしてしまうことが多いようです。
しかし、がんという病気の療養を継続していくうえでは、生活の一部を見直したり、変えなくてはならなくなることがどうしても出てきます。「これまでどおり」にこだわらず、「どうしたら無理なく、居心地のよい生活を続けていけるか」という観点で、ご家族や周囲の人に遠慮しすぎずに、自分のつらさや希望を素直に伝えてみましょう。
ご家族は、身近にいるからこそ、どのように接したらよいか悩んだり、変に遠慮していたりすることもあります。あなたが感じているつらさや苦しさは、外見からはわかりにくいことも多く、自分から言わないと相手に伝わらないことも多々あります。病気や治療の状況との兼ね合いで、今の自分にできること、難しいこと(今はまだ難しそうなこと)などを率直に伝えてご家族や親しい人の手を借り、「がんばりすぎなくていい日常」を一日一日積み重ねていきましょう。
また、ご家族以外にも、病気のことを含めて気兼ねなく話せる友人や親しい人に話を聞いてもらうだけでも、気持ちが軽くなることもあります。
一人で抱え込まず、些細なことでも話せる関係を大切にしていきましょう。
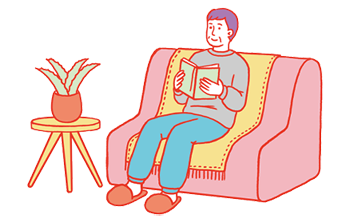
(ご家族へ)支援者となってくれる友人・知人を見つけましょう
がん患者さんのご家族の多くは、がんと診断されたご本人と同じかそれ以上に、大きな不安や気分の落ち込みを経験すると言われています。しかしその一方で、「一番つらいのは本人なんだから、私が弱気じゃ駄目だ」とか、「私が支えなくては」などと、家族としてのつらさに蓋をしてしまうことがしばしばあります。
「在宅で療養することになった」と周囲や離れた親戚などに伝えると、「がんばって支えてあげてね」とか「家族が頼みの綱だから」などと励まされたり、時には「家でがん患者を看るなんて……」などと在宅療養に否定的な言葉が返ってきたりして、ご家族はますます自分のつらさを表に出しにくくなってしまうこともあります。
しかし、患者さんのご家族だからといって、すべてを自分たちだけで抱え込む必要はまったくありません。つらい、と感じたときには、必要な支援を求めましょう。近所で親しい方や、在宅療養に理解を示してくれる知人や友人でも構いません。ちょっとした手助けをしてくれたり、精神的にあなたの支えになってくれたりする人を一人でも多く見つけておくことも、この先の大きな支えになるでしょう。外部の信頼できる相談先に相談するのもよい方法です(第1章「1-3.在宅療養に関する、信頼できる情報源」参照)。
実際に在宅での生活が始まると、話し相手やお手伝いをしてくれる人が徐々に増えてくることもあります。在宅での暮らしを話せる人が周りにいることは、ご家族にとっての心の支えになります。ご家族もまた、「がんばりすぎない」毎日を送れるように、環境を整えていきましょう。

 ACP(アドバンス・ケア・プランニング)―― 話し合いの大切さ
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)―― 話し合いの大切さ
がんを患った娘への話の取っかかりは、東北の震災を例として、私から口火を切りました。当たり前のように帰宅すると思っていたのに、「さよなら」を言えないお別れはどれほどつらかったか。余命を聞きながらも治療して生きている娘もつらいですよね。明日、もしかしたら事故、災難でみんなと別れてしまうかもしれない。でも今日、今はまだ大丈夫。
「あなたはどうしたい?」
「お母さんの最期はこうしたい。こうしてほしいなあ……」
それからは治療が変わるたびに話し合いました。そして話の最後に毎回、「全部は叶えてあげられるかわからないけど、家族みんな全力であなたの願いを叶える努力をするよ」と伝えました。
最終的に決まったのは、以下のことでした。
- 棺に入れる物
- 最期はきっと麻酔でそのまま逝ってしまうだろうから、麻酔を入れる前のお別れは「じゃあ、またね」と家族みんなで笑って送ってほしい
- 家で普通に逝きたい
娘は限られた時間のなか、「自分がいなくなってもお母さんを時々気にかけてね。母さんはヘタレだから」と笑ってほかの方に託してくれました。
4年半の闘病のなか、お互いに想い、想われたこと。この話し合いは、私にとってとても大きなことであり、大切な大切な宝物です。
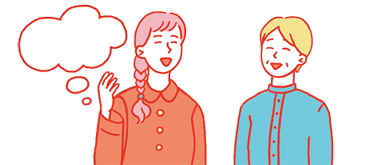
 支援は一歩ずつ段階を踏んで
支援は一歩ずつ段階を踏んで
夫は58歳でしたが、末期がんとの診断で介護保険の対象でした。担当のケアマネジャーさんが看護師さんということもあり、今後在宅で過ごすためのさまざまなアドバイスをいただきました。子どもたちは県外にいて頼れない状態でしたので、外部の方々のお力をお借りするしかありませんでした。お風呂や手すりなどの住宅改修で、ケアマネジャーさんをはじめ、いろいろな方々が少しずつ家に来られるようになり、在宅医、ヘルパーさん、訪問看護師さん、在宅リハビリテーションの理学療法士さんの方々を、夫は自然に受け入れられるようになりました。
また、夫には日記のように「備忘録」を書いてもらっていたので、ノートを介して自然に話をすることで気持ちを知ることもできました。「エンディングノート」*というと構えてしまいますが、一冊のノートを交換日記のように書くほうが、かしこまった話も違和感なくできたように思います。
*エンディングノート:人生の終末期にあたり、ご本人の想いや希望をご家族などに伝えるために書き留めておくノート。
 今とこれからを話し合う
今とこれからを話し合う
父ががんとなり自宅での療養が始まるにあたり、今まで話したことがなかったことを話すようにしました。そのなかで、これからの療養にあたり、費用を考えなくてはなりませんでしたが、家計管理は父がしていたこともあり、このとき初めて家計の実情について知りました。
民間の医療保険には入っておらず、また預貯金もほとんどなく、在宅療養を始める以前に、治療費の捻出もままならない状況でした。年金は十分にあったのですが、その年金が父の兄弟への貸付に回っていました。
治療や在宅療養に必要なお金を確保するために社会保険の利用を検討し、治療方法の再考などに際してもお金が最大の問題でした。今は兄弟からの返済を含め、なんとか治療と在宅療養ができています。家族がすべてを話し合うところから、心構えや準備が始まると実感しました。
 家族は主役ではなく、本人の想いに寄り添うことが大切
家族は主役ではなく、本人の想いに寄り添うことが大切
父が、命の期限を告げられたとき、病弱な母に代わり娘である自分がすべてを取り仕切らなくてはならないと思っていました。今後の治療方針、療養場所、生活など、何から手をつけたらよいのか……。まず本やインターネットで情報を集め、親戚や友人に相談しながらも、頭のなかが混乱していました。
そんなとき、知り合いの人から「決めるのはお父さんだろ。それはお父さん自身の問題だから、あなただけで決めるべきではないのですよ」と言われたのです。一瞬理解できませんでしたが、はっと気づきました。自分がキーパーソンとしてすべてを背負うのだという過度な気負いから、私は自分の立ち位置を勘違いしていたのです。中心は父本人であること、選択や決断を迫られたときには、「父の意思と願いにいかに沿えるか」を判断の基準にするということ。そんな一番大切なことを見失っていました。
父の人生、父と母の夫婦の物語の主人公はあくまで父、あるいは両親なのだから、脇を固める私たち家族は自分の思いや他人の意見に振り回されず、ただ裏方として主役を支えながら物語の最終章を見届ければよいと思ったとき、覚悟ができました。
 笑顔と活気が戻り、準備を整えて故郷へ
笑顔と活気が戻り、準備を整えて故郷へ
父が自宅での療養を決めてから2か月。往診の先生や看護師さんの協力で、病院にいるときよりも痛みが和らぎ、本人、家族が想像していた以上に動けるようになり、笑顔と活気が戻りました。人間は欲が出る生き物のようで、生まれ故郷の佐渡に最後にもう一度行きたい、先祖の墓参りをしたい、親戚にあいさつしたいと希望するようになりました。父は筋金入りの頑固者。言い出したら聞きません。娘としても、なんとか希望を叶えてあげたいと願い、往診の先生と看護師さんに相談しました。先生には、万が一のための紹介状(診療情報提供書)を準備いただき、看護師さんには旅行中の薬の準備、往復の新幹線やフェリーなどの移動手段について助言をもらい、準備万端でいざ佐渡へ。家族全員で降り立った佐渡の澄み切った空気は、移動の疲れを吹き飛ばすほどでした。
 夢を実現するために、「無理」と思わないで声に出してみる
夢を実現するために、「無理」と思わないで声に出してみる
夫の夢は、退職後に夫婦で車に乗って日本一周することでした。しかし、58歳でがん治療のために退職せざるを得なくなり、旅行も夢のまた夢となってしまいました。そんなときに「一番行きたかったところは?」と聞いたところ、「北海道の摩周湖」との答えでした。すでに進行して体力もだいぶ落ちておりました。主治医に相談したところ、「知り合いの医者が北海道にいるので連絡しておくから安心して行っておいで」とのこと。その言葉をありがたくいただき2人で摩周湖を目指して旅をしました。霧も晴れ、念願の美しい摩周湖に出会えました。
半年後、今度は自信がついたのか、「台湾の故宮博物院に行ってみたい」と希望し、在宅医が「知り合いが台湾にいるから連絡しておきますよ」と言ってくださり、娘と3人で行くことができました。最高の2つの思い出ができました。
 「病人」扱いせず、普段どおりの生活を心がける
「病人」扱いせず、普段どおりの生活を心がける
夫の訪問看護をお願いして2か月が経った頃、食事のことで言い争いになったことがありました。夫にすれば、食べたくないのに無理に食べさせようとする私に腹が立つ、私にすれば、なんとか食べてもらおうと一生懸命なのに、と互いにストレスが溜まってきていたのでしょう。
冷静になると、当然私が悪いことに気づき「ごめんね」と謝ると、「こちらこそ」と夫が小さい声で答え、今まで言ったこともない言葉に思わず吹き出して2人で笑ってしまいました。
夫を介護することに必死で、「病人」扱いされ焦りいら立つ夫のつらさを思うゆとりをなくしていたことに気づきました。病院なら「病人」ですが、家では今までどおり、一家の主としての日常生活をさせてあげるべきでした。
それ以降は、過去のこと、将来のことなど2人でいろいろ話す時間が増えました。在宅のよさは、そのような話が率直にできる時間がたくさんあることではないかと思います。