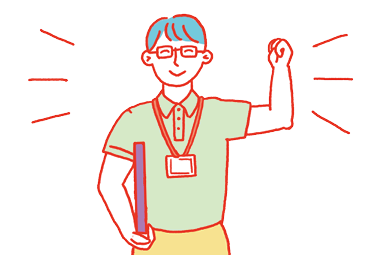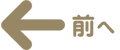1-3.在宅療養に関する、信頼できる情報源
1-3-1.在宅療養に関する情報を収集しましょう
在宅療養を始めるにあたっては、患者さん本人やご家族の気持ち・希望に加え、具体的にどのように過ごしていくのかの見通しを立てたり、在宅医療や看護・介護サービスの手続きをしたりするための情報収集が欠かせません。また、在宅療養が始まってから、新たな疑問や心配ごと、誰かに相談したいことが出てくるかもしれません。
在宅療養に関わる仕組みや利用できる制度は、都道府県や市区町村単位で異なることがあるため、本書の内容だけでは解決できないこともあるでしょう。そのようなときにも役立つ情報として、信頼できる代表的な相談先やウェブサイトを以下にまとめました。
●担当医(主治医)・看護師などの医療者
在宅療養が始まる前も、始まってからも、いつでも相談できるよう、不安なこと、困ったこと、悩んだこと、疑問に思ったことがあれば、まずはメモをしておいて、身近な担当医や看護師に話してみましょう。忙しそうで話しにくいと思われるかもしれませんが、心配なことを率直に話せる関係ができると、その後の療養においても心強い味方となります。治療の見通しや病状についてはもちろん、病気や治療に直接関係のないことも相談して構いません。心配ごとの内容に応じて、具体的な相談先などを紹介してくれます。
●がん相談支援センター
がん相談支援センターは、全国のがん診療連携拠点病院や、地域がん診療病院に必ず設置されている「がんに関する相談窓口」です。がんにまつわる悩みや不安、療養生活全般、医療費などの心配や、治療後の社会復帰に関することなど、がんに関係することはなんでも相談ができます。
がん相談支援センターは、設置されている病院にかかっていなくても、誰でも(患者さんご本人やご家族はもちろん、友人や職場の方など、誰でも)無料で利用することができます。電話での相談も可能です。自宅から離れている病院で治療をしている場合は、自宅近くの病院のがん相談支援センターを利用するのもよいでしょう(「8-4.信頼できる情報源」参照)。
●病院の地域連携室/退院支援室
病院に設置された地域連携室や退院支援室(病院によって名称が異なる場合があります)は、入院患者さんの退院後の療養について、必要に応じてお住まいの地域の医療機関などと連携をとり、切れ目のない医療やケアが提供されるよう調整を図ることを目的に設置されている部門です。看護師や医療ソーシャルワーカー(社会福祉の専門家)などが専任のスタッフとして常駐し、在宅療養を希望する人への情報提供や相談などを受け付けています。入院治療を受ける方は、こうした部門のサポートにより、入院前・入院中から退院後の生活を見据えて準備することができます。
●お住まいの市区町村窓口/地域包括支援センター
地域包括支援センターは、各自治体に設置された、高齢者とそのご家族、支援を行っている方の総合相談窓口です。在宅療養にあたり、介護保険を利用したい場合の相談や、日常生活上の困りごとを相談したりすることができます。お住まいに近い地域包括支援センターの場所は、インターネットで検索することもできますし、市区町村の窓口に尋ねても教えてもらえます。
●各都道府県のウェブサイトやがんの療養ガイドブック
がんの患者さんが増えている現在、国はがんになっても安心して暮らせる地域づくりを推進しており、それぞれの都道府県がさまざまな施策を展開しています。その一環として、各都道府県の事情を加味して、それぞれが独自の「がんの療養ガイドブック」を作成しています(ガイドブックの名称は「サポートハンドブック」「地域のがん情報」など、都道府県によってさまざまです)。自治体の窓口やがん診療連携拠点病院などでは、これらの冊子版を配布したり見本を掲示しているほか、各都道府県や市区町村のウェブサイトでは、ガイドブックのPDF版や、がんに関連するさまざまな地域の情報を掲載しています。
●がん情報サービス(ウェブサイト)
https://ganjoho.jp/ ![]()
がん情報サービスは、国立がん研究センターが運営するウェブサイトです。がんの種類ごとの詳しい情報や療養上のアドバイスなどが、専門家のチェックを経て掲載されています。また、全国の「がん相談支援センター」(前述)の所在地検索や、各都道府県が作成しているがんの療養ガイドブックの PDF版などを紹介しているページもあります。がんの総合情報サイトとして、大いに活用したいウェブサイトです。
●病院や患者会・患者団体、自治体などが主催する公開講座やウェブサイト
がん治療を行っている病院や、患者会・患者支援団体、自治体などでは、がんの療養に関するさまざまな情報をウェブサイトで公開していたり、公開講座を各地で開催したりしています(近年ではオンラインでの開催も増えています)。在宅療養に関する情報ばかりとは限りませんが、医療費の助成制度や、栄養の話題、がん経験者の実体験などを交えたお話など、療養を続けるうえで力となる情報収集の場として活用することができます。公開講座などの開催情報は、病院内の掲示板や、各団体・自治体のウェブサイトなどで見つけることができます。
あなたの在宅療養の輪郭が見えてきたでしょうか? 信頼できる確かな情報源から上手に情報を収集し、少しずつでも不安や心配ごとを減らしながら在宅療養をスタートさせましょう。
ご家族の体験談 頼れる「ケアマネさん」
頼れる「ケアマネさん」
だんだん母親の状態がよくないと感じられるようになりました。最初のケアマネジャーさんから、事情があって同じセンターに所属している別の方に代わりました。地域の医療や介護について多くの知識をもっている、現場経験が多い、人脈がすごい、そんな「ケアマネさん」でした。母に寄り添い、私の心に寄り添ってくれました。
在宅で床ずれがひどくなったとき医療機関につないでくれたこと、入院している病院を出たらどんな選択肢があるかを提案してくれたこと、日中の心配ごとの解消も兼ねて在宅リハビリテーションを提案して機関につないでくれたこと、介護ベッドの必要性から介護用品の会社につないでくれたこと、訪問看護の看護師さんとしっかり情報の共有をしていたことなど、あのケアマネさんがいたからこそ家族はふんばることができました。
「あの人なら知っている」「あの人ならつないでくれる」「なんとかなる」と思わせてくれるケアマネさんでした。