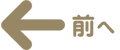第4章 住み慣れた場所で自分らしく暮らす
この章では、住み慣れた環境(在宅)で療養生活を送るときのご家族の心構えや必要な準備、介護保険の利用方法、在宅医やケアマネジャーの探し方、コミュニケーションのためのヒントについてまとめています。
在宅での療養生活を始めるにあたって知っておきたい知識のほか、患者さんやご家族の支え合いの場についても紹介しています。
- 自宅で治療を継続したり、必要なケアを受けることができるようになってきています。
- 信頼できる在宅支援チーム(在宅医、訪問看護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士、ケアマネジャー、介護福祉士、ヘルパーなど)と出会うために、病院や自治体の相談窓口などを活用し、情報を収集しましょう。介護保険も活用していきましょう。
- 在宅での治療やケアでは、苦痛やつらさを取り除き、ご本人やご家族の望む生活を叶えることがより重視されます。
- 納得のいく在宅療養となるよう、ご家族だけで抱え込まず、ご本人やご家族の希望や心配ごとなどは、遠慮なく在宅支援チームに相談したり、周囲の人に伝えたりしていきましょう。
4-1.在宅で治療やケアを受けるときの準備
4-1-1.自宅で治療やケアを受ける、「在宅医療」という選択肢があります
これまでの章では、短期の入院を伴いながらも、おもに通院で治療や療養を進めることになったTさん、Eさんのお話をお伝えしてきました。多くのがん療養は今、TさんやEさんのように、住み慣れた自宅で過ごしながら、通院で治療を継続するスタイルが増えてきています。
一方、通院が難しい場合などでは、医師や看護師が自宅に訪問し、必要な医療やケアを提供する「訪問診療」や「訪問看護」といった制度(在宅療養支援制度)を利用するかたちでの在宅療養(在宅医療)を選択される方も増えています(第1章1-1-4.参照)。
次に紹介する「Sさん」も、入院や通院による治療を経て、住み慣れた自宅で在宅医療を受けながら過ごすことを決めた一人です。Sさんご家族と相談員「Nさん」とのやりとりをみながら、在宅医療の始め方や、療養上の心配ごとなどについて、一緒に考えてみましょう。
在宅医療を受けながら、住み慣れた自宅で過ごすことを決めたSさん
 Sさん(65歳、男性)は、妻と社会人の娘の3人暮らしです。結婚して離れた場所に住む息子が1人います。長年勤めた会社の定年退職を間近に控えた64歳のときに膵臓がんが見つかり、その後の検査で、すでに根治が難しい状態であることがわかりました。がんの進行を抑制したり、症状を和らげる目的で入院し、抗がん剤治療や緩和ケア(痛みや苦痛を和らげる治療)を受けてきましたが、定年後は妻と自宅でのんびりした生活を送りたいと考えていたこともあり、退院して、住み慣れた自宅に帰りたいと考えるようになりました。
Sさん(65歳、男性)は、妻と社会人の娘の3人暮らしです。結婚して離れた場所に住む息子が1人います。長年勤めた会社の定年退職を間近に控えた64歳のときに膵臓がんが見つかり、その後の検査で、すでに根治が難しい状態であることがわかりました。がんの進行を抑制したり、症状を和らげる目的で入院し、抗がん剤治療や緩和ケア(痛みや苦痛を和らげる治療)を受けてきましたが、定年後は妻と自宅でのんびりした生活を送りたいと考えていたこともあり、退院して、住み慣れた自宅に帰りたいと考えるようになりました。
そこで、まずは家族にその希望を伝えたうえで、Sさん・家族・担当医で話し合いの場をもちました。Sさんと家族が担当医に希望を伝えたところ、担当医はすぐにSさんと家族の希望に沿って、今後は痛みや生活上のつらさを取り除くケアを重点的に行うこと、住み慣れた環境で医療を受けながら暮らせるように、在宅での療養に向けた準備を進めていくことを提案してくれました。在宅でも病院と同じように、痛みやつらさを取り除くための治療を受けられることも教えてくれました。入院中のSさんに代わり、Sさんの家族は早速、Sさんの在宅療養に向けた準備に取りかかることになりました。
4-1-2.「キーパーソン」を決め、周囲の支援者や理解者を増やしましょう
![]() 病気が治らないことを受け入れるのはつらいのですが、本人が自宅で過ごすことを望むのなら、その思いを叶えてあげたいと思います。ただ、これまでは入院している期間が長かったので、退院してきたときにどう接したらよいのか……。病気を抱えた家族を自宅でケアするのも初めてです。受け入れる準備も必要だし、手続きのことも、何もわかっていません。気持ちの整理もついていないですし、正直、何から手をつけてよいのか……。
病気が治らないことを受け入れるのはつらいのですが、本人が自宅で過ごすことを望むのなら、その思いを叶えてあげたいと思います。ただ、これまでは入院している期間が長かったので、退院してきたときにどう接したらよいのか……。病気を抱えた家族を自宅でケアするのも初めてです。受け入れる準備も必要だし、手続きのことも、何もわかっていません。気持ちの整理もついていないですし、正直、何から手をつけてよいのか……。
![]() この半年ほどで目まぐるしい変化があって、おつらく大変な時期を過ごされてきたのですね。これからのご自宅での生活では、Sさんとご家族が心を落ち着けて過ごせるように、私や医療・介護スタッフがお手伝いしますから、安心してくださいね。
この半年ほどで目まぐるしい変化があって、おつらく大変な時期を過ごされてきたのですね。これからのご自宅での生活では、Sさんとご家族が心を落ち着けて過ごせるように、私や医療・介護スタッフがお手伝いしますから、安心してくださいね。
![]() ありがとうございます。
ありがとうございます。
![]() Sさんの生活の場を整えたり、在宅医療や介護保険の手続きなど、いろいろやらねばならないことはありますが、その前にお伝えしたい大切なことがあります。それは、奥さまだけでSさんの身の回りのすべてのことを背負おうと思わなくてよいということです。ほかのご家族や周囲の方(支援者)、時にはSさんご自身にも協力してもらって、一緒に支え合って暮らしていく、そのくらいの気持ちで大丈夫ですよ。
Sさんの生活の場を整えたり、在宅医療や介護保険の手続きなど、いろいろやらねばならないことはありますが、その前にお伝えしたい大切なことがあります。それは、奥さまだけでSさんの身の回りのすべてのことを背負おうと思わなくてよいということです。ほかのご家族や周囲の方(支援者)、時にはSさんご自身にも協力してもらって、一緒に支え合って暮らしていく、そのくらいの気持ちで大丈夫ですよ。
![]() 同居の娘はできるだけ協力すると言ってくれています。息子は遠方で仕事も忙しそうですが、話し相手くらいにはなってくれそうです。
同居の娘はできるだけ協力すると言ってくれています。息子は遠方で仕事も忙しそうですが、話し相手くらいにはなってくれそうです。
![]() 最も身近な娘さん・息子さんが支援者になってくれるのは心強いですね。ではまず、誰が家族の窓口になるかを確認しておきましょうか。
最も身近な娘さん・息子さんが支援者になってくれるのは心強いですね。ではまず、誰が家族の窓口になるかを確認しておきましょうか。
![]() 家族の窓口?
家族の窓口?
![]() 「キーパーソン」とでも言いましょうか。Sさんご本人の希望に沿えるように、ご家族や関係者の意見を取りまとめて、医療・介護関係者とおもにやりとりする方です。もちろん、最初はSさんご本人がご自分の希望をもとに医療者ともやりとりできるでしょう。けれども、今後徐々に身体が弱ってきたときには、それが難しくなることもあります。そのときは、Sさんの近くにいる方が、治療やケアの方針・内容について判断したり、在宅医や看護師、ケアマネジャーなどに伝えたりしなければなりません。
「キーパーソン」とでも言いましょうか。Sさんご本人の希望に沿えるように、ご家族や関係者の意見を取りまとめて、医療・介護関係者とおもにやりとりする方です。もちろん、最初はSさんご本人がご自分の希望をもとに医療者ともやりとりできるでしょう。けれども、今後徐々に身体が弱ってきたときには、それが難しくなることもあります。そのときは、Sさんの近くにいる方が、治療やケアの方針・内容について判断したり、在宅医や看護師、ケアマネジャーなどに伝えたりしなければなりません。
![]() まだ考えられませんが、考えておく必要があることなのですね。
まだ考えられませんが、考えておく必要があることなのですね。
![]() 「きっと、普段のこの人ならこう考えるんじゃないかな」とSさんの気持ちや価値観を共有できる方が適任です(第1章1-2-2.参照)。奥さまでは荷が重すぎると感じるなら、息子さんでも娘さんでもよいと思います。ご家族の窓口(キーパーソン)を決めて、療養生活を円滑に過ごせるようにしていきましょう。
「きっと、普段のこの人ならこう考えるんじゃないかな」とSさんの気持ちや価値観を共有できる方が適任です(第1章1-2-2.参照)。奥さまでは荷が重すぎると感じるなら、息子さんでも娘さんでもよいと思います。ご家族の窓口(キーパーソン)を決めて、療養生活を円滑に過ごせるようにしていきましょう。
![]() ずっとそばにいる私が適任なのでしょうね。幸い家族仲はよいので家族内では話はまとまると思いますが、地方に住んでいる夫の妹が在宅での療養に反対しています。まだ治る見込みのあるほかの治療法があるのではないか……と。夫の状態がさらに悪くなったときに何か言われたり、あとになって責められたりしないか、心配です。
ずっとそばにいる私が適任なのでしょうね。幸い家族仲はよいので家族内では話はまとまると思いますが、地方に住んでいる夫の妹が在宅での療養に反対しています。まだ治る見込みのあるほかの治療法があるのではないか……と。夫の状態がさらに悪くなったときに何か言われたり、あとになって責められたりしないか、心配です。
![]() おっしゃるとおり、ご本人やご家族が在宅療養を希望しても、緩和ケアやその先の看取りをめぐって、親族間でのトラブルが起こる可能性があります。一般的に、ご本人と離れて暮らしている親族の方が在宅療養に不安や不満を感じる理由として、在宅療養がどのようなものなのかをイメージするのが難しいことがあるようです。
おっしゃるとおり、ご本人やご家族が在宅療養を希望しても、緩和ケアやその先の看取りをめぐって、親族間でのトラブルが起こる可能性があります。一般的に、ご本人と離れて暮らしている親族の方が在宅療養に不安や不満を感じる理由として、在宅療養がどのようなものなのかをイメージするのが難しいことがあるようです。
![]() そうかもしれません。当事者の私たちだって、まだまだわからないことだらけで、戸惑いや不安があるのですから。
そうかもしれません。当事者の私たちだって、まだまだわからないことだらけで、戸惑いや不安があるのですから。
![]() 在宅療養を望んでいるご本人のお気持ちや、在宅に関わる医療・介護のスタッフがどのような態勢でサポートするのか、ご家族がどのような役割分担でSさんを支えるのか、あらかじめお伝えしておくとよいと思います。それでも理解が得られなければ、医師から直接説明してもらうこともできます。
在宅療養を望んでいるご本人のお気持ちや、在宅に関わる医療・介護のスタッフがどのような態勢でサポートするのか、ご家族がどのような役割分担でSさんを支えるのか、あらかじめお伝えしておくとよいと思います。それでも理解が得られなければ、医師から直接説明してもらうこともできます。
![]() そうなのですね。私があやふやに説明するよりも、専門家から話していただいたほうが、納得してもらえるかもしれませんね。
そうなのですね。私があやふやに説明するよりも、専門家から話していただいたほうが、納得してもらえるかもしれませんね。
![]() 在宅療養が実際に始まってからも、親戚の方には折に触れて経過を報告し、やりとりの不一致や摩擦が生じないように心がけるとよいと思います。
在宅療養が実際に始まってからも、親戚の方には折に触れて経過を報告し、やりとりの不一致や摩擦が生じないように心がけるとよいと思います。
![]() 本当にやるべきことだらけですね。私にできるのかしら……。
本当にやるべきことだらけですね。私にできるのかしら……。
![]() 最初にお伝えしたとおり、一人で抱え込まずに、周囲を巻き込んで、みんなでSさんを支えていきましょう。ちょっとした手伝いを気軽に頼めたり、些細なことでも話せる相談相手を一人でも多く見つけておくことも、大きな支えになると思います(第1章1-2-4.(ご家族へ)参照)。
最初にお伝えしたとおり、一人で抱え込まずに、周囲を巻き込んで、みんなでSさんを支えていきましょう。ちょっとした手伝いを気軽に頼めたり、些細なことでも話せる相談相手を一人でも多く見つけておくことも、大きな支えになると思います(第1章1-2-4.(ご家族へ)参照)。

第1章でもお伝えしたとおり(1-1-2.参照)、病院での医療と在宅医療は、同じ「医療」でも、目指す方向性にそれぞれ特徴があります。
病院での医療は、一言で表すなら「集中的に病気に対応する医療やケア」です。大ケガや脳卒中などのように一刻を争うときや、がん治療において手術や放射線による治療、抗がん剤による治療を受けるときなどには、専門的なスタッフと設備が整った病院において、治療やケアが行われます。病院の性質によって、急性期・回復期・慢性期のように、機能に応じた役割を担っています。それぞれの役割に応じた医師や看護師をはじめとした医療スタッフが対応しています。
また、通院して治療を継続したり、在宅で療養するまでの準備や態勢を整える役割を担うこともありますし、在宅医療を支える医療機関や施設と連携して入院による治療やケアを行うこともあります。入院環境において、緩和ケア病棟やホスピスなど、在宅環境に近い医療やケアを提供する施設もあります。
一方の在宅医療は、「在宅環境において、寄り添い、支える医療やケア」と言えます。在宅医療を選択する患者さんは、完治が難しい病気や障がいを抱えていることが多いです。病気を「治す」ことは難しい、だからこそ、慣れ親しんだ環境で、その人らしく、ご家族や気心の知れた人とともに、制限や制約ができるだけ少ない状態で大切な日々を過ごすことを最優先に、痛みや生活上のつらさを取り除く医療やケアを中心に行っていく――つまり、在宅環境において、ご本人やご家族の思いや希望が何よりも重視されるのが、「寄り添い、支える」ことだと言えます。
「病院での医療」に慣れていると、「在宅医療」は自由度が高く、さまざまな職種が入れ代わり立ち代わり自宅にやってきて知恵を出し合い生活を支えてくれることに、時にギャップを感じ、戸惑うこともあるかもしれません。ですが、在宅医療に関わるスタッフは皆、ご本人やご家族が、その人らしい充実した毎日を過ごせることをとても大切に思っています。「こんなことを言ったら迷惑かな」とか「本当はこうしたいけど、わがままに思われるかも」などと思い悩まず、在宅での療養生活が納得いくものになるよう、「どのように過ごしていきたいか」「何をしたいか」や、あるいは反対に「これだけはしたくない」ことなども含め、ご本人の希望を遠慮せずに伝えていくことをぜひ大切にしてください(第1章1-2-2.参照)。

 頼りになる「私のチーム」
頼りになる「私のチーム」
私はAYA世代*でがんになり、その後再発や転移を経験し、今も治療を続けながら自宅で生活しています。再発したときに私が最初にしたことは、「相談できる人を増やすこと」でした。また再発したり進行がんになったときに困らないようにしておきたいと思いました。そこで、主治医の先生と相談し、緩和医療科の先生とサイコオンコロジー(精神腫瘍科)の先生にかかり始めました。どちらの先生も予約が取りづらいので、いざ本当に困ったときにすぐにかかれなかったり、先生方と人間関係ができていなかったりして、しんどいときに一から関係を築くのは大変だと思ったからです。
その後は緩和ケアの認定看護師さん、化学療法の認定看護師さん、専門薬剤師さん、心理士さん、ソーシャルワーカーさんなどたくさんの方とつながることができ、いわゆる医療者の方が中心となってつくるチーム医療のチームと違い、自分自身が中心となり困ったときに助けてもらえる「私のチーム」をつくることができました。そのチームがあるのでとても心強いです。
 退院前の準備、そして自宅へ
退院前の準備、そして自宅へ
母親の入院を機に、介護保険の申請をすることになりました。病院のソーシャルワーカーさんからおおまかな手順を聞き、信頼できる施設のケアマネジャー(ケアマネ)さんに依頼することを決めました。笑顔の感じのいいケアマネさんは、介護認定や手続きについて一から教えてくれ、母の状態、家族の希望などを考えたケアプランを作成してくれました。
退院して自宅へ……。本当ならうれしいことですが、不安もありました。退院前カンファレンスで、数名のスタッフが自宅に来て必要なことを母と検討する機会をもつことにしました。看護師・リハビリテーションスタッフ・ケアマネ・介護用品の会社の方などが一緒に自宅に来てくれました。必要な用品やその配置、気をつけることなどを話し合って母が安心した表情になったことを覚えています。
退院までにできなかった手すりの工事でしたが、工事当日、母の希望で設置場所を追加しました。普段の生活をしたい、自分ができることをしたいという母の願いだったと思います。
レンタル用品と配置は母の行動に合うように揃えてセッティングしてもらいました。母は介護用品のスタッフに信頼を寄せていて、定期的な点検時に「この手すりは私の大事なものなの」とよく笑顔で話していました。
退院前、母は私の知らないところで歩行などのリハビリテーションをしていました。大好きなリハビリテーションスタッフに励まされ支えられていました。なんとか日常生活を取り戻すことができたのは、多くの方のおかげでした。