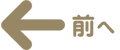4-4.こまめな相談と連絡が在宅療養のカギ
その後、Sさん家族は手分けをして介護保険の申請や、訪問診療をしてくれる在宅医探しを進めました。Sさん一家が長年お世話になっていたかかりつけ医が、がん患者さんの訪問診療にも対応していることがわかり、安心してお願いすることができました。かかりつけ医からの紹介で、担当してくれるケアマネジャーも決まり、訪問診療・訪問看護や介護ケアのスケジュール(ケアプラン)が組まれ、Sさん一家の在宅療養が始まりました。
4-4-1.実際に在宅での療養が始まったら
![]() こんにちは、その後いかがですか?
こんにちは、その後いかがですか?
![]() 夫が帰ってきてしばらくは落ち着かず大変でしたが、ようやく慣れてきました。本人も「やっぱり家はいいな」なんて言って、安心した顔を見せてくれたので、大変だけどよかったと思いました。
夫が帰ってきてしばらくは落ち着かず大変でしたが、ようやく慣れてきました。本人も「やっぱり家はいいな」なんて言って、安心した顔を見せてくれたので、大変だけどよかったと思いました。
![]() それはよかったですね。前にもお話ししましたが、今後、Sさんの体調や病状の変化によって、介護用具などは使い勝手が悪いと感じるものも出てくるかもしれません。介護保険でレンタルしたベッドや床ずれ予防用具などは、Sさんに合わなければ変更することもできます。また、トイレ用品や入浴用品など購入しなければならないものは、見本を使ってみるなどして、ご自宅やご本人の体に合うものを探してみてください。取扱店によって品揃えや対応も異なるので、ケアマネジャーに相談しながら、柔軟に対応してくれるところを見つけましょう。
それはよかったですね。前にもお話ししましたが、今後、Sさんの体調や病状の変化によって、介護用具などは使い勝手が悪いと感じるものも出てくるかもしれません。介護保険でレンタルしたベッドや床ずれ予防用具などは、Sさんに合わなければ変更することもできます。また、トイレ用品や入浴用品など購入しなければならないものは、見本を使ってみるなどして、ご自宅やご本人の体に合うものを探してみてください。取扱店によって品揃えや対応も異なるので、ケアマネジャーに相談しながら、柔軟に対応してくれるところを見つけましょう。
![]() ケアプランについては、どの程度の変更が可能なのでしょう?
ケアプランについては、どの程度の変更が可能なのでしょう?
![]() 介護保険は認定された要介護度によって、利用できるサービスの限度額が決まります。基本的にはその範囲内でのサービス内容(ケアプラン)となりますが、ご本人やご家族が希望すれば、限度額を超える分は自己負担でサービスを受けることができます。また、ケアプランはご本人の状態に応じて見直しができますので、ケアマネジャーとこまめに連絡を取り合い、相談していきましょう。
介護保険は認定された要介護度によって、利用できるサービスの限度額が決まります。基本的にはその範囲内でのサービス内容(ケアプラン)となりますが、ご本人やご家族が希望すれば、限度額を超える分は自己負担でサービスを受けることができます。また、ケアプランはご本人の状態に応じて見直しができますので、ケアマネジャーとこまめに連絡を取り合い、相談していきましょう。
![]() 夫が喜んでくれたのはうれしいのですが、こちらはなかなか気の休まる時間がありませんね。このまま在宅療養を続けられるのか、こちらが参ってしまわないか、不安もよぎります。
夫が喜んでくれたのはうれしいのですが、こちらはなかなか気の休まる時間がありませんね。このまま在宅療養を続けられるのか、こちらが参ってしまわないか、不安もよぎります。
![]() そうですね。そのようなときは、遠慮なく在宅医や訪問看護師、ケアマネジャーなどに気持ちを打ち明けてください。サポートを手厚くすることで乗り切れるかもしれませんし、必要に応じてSさんの一時的な入院の手はずを整えるなどの対策を、一緒に考えることができます。
そうですね。そのようなときは、遠慮なく在宅医や訪問看護師、ケアマネジャーなどに気持ちを打ち明けてください。サポートを手厚くすることで乗り切れるかもしれませんし、必要に応じてSさんの一時的な入院の手はずを整えるなどの対策を、一緒に考えることができます。
![]() ありがとうございます。心強いです。
ありがとうございます。心強いです。
![]() 前にもお伝えしたとおり、奥さま一人で背負おうとしなくて大丈夫です。つらいと感じたときは、遠慮せず、早めに在宅支援チームの誰かに打ち明けてください。こまめな連絡や相談が、在宅療養を無理なく継続するカギだということを、ぜひ忘れないでくださいね。
前にもお伝えしたとおり、奥さま一人で背負おうとしなくて大丈夫です。つらいと感じたときは、遠慮せず、早めに在宅支援チームの誰かに打ち明けてください。こまめな連絡や相談が、在宅療養を無理なく継続するカギだということを、ぜひ忘れないでくださいね。
4-4-2.「できるわけがない」と思うことも相談を
![]() はい、すみません、早々に弱音を吐いてしまって……。
はい、すみません、早々に弱音を吐いてしまって……。
![]() いいえ、大丈夫ですよ。ほかに気になっていることはありませんか?
いいえ、大丈夫ですよ。ほかに気になっていることはありませんか?
![]() 無理だとは思うのですが、もう少し落ち着いたら、夫が動けるうちに、家族でどこかに出かけられないかと……。夫は温泉が好きなので、近場でももし旅行ができたらうれしいのですが。日帰りでも構いません。
無理だとは思うのですが、もう少し落ち着いたら、夫が動けるうちに、家族でどこかに出かけられないかと……。夫は温泉が好きなので、近場でももし旅行ができたらうれしいのですが。日帰りでも構いません。

![]() そうなのですね。ご本人に「行きたい」という気持ちさえあれば、行ける場合が多いようですよ。体調や移動の手段、滞在先の環境などが整えば宿泊も可能ですから、ぜひ在宅医に相談してみてください。事前にどんな用意が必要か、旅先で具合が悪くなったときどうすればよいかなどについて確認しましょう。外出は気分転換にもなりますし、ご家族にとってもよい思い出づくりができますね。
そうなのですね。ご本人に「行きたい」という気持ちさえあれば、行ける場合が多いようですよ。体調や移動の手段、滞在先の環境などが整えば宿泊も可能ですから、ぜひ在宅医に相談してみてください。事前にどんな用意が必要か、旅先で具合が悪くなったときどうすればよいかなどについて確認しましょう。外出は気分転換にもなりますし、ご家族にとってもよい思い出づくりができますね。
![]() そうですか、できるのですね。できるわけがないと半分は諦めていたのです。
そうですか、できるのですね。できるわけがないと半分は諦めていたのです。
![]() 在宅医療では、ご本人とご家族の“生活”に重点が置かれます。生活の質(QOL)が保たれるよう、ご本人に意欲がある限り、散歩や趣味、旅行など、ご本人が望むことを続けられるようサポートするのも、在宅支援チームの役割です。「無理かな」と思うことも、ぜひ相談してみてください。チームの力を借りて、充実した家族の時間を過ごすことを大切にしてくださいね。
在宅医療では、ご本人とご家族の“生活”に重点が置かれます。生活の質(QOL)が保たれるよう、ご本人に意欲がある限り、散歩や趣味、旅行など、ご本人が望むことを続けられるようサポートするのも、在宅支援チームの役割です。「無理かな」と思うことも、ぜひ相談してみてください。チームの力を借りて、充実した家族の時間を過ごすことを大切にしてくださいね。
 伝える勇気、口に出す勇気
伝える勇気、口に出す勇気
再発・転移を経験し、現在も進行がん患者として治療を続けています。初めてがんになったときは、周りに相談できる人がおらず、また家族には心配をかけたくない思いと、「言ってもわからないだろう」という思いから誰にも相談できませんでした。その後、さまざまな経験を経て、今は相談できる人が周りにたくさんいます。家族、病気をとおして出会った仲間、主治医の先生、緩和ケアや精神腫瘍科の先生、看護師さん、薬剤師さん、ソーシャルワーカーさん、心理士さんなどです。でもそれは、いつの間にか相談できる人が周りに集まってきたわけではありません。それぞれのタイミングでそれぞれの立場の人に、自分が話を聞いてほしい、助けてほしい、困っているということを伝えるようになったからです。
がんになる前の私は、そしてがんになったばかりの頃の私は、自分のことを他人に話したり、相談したりすることが苦手でほとんどできませんでした。しかし、がんになり、気づいてほしい、察してほしいという考えでは救われないことに気づき、最初はとても勇気がいりましたが、困っていることを口に出す、助けてほしい、やってほしいことを、また反対に、やってほしくないこと、言ってほしくないことを伝えるようにしたら、助けてくれる人が周りにたくさんいることに気づくことができました。