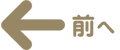2-4.薬物療法(抗がん剤治療)を通院で受ける
薬物療法は、がんの三大治療のひとつで、抗がん剤を中心とするがん治療薬を用いて、がんを治したり、進行を抑えたり、がんに伴う症状を緩和するなどの目的で行われます。
通院による抗がん剤治療は、おもに注射や点滴、または内服で行われます。治療の期間はがんの種類や病状によってさまざまですが、近年は、薬物療法とほかの治療法(手術療法、放射線療法)を組み合わせて行う「集学的治療」が多く行われています。
2-4-1.治療の方法と、大切な副作用のコントロール
![]() T さんは、まずは通院で点滴による抗がん剤治療を受けるのでしたね。
T さんは、まずは通院で点滴による抗がん剤治療を受けるのでしたね。
![]() はい。はじめは3週間に1回、病院の「外来化学療法室」という、通院で行う抗がん剤治療専用の部屋で点滴による治療を受けることになっています。初回の投与は入院して行う病院もあるそうですが、私が通っている病院では、初回から通院で行うそうです。
はい。はじめは3週間に1回、病院の「外来化学療法室」という、通院で行う抗がん剤治療専用の部屋で点滴による治療を受けることになっています。初回の投与は入院して行う病院もあるそうですが、私が通っている病院では、初回から通院で行うそうです。
![]() かつては初回だけでなく、長く入院して抗がん剤治療が行われていましたが、がん治療そのものの進歩に加えて、「支持医療(サポーティブケア)」が大きく進歩したことで、短期間の入院+通院、あるいは通院のみで抗がん剤治療を行うことができるようになってきました。
かつては初回だけでなく、長く入院して抗がん剤治療が行われていましたが、がん治療そのものの進歩に加えて、「支持医療(サポーティブケア)」が大きく進歩したことで、短期間の入院+通院、あるいは通院のみで抗がん剤治療を行うことができるようになってきました。
![]() 支持医療って何ですか?
支持医療って何ですか?
![]() 支持医療(サポーティブケア)とは、がんの治療によって起こる副作用を予防したり、副作用を早期に発見してしっかり抑える治療のことです。支持医療によってつらい症状をしっかり抑え、その結果、治療中も普段どおりに生活を送れたり、効果が期待できる十分な強度のがん治療を継続することができるようになってきたのですよ。
支持医療(サポーティブケア)とは、がんの治療によって起こる副作用を予防したり、副作用を早期に発見してしっかり抑える治療のことです。支持医療によってつらい症状をしっかり抑え、その結果、治療中も普段どおりに生活を送れたり、効果が期待できる十分な強度のがん治療を継続することができるようになってきたのですよ。
![]() そういえば、担当医の先生も、抗がん剤による吐き気には、今はよいお薬がたくさんあるので、あまり心配しすぎなくて大丈夫ですよ、とお話しされていました。
そういえば、担当医の先生も、抗がん剤による吐き気には、今はよいお薬がたくさんあるので、あまり心配しすぎなくて大丈夫ですよ、とお話しされていました。
![]() そうですね、吐き気が起こりやすいとわかっている抗がん剤を使う場合には、点滴の順番を調整して、先に吐き気止めを投与して吐き気を予防するなど、お薬の使い方もさまざまに工夫されてきています。
そうですね、吐き気が起こりやすいとわかっている抗がん剤を使う場合には、点滴の順番を調整して、先に吐き気止めを投与して吐き気を予防するなど、お薬の使い方もさまざまに工夫されてきています。
![]() 「抗がん剤」=吐き気や嘔吐のイメージがあったのですが、先生からそれを聞いて少しホッとして、安心して治療を受けようと思いました。
「抗がん剤」=吐き気や嘔吐のイメージがあったのですが、先生からそれを聞いて少しホッとして、安心して治療を受けようと思いました。
![]() ご自宅での生活を普段に近いものにするためにも、がん自体の治療と併せて、治療に伴う副作用を取り除く支持医療もしっかり受けていく、ということをぜひ大切にしてくださいね。
ご自宅での生活を普段に近いものにするためにも、がん自体の治療と併せて、治療に伴う副作用を取り除く支持医療もしっかり受けていく、ということをぜひ大切にしてくださいね。
![]() 副作用をひたすら我慢しなくてよいのだと思うと、少し安心します。
副作用をひたすら我慢しなくてよいのだと思うと、少し安心します。
![]() そうですね。治療によって起こりうる副作用のすべてをなくすことは、残念ながらまだできませんが、特に吐き気やだるさ、痛みなどは、検査などでわかる症状ではなく、治療を受けるご本人にしかわからないつらい症状ですから、軽いと思うものでも我慢せず、診察や治療の際に、担当医のほか、看護師や薬剤師などに遠慮なく伝えて、しっかりケアを受けながら、治療を継続していきましょう。
そうですね。治療によって起こりうる副作用のすべてをなくすことは、残念ながらまだできませんが、特に吐き気やだるさ、痛みなどは、検査などでわかる症状ではなく、治療を受けるご本人にしかわからないつらい症状ですから、軽いと思うものでも我慢せず、診察や治療の際に、担当医のほか、看護師や薬剤師などに遠慮なく伝えて、しっかりケアを受けながら、治療を継続していきましょう。
2-4-2.自分でわかる副作用と、自分ではわからない副作用
![]() ところで、抗がん剤治療の副作用には、自分でわかる副作用と、自分ではわからない副作用があるのをご存知ですか?
ところで、抗がん剤治療の副作用には、自分でわかる副作用と、自分ではわからない副作用があるのをご存知ですか?
![]() 自分でわかる副作用は、吐き気や体のだるさ……などですよね。でも、自分ではわからない副作用とは……?
自分でわかる副作用は、吐き気や体のだるさ……などですよね。でも、自分ではわからない副作用とは……?
![]() 血液検査などの数値で変化が現れるものです。白血球や赤血球、血小板の数値や、肝機能、腎機能の状態などは自分ではわからないので、外来通院の場合には、治療の前日や当日、治療前に血液検査などを行って、安全に治療が可能な状態かどうかなどを担当医が判断します。もちろん、医師が確認するとはいえ、ご自身でも毎回の検査結果を把握し、結果をもとに生活上で気をつけるべきことがないか、など、注意を払っていけるとよいですね。
血液検査などの数値で変化が現れるものです。白血球や赤血球、血小板の数値や、肝機能、腎機能の状態などは自分ではわからないので、外来通院の場合には、治療の前日や当日、治療前に血液検査などを行って、安全に治療が可能な状態かどうかなどを担当医が判断します。もちろん、医師が確認するとはいえ、ご自身でも毎回の検査結果を把握し、結果をもとに生活上で気をつけるべきことがないか、など、注意を払っていけるとよいですね。
![]() 抗がん剤治療では、白血球数が減少する時期があると聞きました。白血球は免疫に関わる細胞なので、白血球が低下している間は、感染予防にいっそう注意が必要だと、確か看護師さんが言っていました。
抗がん剤治療では、白血球数が減少する時期があると聞きました。白血球は免疫に関わる細胞なので、白血球が低下している間は、感染予防にいっそう注意が必要だと、確か看護師さんが言っていました。
![]() そうですね。近年では、がんの治療薬にもさまざまな種類があり、起こりうる副作用も、使用する薬剤や量によって異なります。ご自身に使用される薬剤とその副作用、またその対策について、担当医や看護師、薬剤師などから説明がありますから、よく確認するようにしましょう。また、心配な点や不安なことは、治療前だけでなく、治療中や治療後でも、いつでも尋ねていただいて構いません。
そうですね。近年では、がんの治療薬にもさまざまな種類があり、起こりうる副作用も、使用する薬剤や量によって異なります。ご自身に使用される薬剤とその副作用、またその対策について、担当医や看護師、薬剤師などから説明がありますから、よく確認するようにしましょう。また、心配な点や不安なことは、治療前だけでなく、治療中や治療後でも、いつでも尋ねていただいて構いません。
![]() ……やっぱり、またちょっと不安になってきました。
……やっぱり、またちょっと不安になってきました。
![]() 急にいろいろお伝えしすぎてしまいましたね。でも、実際に治療が始まってみると、人によっては心配するほどの症状が現れなかったり、なかにはまったくケロッとしたりしている方もいます。その個人差は、実際に治療を開始してみないと、医療者にもわからないのです。伝えたいことや気になることを書き留めておいて、あとは治療中にその都度、担当医や看護師にこまめに心身の状況を伝えて対応していくことで大丈夫ですよ。
急にいろいろお伝えしすぎてしまいましたね。でも、実際に治療が始まってみると、人によっては心配するほどの症状が現れなかったり、なかにはまったくケロッとしたりしている方もいます。その個人差は、実際に治療を開始してみないと、医療者にもわからないのです。伝えたいことや気になることを書き留めておいて、あとは治療中にその都度、担当医や看護師にこまめに心身の状況を伝えて対応していくことで大丈夫ですよ。
![]() 考えすぎもよくないですね。
考えすぎもよくないですね。
![]() 参考までに、「細胞障害性抗がん剤」によって起こる副作用とその発現時期の目安を示しておきますね(下表)。もちろん、ここにあげた副作用のすべてが起こるわけではなく、また、近年多く使われるようになった「分子標的治療薬」や「免疫チェックポイント阻害薬」と呼ばれる新しいタイプのがん治療薬では、従来の抗がん剤とは異なる(この表に示されていない)副作用が現れることがあります。繰り返しになりますが、ご自身に使用される治療薬に応じて、担当医などとともに対処法を考えるようにしてくださいね。
参考までに、「細胞障害性抗がん剤」によって起こる副作用とその発現時期の目安を示しておきますね(下表)。もちろん、ここにあげた副作用のすべてが起こるわけではなく、また、近年多く使われるようになった「分子標的治療薬」や「免疫チェックポイント阻害薬」と呼ばれる新しいタイプのがん治療薬では、従来の抗がん剤とは異なる(この表に示されていない)副作用が現れることがあります。繰り返しになりますが、ご自身に使用される治療薬に応じて、担当医などとともに対処法を考えるようにしてくださいね。

| 抗がん剤(細胞障害性抗がん剤)副作用発現時期の目安 | |
| 自分でわかる副作用 | 自分ではわからない副作用 (検査で判明する副作用) |
| 治療直後 急性の吐き気・嘔吐、アレルギー反応、血圧低下、不整脈、頻脈、呼吸困難 など ~1週間頃 遅延性の吐き気· 嘔吐、食欲低下、全身倦怠感、便秘 など ~2週間頃 口内炎、下痢 など 2週間~ 脱毛、神経毒性(指や足先のしびれ感、耳鳴り)など |
1週間~3週間頃 肝・腎・心臓機能障害、骨髄抑制(白血球・好中球低下、血小板低下)など 2週間~ 骨髄抑制、貧血 など |
新しいがん治療薬
分子標的治療薬
がん細胞がもつ特徴を分子レベルで捉え、その分子を標的としてがん細胞を攻撃する新しいタイプの治療薬です。従来の抗がん剤(細胞障害性抗がん剤)にみられる吐き気、白血球減少、脱毛などの副作用が少ない反面、特有の副作用があります。
おもな副作用:皮疹、アレルギー様症状、間質性肺炎 など
免疫チェックポイント阻害薬
人体がもっている免疫の仕組みを利用してがんを治療する、新しいタイプの治療薬です。免疫を活性化させるため、正常な細胞もその影響を受けることがあり、免疫関連有害事象と呼ばれる特有の副作用が現れることがあります。
おもな副作用:下痢、肝機能障害、甲状腺機能障害、皮膚のかゆみ、間質性肺炎 など
2-4-3.緊急度の高い副作用
![]() これもまた、参考までにですが、抗がん剤治療において、一般的に緊急度の高い症状(副作用)についても、お伝えしておきます。以下のような症状がみられたら、躊躇せず、早めに病院に連絡を入れましょう。また、医師からあらかじめ対処法を指示されている場合には、その指示に沿って対応しましょう。もちろん、これ以外の症状でも、不安や気がかりな点があれば確認して構いませんし、通院の際にも遠慮なく尋ねてください。
これもまた、参考までにですが、抗がん剤治療において、一般的に緊急度の高い症状(副作用)についても、お伝えしておきます。以下のような症状がみられたら、躊躇せず、早めに病院に連絡を入れましょう。また、医師からあらかじめ対処法を指示されている場合には、その指示に沿って対応しましょう。もちろん、これ以外の症状でも、不安や気がかりな点があれば確認して構いませんし、通院の際にも遠慮なく尋ねてください。
- 普段に比べ体温が高くなった(38.5℃以上など)
- 吐き気や嘔吐、下痢などで水分が摂れない
- 食欲不振や口内炎などで食事が摂れない
- 痛みやしびれ、だるさ、皮膚症状などが強く、動けない、眠れない
- (点滴の場合) 点滴後に針を刺した部分の痛みや赤み、腫れが出てきた
- 尿が出ない/極端に少ない
- 息切れや息苦しさが現れた
- そのほか、明らかにいつもと違う感じがする/おかしい
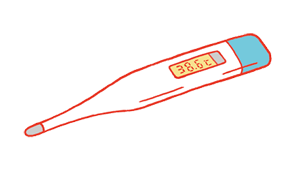
2-4-4.抗がん剤治療中の食事について
![]() 抗がん剤治療を受けている間、生活上で気をつけなければならないことはあるでしょうか。たとえば、治療中に食べないほうがよいものがあるとか……。
抗がん剤治療を受けている間、生活上で気をつけなければならないことはあるでしょうか。たとえば、治療中に食べないほうがよいものがあるとか……。
![]() 治療にあたって、もし守ってほしいことがあれば、必ず担当医や看護師、薬剤師などから説明がありますので、指示がないのであれば、元の生活から特段、何かを変えなければならないといったことはありません。
治療にあたって、もし守ってほしいことがあれば、必ず担当医や看護師、薬剤師などから説明がありますので、指示がないのであれば、元の生活から特段、何かを変えなければならないといったことはありません。
![]() 担当医からは特に言われていないのですが、生ものや生野菜・果物などは避けたほうがよいと、インターネットのどこかのサイトに書いてありました。
担当医からは特に言われていないのですが、生ものや生野菜・果物などは避けたほうがよいと、インターネットのどこかのサイトに書いてありました。
![]() 医師から「加熱したものを食べるように」などの説明がなければ、生ものも、生野菜・果物も、特段問題になりません。むしろ、治療をしっかり受けていくためには、食べられるものをおいしく食べて、体力を維持していくことのほうが大切です。
医師から「加熱したものを食べるように」などの説明がなければ、生ものも、生野菜・果物も、特段問題になりません。むしろ、治療をしっかり受けていくためには、食べられるものをおいしく食べて、体力を維持していくことのほうが大切です。
![]() そうなのですか。インターネットの情報を、すべて自分に当てはめて考えるのは危険ですね。気をつけないと……。
そうなのですか。インターネットの情報を、すべて自分に当てはめて考えるのは危険ですね。気をつけないと……。
![]() とはいえ、今後治療の副作用で、食欲が低下したり、口内炎ができて食べにくかったりすることがあるかもしれません。こうしたとき、「食べなくては」と思うあまりに、食事がつらいものになってしまわないように……。症状のあるときは、無理のない範囲で、食べられるものを食べる、ということで大丈夫です。食事に関する心配ごとがあれば、通院先の管理栄養士から、食べやすい食事の摂り方などを教えてもらうこともできますよ。
とはいえ、今後治療の副作用で、食欲が低下したり、口内炎ができて食べにくかったりすることがあるかもしれません。こうしたとき、「食べなくては」と思うあまりに、食事がつらいものになってしまわないように……。症状のあるときは、無理のない範囲で、食べられるものを食べる、ということで大丈夫です。食事に関する心配ごとがあれば、通院先の管理栄養士から、食べやすい食事の摂り方などを教えてもらうこともできますよ。
![]() そうなのですね、わかりました。
そうなのですね、わかりました。
2-4-5.自宅で行う内服薬の管理
![]() 薬物療法を受けるにあたって、ほかに気をつけておいたほうがよいことはあるでしょうか?
薬物療法を受けるにあたって、ほかに気をつけておいたほうがよいことはあるでしょうか?
![]() そうですね。 Tさんは点滴での抗がん剤治療となりますが、がんの薬物療法では、内服薬の抗がん剤が用いられる場合があるほか、吐き気止め(制吐薬)や鎮痛薬など、治療に伴う副作用を抑える薬が複数処方されます。もともと別の病気をもっている方であれば、服用すべき薬の種類や数はさらに多くなりますし、また、内服の抗がん剤のなかには、休薬期間が設けられている(飲む期間と飲まない期間がある)薬などもあります。そのため、在宅療養では、こうしたさまざまな種類の薬剤を適切に、患者さんご自身またはご家族でしっかり管理することが、とても重要です。
そうですね。 Tさんは点滴での抗がん剤治療となりますが、がんの薬物療法では、内服薬の抗がん剤が用いられる場合があるほか、吐き気止め(制吐薬)や鎮痛薬など、治療に伴う副作用を抑える薬が複数処方されます。もともと別の病気をもっている方であれば、服用すべき薬の種類や数はさらに多くなりますし、また、内服の抗がん剤のなかには、休薬期間が設けられている(飲む期間と飲まない期間がある)薬などもあります。そのため、在宅療養では、こうしたさまざまな種類の薬剤を適切に、患者さんご自身またはご家族でしっかり管理することが、とても重要です。
![]() なるほど。医療者が常に身近にいて管理してくれる入院とは大きく違う点ですね。
なるほど。医療者が常に身近にいて管理してくれる入院とは大きく違う点ですね。
![]() そうなんです。がんの薬物療法では、副作用の予防や対策も含めて、一人ひとりの患者さんに最適と考えられる薬剤が組み合わされて処方されているので、うっかり飲み忘れたり、自己判断で飲んだり飲まなかったり……が続くと、想定した治療効果が十分に得られなかったり、思わぬ副作用に悩まされたりなど、治療自体が成立しなくなってしまうことがあります。
そうなんです。がんの薬物療法では、副作用の予防や対策も含めて、一人ひとりの患者さんに最適と考えられる薬剤が組み合わされて処方されているので、うっかり飲み忘れたり、自己判断で飲んだり飲まなかったり……が続くと、想定した治療効果が十分に得られなかったり、思わぬ副作用に悩まされたりなど、治療自体が成立しなくなってしまうことがあります。
![]() 飲み忘れや飲み間違いを自分で防ぐ……簡単そうで、案外うっかりしてしまいそうな気がします。
飲み忘れや飲み間違いを自分で防ぐ……簡単そうで、案外うっかりしてしまいそうな気がします。
![]() そうですね。そこで、ご自宅でできる服薬管理のポイントとして、次のような工夫をしてみるとよいと思います。
そうですね。そこで、ご自宅でできる服薬管理のポイントとして、次のような工夫をしてみるとよいと思います。
自宅でできる服薬管理の工夫
1 服薬する薬の種類とタイミングの把握
まずは、処方された薬剤について、それぞれの1回量、服用のタイミング、服用にあたっての注意事項を、薬袋に書かれた内容や添付された説明書などで確認し、何をいつ飲まなければいけないか、全体のスケジュールを把握しましょう。
2 服薬予定表や服薬カレンダーの活用
病院や調剤薬局で、すべての薬剤の服薬予定を記した一覧表などを用意してくれる場合もあります。また、その日に飲む薬剤を1日ごとに分けて入れておける袋のついた、壁掛け型の「服薬カレンダー」や、1回に服用する薬剤を小分けに入れておける「ピルケース」なども市販されています。こうした服薬管理グッズを活用するのも、飲み間違いや飲み忘れを防ぐよい方法です。
3 服薬支援アプリや服薬手帳を活用する
スマートフォンを利用している方は、服用時間になるとアラートなどで知らせてくれる機能がついたアプリなどを使用するのもよい方法です。服薬時の体調や気になる症状などを記入できる機能がついたものもあります。もちろん、これらを「服薬手帳」のようなかたちで、手帳やノートに記録しておくのもよいでしょう。記録を残しておくと、通院時に医師や薬剤師に服薬状況や症状の有無などを伝えやすくなるというメリットもあります。また、製薬会社が、薬を使う方向けに作成しているパンフレットや手帳などを使うのもよいでしょう。
4 家族が共同で確認できるような工夫も
書き込みのできる大きめのカレンダーを用意して、目につきやすい壁などに貼り、朝・昼・晩と、飲んだら線を引くなどの工夫は、ご家族が協力して飲み忘れを防ぐのに役立ちます。「お薬飲んだ?」などの声かけも、ご本人の気づきや励みにつながります。
5 調剤薬局の「在宅訪問薬剤管理指導」を利用する
在宅療養で、通院が難しくなった場合などでは、処方医の指示に基づいて、調剤薬局の薬剤師が自宅を訪問して薬剤を届けてくれたり、服薬状況の確認、服用についてのアドバイスなどを受けられるサービスを利用することもできます。
6 そのほか、わからないことは薬剤師に相談する
病院の薬剤師、調剤薬局の薬剤師は、薬の管理や使い方、副作用が起こったときの対応について相談にのってくれます。不安や心配ごと、疑問があれば遠慮なく尋ねてみましょう。
2-4-6.医療用麻薬の保管と管理
![]() それから、 Tさんは今のところ使用する予定になっていませんが、がんそのものによって生じる痛みを抑える鎮痛薬として、「医療用麻薬」が用いられることがあります。
それから、 Tさんは今のところ使用する予定になっていませんが、がんそのものによって生じる痛みを抑える鎮痛薬として、「医療用麻薬」が用いられることがあります。
![]() 麻薬……ですか??
麻薬……ですか??
![]() 名前を聞くと皆さん驚かれますが、さまざまな症状のなかでも、「痛み」は生活の質(QOL)に大きく影響を及ぼす症状なので、がんの進行度に関係なく、痛みの強さや程度に応じて、さまざまな鎮痛薬とともに、医療用麻薬も広く使われているんですよ(第6章6-3-1.参照)。
名前を聞くと皆さん驚かれますが、さまざまな症状のなかでも、「痛み」は生活の質(QOL)に大きく影響を及ぼす症状なので、がんの進行度に関係なく、痛みの強さや程度に応じて、さまざまな鎮痛薬とともに、医療用麻薬も広く使われているんですよ(第6章6-3-1.参照)。
![]() 病院内だけでなく、在宅療養でも使われるのですか?
病院内だけでなく、在宅療養でも使われるのですか?
![]() はい、在宅療養の場でも、医師が必要と判断した場合には、適切な管理のもとに処方され、安全に使用されています。ですが、ほかの薬剤と異なり、「麻薬及び向精神薬取締法」に則った扱いが必要です。処方を受けた際には、特に次のことに注意して管理・保管するようにしてくださいね。
はい、在宅療養の場でも、医師が必要と判断した場合には、適切な管理のもとに処方され、安全に使用されています。ですが、ほかの薬剤と異なり、「麻薬及び向精神薬取締法」に則った扱いが必要です。処方を受けた際には、特に次のことに注意して管理・保管するようにしてくださいね。

医療用麻薬の適切な管理方法
- 他人に転用したり、譲り渡したりしないでください。
- 人目につきにくく、子どもやペットなどの手の届かない場所、かつ、ほかのものと間違って使用しないよう、扉の閉まる棚などに、ほかのものと区別して保管しましょう
- 製剤の安定性を考慮し、直射日光を避けて保管しましょう。
- 薬があまったり、不要になった場合には、交付を受けた病院または調剤薬局に返却しましょう。
![]() わかりました。家族にも伝えておこうと思います。
わかりました。家族にも伝えておこうと思います。