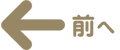2-6.手術療法前後の在宅療養
近年、がんの手術療法も大きく進歩しています。以前であれば手術が難しかったがんも、薬物療法や放射線療法と組み合わせることで手術できるようになったり、小さな術創で済む「鏡視下手術」や、人の手で処置を施すことが難しかった部位にもアプローチできる「ロボット支援下手術」も積極的に行われるようになり、より体に負担の少ない、術後の生活の質(QOL) を重視した治療が行われるようになりました。こうした進歩を背景に、手術療法においても数日~10日程度と短い入院期間で治療を受け、術後の時間を自宅で療養される方が増えています。
![]() 私の場合、薬物療法でがんを小さくしてから、手術でがんを取り除く……という治療の順番になっているのですが、これまでの人生で入院なんてしたことがないですし、それに、短期間とはいえ、入院中の仕事や子どものことも気がかりで……。手術が無事に終わったとして、自分の体がどんな状態になるのか、まだイメージもつきませんし……。考えると次々不安が出てきて、頭が混乱してしまいます。
私の場合、薬物療法でがんを小さくしてから、手術でがんを取り除く……という治療の順番になっているのですが、これまでの人生で入院なんてしたことがないですし、それに、短期間とはいえ、入院中の仕事や子どものことも気がかりで……。手術が無事に終わったとして、自分の体がどんな状態になるのか、まだイメージもつきませんし……。考えると次々不安が出てきて、頭が混乱してしまいます。
![]() お気持ちはとてもよくわかります。多くの患者さんやご家族が、そのようにおっしゃいます。がんの治療は長丁場です。あまり根詰めて考えすぎても息切れしてしまいますから、今思い浮かぶ心配ごとや不安から、少しずつ解消していけるように整理してみましょう。
お気持ちはとてもよくわかります。多くの患者さんやご家族が、そのようにおっしゃいます。がんの治療は長丁場です。あまり根詰めて考えすぎても息切れしてしまいますから、今思い浮かぶ心配ごとや不安から、少しずつ解消していけるように整理してみましょう。
![]() はい。一緒に考えてくださる方がいると心強いです。
はい。一緒に考えてくださる方がいると心強いです。
![]() そうですね。ご家族や親しい人たちも、きっとあなたの力になりたいと思っているはずですから、治療に関わることでも生活に関わることでも、今ある不安や課題を共有して、みんなで乗り越えていけるとよいですね。
そうですね。ご家族や親しい人たちも、きっとあなたの力になりたいと思っているはずですから、治療に関わることでも生活に関わることでも、今ある不安や課題を共有して、みんなで乗り越えていけるとよいですね。
2-6-1.手術前の備え
![]() まず、手術のための入院についてですが、最近は、手術の詳しい説明は入院前に外来で行われることが多く、実際に入院するのは、手術日の前日~数日前であることが多いようです。入院中の生活や、術前・術後の注意点については、担当医や担当看護師から必ず事前に説明がありますから、安心してください。指示のあったこと以外は、特別な用意は基本的に必要ありませんよ。
まず、手術のための入院についてですが、最近は、手術の詳しい説明は入院前に外来で行われることが多く、実際に入院するのは、手術日の前日~数日前であることが多いようです。入院中の生活や、術前・術後の注意点については、担当医や担当看護師から必ず事前に説明がありますから、安心してください。指示のあったこと以外は、特別な用意は基本的に必要ありませんよ。
![]() とは言っても、手術に備えて何か事前に自分にできることはないのでしょうか。
とは言っても、手術に備えて何か事前に自分にできることはないのでしょうか。
![]() 喫煙習慣があると、手術時に麻酔が効きにくかったり、術後に肺炎などの合併症を起こしやすくなるため禁煙していただきたいのですが、Tさんはもうたばこはやめていましたね。
喫煙習慣があると、手術時に麻酔が効きにくかったり、術後に肺炎などの合併症を起こしやすくなるため禁煙していただきたいのですが、Tさんはもうたばこはやめていましたね。
![]() はい。今はもう吸っていません。
はい。今はもう吸っていません。
![]() それから、もし、血液を固まりにくくするお薬を服用しているなら、数日前から別の薬に切り替えたり、あらかじめ中断するように説明があることがあります。手術の際の出血の増加を防ぐためです。このほかにも、もし服用している薬やサプリメント、健康食品などがあれば、事前に担当医に伝えるようにしましょう。
それから、もし、血液を固まりにくくするお薬を服用しているなら、数日前から別の薬に切り替えたり、あらかじめ中断するように説明があることがあります。手術の際の出血の増加を防ぐためです。このほかにも、もし服用している薬やサプリメント、健康食品などがあれば、事前に担当医に伝えるようにしましょう。
![]() 私は今は特にありません。
私は今は特にありません。
![]() そうであれば、あとは手術に備えて体力を落とさないように、軽い運動やバランスのよい食事、睡眠など、日常生活のなかで、できる範囲で体調を整えておくことで大丈夫です。
そうであれば、あとは手術に備えて体力を落とさないように、軽い運動やバランスのよい食事、睡眠など、日常生活のなかで、できる範囲で体調を整えておくことで大丈夫です。
![]() それなら特別なことではないので、自分にもできそうです。
それなら特別なことではないので、自分にもできそうです。
![]() それならよかったです。また、生活の備えとして、入院中や、退院後もしばらくの間は、手術前とまったく同じように動くのは難しい場合も多いので、家事やお子さんのお世話の分担などは、早めにご家族内で相談しておくとよいと思います。実家のご両親やきょうだい、頼れるご近所の方、ご友人など、信頼できる人の手を借りることもぜひ考えてください。
それならよかったです。また、生活の備えとして、入院中や、退院後もしばらくの間は、手術前とまったく同じように動くのは難しい場合も多いので、家事やお子さんのお世話の分担などは、早めにご家族内で相談しておくとよいと思います。実家のご両親やきょうだい、頼れるご近所の方、ご友人など、信頼できる人の手を借りることもぜひ考えてください。
![]() 夫は、自分ががんばると言ってくれましたが、隣の市に住んでいる妹や、仲良しのママ友にも、子どもの送り迎えなどのサポートをお願いできるか聞いてみたいと思います。
夫は、自分ががんばると言ってくれましたが、隣の市に住んでいる妹や、仲良しのママ友にも、子どもの送り迎えなどのサポートをお願いできるか聞いてみたいと思います。
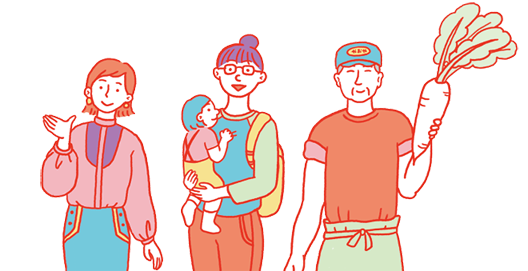
![]() そうですね。もし、ご家族や周囲の人では手が足りなそうであれば、廉価で子どもの送迎などを代行してくれる、自治体の子育て支援のサービスを検討してみるのも手です。お住まいの市区町村窓口に相談すると、ほかにも利用できるサービスを教えてくれると思います。家事代行や宅食、ベビーシッターなど、民間のサービスもありますから、いざというときには頼れるように、インターネットなどで調べておくとよいですね。
そうですね。もし、ご家族や周囲の人では手が足りなそうであれば、廉価で子どもの送迎などを代行してくれる、自治体の子育て支援のサービスを検討してみるのも手です。お住まいの市区町村窓口に相談すると、ほかにも利用できるサービスを教えてくれると思います。家事代行や宅食、ベビーシッターなど、民間のサービスもありますから、いざというときには頼れるように、インターネットなどで調べておくとよいですね。
![]() いくつか手段を考えておくと、安心できそうです。
いくつか手段を考えておくと、安心できそうです。
![]() それと、もし余裕があったらですが、入院時に持っていくと役立つグッズなどを、入院前説明のときなどに、看護師さんに聞いておくとよいかもしれません。入院中に必要になる物品のリストは、多くの病院で事前に渡してくれますが、Tさんと同じ部位の手術を受けた人が、あってよかったと思ったグッズなどは、担当の看護師さんがよく知っていたりします。また、同じ病気や治療を経験した人からのアドバイスも参考になることがあります。時間があれば、患者会・患者団体の集まりやピアサポート(同じ病気や立場を経験した人による支援)などに参加してみてもよいかもしれません。
それと、もし余裕があったらですが、入院時に持っていくと役立つグッズなどを、入院前説明のときなどに、看護師さんに聞いておくとよいかもしれません。入院中に必要になる物品のリストは、多くの病院で事前に渡してくれますが、Tさんと同じ部位の手術を受けた人が、あってよかったと思ったグッズなどは、担当の看護師さんがよく知っていたりします。また、同じ病気や治療を経験した人からのアドバイスも参考になることがあります。時間があれば、患者会・患者団体の集まりやピアサポート(同じ病気や立場を経験した人による支援)などに参加してみてもよいかもしれません。
2-6-2.退院後に向けた備え
![]() 手術のあと、早く自宅に帰れるのはうれしいのですが、一方で、創口が開いちゃったらどうしようとか、強い痛みや熱が出たりしたときはどうしたらよいのか……など、入院していればすぐに担当医の先生や看護師さんに伝えられるようなことが、自宅では難しいので、その点も少し不安です。
手術のあと、早く自宅に帰れるのはうれしいのですが、一方で、創口が開いちゃったらどうしようとか、強い痛みや熱が出たりしたときはどうしたらよいのか……など、入院していればすぐに担当医の先生や看護師さんに伝えられるようなことが、自宅では難しいので、その点も少し不安です。
![]() 手術後の合併症などの心配が少なく、順調に回復していることが確認できてからの退院となります。退院後は外来で定期的な診察がありますが、気になる症状があったときに相談できる連絡先を、退院前に確認しておくと安心ですね。
手術後の合併症などの心配が少なく、順調に回復していることが確認できてからの退院となります。退院後は外来で定期的な診察がありますが、気になる症状があったときに相談できる連絡先を、退院前に確認しておくと安心ですね。
![]() 手術後は、長く安静にしているのではなく、できるだけ早く体を動かし始めるのがよいと聞きました。
手術後は、長く安静にしているのではなく、できるだけ早く体を動かし始めるのがよいと聞きました。
![]() そうですね。手術後は創の痛みやひきつれ感などがあり、体を動かしにくかったり、動かしたくない感じがしたりするかもしれませんが、安静にしすぎると、体の機能が弱ってしまい、回復に時間がかかり、合併症も生じやすくなることが知られています。動かしてよい時期や範囲などは、体の状態や手術の内容によっても異なるので、担当医や看護師からの説明をもとに積極的に動かすようにしてください。
そうですね。手術後は創の痛みやひきつれ感などがあり、体を動かしにくかったり、動かしたくない感じがしたりするかもしれませんが、安静にしすぎると、体の機能が弱ってしまい、回復に時間がかかり、合併症も生じやすくなることが知られています。動かしてよい時期や範囲などは、体の状態や手術の内容によっても異なるので、担当医や看護師からの説明をもとに積極的に動かすようにしてください。
![]() わかりました。
わかりました。
![]() 入院中と違い、自宅に帰ると、溜まっている家事や仕事のこと、お子さんのお世話など、どうしても気になって、つい無理をしてしまいがちです。ですが、治療後間もない体は、思っている以上に大きなダメージを負っていると考えて、体調が優れないときには無理をしないこと、疲れたらすぐに横になれる環境をつくっておくなど、ぜひ「がんばりすぎない」ことを大切にしてくださいね。これは、手術に限らず、ほかの治療でも同じですよ。
入院中と違い、自宅に帰ると、溜まっている家事や仕事のこと、お子さんのお世話など、どうしても気になって、つい無理をしてしまいがちです。ですが、治療後間もない体は、思っている以上に大きなダメージを負っていると考えて、体調が優れないときには無理をしないこと、疲れたらすぐに横になれる環境をつくっておくなど、ぜひ「がんばりすぎない」ことを大切にしてくださいね。これは、手術に限らず、ほかの治療でも同じですよ。
![]() なんだか Nさんには、私の行動を見透かされているみたいです……。がんばりすぎないよう、気をつけますね。
なんだか Nさんには、私の行動を見透かされているみたいです……。がんばりすぎないよう、気をつけますね。