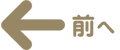3-5.経済的な側面への支援制度
Eさんの奥さんも心配していたように、特に家計を支える人に療養が必要になった場合には、経済的な側面の心配ごとも出てくるかもしれません。これらに関する支援制度についても、正しい情報を得て、使える制度を見逃さずに活用していくことで、医療費の負担を軽減したり、生活費などの補填に役立てたりすることができます。
ここでは、経済的な側面に対する代表的な制度をいくつかご紹介します。こうした制度は、本人(または代理人)の申請によって初めて利用可能になるものが多くあります。また、患者さんの状況により、ここにあがっていない制度を活用できることもあります。病院内の医療ソーシャルワーカーや、がん相談支援センターに相談しながら、支援制度をうまく活用し、負担を軽減していきましょう。以下に紹介する制度についてより詳しく知りたい場合にも、がん相談支援センターや通院している病院の医療ソーシャルワーカーなどから説明を聞くことができます。
3-5-1.医療費の負担軽減に役立つ制度
●高額療養費制度/限度額適用認定証
1か月に医療機関や薬局の窓口で支払った金額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、超過分の金額が払い戻される制度です。ただし、払い戻しまでに少なくとも3か月程度かかることから、窓口での支払い負担を減らすために、事前に「限度額適用認定証」の交付手続きを行うことで、窓口での1か月分の支払額を自己負担限度額までとすることができます。申請窓口は、いずれも加入している健康保険の相談窓口です。企業にお勤めの方は総務などの担当者に確認してみましょう。国民健康保険の加入者は市区町村の窓口に相談しましょう。
●高額医療・高額介護合算療養費制度
世帯内で同一の医療保険加入者について、8月~翌年7月までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合、超過分の払い戻しを受けられる制度です。窓口は各市区町村の介護保険担当部門や、加入している健康保険の相談窓口です。
●その他の制度
対象者は限定されますが、ほかにも次のような支援制度があります。
小児慢性特定疾病医療費助成制度
都道府県が指定する医療機関において「小児がん」と診断され、保険診療を受けた場合に利用できる医療費の助成制度です。
石綿(アスベスト)健康被害救済制度
過去に石綿を扱う業務に従事していた人が、石綿を原因とした中皮腫や肺がんなどを発病した場合に、労災補償の対象となる制度です。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭などの親子の医療費が助成される制度です。
心身障害者医療費助成制度
心身に重度の障害がある人の医療費の自己負担分の全額または一部が助成される制度です。
高額医療費貸付制度
一部の健康保険組合では、組合独自の支援制度を設けています。全国健康保険協会などでは、高額医療費貸付制度という制度を設けており、高額な医療費の支払いにあてるための費用が必要である場合に、高額療養費が支給されるまでの間、無利子で貸付してくれる仕組みがあります。
3-5-2.生活費などの補填に役立つ制度
●傷病手当金
会社員や公務員など被用者保険の被保険者が、傷病のために働けなくなったときに支給を受けられる制度です。条件などがありますので、まずは勤務先の担当者に確認してみましょう。
●老齢年金の繰り上げ受給
65歳から受給できる老齢年金を、希望により60歳から繰り上げて受け取ることができる制度です。日本年金機構のウェブサイトで詳細を確認することができます。
●障害年金
傷病によって生活や仕事などが著しく制限されるようになった人が、規定の条件を満たす場合に、現役世代の人も含めて受け取ることができる年金です。請求には医師の診断書などが必要となるため、まずは病院の医療ソーシャルワーカーや相談窓口に相談してみましょう。
●身体障害者手帳
人工肛門を造設した場合や咽頭全摘出術を受けた場合など、所定の障害の状態にあると認められた場合に、公共料金や交通機関運賃の割引、税の減免などを受けられる手帳の交付を受けることができます。窓口は各市区町村の障害福祉担当窓口です。
●雇用保険による基本手当
雇用保険の被保険者だった人が離職した場合で、働く意思があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない場合に、原則として離職した日の翌日から最大1年間支給される手当です。窓口はお住まいの区域を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。
●医療費控除(確定申告による所得税の還付)
1年間に一定以上の医療費の支払い(自己負担)があった場合に、所得控除として、納めた税金の一部が還付される制度です。毎年2月16日~3月15日までに確定申告を行うことで還付を受けることができます。窓口はお住まいの地域を管轄する税務署です。国税庁のウェブサイトでも詳細を確認できます。
●生活福祉資金貸付制度・生活保護制度
生活が困窮し、生活費の支援が必要な状況となった場合の公的制度として、社会福祉協議会による「生活福祉資金貸付制度」(生活資金の貸付)や、他の制度を利用しても生活費が捻出できない場合の国の制度「生活保護制度」などがあります。前者はお住まいの地域の社会福祉協議会、後者は福祉事務所が窓口となっています。
3-5-3.その他の制度
このほかに、個人で加入している民間の医療保険やがん保険などからの給付や、住宅ローンなどの支払い免除特約(特定の病気になったときに、以後の支払いを免除とする特約など)がないかなども、忘れずに確認するようにしましょう。学費の心配がある場合には、奨学金制度などを利用することもできます。また、第4章では「介護保険制度」についても情報を掲載しています。
●コラム 「ヘルプマーク」を知っていますか?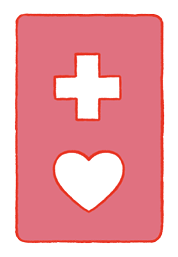 ヘルプマークとは、外見からはわからない障がいや病気、妊娠初期などで援助や配慮を必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。はじめは東京都が作成し、現在では全国の都道府県に普及し、必要な方に無料配布されています。がん治療などで体調に不安がある場合にも活用することができます。配布窓口は各自治体により異なるため、お住まいの自治体のウェブサイトなどで確認してみましょう。自治体によっては、ご自宅のプリンタ等で印刷ができるヘルプマークカードのダウンロードも可能になっています。
ヘルプマークとは、外見からはわからない障がいや病気、妊娠初期などで援助や配慮を必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。はじめは東京都が作成し、現在では全国の都道府県に普及し、必要な方に無料配布されています。がん治療などで体調に不安がある場合にも活用することができます。配布窓口は各自治体により異なるため、お住まいの自治体のウェブサイトなどで確認してみましょう。自治体によっては、ご自宅のプリンタ等で印刷ができるヘルプマークカードのダウンロードも可能になっています。