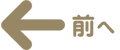3-2.職場への伝え方とコミュニケーション
仕事と治療の無理のない両立を考えるときには、家族や周囲の人に加え、職場の方の理解と協力が欠かせません。病気のことを職場に伝えずに済ませたい、と思うかもしれませんが、がん治療においては、入院や定期通院などで一時的に休暇をとったり、場合によっては休職などの手続きが必要になることもあります。また、時には治療が予定どおりに進まず、当初の予定からスケジュールを調整する必要が出てくることもあります。
そのため、職場のしかるべき人には、病状や今後の見通しを伝え、理解と協力を得ることが、結果的には職場や仕事への影響を小さくし、復帰までの道のりをスムーズにすることにつながります。
3-2-1.職場への伝え方とタイミング
![]() 仕事と治療の両立を考えたとき、まずは何をすればよいでしょうか?
仕事と治療の両立を考えたとき、まずは何をすればよいでしょうか?
![]() そうですね、診断を受けたばかりで、ここからさらに治療のための検査なども始まりますので、とても忙しい時期だと思いますが、まずは次のようなことが必要になると思います。
そうですね、診断を受けたばかりで、ここからさらに治療のための検査なども始まりますので、とても忙しい時期だと思いますが、まずは次のようなことが必要になると思います。
治療と仕事の両立に向けて、まず確認したいこと
- ご家族に、治療と仕事を両立したい意向を伝え、ご家族の意見も聞き、話し合ってみましょう。
担当医に確認
- 担当医と治療方針を決めたら、その治療を行った場合に考えられる療養のスケジュールを確認しましょう(職場に「今後の見通し」や「復帰時期の見通し」を伝えるために大切です)。
- その際、職場への伝え方や伝えるタイミングについても、担当医に相談できます。仕事の内容や仕事上のスケジュールを担当医に伝えることで、治療の時期や内容を調整できることもあります(治療効果に影響を及ぼさない範囲で、職場の繁忙期を避けて治療時期を設定したり、仕事に必要な能力に影響が出にくい薬を使ったりなどの対応が可能か、などを相談することができます)。
- 治療後に考えうる副作用や後遺症などが、現在の仕事に影響するかどうか(治療後にできなくなったり、難しくなったりすることがあるか)についても、担当医に確認しましょう。
職場での確認
- 職場の「就業規則」を確認しましょう。休暇の範囲や種類、休職制度(会社によって内容が異なる)がどうなっているか、仮に退職が必要となった場合に、有給休暇の消化方法や、退職金制度がどうなっているかなどを知ることができます(「就業規則」は、常時従業員10名以上の規模の企業には作成が義務付けられており、従業員なら誰でも見ることができます。手近になければ、人事や総務の担当者に尋ねてみましょう。10名未満の企業では「就業規則」が設けられていない場合があります。その場合には、企業側と直接相談が必要です。派遣社員の人は、まず派遣元に相談しましょう)。
- 職場では、まずは信頼できる上司や人事の担当者に、病状や見通しについて伝えましょう。
- 産業医や産業保健師がいる職場では、医学的な観点から必要な配慮などについて、会社との間に入ってもらい、業務の調整などに関するサポートや助言を得ることができます。
![]() 職場に伝えるタイミングとしては、いつ頃がよいのでしょうか。会社には、健康診断の結果から、胃の精密検査を受けることになった、というところまでは伝えています。
職場に伝えるタイミングとしては、いつ頃がよいのでしょうか。会社には、健康診断の結果から、胃の精密検査を受けることになった、というところまでは伝えています。
![]() そうですね。これから、治療が始まる前の検査などでもお休みをとったりする必要が出てくると思いますので、それによって業務に調整が必要になりそうなら、そのタイミングで今わかっていることを伝えておくとよいと思います。その後は、今後の治療スケジュールがある程度明らかになったタイミングで、治療後の見通しなどを含めて、治療が始まる前までにお話しになるとよいのではないでしょうか。
そうですね。これから、治療が始まる前の検査などでもお休みをとったりする必要が出てくると思いますので、それによって業務に調整が必要になりそうなら、そのタイミングで今わかっていることを伝えておくとよいと思います。その後は、今後の治療スケジュールがある程度明らかになったタイミングで、治療後の見通しなどを含めて、治療が始まる前までにお話しになるとよいのではないでしょうか。
![]() 病状なども細かく説明したほうがよいのでしょうか。
病状なども細かく説明したほうがよいのでしょうか。
![]() 会社側が把握したいのは、Eさんの詳細な病状というよりは、仕事への影響がどのくらいか、どのくらいの期間仕事から離れる必要があるのか、といったことですから、Eさんが話したくないことがあれば、無理に話す必要はありません。
会社側が把握したいのは、Eさんの詳細な病状というよりは、仕事への影響がどのくらいか、どのくらいの期間仕事から離れる必要があるのか、といったことですから、Eさんが話したくないことがあれば、無理に話す必要はありません。
![]() とはいえ、「がんが見つかった」と伝えたら、いろいろ聞かれそうです。
とはいえ、「がんが見つかった」と伝えたら、いろいろ聞かれそうです。
![]() そうですね。どうしても聞かれる可能性のあることは、自分のなかで「ここまでは話せる」というラインをあらかじめ想定しておくと、急に尋ねられたときなどにも、慌てないでお話ができると思います。病名や治療内容、回復の見込み、などでしょうか。
そうですね。どうしても聞かれる可能性のあることは、自分のなかで「ここまでは話せる」というラインをあらかじめ想定しておくと、急に尋ねられたときなどにも、慌てないでお話ができると思います。病名や治療内容、回復の見込み、などでしょうか。
![]() なるほど……。
なるほど……。
![]() ほかの患者さんのお話をお聞きすると、病名を伝えた相手から、よく「ステージ(病期)は?」と聞かれることがあるようです。ですが、相手が医療者でないなら、ステージを伝えて「なるほど、そういう状況か」とパッとわかる方は実はほとんどいないはずですし、ステージと働けるかどうかは直接関係のないことです。ですから、詳細な病状というよりかは、Eさんの就業や復帰に影響のあることを中心にお話しになればよいと思いますよ。
ほかの患者さんのお話をお聞きすると、病名を伝えた相手から、よく「ステージ(病期)は?」と聞かれることがあるようです。ですが、相手が医療者でないなら、ステージを伝えて「なるほど、そういう状況か」とパッとわかる方は実はほとんどいないはずですし、ステージと働けるかどうかは直接関係のないことです。ですから、詳細な病状というよりかは、Eさんの就業や復帰に影響のあることを中心にお話しになればよいと思いますよ。
3-2-2.伝えておきたいポイントとコミュニケーションのコツ
![]() わかりました。会社と話すときに、この点を伝えておくとよい、といった具体的な点はありますか?
わかりました。会社と話すときに、この点を伝えておくとよい、といった具体的な点はありますか?
![]() そうですね。具体的には、以下のようなことを話せると、会社側もEさんが不在の間や復帰後に必要な備えができるのではないでしょうか。
そうですね。具体的には、以下のようなことを話せると、会社側もEさんが不在の間や復帰後に必要な備えができるのではないでしょうか。
会社側に伝えておくとよいポイント
- 治療期間(いつから、どのくらいの期間、職場から離れる必要があるか)
- 復帰の可否、時期の見込み
- 不在期間中や復帰後に、職場側にどのような配慮が必要になるか
- 仕事に対するご自分の希望や思い、考え方
![]() 担当医からは、「今後の検査の結果を見て最終的な治療方針を決めましょう。治療の後遺症や副作用の出方などは個人差があるので、治療スケジュールはあくまで目安と思ってください」と言われました。会社にはどのように伝えれば……。
担当医からは、「今後の検査の結果を見て最終的な治療方針を決めましょう。治療の後遺症や副作用の出方などは個人差があるので、治療スケジュールはあくまで目安と思ってください」と言われました。会社にはどのように伝えれば……。
![]() 現時点での暫定的な予定であることを伝え、変更があればその都度連絡を入れることを伝えておきましょう。状況変化に応じて随時、継続的に報告していくことが大切です。やるべきことや、決めなくてはならないことがたくさんあって、とても大変な時期だと思いますが、復帰への強い意思はそのような誠実な態度からも会社側に伝わると思います。
現時点での暫定的な予定であることを伝え、変更があればその都度連絡を入れることを伝えておきましょう。状況変化に応じて随時、継続的に報告していくことが大切です。やるべきことや、決めなくてはならないことがたくさんあって、とても大変な時期だと思いますが、復帰への強い意思はそのような誠実な態度からも会社側に伝わると思います。
![]() はい。小さな会社ですが、その分、結束力は強いです。みんなに迷惑をかけるし、本当に働けるのか不安はありますが、自分がこれまで営業職で培ってきた知識や経験で、手術後にも何か少しは役に立てると思います。少し気持ちが落ち着いてきました。
はい。小さな会社ですが、その分、結束力は強いです。みんなに迷惑をかけるし、本当に働けるのか不安はありますが、自分がこれまで営業職で培ってきた知識や経験で、手術後にも何か少しは役に立てると思います。少し気持ちが落ち着いてきました。
![]() つい「できなくなること」に意識が向きがちですが、「できること」を考えてみるとよいかもしれませんね。
つい「できなくなること」に意識が向きがちですが、「できること」を考えてみるとよいかもしれませんね。
![]() うちの会社では、病気で長く職場を離れたり、復職したりした人の前例がないので、同僚や経営者の理解を得られるか心配ではありますが、最初から諦めないで、丁寧に話してみたいと思います。
うちの会社では、病気で長く職場を離れたり、復職したりした人の前例がないので、同僚や経営者の理解を得られるか心配ではありますが、最初から諦めないで、丁寧に話してみたいと思います。
![]() 病気は誰にとっても突然やってくるものですから、お互いさまです。復職後に恩返しするつもりで、今は体のことを第一に考えられるよう、会社の方と話し合いができるとよいですね。
病気は誰にとっても突然やってくるものですから、お互いさまです。復職後に恩返しするつもりで、今は体のことを第一に考えられるよう、会社の方と話し合いができるとよいですね。
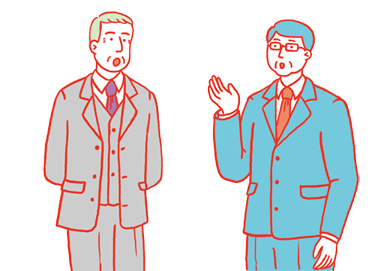
個人事業主やフリーランスの人にがんの療養が必要になったときには、会社勤めの人とはまた異なる問題が生じます。クライアントからの依頼に対して受注契約のうえで仕事をするかたちが多いことから、自身が働けない間の仕事のやりくりや収入面での厳しさは、時に企業で働く人以上となりがちです。
個人事業主の多くが加入している国民健康保険には、会社員が加入する健康保険と異なり、働けない期間の給与をカバーしてくれる傷病手当金のような公的な支援制度がありません。民間の医療保険や共済制度などを活用し、がんに限らず「働けなくなったとき」を念頭に置いた備えをしておくことや、自分が請け負った仕事を手伝ってくれる同業者のネットワークづくりなどを日頃から心がけておくことも備えになります。
がん相談支援センター(第1章「1-3.在宅療養に関する、信頼できる情報源」参照)では、個人事業主やフリーランスの方、契約社員など非正規雇用の方の相談ももちろん受け付けています。
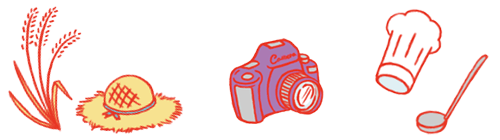
 職場への伝え方とコミュニケーション
職場への伝え方とコミュニケーション
両親のがん、配偶者のがんを経験しました。手術や治療が必要になったとき、真っ先に「できるだけそばにいたい」と思いました。しかし、私は会社員です。検査や通院、入退院時、お見舞いなどを考えると、介護休暇制度はすぐに使い切ってしまいます。家族として認められる休暇は決して多くはありません。有給休暇を合わせても、先々に不安が押し寄せ、悩んだ末に退職を視野に入れ、今の家族の病状や、できるだけそばにいたい思い、会社にも迷惑をかけたくない思い、両立できるならばできる限りがんばりたいことを正直に会社に相談しました。
結果的には、会社側からの提案により、私は仕事と介護を両立することができました。具体的には、休暇の取得は時間単位で事後申請すればよい、外出先・在宅も業務時間としてカウント、勤務時間は1週間単位で満たせばよい、などです。
権利として利用できる制度から考えるだけでなく、会社が応援してくれる可能性もあることを忘れずに、相談してよかったと思っています。