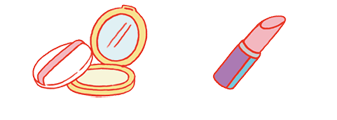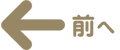7-3.最期が近づいたときの変化と対応
最期のときが近づくと、身体からサインが現れます。それはおもに意識の低下(刺激や痛みなどへの反応がなくなる)や呼吸の変化です。こうした兆候(サイン)を初めて目にする場合は、驚き、気が動転するかもしれません。それが自然な変化であることをあらかじめ知っておくと、落ち着いて向き合うことができるようになるでしょう。
7-3-1.最期のときが近づいたサイン
![]() 私も子どもたちも、人が亡くなることに立ち会った経験がありません。そのときひどく痛がったり、苦しんだりしないでしょうか。
私も子どもたちも、人が亡くなることに立ち会った経験がありません。そのときひどく痛がったり、苦しんだりしないでしょうか。
![]() 意外に思われるかもしれませんが、痛みやつらさをしっかり取り除くことで、実はがんの患者さんの最期は、多くの場合とても穏やかで、“息をひきとる”あるいは“眠る”ように、静かにお亡くなりになります。すでに在宅医から聞いていらっしゃるかもしれませんが、自然な死への過程として、無呼吸の時間が増えたり、呼吸が途切れ途切れになったり、肩やあごを動かして、あえぐような動きになったりすることがあります。このとき、苦しそうに見えるかもしれませんが、脳が徐々に低酸素状態となるためご本人は苦しく感じていません。むしろ、すべての苦痛から解放されていますので、声をかけたり手を握ったり足をやさしくさすったりしながら傍らで見守りましょう。反応することが難しくなっているだけで、ご家族の声や手のぬくもりはご本人に伝わっています。呼吸回数が減ると心拍数も減少してやがて息をひきとります。
意外に思われるかもしれませんが、痛みやつらさをしっかり取り除くことで、実はがんの患者さんの最期は、多くの場合とても穏やかで、“息をひきとる”あるいは“眠る”ように、静かにお亡くなりになります。すでに在宅医から聞いていらっしゃるかもしれませんが、自然な死への過程として、無呼吸の時間が増えたり、呼吸が途切れ途切れになったり、肩やあごを動かして、あえぐような動きになったりすることがあります。このとき、苦しそうに見えるかもしれませんが、脳が徐々に低酸素状態となるためご本人は苦しく感じていません。むしろ、すべての苦痛から解放されていますので、声をかけたり手を握ったり足をやさしくさすったりしながら傍らで見守りましょう。反応することが難しくなっているだけで、ご家族の声や手のぬくもりはご本人に伝わっています。呼吸回数が減ると心拍数も減少してやがて息をひきとります。
![]() そうなのですね。苦しくないのだとわかれば安心です。
そうなのですね。苦しくないのだとわかれば安心です。
![]() 下顎呼吸(口をパクパクさせるように動かす呼吸)が現れてから亡くなるまでは1~2時間のことが多いのですが、数日のこともあり、亡くなり方はお一人おひとりで異なります。「眠るように息をひきとる」と言うように、文字どおり、普段の生活でちょっとうたた寝をしていると思ったら、息をひきとっていらっしゃった、ということもありますが、いつもの環境のなかで、きっと安らかに最期の時間を過ごすことができたということだと思います。のどの奥のほうでゴロゴロと音がすることもあります(喘鳴)。痰がからんで苦しそうに感じますが、これもご本人は苦しく感じていません。吸引器を用いてもうまく取れないことが通常ですので、顔を横に向けるなどして見守りましょう。
下顎呼吸(口をパクパクさせるように動かす呼吸)が現れてから亡くなるまでは1~2時間のことが多いのですが、数日のこともあり、亡くなり方はお一人おひとりで異なります。「眠るように息をひきとる」と言うように、文字どおり、普段の生活でちょっとうたた寝をしていると思ったら、息をひきとっていらっしゃった、ということもありますが、いつもの環境のなかで、きっと安らかに最期の時間を過ごすことができたということだと思います。のどの奥のほうでゴロゴロと音がすることもあります(喘鳴)。痰がからんで苦しそうに感じますが、これもご本人は苦しく感じていません。吸引器を用いてもうまく取れないことが通常ですので、顔を横に向けるなどして見守りましょう。
7-3-2.在宅支援チームに連絡するタイミング
![]() 在宅医や訪問看護師さんには、どのタイミングで連絡すればよいのでしょう。
在宅医や訪問看護師さんには、どのタイミングで連絡すればよいのでしょう。
![]() 目安としては、呼吸が浅くなってきたときに連絡する方が多いのですが、実際に医師を呼ぶのは呼吸が途切れ途切れになったとき、下顎呼吸と呼ばれる、口をパクパクと動かすような呼吸が現れたとき、あるいは息をひきとったときに連絡するなどの場合があります。継続して在宅医や訪問看護師の診察を受けていれば、夜中に旅立たれた場合でも、ご家族でゆっくりお別れをし、朝になってから連絡するということもあります。在宅支援チームの看取りの方針を確認し、ご家族の希望もお伝えして、連絡するタイミングをある程度決めておくとよいと思います。あらかじめ決めたとしても、不安になったら、いつでも在宅医や訪問看護師に相談しましょう。
目安としては、呼吸が浅くなってきたときに連絡する方が多いのですが、実際に医師を呼ぶのは呼吸が途切れ途切れになったとき、下顎呼吸と呼ばれる、口をパクパクと動かすような呼吸が現れたとき、あるいは息をひきとったときに連絡するなどの場合があります。継続して在宅医や訪問看護師の診察を受けていれば、夜中に旅立たれた場合でも、ご家族でゆっくりお別れをし、朝になってから連絡するということもあります。在宅支援チームの看取りの方針を確認し、ご家族の希望もお伝えして、連絡するタイミングをある程度決めておくとよいと思います。あらかじめ決めたとしても、不安になったら、いつでも在宅医や訪問看護師に相談しましょう。
![]() 緊急事態のときや不安なときには、救急車を呼んだほうがよいのでしょうか。
緊急事態のときや不安なときには、救急車を呼んだほうがよいのでしょうか。
![]() 緊急事態と感じて、動転して救急車を呼ぼうとしてしまうかもしれませんね。でも、ここで落ち着いて考えることが大切です。自然で穏やかな在宅での看取りを決意したときの皆さんのお気持ちと、ご本人の希望を思い起こして、在宅支援チームにも連絡し、落ち着いて対応しましょう。そうすることにより、在宅での自然な看取りをすることができるのですから。救急車を呼ぶと、通常、救急隊は心臓マッサージなどの蘇生処置をしたり、警察に連絡したりすることもあり、ご本人の希望とかけはなれた状況になってしまいます。
緊急事態と感じて、動転して救急車を呼ぼうとしてしまうかもしれませんね。でも、ここで落ち着いて考えることが大切です。自然で穏やかな在宅での看取りを決意したときの皆さんのお気持ちと、ご本人の希望を思い起こして、在宅支援チームにも連絡し、落ち着いて対応しましょう。そうすることにより、在宅での自然な看取りをすることができるのですから。救急車を呼ぶと、通常、救急隊は心臓マッサージなどの蘇生処置をしたり、警察に連絡したりすることもあり、ご本人の希望とかけはなれた状況になってしまいます。
![]() そうなのですね。
そうなのですね。
![]() こうした点からも、変化があったときの連絡のタイミングや段取りは事前に在宅医や訪問看護師に確認しておくことが大切です。ご本人は心穏やかに、ご家族や親しい友人・知人に囲まれながら、最期の時間を過ごすことを希望されるかもしれません。ご臨終の瞬間に立ち会うことができないこともあるかもしれませんが、お別れのときを一緒に過ごすことが、ご本人とご家族の心の平穏につながると考えれば、必ずしも臨終の時間に間に合うということにこだわらないという考え方もあります。最期のときをともに過ごすことで、心穏やかなひとときを送ることができると思います。また、ご両親など近しいご家族・ご親戚で看取りが近くなってきていることを伝えきれていない場合は、ある程度意識がしっかりしている間に面会をしていただくと、付き添っているご家族の重荷が下りることもありますし、グリーフケア(悲嘆のケア)* にもつながるため、そのタイミングがわからない場合はぜひ担当の医療者(在宅支援チーム)と相談をしてください。
こうした点からも、変化があったときの連絡のタイミングや段取りは事前に在宅医や訪問看護師に確認しておくことが大切です。ご本人は心穏やかに、ご家族や親しい友人・知人に囲まれながら、最期の時間を過ごすことを希望されるかもしれません。ご臨終の瞬間に立ち会うことができないこともあるかもしれませんが、お別れのときを一緒に過ごすことが、ご本人とご家族の心の平穏につながると考えれば、必ずしも臨終の時間に間に合うということにこだわらないという考え方もあります。最期のときをともに過ごすことで、心穏やかなひとときを送ることができると思います。また、ご両親など近しいご家族・ご親戚で看取りが近くなってきていることを伝えきれていない場合は、ある程度意識がしっかりしている間に面会をしていただくと、付き添っているご家族の重荷が下りることもありますし、グリーフケア(悲嘆のケア)* にもつながるため、そのタイミングがわからない場合はぜひ担当の医療者(在宅支援チーム)と相談をしてください。
*グリーフケア(悲嘆のケア):第7章7-4-2.参照
7-3-3.お別れのときにできること
![]() 亡くなったときに私たちができることはなんでしょうか。
亡くなったときに私たちができることはなんでしょうか。
![]() そうですね。これまでの人生、闘病、仕事、ご家族へ向けてくれた愛情などに感謝のお気持ちを込めて、労いの言葉をかけて差し上げましょう。そして、もしベッドの背もたれが上がっていれば下ろし、ご本人を仰向けにして枕もとを整えます。目が開いていれば閉じ、はずしてあった義歯があれば口に入れます。下顎が下がって口が開いているときは、小さなタオルを丸めてあごの下に入れるか、枕を少し高くして口を閉じるようにしましょう。衣服や寝具を整え、周辺を片付けるなどして、落ち着いてお別れができるような環境を整えましょう。看護師などが立ち会っていれば手を貸してくれると思いますが、これらはご家族が行える最後のご本人へのケアですので、ご家族が声をかけたり、さすったりしながら無理なく可能な範囲で行っていただけるとよいと思います。
そうですね。これまでの人生、闘病、仕事、ご家族へ向けてくれた愛情などに感謝のお気持ちを込めて、労いの言葉をかけて差し上げましょう。そして、もしベッドの背もたれが上がっていれば下ろし、ご本人を仰向けにして枕もとを整えます。目が開いていれば閉じ、はずしてあった義歯があれば口に入れます。下顎が下がって口が開いているときは、小さなタオルを丸めてあごの下に入れるか、枕を少し高くして口を閉じるようにしましょう。衣服や寝具を整え、周辺を片付けるなどして、落ち着いてお別れができるような環境を整えましょう。看護師などが立ち会っていれば手を貸してくれると思いますが、これらはご家族が行える最後のご本人へのケアですので、ご家族が声をかけたり、さすったりしながら無理なく可能な範囲で行っていただけるとよいと思います。
![]() 亡くなったあとは、どうしたらよいのでしょうか。
亡くなったあとは、どうしたらよいのでしょうか。
![]() 最初に必要なことは、医師にご本人の死亡を確認してもらい、死亡診断書を書いてもらうことです。ご家族だけで看取られた場合でも、在宅医、訪問看護師に連絡し、亡くなられた時刻をお伝えしましょう。継続して在宅医の診察を受けていて、病気の経過による死であることが明らかであれば、警察が入ることはありません。
最初に必要なことは、医師にご本人の死亡を確認してもらい、死亡診断書を書いてもらうことです。ご家族だけで看取られた場合でも、在宅医、訪問看護師に連絡し、亡くなられた時刻をお伝えしましょう。継続して在宅医の診察を受けていて、病気の経過による死であることが明らかであれば、警察が入ることはありません。
![]() わかりました。
わかりました。
![]() その後、看護師などと一緒に、ご本人の体をきれいにし、着替えをします。ご家族の手で行うとご本人が喜ばれるかもしれませんね。タオルと温かいお湯を準備して全身を拭き、希望があれば洗髪し、ひげそり、顔そりなどをします。旅支度として、ご本人が好きだった服装やご家族が望む服装に着替えます。着物や白装束にこだわる必要はありません。今は、口や耳などに脱脂綿を入れることもほとんどありません。床ずれ(褥瘡)や傷、ストーマ(人工肛門)などがある場合には、看護師に手当の方法を相談しましょう。整髪し、お化粧をして、ご希望があれば胸の上で手を組みます。これらのケアを葬儀会社が行うこともあります。
その後、看護師などと一緒に、ご本人の体をきれいにし、着替えをします。ご家族の手で行うとご本人が喜ばれるかもしれませんね。タオルと温かいお湯を準備して全身を拭き、希望があれば洗髪し、ひげそり、顔そりなどをします。旅支度として、ご本人が好きだった服装やご家族が望む服装に着替えます。着物や白装束にこだわる必要はありません。今は、口や耳などに脱脂綿を入れることもほとんどありません。床ずれ(褥瘡)や傷、ストーマ(人工肛門)などがある場合には、看護師に手当の方法を相談しましょう。整髪し、お化粧をして、ご希望があれば胸の上で手を組みます。これらのケアを葬儀会社が行うこともあります。
7-3-4.葬儀会社に連絡するタイミング
![]() 葬儀会社には、いつ連絡をしたらよいのですか?
葬儀会社には、いつ連絡をしたらよいのですか?
![]() 医師に死亡診断書を書いてもらったあとに連絡するのが一般的です。葬儀会社の方は、死亡診断書があるかどうかをご家族に尋ねます。死亡診断書が手元にまだない状況でも、葬儀の段取りなどの打ち合わせだけでも行う場合があります。医師や葬儀会社に確認しましょう。葬儀会社の方は、死亡診断書を確認したあとに、ご本人のお体を移動したり、お着替えをしたりできるようになります。葬儀は、ご本人が旅立たれたあと、遺されたご家族が歩み出していくために必要な儀式とも言えます。予算と相談をしながら、無理のない範囲で準備を進めましょう。
医師に死亡診断書を書いてもらったあとに連絡するのが一般的です。葬儀会社の方は、死亡診断書があるかどうかをご家族に尋ねます。死亡診断書が手元にまだない状況でも、葬儀の段取りなどの打ち合わせだけでも行う場合があります。医師や葬儀会社に確認しましょう。葬儀会社の方は、死亡診断書を確認したあとに、ご本人のお体を移動したり、お着替えをしたりできるようになります。葬儀は、ご本人が旅立たれたあと、遺されたご家族が歩み出していくために必要な儀式とも言えます。予算と相談をしながら、無理のない範囲で準備を進めましょう。
あらかじめ状態の変化について耳にしていても、急激な身体の変化を目の当たりにして動転してしまい、落ち着いた環境で看取りの時間を過ごせないということはよくあります。ご本人とご家族が心穏やかに過ごせることが、この時期には一番大切なことです。在宅医や訪問看護師から、臨終に際してどのような変化が起こるのかについて聞いておいたり、立ち会うほかの家族や親族とも共有しておくと、落ち着いて穏やかな時間を過ごすことができるでしょう。
予期しないことが起こる可能性もあることを知っておく
がんの患者さんの多くは、たいていの場合、穏やかな最期のときを迎えます。しかし、体が衰弱した時期には急に具合が悪くなったりするなど、予期しないことも起こりえるため、こうした可能性を念頭に置いておくことも必要です。たとえば、急な出血や息苦しさ、けいれんや意識の低下などです。在宅医や訪問看護師に連絡して、いつから、どのような症状があるのか、意識はどうかなどを伝えたうえで、今後どのように対処すればよいかについて説明を受けましょう。
病状について、予測できる範囲の出来事であれば、今後なんらかの処置や対応が必要であるか、医療機関を受診したほうがよいかなど、確認しておくとよいでしょう。ご本人が安心できるよう誰かが傍らにいて、楽な姿勢をとらせたりしてあげながら在宅医や訪問看護師などのスタッフを待って、診察を受けることもあります。
 在宅療養のご褒美は、孫娘が施したエンゼルメイク
在宅療養のご褒美は、孫娘が施したエンゼルメイク
85歳の母は、肺がんで亡くなりました。私と孫3人で手をつなぎ合い見守るなか、静かに息をひきとりました。息が止まった時間を先生に連絡すると、間もなく到着し死亡確認をしてくださって、看護師さんと一緒に洗髪し、身体を拭き、大好きだった訪問着に着替えました。そして、看護師さんの勧めで20歳代の孫娘が死化粧を行うことになりました。
眉毛を整え、ファンデーションをきれいに塗り、アイライン、チーク、口紅と進めていくと、母が生き生きと蘇ったようになりました。肺がんとわかってから、血色も悪くつらそうだったけれど、最期のお別れの顔を見るたびにすべての苦痛が吹き飛んでいったように感じました。父のときは、病院で亡くなり、家族は病室の外でケアが終わるのを待っていました。在宅で、亡くなったあとのケアを家族が一緒にすることで、こんな素敵なプレゼントが待っていました。