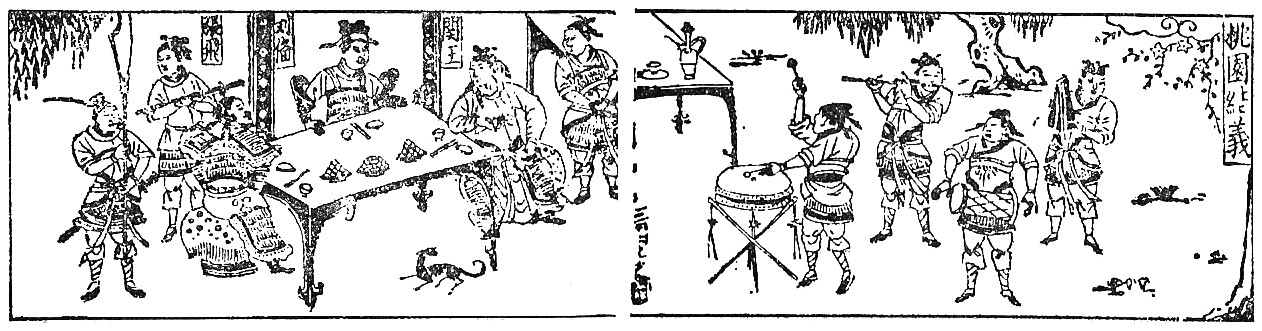厥
- 医経
- by shenquzhai
- 2006/04/26
厥というのはやっぱりよく分からない。
一般的な辞書を引いても、虚詞として「その」とか「すなわち」とかの他は、動詞として「岩を掘る」とか「頭をさげてぬかづく」とか、名詞として「石」とかくらいで、そして唐突に中医の術語として「卒倒」とか「手足の冷え」とかが有る。頭をさげすぎてつんのめるのから卒倒まではほんの一歩かも知れないけれど、『素問』や『霊枢』に出てくる厥を理解するには、これではちょっと足りないだろう。
古医書の訓詁に即して言えば、むしろ「厥は逆なり」であって、辞書の知識から言えば「蹶」(つまづく)の本字であるというのが良いのではないか。では何が何に逆し、つまづくのか。
『霊枢』厥病篇の頭痛と心痛の厥と真から推し量れば、真は頭脳や心臓の損壊であり、厥は機能障碍であろう。厥頭痛や厥心痛なら、経脈の末端近くを取って治療できると言うのだから、機能の障碍が経脈を変動させ、末端近くのポイントに異常を発生して、だから翻って、ポイントの異常を是正すれば、その情報は経脈の変動を治め、機能の障碍を改善する、という理屈になる。モノ自体が壊れているわけではないから、そうしたことが期待できるわけだ。情報伝達物質としての気が伝達経路としての経脈上でつまづいている。
『霊枢』経脈篇の是動病に、肺手太陰は臂厥、胃足陽明は骭厥、心手少陰は臂厥、足太陽は踝厥、腎足少陰は骨厥、足少陽は陽厥とある。是動病は経脈説を発想する起点となったポイントの主治病症である。躯幹に発生した病症が、先のほうの経脈上に気のつまづきを生む。心肺の病症では上肢に起こし、胃の病症ではスネに起こし、背中に関わる病症では踝に起こし、腎の病症では深部の骨に起こす。足少陽の陽厥は少し毛色が変わっていて、ぴったりの言い回しを思いつかないが、考え方としてはこれらに倣うべきだろう。
身体は経脈によって縦横に連絡されていると認識され、疾病はいずれもその連絡の齟齬を伴っていると考えるようになれば、肉体という物質そのものの損壊によるものではない限り、病苦は全て「経脈上の気のつまづき」と表現することができる。『素問』、『霊枢』において病症を説明するのに最も多く用いられる文字であるのも当然であろう。我々、経脈説を奉じるものの観点から言えば、広義の厥は病と言うのとほとんど同じである。そして、つまづきが最も顕著な症状であるところの卒倒とか手足の冷えを、その狭義とする。
一般的な辞書を引いても、虚詞として「その」とか「すなわち」とかの他は、動詞として「岩を掘る」とか「頭をさげてぬかづく」とか、名詞として「石」とかくらいで、そして唐突に中医の術語として「卒倒」とか「手足の冷え」とかが有る。頭をさげすぎてつんのめるのから卒倒まではほんの一歩かも知れないけれど、『素問』や『霊枢』に出てくる厥を理解するには、これではちょっと足りないだろう。
古医書の訓詁に即して言えば、むしろ「厥は逆なり」であって、辞書の知識から言えば「蹶」(つまづく)の本字であるというのが良いのではないか。では何が何に逆し、つまづくのか。
『霊枢』厥病篇の頭痛と心痛の厥と真から推し量れば、真は頭脳や心臓の損壊であり、厥は機能障碍であろう。厥頭痛や厥心痛なら、経脈の末端近くを取って治療できると言うのだから、機能の障碍が経脈を変動させ、末端近くのポイントに異常を発生して、だから翻って、ポイントの異常を是正すれば、その情報は経脈の変動を治め、機能の障碍を改善する、という理屈になる。モノ自体が壊れているわけではないから、そうしたことが期待できるわけだ。情報伝達物質としての気が伝達経路としての経脈上でつまづいている。
『霊枢』経脈篇の是動病に、肺手太陰は臂厥、胃足陽明は骭厥、心手少陰は臂厥、足太陽は踝厥、腎足少陰は骨厥、足少陽は陽厥とある。是動病は経脈説を発想する起点となったポイントの主治病症である。躯幹に発生した病症が、先のほうの経脈上に気のつまづきを生む。心肺の病症では上肢に起こし、胃の病症ではスネに起こし、背中に関わる病症では踝に起こし、腎の病症では深部の骨に起こす。足少陽の陽厥は少し毛色が変わっていて、ぴったりの言い回しを思いつかないが、考え方としてはこれらに倣うべきだろう。
身体は経脈によって縦横に連絡されていると認識され、疾病はいずれもその連絡の齟齬を伴っていると考えるようになれば、肉体という物質そのものの損壊によるものではない限り、病苦は全て「経脈上の気のつまづき」と表現することができる。『素問』、『霊枢』において病症を説明するのに最も多く用いられる文字であるのも当然であろう。我々、経脈説を奉じるものの観点から言えば、広義の厥は病と言うのとほとんど同じである。そして、つまづきが最も顕著な症状であるところの卒倒とか手足の冷えを、その狭義とする。
 むかし、まだ原塾を始めたばかりの頃、島田先生らが、多分、東洋学術出版社の山本社長の先導で、中国各地の中医学院を訪問したことが有った。そのとき創刊したばかりの『塾報』を持ってまわって、学術交流を提案してみえた。まもなく天津中医学院から交流の打診があって、そのころ、郭靄春教授の『黄帝内経素問校注語訳』が仲間内で評判になっていたことも有って、飛びつくようにして行ってきました。一九八五年の十一月のことです。図はその時の記念品のバッチです。当時、無理矢理コピー機で採った画像が残ってました。本当は赤を主体としてます。何かの交流会の使い回しだと思うけれど、裏の刻印は新しくしたあったように記憶しています。これが「岐黄」の文字が入ったモノの初めです。
むかし、まだ原塾を始めたばかりの頃、島田先生らが、多分、東洋学術出版社の山本社長の先導で、中国各地の中医学院を訪問したことが有った。そのとき創刊したばかりの『塾報』を持ってまわって、学術交流を提案してみえた。まもなく天津中医学院から交流の打診があって、そのころ、郭靄春教授の『黄帝内経素問校注語訳』が仲間内で評判になっていたことも有って、飛びつくようにして行ってきました。一九八五年の十一月のことです。図はその時の記念品のバッチです。当時、無理矢理コピー機で採った画像が残ってました。本当は赤を主体としてます。何かの交流会の使い回しだと思うけれど、裏の刻印は新しくしたあったように記憶しています。これが「岐黄」の文字が入ったモノの初めです。 上海に居たときには、いくつもの印を刻ってもらいました。大体は豫園の集雲閣か南京路の朶雲軒で、別に書法の趣味が有るわけじゃないから、ほとんどは蔵書印ですが、いくつかはお遊びです。「神麹斎」の他に、「蔭軒」とか「無齋」とか。「無齋」は友人に進呈してしまったけれど、篆書でこの二字を横に並べると実に良い感じになっていた。「岐黄」はどういうつもりだったか覚えてないが、瑪瑙の印材を見つけて適当な文字を選んだんだろう。無論、岐伯と黄帝なんだけど、考えてみると「岐阜の黄帝」でもある。
上海に居たときには、いくつもの印を刻ってもらいました。大体は豫園の集雲閣か南京路の朶雲軒で、別に書法の趣味が有るわけじゃないから、ほとんどは蔵書印ですが、いくつかはお遊びです。「神麹斎」の他に、「蔭軒」とか「無齋」とか。「無齋」は友人に進呈してしまったけれど、篆書でこの二字を横に並べると実に良い感じになっていた。「岐黄」はどういうつもりだったか覚えてないが、瑪瑙の印材を見つけて適当な文字を選んだんだろう。無論、岐伯と黄帝なんだけど、考えてみると「岐阜の黄帝」でもある。 晋の畢卓が、「一手に蟹螯を持ち、一手に酒盃を持ちて、酒池中に拍浮すれば、一生を了るにたる」と云ったと『世説新語』に載っていて、天晴れ酒飲みの蟹好きの名言と思っていたけれど、『酒牌』の解説によると、『晋書』の畢卓の伝には「得酒滿數百斛船,四時甘味置兩頭,右手持酒杯,左手持蟹螯,拍浮酒船中,便足了一生矣。」とあるらしい。「右手に酒杯を持ち」なんですね。
晋の畢卓が、「一手に蟹螯を持ち、一手に酒盃を持ちて、酒池中に拍浮すれば、一生を了るにたる」と云ったと『世説新語』に載っていて、天晴れ酒飲みの蟹好きの名言と思っていたけれど、『酒牌』の解説によると、『晋書』の畢卓の伝には「得酒滿數百斛船,四時甘味置兩頭,右手持酒杯,左手持蟹螯,拍浮酒船中,便足了一生矣。」とあるらしい。「右手に酒杯を持ち」なんですね。 海漫漫
海漫漫