「19世紀の生理学と痛み」
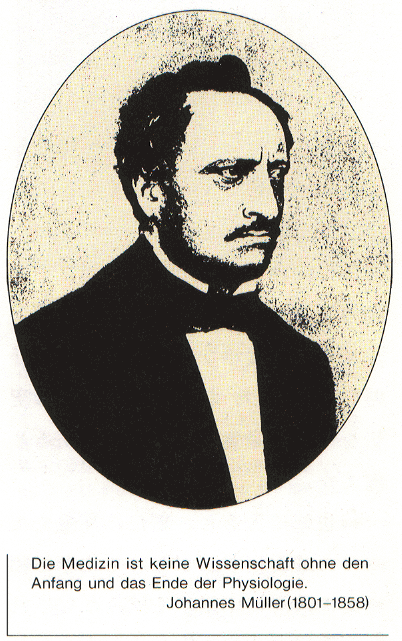 19世紀初期の神経生理学的概念の発展の第1は、ベルとマジャンデイによってなされた発見である。脊髄前根は、骨格筋を収縮させるインパルスを脊髄から末梢へ伝える運動神経からなり、後根は逆に末梢からのインパルスを脊髄へ伝える感覚神経からなるというものである。この法則の発見によって、感覚機能のみをもった末梢神経の存在が確固とした基盤にたって認識されるようになった。
19世紀初期の神経生理学的概念の発展の第1は、ベルとマジャンデイによってなされた発見である。脊髄前根は、骨格筋を収縮させるインパルスを脊髄から末梢へ伝える運動神経からなり、後根は逆に末梢からのインパルスを脊髄へ伝える感覚神経からなるというものである。この法則の発見によって、感覚機能のみをもった末梢神経の存在が確固とした基盤にたって認識されるようになった。
同じ頃、ミュラーは、特殊エネルギーの法則という概念に到達した。それは、ある男が夜、森の中を歩いていたところ、突然別の男に襲われ、それが彼の政敵であったとして、告訴したことにはじまる。裁判官が、彼の政敵であったことがどうして判ったかと尋問したところ、撲られた瞬間、目から光が出て、相手の顔がみえたと答えた。それが大問題となって、果して眼から光が出て相手の顔がみえるだろうかという疑問の解決をせまられることになった。たまたまベルリン大学の教授であったミューラーがそれを調査する委員会のメンバーの一人として参加することになった。その結果、眼から出た光によって相手の顔がみえるというのは誤りであること、また顔を撲られて眼から光が出たというのは、視神経が興奮したためであること、つまり、視神経の興奮は、光以外の刺激によっても起こりうるが、その場合にも光を感じることなどが結論された。その結果、感覚の種類の差は刺激に反応する感覚神経の差によって決められるという法則に到達したわけである。そしてミューラーは痛みをおこすのに役立つ感覚神経があると書き、痛みを独立した感覚とみなす立場、すなわち特殊説の立場をとった。その後フォン・フライが皮膚の痛点を発見して、特殊説をさらに発展させた。
このような考えに対して、古くからある別の考えを主張し続ける学者もあった。ある人たちは、アリストテレス以来の伝統に從がって、痛みを快感に相対する情動とみる説を主張し続けた。他の人たちは、すべての感覚が過度に強まると痛みになると主張した。この説を強度説と呼んでいる。
実験心理学の創始者とされるヴントは強度説の立場をとり、痛みの受容器は、熱、寒冷、触刺激などの受容器と同じであると主張した。これらの受容器からきたインパルスの強さが中等度のときには、温度感覚や触覚をおこす脊髄内上行性伝導路が興奮し、末梢受容器からのインパルスが過度に増強すると、痛みをおこす脊髄内上行性伝導路が興奮すると考えた。この考えによると、感覚の分化が末梢ではなく脊髄内でおこるということになる。フォン・フライの弟子のゴールドシャイダーがこの強度説を強く主張し、師弟で相争うことになった。痛みを快感に相対する情動とみなし、感覚の側面を否定する考えは次第にその力を失っていったが、特殊説と強度説の対立は長く続き、20世紀後半にまでおよんだ。 |
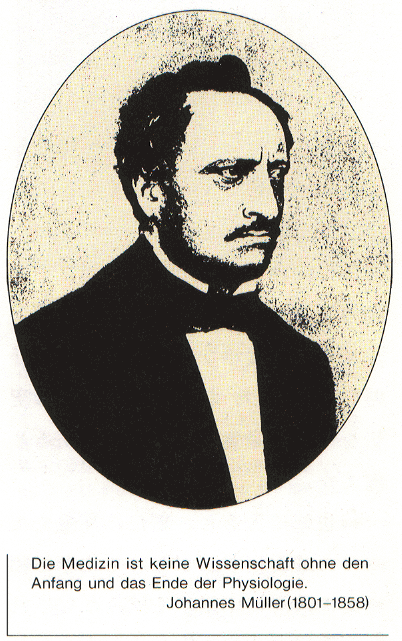 19世紀初期の神経生理学的概念の発展の第1は、ベルとマジャンデイによってなされた発見である。脊髄前根は、骨格筋を収縮させるインパルスを脊髄から末梢へ伝える運動神経からなり、後根は逆に末梢からのインパルスを脊髄へ伝える感覚神経からなるというものである。この法則の発見によって、感覚機能のみをもった末梢神経の存在が確固とした基盤にたって認識されるようになった。
19世紀初期の神経生理学的概念の発展の第1は、ベルとマジャンデイによってなされた発見である。脊髄前根は、骨格筋を収縮させるインパルスを脊髄から末梢へ伝える運動神経からなり、後根は逆に末梢からのインパルスを脊髄へ伝える感覚神経からなるというものである。この法則の発見によって、感覚機能のみをもった末梢神経の存在が確固とした基盤にたって認識されるようになった。