| 痛みの世界史 連載6 → |
|
1991.1-5 |
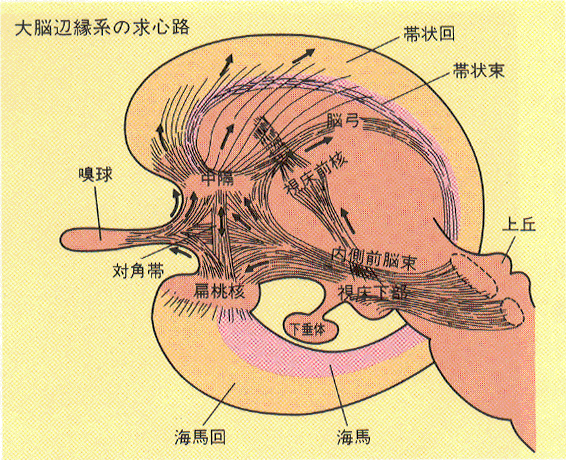 古くから「病気は天が人類に課した実験である」と言われてきた。焦点性てんかんの臨床症状を詳しく観察して、運動中枢の概念に到達したジャックリンは、「病気による神経系の実験の結果を目撃するのは医師だけであり、彼らは心の心理学に関する知識を今後ますます手中にすると期待される」と述べている。
古くから「病気は天が人類に課した実験である」と言われてきた。焦点性てんかんの臨床症状を詳しく観察して、運動中枢の概念に到達したジャックリンは、「病気による神経系の実験の結果を目撃するのは医師だけであり、彼らは心の心理学に関する知識を今後ますます手中にすると期待される」と述べている。てんかんの大発作の直前に短時間だけ現れる異常状態ないし異常体験を前兆と呼んでいる。前兆のときにはまだ意識が保たれており、後から追想することができる。前兆の内容は多彩で、精神発作が前兆として現れることもある。ドストエフスキーの場合がそれであった。彼は、そのときの体験を自己の作品に中で「幸せ・・それはあまりにも強く、しかも甘美で、この喜びの2,3秒間を生涯の10年と取りかえてもよい」と記している。
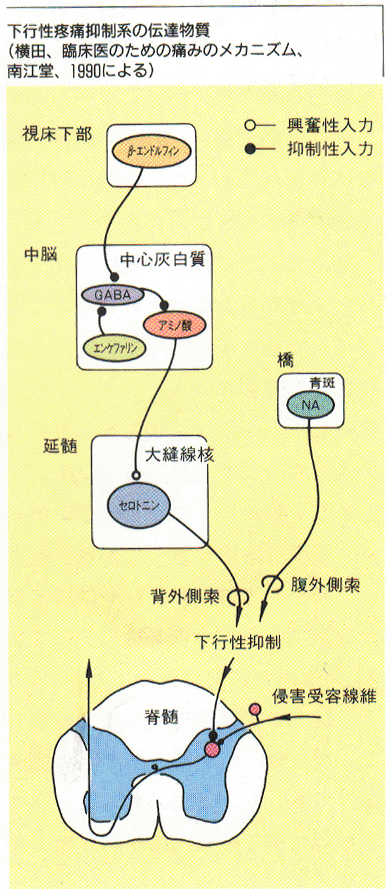 筆者の恩師マックリーン先生は、ドストエフスキーの前兆を大脳辺縁系の異常活動に帰している。先生の考えによると、大脳辺縁系は2つの系に大別される。その一つは扁桃核とその近隣の辺縁系皮質からなる系であり、他の一つは中隔と海馬や帯状回からなる系である。扁桃核を皮質下核とする系の活動が高まると、恐怖や悲しみの情動体験があり、中隔を皮質下核とする系の活動が高まると、逆の情動体験がある。ドストエフスキーの場合には中隔を皮質下核とする系の活動が一過性に高まったのであろう。
筆者の恩師マックリーン先生は、ドストエフスキーの前兆を大脳辺縁系の異常活動に帰している。先生の考えによると、大脳辺縁系は2つの系に大別される。その一つは扁桃核とその近隣の辺縁系皮質からなる系であり、他の一つは中隔と海馬や帯状回からなる系である。扁桃核を皮質下核とする系の活動が高まると、恐怖や悲しみの情動体験があり、中隔を皮質下核とする系の活動が高まると、逆の情動体験がある。ドストエフスキーの場合には中隔を皮質下核とする系の活動が一過性に高まったのであろう。オールズは、ラットがレバーを押せばあらかじめ植込んだ刺激電極を通じて脳に電流が流れるスキナー箱の実験を行った。この実験のとき、刺激電極を中隔に入れておくと、ラットが狂ったようにレバーを押し続けることを確かめた。中隔の電気刺激がラットに快感をもたらしたと解釈された。プールは、このような実験にヒントをえて、難治性疼痛に苦しんでいた老人の中隔に刺激電極を植え込み、痛みを軽減しようと試みた。この治療を受けた患者の一人は、予想通り好ましい気分の変化の恩恵に浴したが、別の患者は、一時的な怒り反応を示した。人間の脳はラットの脳のように単純でない。
この方法はその後普及しなかったが、脳を電気刺激して慢性痛を治療しようとする試みの火を切った。またこのような試みと併行して、実験動物の脳のいろいろな部分に電気刺激を加えて鎮痛効果をえようとする実験が進められ、中枢神経系は痛みを感じる系と、痛みを抑える系の両方をもち、モルヒネのような鎮痛薬の作用が疼痛抑制系の賦活と深くかかわっていることが明らかにされた。
これまでに見出された疼痛抑制系の主要なものは、中脳中心灰白質を出て、延髄の大縫線核で中継された後、脊髄の背外側索を通って脊髄後角に達する系と、青斑を出て脊髄の腹外側索を通り脊髄後角に達する系である。これら二つの系はいずれも、脊髄後角における痛覚伝達を抑制する。青斑を出る系の、脊髄における伝達物質はノルアドレナリンで、α2 受容体がこの抑制作用を媒介する。
α2 主動薬であるクロニジンやチザネジン(テルネリン)を硬膜上腔に注入すると、これらが脊髄に入ってα2 受容体と結合し、鎮痛効果をもたらす。全身投与によっても同様な機序による鎮痛効果がえられると思われる。クロニジンを投与すると全身血圧が下降するが、チザネジンブの場合、この種の副作用がみられない。
| 痛みの世界史 連載 → |
|