13.褥瘡ケア・スキンケア
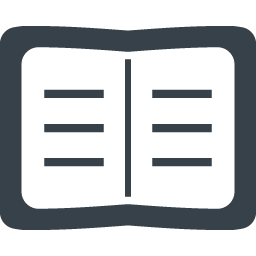 ←褥瘡ケア・スキンケア質指標 ダウンロードはこちら
←褥瘡ケア・スキンケア質指標 ダウンロードはこちら
以下に示すのは利用者と家族に対する自分自身の日頃の看護活動を振り返るチェック項目です。各項目について普段行っている看護活動内容に照らし合わせて次の4つのうち1つを選んで回答してください。(必ずできている:4, おおむねできている:3, あまりできていない:2,全くできていない:1)
褥瘡ケア・スキンケア質指標
基本的姿勢
| 1 |
訪問看護開始時には全ての利用者に対して褥瘡発生の可能性を念頭に置き、褥瘡のリスクならびに褥瘡の有無について確認できた場合には、看護記録に記載する。 |
| 2 |
アセスメントおよびケア方法の決定に際しては、褥瘡の状況とともに介護力・経済力などの心理・社会的側面を考え合わせた褥瘡ケアの目標設定をし、その時点で最善と思われる決定をする。 |
| 3 |
家族・介護者に対して、必要な知識・技術を教育・助言する。 |
[褥瘡のリスクアセスメント] 全般的な褥瘡のリスクアセスメント
| 4 |
訪問看護開始時には障害老人の日常生活自立度B以上に対して褥瘡発生の可能性を念頭に置き、根拠の明らかなリスクアセスメントスケール(例:資料1:在宅版K式スケール、OHスケールなど)を用いて評価している。 |
[褥瘡のリスクアセスメント] 療養環境ならび介護状況のアセスメント
| 5 |
家族・介護者に褥瘡ケアの基本的な知識があるか、褥瘡(予防)管理上、問題が生じていないか、ケアは実施可能かについてアセスメントしている(例えば、介護力、寝具等)。 |
[褥瘡のリスクアセスメント] 低栄養・脱水のアセスメント
| 6 |
褥瘡のリスクがある場合、以下についてアセスメントを行っている。
- 栄養管理(本指標別項目参照)のアセスメント
- 経口摂取の減少、予定の経管栄養の不履行、脱水、発熱、大量な嘔吐、頻繁な下痢などの急激な栄養低下を引き起こすエピソード
|
[褥瘡予防のためのケア] 褥瘡予防のための看護計画
| 7 |
訪問看護開始時に褥瘡発生危険因子がある場合、スケールの点数を参考に、その程度に応じて緊急対応した上で、看護計画を立案する |
[褥瘡予防のためのケア] 体圧分散 (支持面積を広げ、骨突起部への圧の集中を避ける体位支持)・ずれ力 に関するケア
| 8 |
仰臥位の場合は全般的なリスクの高さに応じて、以下に示す基本的な体圧分散ケアを適宜行っている。
- 利用者の身体状況、介護の状況に応じて、適切な体位変換時間を設定する
- 骨突出部の圧迫を避けた体位で(一定時間ごと)の体位変換が望ましいが、スモールシフト※も組み合わせて同一部位に体圧が集中しないように考慮する
(※体位変換による除圧以外に、四肢の位置を変える背部にクッションを挿入または位置を変えることで圧迫の持続を回避する)
- 床上の移動は、スライディングシートの使用や部分ごとすこしづつの移動など、ずれ力を避ける配慮をする
- 家族・介護者がわかりやすいよう体位変換表や図などをベッドサイドに掲げるなどしてケアが継続されるような工夫をおこなっている
- 柔らかい広い面をもつクッションなどで下腿を支え、踵部挙上をしている
- 自力での体位変換が困難な場合は、骨突出や頭側挙上などの個別の状況に合わせて体圧分散寝具を選択し使用する(資料1・2・3)
- 体圧分散寝具は、利用者との遮蔽物(シーツやおむつを重ねすぎない)をなるべく少なくして使用する
|
| 9 |
頭側挙上の場合は全般的なリスクの高さに応じて、以下に示す基本的な体圧分散ケアを適宜行っている。
- 頭側挙上角度は原則として30度までとする。( 呼吸困難緩和等で45度以上にする時には、椅子坐位とするか、底付き防止や姿勢保持機能を備えた体圧分散寝具を選択する。) 頭側挙上時は、ずれないように、足側から挙上してから頭側を上げる
- 背上げをした後、ベッドから起こして背面に加わる外力を除く(背抜き)
|
| 10 |
座位の場合は全般的なリスクの高さに応じて、以下に示す基本的な体圧分散ケアを適宜行っている。
- 接触面積が狭く圧が集中しやすい円座は予防用具としては使用しない
- 日中の大半を車いすで生活する場合は、安定した座面が確保できるようスリングシートを避け、適切な車椅子を選定する
- 坐位姿勢に問題のある利用者の場合は、体位支持方法・椅子・クッションの選択などについて、可能であれば理学療法士または作業療法士に相談している
- 同じ姿勢で長時間座位をとることを避け、15分~1時間おきに除圧動作(資料5)や臥位になるよう勧める
|
[褥瘡予防のためのケア] 皮膚の浸軟防止のケア
| 11 |
浸軟のリスクに応じて、以下に示す基本的な浸軟防止ケアを適宜おこなっている。
- 尿、便失禁がある時には、排泄ケア用具や吸収量の多いパッドや紙おむつの選択と、弱酸性の洗浄剤による陰部洗浄をおこなう
- 便失禁のある場合には、撥水性のあるクリーム(少量のワゼリン等)やスプレー(サニーナ等)で排泄物による化学的刺激から皮膚を保護している
- 多汗がある場合には、清拭後に通気性、吸湿性のある寝衣、シーツへ変更する
- 介護者にはおむつ交換や日々の介護の中で皮膚を観察する習慣をつけることと、発赤がおきた時の初期の手当について指導する
- 皮膚の浸軟状況を定期的にアセスメントしている
|
[褥瘡予防のためのケア] 褥瘡か否かのアセスメント
| 12 |
褥瘡か否かをアセスメントする場合、次の項目について適宜観察している (資料6参照)
- 圧迫部位に一致した発赤、表皮剥離、水ほう、浅い潰瘍のいずれかの真皮までにとどまる皮膚変化がある
- 大きさを観察している(資料7)
- 発赤を透明な板(プラスチック定規など)または指で圧迫しても白く退色しない
- 発生部位を観察し、原因を推測している(骨突起、体位、接触物、皮膚の重なり、浸軟、ずれ、等)
|
[褥瘡予防のためのケア] 褥瘡のアセスメント
| 13 |
褥瘡をアセスメントする場合、次の項目についてDESIGN-Rで評価する(資料6参照)
- 圧迫部位に一致した皮膚の変化や損傷の深さと大きさ
- 滲出液の有無ならびに量や性状
- 炎症/感染の兆候
- 肉芽組織の有無や性状ならびに創面積における割合
- 壊死組織の有無と性状ならびに創面積における割合
- 深さがあるクレーターのポケットを伴っている場合、その部位と大きさ
|
[褥瘡予防のためのケア] 緊急対応を要する褥瘡のアセスメント
| 14 |
緊急な対応を要する褥瘡のアセスメントをする場合、次の感染兆候について適宜観察している。
- 褥瘡の周囲皮膚の発赤の範囲が大きい
- 褥瘡の周囲皮膚の一部に明らかな熱感や腫脹を伴う
- 褥瘡以外の感染は明らかでないのに全身の発熱がある
- 褥瘡の周囲皮膚の一部に膿の貯留を思わせる感触がある
|
[褥瘡のケア] すべての褥瘡に共通する局所ケア
| 15 |
褥瘡の発症要因(体圧、浸潤、ずれ、栄養など)を除去するケアを継続する。 |
| 16 |
適切な創・皮膚のドレッシングが行われている・ 明らかな感染を認め浸出液や膿苔が多い時以外は、消毒薬を用いていない。
- ドレッシング材の除去時、物理的刺激を最小限にする方法(愛護的剥離、必要時剥離剤使用)で行う
- 医師との相談により、褥瘡の状況に応じたドレッシング材や薬剤を選択する (資料7・8参照)
- ドレッシング材の固定は創周囲皮膚への刺激が最小限となる方法(テンションをかけない、必要時保護材・被膜材使用)で行う
|
| 17 |
壊死組織を有する褥瘡に対し、医師によるデブリドマンが必要に応じて施行される。 |
[褥瘡のケア] 感染した褥瘡のケア
| 18 |
褥瘡が感染しているとき、医師と連絡をとりながら、次の管理方法を行っている。
- 毎日洗浄する。膿や壊死組織は微温湯などで洗い流す
- 感染制御作用を持つ薬剤(カデキソマー・ヨウ素、スルファジアジン銀、ポピドンヨード、シュガー)あるいは銀含有ハイドロファイバーを用いる
- 褥瘡部の局所的な圧を考慮し、感染した褥瘡では、密閉しないように注意する
- 浸出液吸収のため、吸収パット(清潔な尿とりパットなど)を圧が褥瘡部に集中しないように広範にあてる
|
| 19 |
褥瘡の感染兆候が明らかで緊急にデブリドマンを要すると考えられたとき、次の対処を適宜実施する。
- 緊急にデブリードメントを要することを、当日のうちに医師に連絡する
- 専門医やWOC看護師への報告を考慮し、可能であれば報告する
- 腫脹している部分の一部でも壊死組織を切除して排液を促すことを考慮し、早急に医師が実施できるよう調整する
|
[褥瘡のケア] 終末期・重症患者の褥瘡ケア
| 20 |
ターミナル期等の褥瘡ケアに苦痛を伴う状況の場合、次の事柄に配慮して褥瘡ケアを実施している。
- 事前に周到に準備し、局所ケアを短時間でできるよう、配慮する
- 局所ケア方法を簡素化し、短時間に局所ケアを行う
- 局所ケアを鎮静剤の効いている時などの、最も苦痛の無い時間に計画的に短時間に行う
|
[スキンケア] 浮腫がある場合のスキンケア
| 21 |
利用者に浮腫があるかどうか観察し、出現している場合はその部位と局所性因子・全身性因子についてアセスメントする。
- 皮膚乾燥を予防するため、保湿外用剤を用いる
- 外傷予防のため、医療用テープの使用は最小限とする
|
[スキンケア] 浮腫がある場合のスキンケア
| 22 |
利用者は高齢であることから、加齢によるドライスキンになりやすいことを念頭に置き、以下の皮膚症状からアセスメントする。
- 背部・四肢伸側皮膚の粃糠様鱗層
- 下腿前面の浅い亀裂の形成
|
| 23 |
入浴時以下のことを家族・介護者に指導する。
- 石鹸で皮膚をこすり過ぎないようにし、よく泡立てて愛護的に洗う
- 湿度が低い時期は入浴後には必ず保湿外用剤を塗布する
- 保湿効果のある洗浄剤の選択をする
|
| 24 |
踵部や仙骨部の乾燥皮膚には、摩擦係数の少ないドレッシング(ポリウレタンフィルム、リモイスパッドなど)を使用する。 |
フォローアップ
| 25 |
ケアの継続・維持のため在宅療養環境を整備する。
- 家族・介護者が常日頃介護がしやすいように必要な物品を扱いやすいように工夫・配置する
- 家族・介護者などの介護従事者のそれぞれの役割に応じて介護を共に計画する
- 在宅療養の限界を見極める(・深さがD以上で高熱を伴う・多発しケアの絶対量が多い・介護力の低下により在宅療養が困難)
- 連携できる医療・介護・福祉チームメンバーに褥瘡(ケア)に関する情報を提供し、協力体制をつくる
|
| 26 |
実施したケアについて、期限を決めて、目標がどの程度達成されたかを評価し、状況に応じて、ケア計画を変更する。
- 利用者にd2以上の褥瘡があり、原則として同じ方法で2週間以上ケアを実施しても改善が見られない場合や、症状の悪化を認める場合は、WOCナースや作業療法士などのリソースを活用して、ケアの実践内容を見直し、ケア計画を修正する
|
