心室中隔欠損症とは
心室中隔欠損症とは
心臓は全身に血液を送り出す「左室」と肺に血液を送り出す「右室」に分かれています。その左右の心室を分けているのが「心室中隔」と呼ばれる部分ですが、そこに穴があいている病気が「心室中隔欠損」という病気です。
先天性心疾患のなかで、もっとも多い病気で、日本では先天性心疾患の約6割を占めるといわれています。穴が小さいものでは、自然閉鎖するものもあります。穴の大きさが大きく、心臓や肺に負担のかかるものは、一般的に手術となります。肺への負担が大きい場合、時間がたつと「肺高血圧」といって、肺の血管が痛んだ状態になり、場合によっては手術ができないようになることもあります。
また、穴の場所によっては、大動脈弁の変形や、閉鎖不全をおこすこともあり、血液の漏れの量にかかわらず、手術になることもあります。
血液の循環
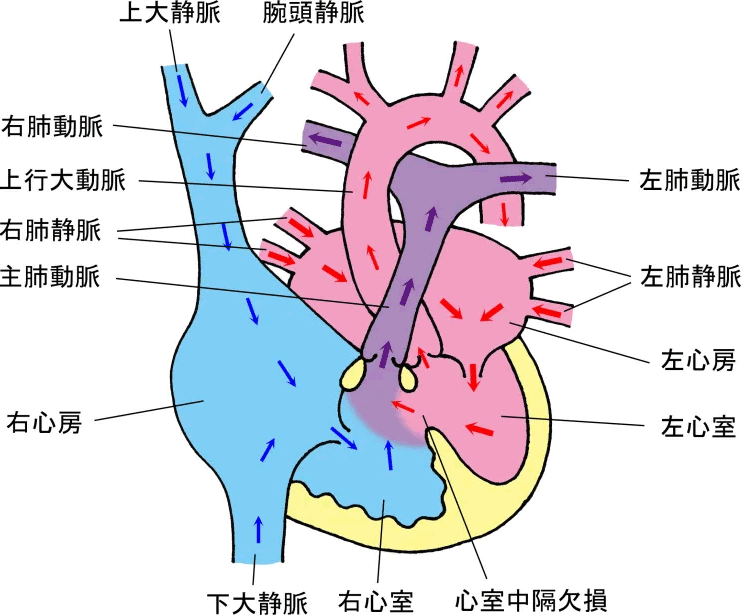
酸素をもらった赤い血液は、心室中隔欠損を通って左室から右室へ向かいます。全身へ回る血液(赤、矢印なし)と全身から戻ってくる血液(青)は、二つずつですが、左室から右室を通って肺を回る血液は赤い矢印の血液も含まれるため、三つになります。そのため、肺へ向かう血液の量が多くなり、肺と心臓両方に負担がかかることとなります。
治療・手術
穴の大きさが大きい場合や心不全が強い場合には手術が選択されます。
手術は人工心肺を用いておこない、「パッチ」と呼ばれる人工のあて布を左右の心室の間にあてて、穴をふさぐという手術を行います。穴をふさいだ後は、まわりの筋肉が成長するので患者さんが成長してもパッチの取替えをする必要はありません。
内科的治療としては、ラシックス、アルダクトンという利尿剤が使われることが一般的です。
長期的な予後
心房中隔欠損の手術後の予後は一般的に非常に良好です。通常、ほかの子どもたちと同様に生活していけると考えられます。
ただ、少なくともこどもさんがひとり立ちするまでは、1~2年おきの外来通院を行い、変化がないかどうかを外来で経過観察することが理想です。


