兪募
- 医論異論
- by shenquzhai
- 2006/05/12
病症と兪募穴の結びつきは、『内経』には有りません。有るのは蔵と背兪との結びつきです。だから、五蔵六府と兪募穴の結びつきの兆しは有るのかも知れません。『難経』に至って、五蔵に募穴と兪穴が有って、陰病には兪穴を、陽病には募穴を取ると言うけれど、別に病症によって兪穴のうちのどれ、募穴のうちのどれを取ると言っているわけではありません。それは確かに、病症に五行を配当し、兪募穴に五行を配当して、だから五行のこの病症の場合にはこの兪募穴という程度のことなら、私たちが知らないだけで、かつて試みた人はいるかも知れません。でも、伝わってないということは、その人は失敗したのでしょう。だから、現在試みて上手くいっているとしたら、その功績は創見というに値すると思います。
『内経』では、井滎兪経合は季節による使い分けが主流のようです。病症については、『霊枢』順気分為四時篇に、井は蔵、滎は色、輸は時、経は音、合は味と言っているあたりがせいぜいで、これもやっぱり主眼は四時に在るはずです。『難経』には、五蔵の病症を配当しているのかも知れない箇所が有ります。つまり、井は心下満、滎は身熱、輸は体重節痛、経は喘欬寒熱、合は逆気而泄。これをそれぞれ五蔵の病として配当できないことはない。でも、これも五つの目立った病症の陰陽の程度を、井滎兪経合の陰陽の程度に重ね合わせたくらいに止めておいたほうが、やっぱり無事だろうと思います。
病症の陰陽虚実と、井滎兪経合の陰陽の度合いとを相応させるのは、まあなんとか大丈夫だろうと思います。背兪の高下の陰陽と相応させるのも、まあ同じ理屈でどうにかなるかも知れません。でもそれは背兪というよりは背中の足太陽経脈上の穴の運用じゃないでしょうか。募穴はどうなんでしょう。陰陽的な使い分けは、何か別の理屈を探さないと、ちょっと難しくはないですか。
もともとは、兪募穴は蔵府との相関で、井滎兪経合は陰陽虚実との相関ではなかったかと思っています。両者を連環させれば、新しい面白い世界が開けるのかも知れません。けれども、そんなことをして大丈夫かという畏れも感じます。五行の配当だけを頼りにしてそうするのでは、かつて試みて失敗した先人の跡をたどるに過ぎないのではないでしょうか。
やっぱり、兪募穴は蔵府のものとしておいたほうが良くはないでしょうか。背兪穴も募穴も本当は直接に蔵府と繋がっているのであって、それをどれかの経脈の穴のようにいうのも、整理の都合上のことに過ぎないと思っています。
『内経』では、井滎兪経合は季節による使い分けが主流のようです。病症については、『霊枢』順気分為四時篇に、井は蔵、滎は色、輸は時、経は音、合は味と言っているあたりがせいぜいで、これもやっぱり主眼は四時に在るはずです。『難経』には、五蔵の病症を配当しているのかも知れない箇所が有ります。つまり、井は心下満、滎は身熱、輸は体重節痛、経は喘欬寒熱、合は逆気而泄。これをそれぞれ五蔵の病として配当できないことはない。でも、これも五つの目立った病症の陰陽の程度を、井滎兪経合の陰陽の程度に重ね合わせたくらいに止めておいたほうが、やっぱり無事だろうと思います。
病症の陰陽虚実と、井滎兪経合の陰陽の度合いとを相応させるのは、まあなんとか大丈夫だろうと思います。背兪の高下の陰陽と相応させるのも、まあ同じ理屈でどうにかなるかも知れません。でもそれは背兪というよりは背中の足太陽経脈上の穴の運用じゃないでしょうか。募穴はどうなんでしょう。陰陽的な使い分けは、何か別の理屈を探さないと、ちょっと難しくはないですか。
もともとは、兪募穴は蔵府との相関で、井滎兪経合は陰陽虚実との相関ではなかったかと思っています。両者を連環させれば、新しい面白い世界が開けるのかも知れません。けれども、そんなことをして大丈夫かという畏れも感じます。五行の配当だけを頼りにしてそうするのでは、かつて試みて失敗した先人の跡をたどるに過ぎないのではないでしょうか。
やっぱり、兪募穴は蔵府のものとしておいたほうが良くはないでしょうか。背兪穴も募穴も本当は直接に蔵府と繋がっているのであって、それをどれかの経脈の穴のようにいうのも、整理の都合上のことに過ぎないと思っています。
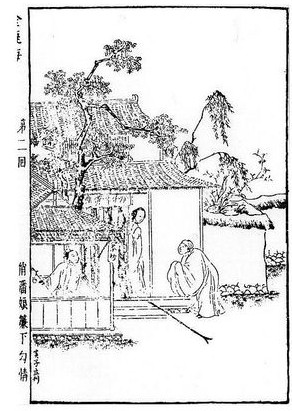 この朱にした二十四字を、中国図書刊行社の戴鴻森新校点本ではわざわざ刪去しているけれど、そんなにやばいこと書いてありますか。やっぱり我々の感受性が鈍くなったんですかねえ。
この朱にした二十四字を、中国図書刊行社の戴鴻森新校点本ではわざわざ刪去しているけれど、そんなにやばいこと書いてありますか。やっぱり我々の感受性が鈍くなったんですかねえ。 実は、そのちょっと前の戦いで、王英は扈三娘に生け捕りにされている。つまり自分より弱い男なのである。しかも渾名は矮脚虎、短足である。もうちょっとましな相手を選んでやっても、と余計な心配をするけれど、では、この夫婦は仲が悪いのかというとそうでもなさそうなのである。大体が、『水滸伝』はもともと人材集めの物語のようなもので、仲間になってしまった豪傑にはほとんど無頓着であるから、具体的な描写は無い。でも、最後の方臘との戦いで、王英が斬られたのをみて、仇討ちとばかりに飛び出して返り討ちにあっているのだから、まあ仲もそこそこだったんじゃないかと思うわけです。どうして、武大と金蓮の場合と違うのか。勿論、説明は無い。無いけれど、扈三娘は梁山泊の豪傑の中で唯一の良家の子女で、王英は梁山泊の豪傑の中で随一(唯一ではないが)の色好みなんですね。ここに秘密が有りそうに思う。下品になるといけないので、詳しくは言わない。
実は、そのちょっと前の戦いで、王英は扈三娘に生け捕りにされている。つまり自分より弱い男なのである。しかも渾名は矮脚虎、短足である。もうちょっとましな相手を選んでやっても、と余計な心配をするけれど、では、この夫婦は仲が悪いのかというとそうでもなさそうなのである。大体が、『水滸伝』はもともと人材集めの物語のようなもので、仲間になってしまった豪傑にはほとんど無頓着であるから、具体的な描写は無い。でも、最後の方臘との戦いで、王英が斬られたのをみて、仇討ちとばかりに飛び出して返り討ちにあっているのだから、まあ仲もそこそこだったんじゃないかと思うわけです。どうして、武大と金蓮の場合と違うのか。勿論、説明は無い。無いけれど、扈三娘は梁山泊の豪傑の中で唯一の良家の子女で、王英は梁山泊の豪傑の中で随一(唯一ではないが)の色好みなんですね。ここに秘密が有りそうに思う。下品になるといけないので、詳しくは言わない。