緩急小大滑濇
- 医論異論
- by shenquzhai
- 2006/04/07
『霊枢』邪気蔵府病形篇の変化の病形を診る脈は、緩急小大滑濇であるから、どうしたって三つの要素の二者択一の積み重ね、あわよくば座標軸で解釈しようとしてしまうが、本当は後文の「刺之奈何」から考えたほうが良いのかも知れない。
緩は、熱である。だから針を浅く入れて、速やかに抜く。
急は、寒である。だから針を深く入れて、久しく留めておく。緩急は確かに二者択一で問題ない。
小は、血気がともに少ないのであるから、針治療にはむかない。だから滋養の薬物を投与する。
大は、小とは対照的に瀉法が主となる。ただし、気は多いから少し瀉すようにするけれど、血は少ないから出血はさせないようにする。
滑は、陽気が盛んで、わずかに熱が有る。だから、針を浅くいれてその陽気を瀉して、その熱を去る。緩の刺法と実質的な違いは無い。つまり緩と滑の表現する性質は同じようなもので、程度に差が有るのだろう。気を瀉すのを主意とするという点では、大とも似たところが有る。
濇は、血が多くて気は少なく、わずかに寒が有る。だから、必ずよく揉んでから針を入れて必ず脈に中て、久しく留めた後に抜く。針を深く入れて、久しく留める点においては、急の刺法とさしたる違いは無い。抜いた後もすぐその後を揉んでおく。(そうしないと、多血だから出血してしまう?)
この多血少気の濇に相い対するものは、多気少血の大であるはずなのに、刺法にそれが反映されてない。また『脈経』巻四の平雑病脈の「濇則少血」と、この篇の刺法中で言う「無令其血出」によって、濇は少血とすべきだとする意見が有る。むしろこっちのほうが常識でしょう。それでは小と濇がほとんど同じになってしまうが、つまり、濇は小と似たようなもので程度の差ということかも知れない。
乃ち濇は冷えによって滞りがちになることと、生命力の低下傾向という、二つの情況を表現している。
つまり、緩大滑の傾向か急小濇の傾向かに二分し、さらに精密に診る。座標軸ではなさそうである。
緩は、熱である。だから針を浅く入れて、速やかに抜く。
急は、寒である。だから針を深く入れて、久しく留めておく。緩急は確かに二者択一で問題ない。
小は、血気がともに少ないのであるから、針治療にはむかない。だから滋養の薬物を投与する。
大は、小とは対照的に瀉法が主となる。ただし、気は多いから少し瀉すようにするけれど、血は少ないから出血はさせないようにする。
滑は、陽気が盛んで、わずかに熱が有る。だから、針を浅くいれてその陽気を瀉して、その熱を去る。緩の刺法と実質的な違いは無い。つまり緩と滑の表現する性質は同じようなもので、程度に差が有るのだろう。気を瀉すのを主意とするという点では、大とも似たところが有る。
濇は、血が多くて気は少なく、わずかに寒が有る。だから、必ずよく揉んでから針を入れて必ず脈に中て、久しく留めた後に抜く。針を深く入れて、久しく留める点においては、急の刺法とさしたる違いは無い。抜いた後もすぐその後を揉んでおく。(そうしないと、多血だから出血してしまう?)
この多血少気の濇に相い対するものは、多気少血の大であるはずなのに、刺法にそれが反映されてない。また『脈経』巻四の平雑病脈の「濇則少血」と、この篇の刺法中で言う「無令其血出」によって、濇は少血とすべきだとする意見が有る。むしろこっちのほうが常識でしょう。それでは小と濇がほとんど同じになってしまうが、つまり、濇は小と似たようなもので程度の差ということかも知れない。
乃ち濇は冷えによって滞りがちになることと、生命力の低下傾向という、二つの情況を表現している。
つまり、緩大滑の傾向か急小濇の傾向かに二分し、さらに精密に診る。座標軸ではなさそうである。

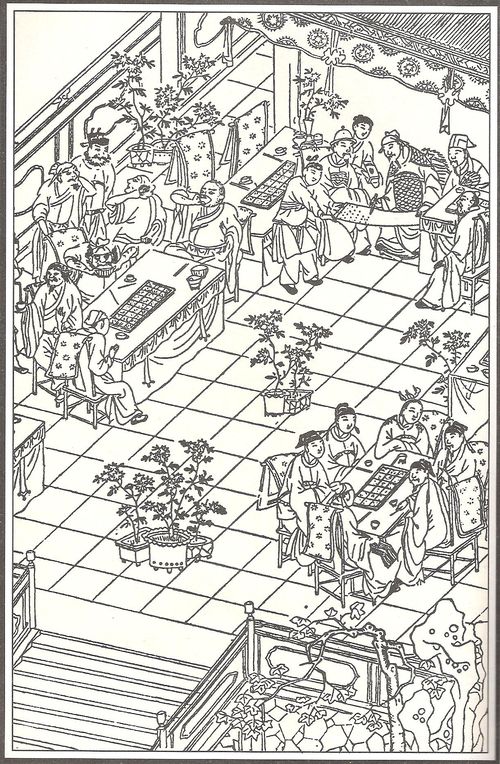
 中国人というのは、なんのかのと言っても、やっぱり道教がお気に入りで、弁証論だの唯物主義だのと言ったところで、進香も易占も護符も、別にすたれた様子は無い。で、彼らの望むところは不老長生であって、なろうことなら仙人になりたい。
中国人というのは、なんのかのと言っても、やっぱり道教がお気に入りで、弁証論だの唯物主義だのと言ったところで、進香も易占も護符も、別にすたれた様子は無い。で、彼らの望むところは不老長生であって、なろうことなら仙人になりたい。 中国在住の某氏の情報によれば、上海中医薬大学は、香港の骨董市場にもちこまれた戦国末~前漢の竹簡若干を入手した模様。内容は医学に関わるもののようで、五色、奇咳、揆度、石神などの文字が見えるそうです。ただし、長く水に漬かっていたものらしく、コンニャクのようなぶよぶよの状態で、上海中医薬大学では扱いかねて、現在、上海博物館に初歩的な処理を依頼しているとのことです。内容についての研究は処理が終わってからになりそうです。なお、出土地は山東のようですが、盗掘の品らしく詳しくは不明。
中国在住の某氏の情報によれば、上海中医薬大学は、香港の骨董市場にもちこまれた戦国末~前漢の竹簡若干を入手した模様。内容は医学に関わるもののようで、五色、奇咳、揆度、石神などの文字が見えるそうです。ただし、長く水に漬かっていたものらしく、コンニャクのようなぶよぶよの状態で、上海中医薬大学では扱いかねて、現在、上海博物館に初歩的な処理を依頼しているとのことです。内容についての研究は処理が終わってからになりそうです。なお、出土地は山東のようですが、盗掘の品らしく詳しくは不明。 江戸の考証学者の多くは、号の一字に植物を用いている。先ず伊沢蘭軒がそうであるし、その子の榛軒と柏軒、榛軒の養嗣の棠軒、みなそうである。多紀家でも、元簡は桂山、元胤は柳沂、元堅は茝庭。茝が、セリ科の香草でヨロイグサというのが、具体的にどんなものか知らないが、みなまあまともな植物を選んでいる。森立之の枳園は皮肉れていて、『晏子春秋』の「橘は淮南に生ずれば橘と為り、淮北に生ずれば枳と為る」をふまえて、在るべきところに居ないとうそぶく。無論、橘のほうが価値が有るという常識に従えば、であるが。
江戸の考証学者の多くは、号の一字に植物を用いている。先ず伊沢蘭軒がそうであるし、その子の榛軒と柏軒、榛軒の養嗣の棠軒、みなそうである。多紀家でも、元簡は桂山、元胤は柳沂、元堅は茝庭。茝が、セリ科の香草でヨロイグサというのが、具体的にどんなものか知らないが、みなまあまともな植物を選んでいる。森立之の枳園は皮肉れていて、『晏子春秋』の「橘は淮南に生ずれば橘と為り、淮北に生ずれば枳と為る」をふまえて、在るべきところに居ないとうそぶく。無論、橘のほうが価値が有るという常識に従えば、であるが。