虎になる
- 雑事
- by shenquzhai
- 2006/05/21
私にとって中島敦の『山月記』は、「己の珠に非ざることを惧れるがゆえに、あえて刻苦して磨こうともせず、また、己の珠なるべきを半ば信ずるがゆえに、碌々として瓦に伍することもできなかった。」という李徴の自嘲の科白に尽きる。ところが唐代伝奇の『李徴』を読み直して、もともとの話は少し違ったかも知れないと思うようになった。
隴西李徴,皇族子,家於虢略。徴少博學,善屬文,弱冠從州府貢焉,時號名士。天寶十載春,於尚書右丞楊没榜下登進士第。後數年,調補江南尉。徴性疎逸,恃才倨傲。不能屈跡卑僚,嘗欝欝不樂。毎同舍會既酣,顧謂其羣官曰:生乃與君等爲伍耶。其僚佐咸嫉之。『山月記』の書き出しと大して違うわけではないが、ここにはわざわざ皇族子と書いて、名族であることを誇示している。隴西の李氏は唐のいわゆる五姓七族の筆頭で、これら七族の出身であるか、あるいは少なくとも姻戚でなければ貴族とは認められなかった。李徴はその端くれであることを誇りに思い、卑僚(卑しい家柄出身の同僚)と同席することを快しとしなかった。彼には、若くして進士に及第する程度には才学も有ったのだから、そろそろ科挙が重んじられるようになる時勢に合わせることさえできれば、相当程度以上の出世は望めたはずなのである。しかし、会合のときに酒がまわるといつも、同僚を顧みて「この世に生まれて君らのようなものと仲間になるのか」などと言っていたのでは、いかに当時でも軋轢は有る。つまり、『李徴』は貴族制から官僚制に変わりつつある時代の波に乗り損ねた、あるいは乗るのを良しとしなかった不器用者の自負と苛立ちと、自嘲と自己嫌悪の物語である。詩家としての成就、名声がどうのこうのとはあまり関係が無い。自分以外はみんな卑しく阿呆であると思えた。その感情を、隠そうとはし、また改めようとはして、だが隠しもならず、また改めもならず、鬱々として楽しまず、ついに狂を発して虎となった。
 劉向『列仙伝』に:
劉向『列仙伝』に: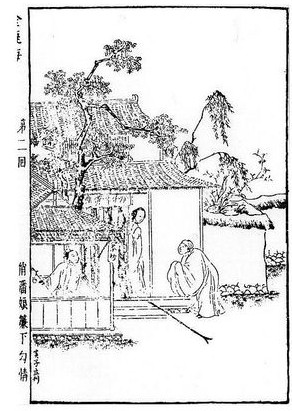 この朱にした二十四字を、中国図書刊行社の戴鴻森新校点本ではわざわざ刪去しているけれど、そんなにやばいこと書いてありますか。やっぱり我々の感受性が鈍くなったんですかねえ。
この朱にした二十四字を、中国図書刊行社の戴鴻森新校点本ではわざわざ刪去しているけれど、そんなにやばいこと書いてありますか。やっぱり我々の感受性が鈍くなったんですかねえ。 実は、そのちょっと前の戦いで、王英は扈三娘に生け捕りにされている。つまり自分より弱い男なのである。しかも渾名は矮脚虎、短足である。もうちょっとましな相手を選んでやっても、と余計な心配をするけれど、では、この夫婦は仲が悪いのかというとそうでもなさそうなのである。大体が、『水滸伝』はもともと人材集めの物語のようなもので、仲間になってしまった豪傑にはほとんど無頓着であるから、具体的な描写は無い。でも、最後の方臘との戦いで、王英が斬られたのをみて、仇討ちとばかりに飛び出して返り討ちにあっているのだから、まあ仲もそこそこだったんじゃないかと思うわけです。どうして、武大と金蓮の場合と違うのか。勿論、説明は無い。無いけれど、扈三娘は梁山泊の豪傑の中で唯一の良家の子女で、王英は梁山泊の豪傑の中で随一(唯一ではないが)の色好みなんですね。ここに秘密が有りそうに思う。下品になるといけないので、詳しくは言わない。
実は、そのちょっと前の戦いで、王英は扈三娘に生け捕りにされている。つまり自分より弱い男なのである。しかも渾名は矮脚虎、短足である。もうちょっとましな相手を選んでやっても、と余計な心配をするけれど、では、この夫婦は仲が悪いのかというとそうでもなさそうなのである。大体が、『水滸伝』はもともと人材集めの物語のようなもので、仲間になってしまった豪傑にはほとんど無頓着であるから、具体的な描写は無い。でも、最後の方臘との戦いで、王英が斬られたのをみて、仇討ちとばかりに飛び出して返り討ちにあっているのだから、まあ仲もそこそこだったんじゃないかと思うわけです。どうして、武大と金蓮の場合と違うのか。勿論、説明は無い。無いけれど、扈三娘は梁山泊の豪傑の中で唯一の良家の子女で、王英は梁山泊の豪傑の中で随一(唯一ではないが)の色好みなんですね。ここに秘密が有りそうに思う。下品になるといけないので、詳しくは言わない。