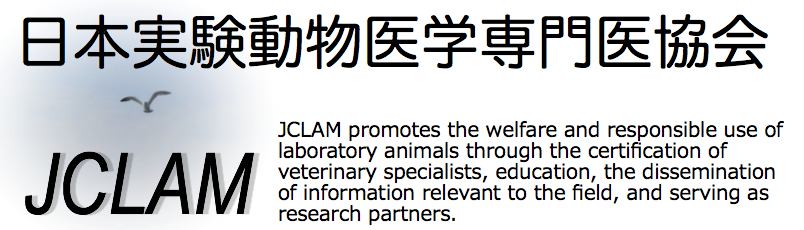会則,規則
認定規則

第1条 目的
日本実験動物医学専門医協会は実験動物医学専門医制度を設け、資格審査と認定試験により実験動物医学専門医を認定する.
第2条 認定審査
認定審査は資格審査と認定試験からなり、合格にはそれぞれが基準点に達しなければならない.但し、国際実験動物医学専門医協会( IACLAM)に所属する各専門医協会の専門医が日本実験動物医学専門医協会の認定を得る場合には、各専門医協会の専門医であることで有資格者とみなし、資格審査のみで合格とする.
1 資格審査の基準 (正会員)
(1)日本の獣医師免許を保有している者.日本以外の国で取得した獣医師免許保有者については、認定委員会でその適否について決定する.
(2)出願時に3年以上継続して日本実験動物医学会会員であること.
(3)別表1の実験動物医学専門医資格単位基準による合計が90単位以上であること.
(4)申請書に申告する単位は、当該申請年度の5月31日までに取得したものであること.
(5)資格審査合格の有効期間は3年間とし、それ以降に筆記試験を受験する場合には、再度申請しなければならない.
2 資格審査の基準 (国際実験動物医学専門医協会( IACLAM)に所属する各専門医協会から転入する正会員)
(1)出願時に国際実験動物医学専門医協会( IACLAM)に所属する専門医協会の会員であること.
(2)日本国内で職を得ていること.
(3)本協会に所属する現役専門医の推薦書 1通
(4)日本実験動物医学会会員であること.
(5)別表2.実験動物医学専門医更新時資格単位基準による合計単位が 80単位以上であること.
(6)申請書に申告する単位は、当該申請年度の 5月 31日までに取得したものであること.
3 資格審査の基準 (客員実験動物医学専門医)
(1)出願時に国際実験動物医学専門医協会( IACLAM)に所属する各専門医協会の会員であること.
(2)本協会に貢献できること.
(3)本協会に所属する現役専門医の推薦書 1通
4 認定試験
(1)資格審査に合格した申請者は、獣医学会開催時に、獣医学会開催地 または認定委員会によって設定された試験会場にて行われる認定試験を受験できる.
(2)試験方法については別途定める.
5 資格審査を申請する者は審査料を申請時に支払わなければならない.
第3条 認定登録
1 認定審査に合格した者は日本実験動物医学専門医協会会長より認定証が交付され、実験動物医学専門医名簿に登録される.
2 認定審査に合格した者は認定を受けるために認定料を支払わなければならない.
第4条 有効期間と更新
1 実験動物医学専門医の資格の有効期間は認定後5年とする.
2 有効期間終了後さらに認定を受ける者は、有効期間終了前に更新をしなければならない.
3 更新 する正会員は次の資格審査をうける.
(1)実験動物医学専門医資格取得後も日本実験動物医学会会員歴が継続していること.
なお、国際専門医協会に所属する各専門医協会の専門医の資格で認定を受けた専門医は、各専門医協会の専門医の資格を継続していること.但し、当該資格を喪失した場合には、その時点で遅滞なく日本実験動物医学会に会員として所属していること、もしくは国際専門医協会に所属する他の専門医協会の専門医の資格を有していること.
(2)別表2.実験動物医学専門医更新時資格単位基準による合計単位が80単位以上であること.
(3)申請書に申告する単位は、当該申請年度の5月31日までに取得したものであること
4 更新する客員実験動物医学専門医は次の資格審査をうける.
(1)日本実験動物医学専門医資格取得後も国際専門医協会に所属する各専門医協会の専門医の資格を継続していること.
(2)当該申請年度の 5月 31日までに本協会への貢献が認められていること.
(3)国際専門医協会に所属する各専門医協会を喪失した場合には、客員実験動物医学専門医の資格は失効する.但し、国際専門医協会に所属する他の専門医協会の専門医の資格を有している場合は客員実験動物医学専門医を継続することができる.
(4)正会員の資格審査に合格した場合は正会員の資格を有する.
5 更新審査を申請する者は審査料を申請時に支払わなければならない.
6 更新審査に合格した者は認定を受けるために認定料を支払わなければならない.
第5条 審査料及び認定料
1 認定審査に係る審査料は新規、更新、他専門医協会から転入問わず 10,000円とする.
2 認定審査に係る受験料は新規、更新問わず 10,000円とする.
3認定料は新規、更新、他専門医協会から転入問わず 10,000円とする.
第6条 認定の取り消し
実験動物医学専門医に適格でない事由が生じた場合は、認定を取り消すことがある.
第7条 名誉実験動物医学専門医
1 協会の目的に顕著に貢献した個人、または特別な業績を有する個人に「名誉実験動物医学専門医」の称号を授与することができる.
2 この称号を授与される者は実験動物医学専門医あるいは生涯認定実験動物医学専門医の資格を有するものとする.
3 この称号を授与される者は日本実験動物医学専門医協会理事の推薦により、日本実験動物医学専門医協会理事会の議を経た後に総会で議決承認を得る.
4 名誉実験動物医学専門医は認定料等の経費の支払いは求められず、選挙権を含む認定制度の運営に携わることはできないが、認定制度の各種活動に加わることができる.
第8条 生涯実験動物医学専門医
1 現役を退いた実験動物医学専門医は認定委員会へ申請することにより、生涯認定実験動物医学専門医として登録する事ができる.
2 生涯実験動物医学専門医は認定料等の経費の支払いは免除され各種選挙権を含む認定制度の運営に携わることはできないが、認定制度の各種活動に加わることができる.
第9条 予備登録
1 認定審査に合格後直ちに認定登録を行わない者、または更新をしない者は予備登録名簿に登録される.予備登録者は実験動物医学専門医として認定されない.
2 予備登録者は認定制度の運営および活動に携わることはできない.また実験動物医学専門医としての権利を行使することはできない.
3 予備登録者は認定登録をするか、または更新申請をして更新審査に合格し、認定経費を納入することにより実験動物医学専門医として認定される.
4 予備登録の有効期限は5年とし、5年経過後認定資格を失う.但し、特別の事情がある場合には認定委員会の審議を経て、延長することができる.
第10条 改正 本規則の改廃は理事会の議決による.
附則
1 この規程は平成10年8月13日から施行する.
2 この規程は平成11年10月25日に改正した.
3 この規程は平成13年4月4日に改正した.
4 この規則は平成18年3月21日に改正した.
5 この規則は平成22年9月16日に改正した. 平成23年度から施行する.
6 この規則は日本実験動物医学会から日本実験動物医学専門医協会に移管され平成24年9月15日に改正した.
7 この規則は平成25年9月19日に改正した.平成27年度から施行する.
8 この規則は平成27年3月27日に改正した.
9この規則は平成28年9月23日に改正した.
10 この規則は平成 29年8月 19日に改正した .
11 この規則は平成 29( 2017)年 10月 12日に改正した.平成 35-36( 2023-2024)年度の更新申請から施行する .
12 この規則は令和 4( 2022)年 2月 28日に改正した .
13 この規則は令和 4( 2022)年 4月 1日に改正した.平成 35-36( 2023-2024)年度の更新申請から施行する .
14 この規則は令和 5( 2023)年 3月 14日に改正した。令和 5−6( 2023-2024)年度(平成 35-36年度)の更新申請から施行する。
15 この規則は令和 5( 2023)年 10月 1日に改正した。令和 6−7( 2024-2025)年度(平成 35-36年度)の更新申請から施行する。
*附則11(第10改正)により、実験動物医学専門医は別表2に記載の協会に対する貢献が求められ、平成35-36年(2023-2024)度以降の更新審査において必須項目として審査されることとなる.
別表1.実験動物医学専門医資格単位基準の内訳
評点は必須分野と選択分野からなる.必須分野は全ての条件を満たすこと.選択分野から30単位以上を取得し、必須分野と選択分野の合計90単位を認定の必要単位とする.
必須分野:つぎの全てを満たすこと.
1.査読制度のある雑誌に掲載され、自らの研究活動を証明できる原著または短報の筆頭著者(査読審査を経て受理されていること)生命科学関連論文1編 20単位
2.直近5年間の日本実験動物医学専門医協会(JCLAM)、日本実験動物医学会(JALAM)主催シンポジウム等への参加2回 20単位 (指導的立場での参加の場合は13単位/回)
3.ウェットハンド研修会Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3つの中から重複しない2つへの参加 20単位
ウェットハンド研修会は下記の通りとする.
Ⅰ. げっ歯類及びウサギの獣医学的管理
Ⅱ. イヌ及びブタの獣医学的管理
Ⅲ. サル類の獣医学的管理
選択分野:必須分野に申請した事項は除くこと.
・実験動物医学分野での経験が5年以上ある10単位
・博士号の取得者 10単位
・査読制度のある雑誌に掲載された原著または短報、あるいは症例報告などの生命科学関連論文(必須分野で審査されたものは除く)
筆頭著者 10単位/編 共著者 5単位/編
・直近5年間のJCLAM、JALAM、日本実験動物学会(略称:JALAS)および日本獣医学会(略称:JSVS)における学会発表
筆頭著者 5単位/回
共著者 2単位/回
・直近5年間のJALAM/JALAS/JSVS 以外の生命科学関連学会での発表
筆頭著者 3単位/回 共著者 1単位/回
・直近5年間のJCLAM、JALAM主催シンポジウム、webセミナー等への参加 5単位/回(必須分野で審査されたものは除く)
・JALAM 主催ウェットハンド研修会への参加 20単位/回 (必須分野で審査されたものは除く.但し、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲについて再度受講したものは取得単位として認める.)
・JCLAM が認めた直近5年間の研修会等への参加 (事前に認定委員会に申請し、参加証明書を添付すること)その都度JCLAM が単位数を決定する(1~5単位)
別表2.実験動物医学専門医更新時資格単位基準の内訳
初回実験動物医学専門医認定申請後または前回更新申請後の5年間の活動について単位をつける.活動は学会活動(学会発表と研修・試験)とそれ以外の2分野からなる.更新に必要な単位数を80単位とし、そのうち第1分野から最低40単位取得する.但し第1分野で80単位を取得しても良い.
なお、以下に示すいずれかの貢献を協会に対して行うことを必須とする.
・ JCLAMの各種委員会 あるいはタスクフォース在籍すること
・ウェットハンド講習会の講師,あるいは JCLAM Forumの講師もしくは座長を務めること(必須項目として申請した場合には、単位を申請することはできない).
・ 試験問題を作成すること.試験問題検討委員会によって適切と判断された問題を対象とする(試験問題検討委員会により妥当な問題と判断された問題に対しては、作成数に応じて単位が得られる).
・その他のJCLAM活動へ貢献すること.
第1分野
・JCLAM、JALAM、JALASおよびJSVSにおける学会発表
筆頭著者 5単位/回 共著者 2単位/回
・JCLAM/JALAM 企画の研修会参加
JCLAM/JALAM主催シンポジウム等への参加 10単位/回
同指導的参加(教育セミナー講師等) 13単位/回
ウェットハンド研修会への参加 20単位/回
同指導的参加(研修会講師等) 30単位/回
webセミナーへの参加 5単位/回
同指導的参加(講師) 8単位/回
・認定試験受験 (全試験を100点満点に換算して)1点=1単位
第2分野
・JALAM/JALAS/JSVS 以外の生命科学関連学会での発表
筆頭著者 2単位/回 共著者 1単位/回
・査読制度のある雑誌に掲載された生命科学関連論文
筆頭著者 10単位/編 共著者 5単位/編
・JCLAMが認めた直近5年間の研修会等への参加および指導的参加 (事前に認定委員会に申請し、参加証明書を添付すること)その都度JCLAMが単位数を設定する (1~5単位)
例:参加 2単位、指導的参加 4単位
・認定試験問題作成(試験問題検討委員会により妥当な問題と判断された問題に対して) 1問=5単位. 但し、単位として認める問題数は5題/年までとする
・研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う(新規・継続)10単位
・博士号の取得 5単位
・動物実験、実験動物に関する評論(新聞・雑誌・TV・ラジオ等)3単位
・動物実験、実験動物に関する本の執筆、編集 5単位
・日本獣医師会生涯研修事業(本会主催事業を除く)1ポイント=1単位20単位まで.他会企画研修会は前もって調査(申告)し、認定委員会が認定し単位を設定する.
◇更新時単位取得例(5年間で80単位取得例)
| 1. 大学勤務者(1) |
||||
| 第1分野 | 日本実験動物学会発表 | 筆頭者 | 1回 | 5単位 |
| 共著者 | 3回 | 6単位 | ||
| 研修会参加 | 5回 | 50単位 | ||
| 第2分野 | 論文発表 | 共著者 | 1回 | 5単位 |
| 他会企画研修会参加 | 5回(×2単位) | 10単位 | ||
| 研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う | 10単位 | |||
| 合計 | 86単位 | |||
| 2. 大学勤務者(2) |
||||
| 第1分野 | 日本実験動物学会発表 | 筆頭者 | 1回 | 5単位 |
| 共著者 | 5回 | 10単位 | ||
| 研修会参加 | 3回 | 30単位 | ||
| 第2分野 | 論文発表 | 共著者 | 1回 | 5単位 |
| 他会企画研修会参加 | 5回(×2単位) | 10単位 | ||
| 研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う | 10単位 | |||
| 試験問題作成 | 5回 | 25単位 | ||
| 合計 | 95単位 | |||
| 3. 製薬会社勤務者(1) |
||||
| 第1分野 | 日本実験動物学会発表 | 共著者 | 3回 | 6単位 |
| 研修会参加 | 4回 | 40単位 | ||
| 第2分野 | 他会企画研修会参加 | 10回(×2単位) | 20単位 | |
| 研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う | 共著者 | 10単位 | ||
| 試験問題作成 | 2回 | 10単位 | ||
| 合計 | 86単位 | |||
| 4. 製薬会社勤務者(2) | ||||
| 第1分野 | 日本実験動物学会発表 | 筆頭者 | 1回 | 5単位 |
| 共著者 | 3回 | 6単位 | ||
| 研修会参加 | 3回 | 30単位 | ||
| 第2分野 | 他会企画研修会参加 | 10回(×2単位) | 20単位 | |
| 研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う | 共著者 | 10単位 | ||
| 試験問題作成 | 2回 | 10単位 | ||
| 日本獣医師会生涯研修事業 | 6単位 | |||
| 合計 | 87単位 | |||
| 5. 地方在住者(1) |
||||
| 第1分野 | 研修会参加 | 4回 | 40単位 | |
| 第2分野 | 他会企画研修会参加 | 5回(×2単位) | 10単位 | |
| 研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う | 10単位 | |||
| 日本獣医師会生涯研修事業 | 20単位 | |||
| 合計 | 80単位 | |||
| 6. 地方在住者(2) |
||||
| 第1分野 | 研修会参加 | 4回 | 40単位 | |
| 第2分野 | 他会企画研修会参加 | 2回(×2単位) | 4単位 | |
| 研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う | 10単位 | |||
| 試験問題作成 | 4回 | 20単位 | ||
| 日本獣医師会生涯研修事業 | 18単位 | |||
| 合計 | 92単位 | |||
| 7. 更新単位を取得していない場合(1)または不足の場合(2) |
||||
| (1) | 認定筆記試験受験 | 80点取得 | 合計80単位 | |
| (2) | 不足分を認定筆記試験受験で取得する | 不足点数 | 合計80単位 | |
2023年10月3日記載。