がんの在宅療養 エピソード募集
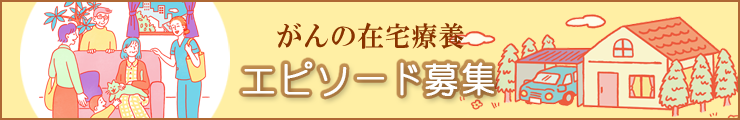
地域におけるがん患者の緩和ケアと療養支援情報 普及と活用プロジェクトでは、「がんの在宅療養」のウェブサイト、そして「がん患者さんとご家族をつなぐ 在宅療養ガイド」では、がんを患った方とご家族、身近な方が、住み慣れた場所で自分らしく安心して暮らすことができることを目指して、信頼できる情報、役に立つ情報をウェブサイトや冊子でご紹介してきました。在宅での療養を少しでもわかりやすく、あたたかみのあるかたちでお伝えするために、がんを患った方やご家族の支援に関わったり見聞きしたりした経験を、ガイドや体験談のかたちでお伝えしています。
また、当プロジェクトでは、全国のさまざまな地域における医療や療養支援を推進するためのエッセンスを引き出していくものとして、がん医療フォーラムや研修会を開催し、その開催記録やアンケート結果をウェブサイトでご覧いただいています。
掲載された情報、エピソードやコラム、フォーラムや研修会の開催記録は、「参考になる」「元気を分けてもらえる」「もう一度向き合えるきっかけとなる」といった声を、アンケートなどで多くいただいています。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により、がんを患う方やご家族のなかには、限られた情報のなかで不安やつらさを感じながら、「いつまでこの状態が続くのか」治療や生活への影響を心配しながら、ご自宅などでお過ごしになっていらっしゃる方が多くいらっしゃると思います。
当プロジェクトでは、ご家族・ご本人・支援する方をはじめ多様な立場の方、在宅施設や医療機関の皆さまのご協力をいただき作成された在宅療養ガイドやウェブサイトでの情報を、さらに充実された役に立つ情報としていきたいと考えています。
在宅での療養生活、治療の継続、普段の過ごし方などで、
伝えたいこと・・・「知ってほしい」「工夫している」「役に立つ」
そんな例やエピソード、がんを患う方・ご家族・支援者の方、医療や介護福祉の専門職の方へのメッセージなどを募集いたします。
この参加要項をお読みいただき、ぜひご協力をお願い申し上げます。
参加要項(ご応募いただくにあたって)
このたびの募集は、「がんの在宅療養」のウェブサイトに、「在宅療養のヒント」「コラム」「私からの応援メッセージ」として、患者さんとご家族向けの療養情報冊子やサイトに掲載させていただくものです。ホームページ「がんの在宅療養 地域におけるがん患者の緩和ケアと療養支援情報 普及と活用プロジェクト(https://plaza.umin.ac.jp/homecare/)」への掲載や、書籍の改訂版やエピソード集としての頒布を予定しております。
なお、スペースの関係上、お寄せいただいたエピソードすべてが掲載されるとは限りませんので、あらかじめご了承の上、ご応募ください。また、意味合いを大きく変えない範囲で編集させていただく場合があります。
| エピソードの例: | がん患者さんとご家族をつなぐ 在宅療養ガイド ご本人の体験談集 https://plaza.umin.ac.jp/homecare/guide2/10_01.html ご家族の体験談集 https://plaza.umin.ac.jp/homecare/guide2/10_02.html |
1.お寄せいただくエピソードのテーマについて
「がん患者さんとご家族をつなぐ 在宅療養ガイド」の章立てに沿ってテーマを設定しています。患者さんとご家族のQOL(生活の質、人生の質)の向上、がんになっても安心して暮らせる社会の構築に向けた、患者さん・ご家族の在宅での療養生活をよりよくするために、「知りたいこと」「伝えたいこと」について、役立つ/参考になるテーマを中心にご協力をお願いします。
テーマは以下の中からお選びください。ひとつ、あるいはご負担にならない範囲で複数のテーマをお送りいただくこともぜひご検討ください。
| (テーマ番号) | テーマ |
| 第1章 在宅での療養を始める | |
| (1-1) | 在宅のあり方は十人十色 |
| (1-2) | ご本人とご家族の心構え |
| (1-3) | 在宅療養に関する、信頼できる情報源 |
| 第2章 通院で治療を始める・続ける | |
| (2-1) | 治療を続けながら家で過ごす人が増えています |
| (2-2) | 通院治療に向けた準備と実際 |
| (2-3) | 通院での治療と副作用・後遺症への対応 |
| (2-4) | 薬物療法(抗がん剤治療)を通院で受ける |
| (2-5) | 放射線療法を通院で受ける |
| (2-6) | 手術療法前後の在宅療養 |
| (2-7) | アピアランスケア(外見の変化に対するケア) |
| (2-8) | がんのリハビリテーション |
| 第3章 社会とのつながりを保つ | |
| (3-1) | 療養しながらでも、仕事や社会生活を継続できます |
| (3-2) | 職場への伝え方とコミュニケーション |
| (3-3) | 仕事と治療の両立に関する、信頼できる情報源 |
| (3-4) | 家族内や地域での役割分担も見直してみましょう |
| (3-5) | 経済的な側面への支援制度 |
| (3-6) | 職場復帰に向けて |
| 第4章 住み慣れた場所で自分らしく暮らす | |
| (4-1) | 在宅で治療やケアを受けるときの準備 |
| (4-2) | 療養を支えるパートナー(在宅支援チーム)の探し方 |
| (4-3) | 在宅での療養環境を整えるには |
| (4-4) | こまめな相談と連絡が在宅療養のカギ |
| (4-5) | 支え合いの場を利用しましょう |
| 第5章 生きること、生ききることに向き合う | |
| (5-1) | 「最期のとき」について考える |
| (5-2) | 家で最期を迎えることについて考える |
| 第6章 人生の最期をともに生きる | |
| (6-1) | 身体的な変化に寄り添う |
| (6-2) | 心理的な変化に寄り添う |
| (6-3) | 痛みやつらさのコントロール |
| (6-4) | 家族もケアや介助を行うことができます |
| (6-5) | 本人と家族の心のケア |
| 第7章 お別れのとき | |
| (7-1) | 人生の最終段階を迎えるとき、温かく寄り添うには |
| (7-2) | 葬儀についての備え |
| (7-3) | 最期が近づいたときの変化と対応 |
| (7-4) | 大切な人を失ったご家族へ |
| (8-1) | その他、上記のテーマで当てはまらないもの |
2.お寄せいただくエピソードの内容
「がん患者さんとご家族をつなぐ 在宅療養ガイド」での各項目をテーマとして、1.の中からお選びいただき、在宅での医療や療養に役に立つ患者さん・ご家族・支援者の方向けの情報や、よりよい療養生活を送る上で参考になるような、エピソードやメッセージをお寄せください。 下記にお示ししたものはテーマに関する話題の一例ですが、必ずしもこの内容に沿う形でお書きいただく必要はありません。
3.文字数と応募いただくテーマ
| 文字数 | |
| 1つのテーマにつき400字程度でお寄せください。 ※「です、ます」調にてお願いします。 ※なるべく平易で具体的な表現でお願いします。 |
|
| テーマの数 | |
| 1つ、あるいは複数のテーマをお送りいただいても構いません。ご負担のない範囲でご協力くださいますようお願いいたします。 | |
4.応募方法と応募様式
下記のいずれかの方法で、必ず上記1.の「テーマ番号」「テーマ名」をお書きの上、ご応募ください。
| a) | 回答様式に記入して、応募フォームに入力して送信 |
| b) | 添付ファイルにてメール送信(下記「応募様式」をお使いください) |
| c) | 郵送にて送信 |
●応募様式はこちらです
・応募フォーム(推奨)
・応募ファイル
| メール: | canhomecare.jp @ gmail.com (迷惑メール防止のために@の前後にスペースが入っています。メールソフトにより、スペースが入ったままでは送信できない場合があります。送信できない場合は、スペースを削除してご利用ください。) |
| 郵送: | 〒173-8605 東京都板橋区加賀2-11-1 帝京大学医学部内科学講座 渡邊 清高 あて |
5.ご留意いただきたいこと
| ・ | お送りいただいたエピソードの内容をもとにコラムを編集作成します。そのためいただいた原稿がそのまま掲載されるとは限りません。場合によっては追加的に取材をお願いする可能性があります。その際にはあらためて確認をさせていただきます。 |
| ・ | エピソードが採用された場合には、薄謝を謹呈させていただきます。当方から連絡させていただく際のご連絡先などを応募様式にお書きください。また、ご承諾いただける場合には、協力者としてお名前や年代・性別・居住地などを掲載させていただきます。 |
| ・ | いただいた原稿をもとに作成したエピソードの著作権は「地域におけるがん患者の緩和ケアと療養支援情報 普及と活用プロジェクト」あるいは、当プロジェクトが許可する第3者が所有いたします。 |
| ・ | ご応募いただいたエピソードはスペースや冊子としてのバランス等を考慮し、掲載されない場合があります。あらかじめご了承ください。 |
| ・ | エピソードの内容によっては、選択していただいたテーマとは別の項目のエピソードとして収載させていただくことがあります。 |
| ・ | 文中に個人や地域を特定できる情報が含まれている場合には、表現や内容を変更することがあります。また、内容により専門家のチェックや修正を受けることがあります。 |
| ・ | 個人情報につきましては、当プロジェクトからのご連絡などに使用いたします。外部に提供することは一切ありません。 |
| ・ | 応募原稿は返却いたしません。手書き原稿の場合は、コピーなど控えをお取りくださいますようお願いいたします。 |
6.お問い合わせ先
こちらからお問い合わせください。


