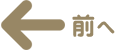認知症との共生社会に向けて 板橋サバイバーシップ研究会 2025
症例提示:医療介入が困難な認知症患者への対応
はじめに ― 訪問診療の現場から
皆さん、こんばんは。帝京大学の磯尾と申します。
私は帝京大学病院で物忘れ外来を担当しているほか、地域の在宅クリニックで訪問診療にも携わっています。今日はその現場で経験している「医療介入が困難な認知症患者さん」の事例をご紹介し、皆さまから、こうしたケースにどのようにアプローチすべきかについてご意見をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
症例紹介 ― 医療介入が難しい高齢者
症例は90歳台の女性です。ある年の夏頃から内服薬を忘れるようになり、年末にはほとんど服薬できなくなっています。そのころから易怒性や興奮性が目立つようになり、家族や近隣の方に対して感情的に怒鳴る場面も見られるようになっています。
翌年春、長年同居していた長男が亡くなり、その後、近隣に住む長女が泊まり込みで介護を始めたところ、認知機能の低下が急速に進んでいることに気づき、訪問診療が導入されました。
初回訪問時の印象ですが、ご本人との会話は「あなたさまはどちらからいらしたのですか」と繰り返すものでした。「○○のクリニックから伺いました」と答えると、「まあ、大変ですね。ありがとうございます」と返されますが、また同じ質問を何度も繰り返されます。やりとりの途中で「今のところ困っていることはありませんので」と話を打ち切られてしまい、それ以上の医療介入ができない状況です。
家族からの訴えと生活の実態
長女からは、ガス栓を閉めても本人が再び開けて使ってしまい危険なこと、弁当宅配を断ってしまうこと、庭の果物を拾って味噌汁に入れて食べてしまうなど、生活上の危険行動が多くみられると相談を受けています。ご本人には病識がほとんどなく、「自分は困っていない」という認識を持っています。体温や血圧の測定には応じてくださいますが、それ以外の医療介入は拒否されます。会話の中で中等度の認知機能低下がうかがえますが、正式な認知機能検査は拒否が強く実施できません。降圧薬も内服できず、血圧の高い状態が続いています。デイサービスやショートステイを提案しても、すべて拒否されています。
生活背景と環境の課題
この方は長年、精神疾患を抱えた長男と二人暮らしをしてきました。家事はすべてご本人が担い、ずっとその形で生活してきたため、長男の死を理解できず、「家にいない」と騒ぐこともあります。突然独り暮らしとなり、長女が泊まり込みで介護を行いながら、ショートステイを併用して生活を続けているという状況です。
生活環境については、70歳台で交通事故による腰椎圧迫骨折を起こし、両側の変形性膝関節症も進行しており、家の中の移動もやっとの状態です。もともと片づけが苦手で、片づける必要性の意識も乏しいため、室内は長年ごみであふれた状態になっています。この環境をどう整えるかも大きな課題になっています。
現時点の課題と今後の議論の方向性
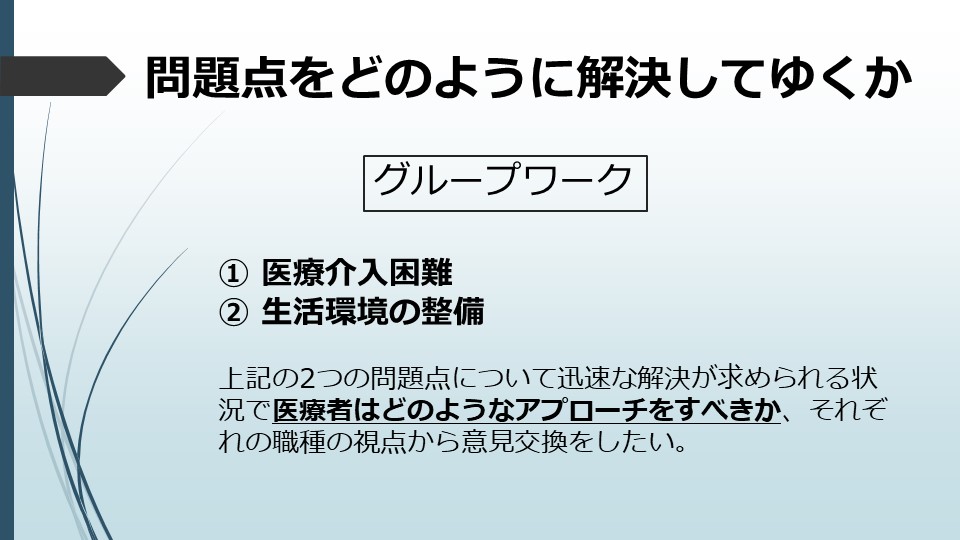
問題点は大きく2つあります。
1つ目は、医療介入が極めて困難であることです。ご本人は明るく多弁ですが、病気や治療の話になると表情が厳しくなり、認知機能検査や内服治療などを強く拒否します。
「人には頼らない」「家は出ない」「薬は飲まない」という三原則のような考えがあり、体温と血圧の測定以外の介入ができない状況です。
2つ目は、生活環境の整備が困難であることです。身体的な制約に加えて、住環境が衛生的にも安全面でも大きなリスクを抱えています。
このように、迅速な対応が求められる中で、医療者がどのようなアプローチを取るべきか、多職種の皆さまと一緒に考えていきたいと思います。本日はそれぞれの専門の立場から、現場での工夫や関わり方について、ぜひご意見をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。