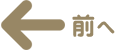認知症との共生社会に向けて 板橋サバイバーシップ研究会 2025
グループワーク:認知症との共生社会に向けて
房野:それでは時間になりました。今回の症例は正解のないテーマで、皆さんで一緒に考える場だと思います。最終的にどうなったかは磯尾先生から後ほどお話しいただく予定です。
それでは、グループで話し合った内容を順番に発表していただきます。
信頼関係の構築と生活機能の視点から
ケアマネジャー:医療介入困難への対応として、内服が難しいなら貼付剤を検討する案が出ました。また、まずは医療ではなく生活機能の視点から、「食事・睡眠・排せつ」が整っているかを確認することが重要だという意見です。
そのうえで、ご本人が何を大切にしているかを探りながら信頼関係を築き、そこから医療介入につなげる流れが望ましいと考えます。アルツハイマー型認知症が背景にあるとすれば、BPSD(周辺症状としての行動・心理症状)に対して薬物療法(ブレクスピプラゾールなど)が選択肢になるかもしれません。
生活環境整備では、介護保険サービスの活用を前提に、デイやショートステイ利用中に家の整理を進める方法が提案されました。長女が介護の中心となっているため、長女を支援の起点にしながら、誰かが継続的に関わることが重要だという意見でまとまりました。
房野:ありがとうございます。やはり信頼関係づくりが第一歩ですね。ショートステイは拒否されていたようですが、つながりの糸口として検討できそうです。
本人理解と関係性づくりの工夫
ケアマネジャー:「医療介入困難」と感じているのは支援者側であり、ご本人自身は困っていないのかもしれません。まずは会話を通じて信頼関係を築き、医療者ではなくいわば「友人」として受け入れてもらえる関係を目指します。息子さんの精神疾患の影響や、ご本人の発達的な特性も視野に入れながら、娘さんからの情報収集が大切です。
生活環境では、ご本人と一緒に片付けを進めるなど、本人の気持ちに寄り添う姿勢が重要です。支援者の写真を貼るなどして「誰が関わっているか」を可視化する工夫も提案されました。娘さんには、ご本人の気持ちを尊重しつつ、旅行や教室などポジティブな目的で外出につなげる提案が有効ではないかという意見が出ています。
房野:ありがとうございます。「本人が困っていないなら、医療介入困難ではないのかもしれない」という視点は大事ですね。写真を貼る工夫も素晴らしいと思います。
ゆっくりとした関わりと安心の確保
ケアマネジャー:ショートステイを利用できているならデイサービスも可能ではないかという意見が出ました。内服が難しい場合は貼付剤などを提案します。
物が多く、捨てられない背景にはご本人にとっての「大切さ」があるため、焦らず、同じ服装・少人数で訪問を続けるなど、安心できる関係をつくることを大切にします。
また、緊急時に備えた訪問看護や医療との連携が確保できるだけでも支援者として安心できるという意見もありました。
房野:確かに、訪問診療が入っているだけでも大きな意味があります。物の整理には信頼関係が不可欠ですね。
言葉と環境を工夫したアプローチ
ケアマネジャー:拒否が強い場合は無理に介入せず、世間話から始めて時間をかけるのが良いという意見です。文字が読めるなら「ガス使用注意」といった表示で環境を整える案も出ました。
薬を嫌がる場合は「サプリメント」と伝えるなど、受け入れやすい言葉遣いを工夫します。また、リハビリという言葉に抵抗がある高齢者も多いため、「体を楽にするための体操」という表現で介入を試みる案が示されました。訪問診療が入っている時点で、すでに医療介入の第一歩は進んでいるとも言えます。
房野:ありがとうございます。拒否感を避けるための言葉選び、とても実践的ですね。
本人理解と「片付けない支援」
訪問看護師:まずは90歳台という年齢や生きてきた背景を理解することから始めます。戦争を経験し、自分で生活を切り開いてきた世代なので、「支援者」という立場を明確にして信頼を得ることが大切です。腰痛や移動の困難さがあるため、認知症ではなく身体面から「腰を楽にする」などのアプローチが有効です。
生活環境では、無理に片付けず、ご本人が大切にしているものを尊重します。本人が満足している空間を、支援者の都合で変えるのではなく、「安全のためにこうしてみましょう」と寄り添いながら提案していくことが重要です。
房野:ありがとうございます。「散らかった状態でも本人にとっては秩序がある」という考え方、まさにその通りですね。
動線確保を優先した環境整備
地域包括支援センター:血圧はやや高めでも急がず、信頼関係を築きながら段階的に医療につなげるのが良いという意見です。環境整備については、片付けよりもまず動線の確保を優先します。転倒や避難経路の確保など、安全を保つ範囲で整理を進めていく方針が共有されました。
房野:ありがとうございます。物を「捨てる」よりも「動ける空間をつくる」発想が現実的ですね。
継続訪問と多様な支援手法
医師:本人が困っていない限り、すぐの介入は難しいため、根気よく訪問を続け、人や話題を変えながら信頼関係を築いていくことが大切です。薬物療法だけでなく、運動・食事など生活全体を支援に含める発想も重要です。環境整備では、手すり設置や調理器具のIH化など安全性を高める工夫、ヘルパーや小規模多機能型居宅介護の利用、訪問を通じた片付け支援などのアイデアが出ました。
房野:ありがとうございます。興味や趣味などの共通点から信頼を築く方法はとても有効ですね。
「待つ医療」と本人中心の視点
ケアマネジャー:問題が起きていないなら、無理に治療を進めず、医師が何度も顔を出して辛抱強く関わる姿勢が必要です。治療を行わない場合も、家族への説明と同意が不可欠です。
また、長男の死など心理的な背景にも目を向け、何が本人の「困りごと」なのかを探ることが大切です。「人に頼らない」「家を出ない」「薬を飲まない」という強い信念は、この方の生きる力でもあります。その強さを肯定的に捉え、本人の味方として寄り添うことを基本に据えます。最終的には、誰が関わるかを明確にし、地域の多職種が協働することで支援を続けることが大切だという結論になりました。
房野:ありがとうございます。非常にバランスの取れたまとめです。本人の意志を尊重しながら支援を続けるという視点が印象的です。
信頼関係と多職種協働の重要性
房野:どのグループからも「信頼関係をつくること」が共通のキーワードとして挙がりました。医療介入困難というのは、医療者側が感じる困難であって、本人にとっては「今の生活で十分」なのかもしれません。だからこそ、焦らず、寄り添いながら、支援者全体で継続的に関わっていくことが必要だと感じます。
それでは、最後にこの患者さんへの実際の対応について、磯尾先生からご紹介いただきます。
はじめに ― 信頼関係づくりの重要性
磯尾:皆さま、本当に貴重なご意見をありがとうございます。お話を伺って、やはり信頼関係を時間をかけてつくっていくことの大切さを改めて感じています。そして、患者さんが本当に何に困っているのか、その一点に丁寧に寄り添うことがいかに重要かを痛感しています。
これから、私たちが実際にどのようにアプローチしたかをご紹介します。これが最善の方法だったとは限りませんが、一つの経過として共有させていただきます。
初期対応 ― 「世間話」と「血圧測定」から始める関わり
皆さまがおっしゃったように、すぐに治療や検査に入るのではなく、まずは世間話から始めました。2〜3回ほど訪問し、世間話を交えながら「血圧や体温が変わっていないね」といった軽い話題をきっかけに短時間の訪問を続けていきました。
もともとこの方は長く高血圧の治療を受けていたこともあり、血圧測定だけは拒否せずに受け入れてくださいました。ある日、本人から「頭が痛い」と訴えがあり、それが一つの転機となりました。
治療への導入 ― 「困りごと」から内服へ
頭痛の訴えをきっかけに、血圧測定の結果を一緒に確認し、「血圧がとても高くなっていることが頭痛の原因かもしれません」と説明しました。この説明を納得していただいたことで、「高血圧症に対する内服だけなら」と受け入れていただけるようになり、少しずつ薬への抵抗感が和らいでいきました。ここが治療開始の第一歩になりました。
BPSD(認知症の行動・心理症状)への対応 ― 内服液を用いた工夫
経過の中で、怒りっぽさや興奮、夜間のせん妄のような症状が出てきました。
ご家族の強い希望もあり、少量のリスペリドン内服液を服用していただくようにしました。結果として興奮が落ち着き、穏やかに過ごせる時間が増えました。
生活支援への拡大 ― デイサービス導入の工夫
次のステップとして、生活リズムを整える目的でデイサービスをお勧めしました。
「おいしい昼食を食べに行く」「外で気分転換をする」という目的に置き換えて提案したところ、前向きに受け入れてくださいました。
最も大きな要因は、デイサービス職員の方々のやさしい対応です。これまで厳しい表情を見せていた患者さんが、出発前にお化粧をして、笑顔で送迎車に乗るようになりました。スタッフの温かい関わりが、行動の変化を引き出したのだと思います。
環境整備と次のステップ
デイサービス通所が定着したことで、その時間を利用して自宅の片付けを進めることができました。結果として、大量のごみを片付けました。確かに思い出の品も混ざっていたと思いますが、生活空間は大きく改善しました。
現在はショートステイを併用しながら在宅生活を続けており、グループホームへの入所申請も進めています。多職種の協力と家族の支えがあってこそ、ここまでたどり着けたと感じています。