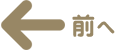住み慣れた地域でがん患者さんを支えるチームづくり 帝京がんセミナー/地域包括ケア懇話会 2019
【第1部】導入と事例提示
患者さんの生活を支える支援の実際

宮本 博司さん
地域包括ケアにおける大学病院の役割
今日は、「患者さんの生活を支える支援の実際」ということで、帝京大学病院がどういう形で患者さんの支援に取り組んでいるかということと、また皆さんもご存じとは思いますが、地域包括ケアとはどのようなものかということを、今一度おさらいするような形でお話ししていきたいと思います。
最初に、帝京大学病院について簡単にご紹介します。当院は1000床を超える病床規模を持つ病院で、2009年に新棟ができて10年経ちました。基本理念は「患者さんそして家族とともに歩む医療」、そして基本方針の中には「地域への貢献」というフレーズが含まれています。つまり、地域包括ケアへの注力も基本方針に沿ったものということです。病院機能としては、高度救命救急センターを有する救急・急性期病院で、救命救急に非常に力を入れています。また、都内に4施設ある地域がん診療連携拠点病院(高度型)のひとつで、外来化学療法、緩和ケアチーム、がん相談支援室などさまざまな機能を有します。
最近、当院の病院長は「当院は地域に根ざした大学病院である」とよく話しておりますが、実際、当院にいらっしゃる患者さんは、外来・入院の患者さんともに板橋区、北区、豊島区、練馬区、そして埼玉在住の方が中心です。このあたりの医療圏域を広く見ていくと、おそらく8割の患者さんは地元で医療を完結させていると考えられ、当院は必然的に、当地域の地域包括ケアの中で治療の中核となる役割を担う存在になっていると考えます。
必要なのは顔が見える関係づくり
2017年度の医師国家試験では、400問のうち4問、地域包括ケアシステムをはじめとする介護保険に関する出題がありました。つまり、今は医学教育の段階から地域包括ケアの必要性の高さを認識していただくことが必要とされる時代になっていると考えられます。介護保険や医療保険の制度は全国画一ですが、地域包括ケアシステムは、「地域特性に応じて市区町村独自に築き上げるもの」とされています。制度というより「仕組み」であり「つながり」であるので、この地域で何ができるかということは、私たち自身で考えていく必要があります。ちなみに「地域包括ケア」という言葉のもととなったのは、1980年代なかば、病院内に福祉の窓口を設置し医療と福祉をつなぐ活動を行った市立三次中央病院(広島県)による実践ですが、その言葉が未だに言われているということは、まだまだ当初課題とされたことが達成・実現できていないということなのでしょう。
最近、AIP(Aging in Place)という言葉を聞かれた方は多いのではないでしょうか。これは「年を重ねても安心して住み慣れたまち(地域)に住み続ける」ということで、東京大学高齢者社会総合研究機構の辻哲夫先生によって提唱された概念です。板橋区もまた「板橋区版AIP」を掲げて、区が目指す地域包括ケアの姿を示していますが、その二番目の柱には「医療・介護連携」が挙がっています。さらにその中身を細かく見ていくと、「在宅医療の体制づくり」「病院と地域医療の連携」などといった内容が出てきますが、その中でも重要なのは「顔が見える関係づくり」という言葉だと、私は思っています。先日、ある場所でお会いした病院の元病院長の先生が「顔が見える関係作りではなくて顔を見せる関係だ」とおっしゃっていましたが、私も「顔が見える」からさらに踏み込んで「顔を見せる」、そこまでいかないとだめなのではないかと、そのように思い始めています。
地域包括ケア推進のための制度『入退院支援加算』
「顔が見える関係」づくりは、患者さんのQOL(生命・生活・人生の質)を支える取り組みとも関係してきます。医療やリハビリテーションの流れは、大きく分けて急性期、回復期、生活期、そして終末期の4つで、患者さんはこれらのステージのどこかにいるということになりますが、そのときにはそれぞれ異なる支援が必要です。例えば急性期は、生活面では多くの犠牲を払っても命が最優先ですが、回復期は食堂で食事ができて、自分でトイレでの排泄ができる、といった生活の質が重視され、生活期はその人それぞれの人生の質が最優先となります。そして、終末期は、尊厳の尊重が何より重要となります。尊厳をどうとらえるかは非常に難しいところですが、シンプルに言えば「その人が大切にしているもの」ということではないかと思います。
では、それぞれの時期の患者さんのQOLをどうやって支えるかということですが、そこにつながるのが「入退院支援加算」です。専従の退院支援の看護師または社会福祉士を置き、入退院時に制度に即した支援を行うと診療報酬上の加算を得られるという制度ですが、これはそうすることで患者さんが退院後の地域での療養や生活を安心して送れるよう問題解決を行うとともに、次の段階につなげるためのものであり、実は地域包括ケアシステムの推進のためにできてきた制度です。最も高い基準では、入院3日以内に退院困難と思われる対象者を抽出し、7日以内に患者さん・家族と面談、さらにカンファレンスを行うことが必要となっています。なおかつ介護連携指導料という新しい制度があり、ケアマネジャーの方に病院に来ていただいて患者さん・ご家族と話していただくと、指導料として報酬上の加算の対象になります。このように、急性期病院にとって入退院支援の担当スタッフは地域とのパイプ役で、患者さんが医療やリハビリテーションのステージを移り変わる場面で重要な役割を担う存在と考えます。
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の実現のためには
急性期から生活期に向けた支援目標の設定は、今、たくさん行われています。1990年代のオーストラリアのケアの現場で使われていた言葉そのままに、ショートタームゴール(短期目標)とロングタームゴール(長期目標)という形で考えられています。短期目標はきわめて物理的で、疾患の治療、リハビリテーションの実施、医療福祉の制度の利用などが設定のポイントですが、ロングタームゴールは望む生活や人生の実現、そして尊厳の尊重などがポイントとなります。ACP(Advance Care Planning:アドバンス・ケア・プランニング)も、この長期目標の方に関わってくることであり、これをどのように行っていくかというのが新しい課題となっています。
ACPは、主に終末期に近い患者さんが、自らの人生の最終段階の医療・ケアについて考え、医療・ケアチームなどと繰り返し話し合い共有する取り組みのことで、私は2018年に日本医師会が終末期の取り組みの見本としてACPを紹介しているのは画期的だったと思っています。これによって教育の場も含むさまざまな現場でACPに注目が集まり、いわばちょっとしたトレンドになってきたからです。
ACPは「意思決定を支援するプロセス、過程のこと」と定義されています。患者さん主体で、医療とケアのチームが「繰り返し話し合いを行う」ことがACP であり、「患者さんの人生観、価値観、希望」という言葉が定義の中に入っています。まさにがんを含めた終末期の患者さんに向き合うとき、私たちが頭に置かなければいけない考え方だと思います。
そのACPの実現のためには病院と地域の連携、話し合いが欠かせませんが、2018年にケアマネジャーの方にアンケートをとった結果、「入退院支援部門の医療ソーシャルワーカー・看護師と連携が取れていますか」という質問では「まあまあ取れている」が半分ぐらい、退院に関しての連携に関する質問でも「ある程度取れている」ということが見て取れるものの、入院に際しての連携については「あまり取れていない」という回答が7割以上となっており、明らかに入院のアクセスが悪くなっていることがわかりました。さらに、「病院にカンファレンスを依頼した際に実際に実施してもらえるか」という質問では、「依頼すれば80%はやってもらえる」という回答は2割以上(27%)、一方で、「実施率20%以下」という回答も2割ほど(17%)と、かなりのばらつきがあるのがうかがえる結果でした。またそれ以前に「急性期病院の敷居が高い、行くのがつらい」という声もありました。そういう意味で、医療側からみた課題は、介護の部分を担う方々といかに一緒にやっていけるかという部分であり、調整が必要でもあると考えます。
ケアマネジャーが力を発揮できる体制づくりを
地域包括ケアは多職種が加わって行うことが大前提で、それらを実際に生かすための図面となるのはケアプランです。ケアマネジャーは介護福祉法による介護保険のケアプランをすればいいようなイメージですが、地域包括ケアの部分では医療や地域との関係も含めてコーディネートしてくださって構わないので、ぜひ各地で力を発揮していただきたいと思います。
板橋区や北区の周辺を含め、東京という地域は区境があってないようなもので、区ごとの壁を越えてサービスが行われていたり、ケアマネジャーが行き来していたりします。そういう意味では、自治体や地域ごとに仕組みを作ることが求められる地域包括ケアプランの中である意味「難しい地域」に位置づけられるかもしれませんが、それでも地域における支援の仕組みやあり方を専門職と専門職が協働してつくっていくためには、こういう場で、顔と顔を合わせて議論していくことが必要です。そして、医療の分野と福祉の分野を行き来する、橋渡し役となれるのは、制度的にも立場的にもケアマネジャーだと私は思います。そういうことができる環境をつくっていければと考えています。