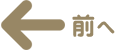がん医療フォーラム 2018 がんを知り、がんと共に生きる社会へ
【第2部】パネルディスカッション
ディスカッション(1)
私たちが望む「がんと共に生きる社会」
| モデレーター: | 渡邊 清高さん、館林 牧子さん |
| パネリスト: | 長瀬 慈村さん、桜井 なおみさん、池辺 英俊さん、馬上 祐子さん、岡 悦郎さん、濱本 満紀さん、岸田 徹さん |

ディスカッションの様子

ディスカッションの様子
渡邊:今まで、患者会・患者支援団体の方からご報告をいただきました。正力厚生会さんが助成している事業としては、「医療機関向け支援」として、私が最初に話をさせていただいた、「がん患者さん向けの療養情報の普及」というプロジェクトをさせていただいています。そして、患者さん・患者支援団体の方向けの助成として、「なかなか情報が届かない」「情報がそもそもない」とか、「なかなか他につながらない」という課題について、さまざまな活動をしていらっしゃる皆さまにご報告いただきました。いろいろなところでつながりの芽ができているという、お話でしたね。
館林:皆さん、おそろいになりました。それでは、これからみんなでディスカッションに進みたいと思います。

渡邊 清高さん

館林 牧子さん

池辺 英俊さん
渡邊:ご紹介いただいた4つの支援団体の方に加えて、第1部でご講演いただきました長瀬さん、桜井さん、池辺さんにも参加いただいて、お話をしていきたいと思います。
がんと共に生きる社会に必要な要素とは
このパネルディスカッションのテーマ、「私たちが望む『がんと共に生きる社会』とは」です。「がんと共に生きる社会」という言葉の中には、いろいろな意味合いが含まれてくると思います。実際の活動報告や、活動を踏まえた今後の展開について、お話をしていただきました。
皆さんが今の活動をされるに至った背景、どうしてこの活動をされていらっしゃるか。そして、私たちが考える「がんと共に生きる社会」というのは、どういうイメージなのかということを、ぜひお話しいただきたいと思います。まず、池辺さんからお話しいただけますか。
池辺:トップバッターというのはびっくりしました。先ほどお話しさせていただいた中で、「患者学」「患者力」と言うのでしょうか、患者側もやはり情報を得てしたたかに、いろいろと医師側と情報交換できるようにならなければいけないということをお話しさせていただきました。
先ほど、ちょっと一つだけ言い足りなかったと思うことがありました。「インフォームド・コンセント」という、医師が伝えて、患者がそれを受けて同意する。「同意する」ということは、その治療において「患者も責任を負う」ということだと思うのですけれども。私の場合もそうだったのですが、多分改善されていないと思うのですが、「インフォームド(説明を受けて)コンセント(同意する)」、これが一度に行われるというのは、私は無理があるということを強く感じています。ぜひ、今後医療関係者にお願いしたいのは、やはりインフォーム、伝えたり説明したら、時間や日にちを置いて同意するということを、これから医療界に浸透させていく必要があるのではないかと思います。
その際には、「治療法はこの資料を参考にしてください」とか、また、資料を渡すとか、できるだけ患者さんをサポートして、情報を医療側から提供するという文化を、もっと徹底させていく必要があるのではないかと思います。私はいま、「ヨミドクター」というサイトを管轄していますので、そういった情報を今後刷新していきたいと思っています。
「インフォームド・コンセント(説明に基づく同意)」を考える
渡邊:ありがとうございます。「インフォームド・コンセント」というのは、どうしても手続き的なものになってしまいがちです。例えば、診断されたときに、「検査の資料ですから、こちらを読んでおいてください」とか、「今、ここに署名してください」「次の検査が」とかというかたちで、限られた時間でたくさんの情報をいっぺんにお話をしないといけないことがあるという問題もあります。
ただ、実際にはその「コンセント」というのは、手続きの一つという見方もあるけれど、「もっと知りたいことがある」とか、検査が必要なことは分かったけれど、「疑問や質問があったら、後で聞いてもいいですよ」とか、「場合によっては、他の選択肢について相談できますよ」ということも含めてやり取りできるといいですよね。
館林:最近では「インフォームド・コンセント」だけではなく、「シェアード・ディシジョン・メイキング(shared decision-making)」といって、例えば、乳がんでもいろんな治療法があり、先ほどの標準治療、つまり推奨できる治療法の中にもいくつかの選択肢があることがあります。ご自分の生活とか人生に合わせて、治療法を医療者と一緒に考えていく方法も出つつあると聞きました。
渡邊:そうですね。ご本人が、「今すぐに決めなきゃいけない」という部分が一部あるかもしれませんが、話し合いの中で例えば、ご本人の「生活」や「治療に関する思いや願い」ということも含めて、普段やり取りができるといいと思いますよね。 長瀬さん、「がんと共に生きる社会」について、いかがでしょうか。

長瀬 慈村さん
長瀬:インフォームド・コンセントということ自体が、説明をして選んでもらうということになっているのですけれども、僕は本来、インフォームド・コンセントというのは、自分の置かれた状況・病気の状態を理解した上で、自分自身でどういう治療を選択するかを判断できるような状態に説明することがインフォームド・コンセントだと、僕は思っていて、そのようにしています。
その場で「お答え、どうしますか」というのではないと僕は思っています。例えば、僕も手術する人間ですので、「じゃあ、うちでやりますか」と言って、「どうしますか。それとも他で手術しますか」と、目の前で答えろと言ってもそれは難しいのですね。ですから、やはりそれはアンフェアなやり方であると思います。
僕は、いったん説明をした後、「翌日、電話でいいから連絡してね」としているのですけれども、そうは言っても、その説明をする時間をどうするかというのと、「翌日」あるいは「来週」といっても、大きな病院だと予約取ってもう1回来ることも難しいとか、いろいろな現実があります。クリニックでできても、大きい病院ではなかなか難しいところがあります。
今は、乳がんの場合ですと、例えば、「乳がん看護認定看護師」というのが育ってきています。医師が話したことをもっとかみ砕いて患者さんに話すことができるようになっています。大きい病院ですと、認定看護師さんがいて、自分の病状に合わせて「こういうことなんだよ。こういう選択をすることができるよ。このときに、こういう問題があるよ」というのを、経済面の相談も含めて全部できるようになってきています。そういうところをご利用されるといいと思います。
「ムンテラ」とかという言葉もあって、「患者さんと家族に説明するムンテラがあります」、とか言うのですけれども。ムンテラとはどういう意味かというと、「口頭による治療」という意味なのです。説明するということじゃなくて治療を施すという意味合いなのですね。だからやっぱり、そういうものを何となくおざなりに使っている医療界が変わらないといけない、変えていかないといけないと思っています。
病と共に生きるという、考え方
「がんと共に生きる」と言いますが、何でもそうですけれども、どの病気が特別なことじゃなくて、生きていけば、年を取っていけば、必ず何かの病気になっていきます。また、若いときから持っているいろんな特徴があって。それぞれに認め合って、その人が生きていくための手助けをし合っていく、自分も助けてもらいながら生きていくというのが当たり前のことなので、特別に「共に生きる」と言うこと自体が、やはり日本は遅れているのかと感じてしまうところですね。
実は僕のおふくろは48のときに膵がん、僕が医学部入った年に亡くなりました。親父は胃がん、大腸がん、それから悪性リンパ腫。3つやって、90まで生きましたが、早期、早期で見つかって生きました。自分の両親で4つのがんを持っているものですから、もちろん僕もなるだろうなと思っていますし。最近は、検診も受けるようにしています。
渡邊:ありがとうございます。がんというのは身近な病気とはいっても、当事者になってみると、その備えが難しいということがあります。普段のやり取りの延長線上で、例えば、「これからどう生きていきたいか、どう過ごしていきたいのか」ということができるといいのですが。病気のことだとか、先ほど桜井さんからもお話がありましたが、「人生設計の見直し」というかたちになってくると、なかなか冷静に判断するのは難しいことがあるのだろうと思います。
今は、こうしたことを声に出していただけると、何かしら相談できる窓口ができつつあります、がんの場合はすぐに決断を迫られるということではなくて、何度か別の方の意見を聞いたり、「セカンドオピニオン」で意見を聞いたりということもできます。そういった仕組みを活用していただくのも、一つの方法と思って伺っていました。 桜井さん、いかがでしょうか。

桜井 なおみさん
桜井:私が望むのは、やはり「がんになっても安心して暮らせる社会」だと思っています。たとえどんな状態であっても、安心して自分らしく暮らせるような社会を、ちょっとずつでも進めていくことができたらいいと思っています。
診察室とか、そういうところのやり取りで考えていくと、100年くらい前のドクターで、ウイリアム・オスラーという方がいて、「よき医師は病気を診る。よりよき医師は患者を診る」とすばらしい言葉を残しています。私は「よりよき医師」がどんどん増えていってほしいと思っています。
社会背景に応じたオーダーメイドの支援の必要性
治療説明をいただくときも、患者の社会背景に応じた治療計画の説明をしてほしいと、ずっと言っています。通り一辺倒にプリントアウトしたものを渡されたり、「患者さん向けの資材がこれです」と、渡されたり。それはどうでもよくて、「私にとってどうなのか」「その治療が私の生活にとってどんな影響があるのか」ということが聞きたかった。でも、そういうオーダーメイドのものがなかなか入ってこないものです。
2018年4月から、「治療と仕事の両立支援」といって、就労支援のことに関して診療報酬が付くようになりました。それはまさに患者さんの社会的背景に応じた治療説明と書類の契約の交換になっていくと思います。ぜひそれを「診療報酬付いたから」ではなく、当たり前のことのようにやっていっていただきたいと思います。診察室のやり取りは、キャッチボールだと思っています、投げる球も優しく捕れるだろうし、もらった側も、それだったらば、「じゃあ、どうなの?」と、自分の言葉で返せるようになるのではないかと期待をしています。
渡邊:患者さんの言葉とか患者さんの目線で病気のことの話をするのは、たやすいようで難しく、どうしても治療や診断の話題が先行しがちで、患者さん自身も声を出しづらい面があります。生活のこととかお金のことまで話してよいのだろうかと、話すらできなくてずっと悶々と悩んでいらっしゃる方も多くいらっしゃると思います。直接担当医に言いづらかったら、例えば、がん相談支援センターを訪ねてみるとか、ご家族から聞いていただいたりとか、看護師さんに聞いてみたりすることもできます。まずは、声に出していただくことが大切ですね。
就労支援の実際と工夫
館林:私も、今は所属長として管理職業務をしているのですが、会社の中にも、社員でがんの人が結構いて、この間、手術から戻ってきたのです。手術のほうが大掛かりなのですが、その後は割と回復していらっしゃいました。抗がん剤治療のときは、はじめはお元気だったのですが、その後に結構ダメージが来た、ということがありました。
一緒に「復職後にどういう仕事をやっていこうか」と言っているときに、ご本人は「すぐにやりたい」とおっしゃるのですが、どうやって相談していったらいいのか、いま一つ私も分からなくて。そういうことがもっと普通にできるようになって、「今、どういう状態なのか」というのが私たちにも分かるようになるといいなと思って、桜井さんのお話をお伺いしていました。
桜井:すごく重要なところです。しかも、「働ける」と言っていても、焦りから「働ける」と言っているケースもあります。心と体と、それから今の治療計画や経済的なところが、本当にバランスが取れているかどうかということを、総合的に考えて仕事を決めていくことが、すごく重要だと思っているところです。
その中で、多分医学的に、その仕事の場合絶対にやってはいけないことはあるのです。例えば、タクシーの運転手さんは、眠気が出るのに「仕事に戻りたいです、大丈夫です」といっても、やはり駄目ですよね。人を乗せていて事故を起こしてしまったら。しかもそれが、フッと寝てしまうことがきっかけになるというのは避けなければいけないです。
でも、「合理的配慮」といって、ちょっと配慮してほしいこと、例えば「月に1回の通院時間は確保してください」と、会社に病院から言ってもらえたら、私たちはすごく楽なわけです。患者自身から言いにくいことでも、きちんと情報共有していくこと、例えば医師から言ってもらえると、すごく楽になるのではないかと思っています。
渡邊:生活上の影響とかというのは、なかなか分かりづらい部分です。「この薬が効く」と言っても、効くのだけど副作用として手のしびれがあって、家事をするのにすごく支障が出るかもしれないとか。脱毛の副作用があって、対人的なお仕事をされていらっしゃる方だと、ご本人にとってはかなりつらいとか。あとは経済的な部分に関して、これが良いことは分かっているのだけど、経済的な面も含めて心配があって、治療について判断ができない、ということもあります。
いろんな悩みを抱えていらっしゃる場面があると、それが言葉としては「治療をやりたくない」「ちょっと自信が持てません」というかたちになってしまいます。でも、その言葉の奥を掘り下げていくと、ご本人が「一番大切にしたいこと」「一番つらくて悩んでいること」を、なかなか引き出せ切れていない、ということがあり得ます。患者さんだけにそれを押し付けるのではなく、こうしたことを引き出すためのいろいろな工夫や仕組みというのが、必要なのではないかと思って聞いていました。
桜井:たぶん、それを主治医だけが対応しているということがもう限界だと思います。看護師さんとかソーシャルワーカーとか得意な方がいらっしゃるので、そういう人たちと情報共有をしていくこと。OT(作業療法士)、PT(理学療法士)の方も例えば20分リハビリをやっていると、私もいろんなことをこぼしたことがあるので、悩みが拾い上げられていると思います。そういうことが、チーム医療の実践なのではないかなと思っています。
私自身も、副作用とか後遺症が「これなんだ」と自分で分かったのは、1年目くらいのことなのです。そのときには、急性期の病院にはほとんど行っていませんでした。これからは、地域がどうそれを考えていくかというところが必要です。そういうときに、患者会とか、病院外で支える人たちの活動が中心になってくるのかなと思っています。
オープンに話せる社会に向けた意識の変化を
渡邊:ありがとうございます。岸田さん、いかがでしょうか。

岸田 徹さん
岸田:「がんと共生する社会」に対してですね。僕は、なおみさんがおっしゃったように、「がんになっても安心して暮らせる社会」、そのためには、僕の情報発信している意味からすると、「やっぱりオープンに話せる社会」だと思います。オープンに話すことは今は難しいと思っています。例えば「がんになりました」と言ったら、日本の場合によく聞かれるのは、「食べ物が悪かったの?」とか、「何かストレスがあったんじゃないの?」というようなかたちで、過去を掘り返されるのですね。そうしたら、何か自分が悪いことをしていたから、がんになった、みたいな気持ちになります。今は2人に1人ががんになる世の中じゃないですか。みんながなる可能性があるのに、「自分が悪いことをしたから」といった感じで言われたら、それ以上何も言えなくなってしまいます。「前世が悪かったんじゃないの」とまで言われてしまいます。そういう意識も、一部にはあるのですよね。
ですから、ここにお越しの皆さんは、きちんと理解をしていただいていると思いますし、「がんになったんだ。じゃあ、一緒にこうやって頑張っていこうね」というかたちで支えていってもらえたら、それが「がんとの共生社会」の一歩だと思います。それを患者さんも、隠さずにオープンに話せるという世の中になれば進んでいくのだと思います。
渡邊:岸田さんの「がんノート」を見て思うのは、発信することについて二の足を踏んでいらっしゃる方が多いのだけれども、岸田さんが今までの殻を一歩乗り越えて発信されることで、「私も」とか「自分も」ということで、どんどんみんなが背中を押されるように発信されています。そういうのを見て、またさらに元気づけられる方がいて。そういうつながりは、医療者と患者さんとの普段の診療の場面では難しいけれども、でも、そこで横につながろうというエネルギーというかドライブが、すごく大きいメッセージになるのではないかと思っています。
岸田:もちろん、無理して発信する必要はないですけれども、時間が経って、発信してもいいなというかたちになったらで、無理する必要はないと思います。だって僕も、親には「がんということを言うな」とも言われていましたから。けれども、「ブログやっちゃっているけど、ま、いいか」みたいな、そんな感じでした。
コミュニケーションを積み重ねる
渡邊:そこで悩んでいることも含めて、素の自分を出した上で、そこも共感できる部分というのはすごく大切なんじゃないかと思って聞いていました。濱本さん、いかがでしょうか。

濱本 満紀さん
濱本:社会ということで考えますと、非常に個別的な話になってしまうかもしれませんが。ここからの積み上げということで、ちょっと申し上げることができればと思います。私は先ほどから、「情報」という話をしてきました。ただ、やはりこういう情報サイトを作っていると、いいものを作ってくれたという反応はいただくのだけれども、同時に、これをどうやって生かそうかというところで足踏みをされる方も多いのです。どれだけ適切な情報、自分に合った情報を得られても、それを使えなかったら宝の持ち腐れです。そこに介在するのは「コミュニケーション」です。お医者さんに対してであり、看護師さんに対してであり、家族に対してなのかもしれません。
コミュニケーションというのは双方向のものです。私たちが作った冊子では、患者と主に医療チームとのコミュニケーションについてまとめています。患者さんはこんなふうに、お医者さんに対して、「もっと聞いてほしい」「パソコンの画面ばかり見ないでこっちを見てほしい」ということはいっぱいあります。そうした調査もしました。でも、お医者さんからも、言いたいことはあるんだよと。「矢継ぎ早に何でもかんでも同じことを聞かないでほしい」、そういう医療者のご意見も入れてあります。
それを、どうすればすり合わせができるかということで、お医者さんたちと患者さんたちに、「ぶっちゃけ座談会」というのもしてもらっています。こういう、一日一日の、一言一言の積み重ねが変えていくんじゃないかなと思います。例えば、インフォームド・コンセントですとか、シェアード・ディシジョン・メイキング(Shared Decision-Making)は、一朝一夕ではできません。その場で下手を打ったと思ったら、もう終わっちゃうじゃないですか。それより初診のときに、にっこり笑ってあいさつをする。先生も「いい天気ですね」「雨、降りそうですね」の一言でもいいのです。そういうことから始まると、この調査の中でもありましたが、バッドニュース(悪い知らせ)をお医者さんがいかに気を遣って聞いたり、伝えたりしてくれるか。そういうテクニックよりも、最初に「こんにちは」と言ってくれた、「いいお天気ですね。猫の名前は何?」と言ってくれた、そのことが、ずっとずっと心の負担を軽くしていって、バッドニュースを受け入れられたというようなお答えが、実はすごく多いのです。そういうことから、私はやはり、一つ一つの小さいことの積み上げが、大きく広がっていったときに、大きなうねりになるような気がします。
さっき「家族」と言いましたが、私は、何人もの家族を失った遺族です。家族の方は、コミュニケーションがうまく取れないで悩んでいます。ご本人が、家族が勧める治療を受けないといけないのかということで、ものすごく悩んでいらっしゃる。そのコミュニケーションをどう取ればいいのか、自分の気持ちをどう伝えればいいか、これが実は一番難しかったりします。もし、残念にして遺族になられたとしても、そのときにご自分が対応されたことに対して、後悔を絶対にしていただきたくはないと申し上げてあります。それは最後まで闘われたご本人に対して、これ以上天国でも気を遣わせることはしてはならないと思うからです。
そういったようなかたちで、一日一日、本当に正解というのが、個人の環境、背景、考え方、家族構成によって出せる答えが違ってくると思うので、本当に慎重にいかないといけない、悩みのつきないところではあります。やはり情報とコミュニケーションから始まり、それをロングスパンに変えていき、横のつながりから社会に広げていくということも、一つ別の視点から申し上げられたらと思いました。ありがとうございます。
患者さんの言葉で話す・伝える
渡邊:ありがとうございます。大阪で患者さんの目線で情報を出す。地域によって、患者さんの欲しい情報というのをどうやって選ぶのか、なかなか難しいという部分だし、「患者さんの言葉に翻訳する」という作業が、難しいのではないかと思うのですが、そこで何か工夫していることとかはありますか。
濱本:最初に立ち上げたときには、まず、その「がん診療連携拠点病院現況報告」という800項目以上の膨大のものから、患者は、この中のどれを有益だと思うだろうかということで、300項目を超えたものをスピード検索できるようにしました。その項目立てまでは、私たちが関わりました。主体は当時の大阪府立成人病センター(現 大阪国際がんセンター)で、私たちがオブザーバーというかたちで入りました。
しっかりとした情報の正確性というのは担保されているわけです。そこに患者の視点を入れていただいた、この両輪はすごく大事だと思います。どちらが欠けても血の通わないものになったり、独善的なものになったりします。もちろん私たちも、項目を選ぶときには、アンケートを周りの患者団体や個人の方に取ったりしました。それを初回にやってからは、新しいカテゴリーやコンテンツを作るときに、そのやり方を踏襲してきました。やはりいろいろな地方に行きますと「大阪はうらやましい、開けている」と言われることがあります。それでも、いくつかの府県で動きつつあるというのは、伺っていてうれしいところです。
渡邊:ありがとうございます。病院情報の発信のモデルになると思います。医療機関に加えて療養を支える施設でも、取り組んでいる医療や療養支援の現状についての情報を、一般の方にどのように届けるのかを考えるときに、住んでいる住民の方や当事者の方の目線を入れる。そのことによって、医療情報で例えば「病院のベッドが何床、何科があります」といった情報だけでなく、メッセージ性を帯びて、安心できる・信頼できるとか、患者さんが選べるようなメッセージも付け加えられると、それが患者さんにとっては信頼や安心につながると思って伺っていました。ありがとうございます。
患者会で話し合う「共に生きる社会」
岡さん、いかがでしょうか。オストミー協会、オストメイトは確かに大腸がんの方ですと高齢の方が多いとのことでした。そのなかで20代から40代の方ですと、年代特有の悩みや課題があると思います。こうした中で考える、「がんと共に生きる社会」についてお話しいただけますか。

岡 悦郎さん
岡:オストメイトもそうなのですが、がんとの共生社会の中で、患者会という視点からお話しします。私は代表でも何でもなくて、逆に一患者として患者団体に参加しているという立場で、これまで患者会に参加してきました。先ほど言われたように、「オストメイトになった」といってポンと行くと、ご高齢の方がほとんどで、われわれが聞いても話が合わないというのがありました。結果的に、若い人が時々来ても、やっぱり次の患者会活動につながっていかないのです。「あまり自分のためになる情報がなかった」、そこで負のスパイラルに陥って、どんどん若い人が患者会から離れていってしまうことがありました。
そこで「20/40フォーカスグループ」をつくって、地域に若い人たちで、日頃お互いに話ができない、話に行けない人同士が集まって話をすると、「そうだよね、そうだよね」というふうに結構盛り上がったのです。そこからまた仲間が増えて、という感じで、今度は負じゃなくて正のスパイラルで良いほうに回っていったというのがあります。
お互いに支え合える関係をつくる
私は、GISTERS(GIST:消化管間質腫瘍)という希少がんの患者団体にも入っているのですが、そこでのエピソードです。私はこうやって、希少がんでストーマになって、自転車も毎週200キロくらい乗って元気に暮らしているのですが、ある患者会に行きまして、旦那さんが希少がんで、お医者さんから「ダブルストーマ(両方で)つまり、骨盤内全摘出をして人工肛門、人工膀胱の両方になる、そういう手術になります」という説明を受けて、ショックを受けられていたのです。私はちょうどストーマで、患者会でお会いしたので、ちょっとお話しさせていただいたのです。そのときには、本当に旦那さんはショックを受けられて、下を向いたまま話さないのです。僕の目を見てくれない。
僕は奥さまとずっとお話ししていて。僕はこんな感じで「大丈夫ですよ。人工肛門があっても別に普通です」と言って。病気のほうもいろいろあって、僕も10回くらい、増悪、転移、再発、転移とかをしているのですが、このようにとても元気なんです。そういう話を小一時間していると、だんだん旦那さんの顔が上がってきて、最後は笑って帰っていただいたのです。その旦那さん、それまで主治医の先生とも話せない状態だったらしいのですが、先生の話を聞いて受け入れて、2が月後には手術を受けられて。その後も、ストーマになられても明るく生活されていて。私にとっても、今でも続くお友達がまた増えたのです。
そのときに僕は、「病気になって良かった」と思ったのです。僕は、これまでボランティアは何もやってこなかったけれども、こんな僕が人を1人助けてあげられたような気がして。すごく僕は、僕が助けられた思い「僕だって何かできるんだ」と。それは、病気のおかげで人を救ってあげられたかなという気持ちで、逆にものすごくその方に感謝しています。
患者会に行けば、お医者さんから以上のいろんな情報を得るとか、悩みの相談とか、そういう面もあるのですが、やっぱり「助け合い」という意味では、患者会の意義は大きいと思います。医療の情報はいろんな地方で皆さんが発信していただいているので情報はきちんとあります。その中で、実際に直接顔を合わせて、会うことによって「こんなピンピンしているよ」という姿を見せてあげると、「本当に元気なんですね」と言っていただけて、それで僕はまた元気になるのです。
そういう感じで患者会は、ライブ的なところでもあると思います。患者会でもいろんなところにフォーカスしているのがありますので、自分に合う患者会を見つけてほしいと思います。患者会は、単純に医療情報とか悩みごとの相談だけではないというところですね。僕自身も、やっぱり患者会に来たら、講演会で先生の話を聞いて、「ああ、大変な病気になってしまった」と暗い感じで帰っていただくのではなくて、患者会に来たのだったら、話して、最後はやっぱり笑って帰っていただけるようなところであればと思って活動しております。
渡邊:ありがとうございます。当事者になったからこそ、いろいろな気付きや、伝えたいこと。患者さんが、当事者が集まる患者会で話をすることで、お互いに支え合うという関係ができるようになるというのは、すばらしいことだと思って伺っていました。
希少がんのネットワークから考える「交流」の大切さ
馬上さん、希少がんは10万人に6人以下と、発症率(罹患率)は少ないですが、希少がん全体で見てみると決してまれではないですし、情報が足りなくて困っている方が多くいらっしゃる中で、どのように「共に生きる社会」を考えていけばよいでしょうか。

馬上 祐子さん
馬上:そうですね。希少がんネットワークは2017年にできました。私は小児がんの患者会を15年間くらいやっていまして。15年前は、「小児がん」は、「そんなことを人に言うのはとんでもない」という感じでした。今では、本人が出てきて、新聞のインタビューに実名で答えて、写真でもお顔を出していらっしゃいます。このように、時を経て、負のイメージがなくなってきているということを感じています。岸田さんや桜井さんなど、当事者の方々が「自分はこうだよ」と、皆さんにお話しされてきたことが積み重なって、こうした状況・雰囲気ができていると思っています。
希少がんは、最初の頃は、同じ病院に誰も同じ病気の人はいないということで、情報は全然ありませんでした。2000年ぐらいからインターネットが普及しまして、ブログや掲示板、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で集うようになりました。その頃から、希少がんの患者会がたくさん出てくるようになったのです。今では希少がんの会がたくさんできて、「では、同じ課題を共有して解決していきたいですね」というところまで来ているのです。
やはり患者同士の交流が、まず一番だと思います。さっき岡さんがおっしゃっていたように、「ピアサポート」つまりお互いに話をすると、気持ちがちょっと楽になるし、お互いの情報も交換できるし、明るい気持ちになれるということがすごく大事だと思います。
一方、希少がんというのは情報が少ないので、先生たちともつながらないと情報をいただけないのです。うちの会では12年くらい、脳神経外科・小児科・内分泌の先生など合併症を管理する先生方などと、そして患者家族が一緒に集うキャンプのようなものを、毎年1年に1回行っています。脳神経外科の先生は、すごく怖いなと最初は思っていたのですが、とても気さくな方々でした。医師の先生方も、「患者家族と交流したい」とものすごく思っていらしたんだな、というのを感じまして、その後もずっと続けさせていただいています。

ディスカッションの様子

ディスカッションの様子
病院の中では時間が限られていて、本当に大学病院の先生は3分くらいで診察をやらないと、患者さんは何百人もいらっしゃるので大変だと思います。それをサポートする看護師さんや医療ソーシャルワーカーさんが、いてほしいというのもあります。腹を割って話せば先生もちゃんと話してくださるというのを、私はすごく実感しているところです。最初は怖いので、何も言い出せないものでした。だんだんとお話をしていくうちに、「こういうふうに言ったら、よく分かってくださるのだな」など、話し方も分かってきました。
はじめに診断されて発症が分かって、頭が真っ白になられている方に、「どうやってサポートをしていくか」ということは、まず考えていかければいけないことだと思います。患者会の役目は、先生と患者をつなげたり、患者会同士、希少な情報を交流して集めたり、また発信していくということになると思います。
渡邊:ありがとうございます。患者会に参加することで、そこで解決できる部分があるかもしれない。解決に結び付かなくても、例えば、次の診察のときに「こうやって質問しよう」とか、対話のきっかけづくりをしてもらう、そんなヒントが得られそうですね。それをもとにご本人がお医者さんとのコミュニケーションについてやり取りができますね。そういった意味では、患者会で話をすることの意義・効用というのはとても大きいと思いました。