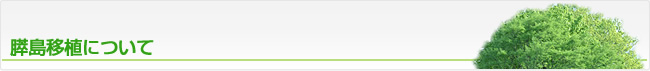- TOP
- 膵島移植について
- 背景
<膵島移植とは>
膵臓は、アミラーゼやリパーゼなどの消化酵素を分泌して消化吸収を助ける外分泌細胞と、インスリンやグルカゴンを分泌して血糖調節を行う内分泌細胞との2種類の、全く働きの異なる細胞群(組織)より構成されています。外分泌細胞は膵臓の99%を占めており、これらの細胞で作られる消化酵素は、膵管と呼ばれる導管を通って十二指腸に放出されます。膵島は直径が約 0.1~0.3 mmの球状の塊で、膵外分泌組織の中に点々と散らばっています。塊として散らばっている様子から“膵臓のなかの島”という意味で膵島の名前がついています。膵臓の中には成人一人あたり約100万個の膵島が存在します。膵島にはα細胞、β細胞、その他ごく少数の働きの違う細胞が含まれます。β細胞は、血糖が上昇した場合に血糖を低下させるホルモンであるインスリンを分泌します。反対に血糖が低下しすぎた時には、α細胞から血糖を上昇させる働きがあるグルカゴンが分泌されます。膵島移植とは、膵臓からのインスリン分泌がなくなってしまったインスリン依存糖尿病(1型糖尿病)に対する根治的治療法の一つであり、膵島組織(特にインスリンを産生するβ細胞)を移植することで、血糖の安定化とインスリン療法からの離脱を目指します。
<膵島移植の歴史>
わが国では、1997年に日本膵・膵島移植学会に膵島移植班が結成され、活動を開始しました。2003年に国内初の臨床膵島分離が国立佐倉病院で実施され、翌年には京都大学で膵島移植が行われました。
以降2007年までに、主に心停止下の臓器提供をうけ、膵島移植が行われました。2012年からは、多施設共同臨床試験が先進医療として開始され、この良好な成績をもとに、2020年4月より膵島移植が保険収載されました。
<膵島移植の方法>
まず、提供者から頂いた膵臓から膵島組織を分離して、100 ml程度の移植用溶液とともに点滴バッグに入れて、膵島浮遊液を準備しておきます。膵島移植は、局所麻酔下で行います。X線透視装置と超音波検査装置を用いて、皮膚から肝臓内の血管である門脈を穿刺し、そこから膵島浮遊液を注入します。注入に要する時間は1バッグあたり約20分程度ですが、移植膵島量に応じて使用バッグ数が増える場合やカテーテル穿刺に時間を要する場合は、1時間程度になることもあります。注入終了後、穿刺したカテーテルは抜去します。
<移植に伴う合併症>
膵島移植手技は現在の医療技術では簡易な技術であり、門脈の採血や血管の造影など同様の手技が数多く施行されています。そのため、移植手術の際の合併症は、臓器移植手術に比較して極めて少ないといえます。膵島移植の主な合併症として、穿刺部の皮下出血や肝臓内の出血や血腫、腹腔内出血などがあります。ごくまれに肝臓内の血管同士がつながってしまうことや、血管と胆管がつながる胆管-血管瘻ができて胆道出血が起こることがありますが、たとえ起こったとしても通常は適切な処置で対応が可能です。移植された膵島により、門脈が閉塞して門脈圧が上昇することも予想されますが、最近の移植方法では報告はごく僅かです。局所麻酔薬など使用する薬剤に対する過敏反応が起こる可能性がありますが、膵島移植にのみ特別に起こる合併症ではありません。
<移植後の合併症>
膵島移植では他人の膵島組織を移植するために、臓器移植と同様にそれを排除しようとする免疫反応である拒絶反応が起こります。この拒絶反応を抑えるため、数種類の免疫抑制剤を長期に渡り服用することが必要となります。移植医療全般に言えることですが、免疫抑制剤の内服により、細菌、ウイルス、真菌類や寄生虫などに対する免疫反応を抑えてしまう可能性があり、感染症にかかる頻度が高くなります。時に重症化して生命の危険をもたらすこともあります。そのため、移植後は定期的な受診で体調のチェックや免疫抑制剤の量の調整を行う必要があります。また、移植を受けた方は、受けない人に比べて悪性腫瘍の発生頻度が高くなることが知られています。そのため、定期的にがん検診を受けることを勧めています。
<移植後の経過>
順調に経過した場合は、2~3週間で退院できます。移植膵島が生着すれば、血糖値の正常化が期待できます。移植直後には、膵島細胞がインスリンを作る負担を軽くするため、たとえ移植膵島がインスリンを分泌していても、インスリンの注射を続けた方が良いと判断される場合があります。生着した膵島が充分量であれば、インスリン注射は不要となります。移植後にも血糖値が高くインスリン注射が必要である場合は、移植膵島が拒絶反応などにより不足していると考えられます。この場合は、インスリン注射を続けて、次の膵島移植の機会を待つことになります。通常インスリン注射が不要となるまでに2〜3回の膵島移植を必要とします。拒絶反応がおこった場合、移植した膵島は自然に消滅しますので、あらためて摘出する必要はありません。