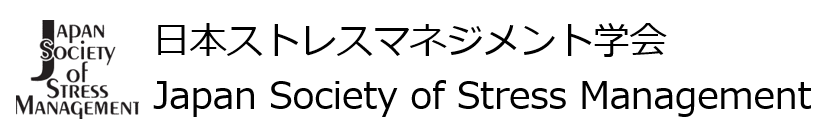ストレスマネジメントは、幅広い年齢層に対して、様々な場でも、平時にも有事にも、実践される活動です。そのため、本学会には、多様な領域におけるストレスマネジメントの実践家と研究者が会員として集っています。特に学会では、教育・特殊教育,災害支援,産業・労働,基礎・医療,及びライフスタイルの5領域について、それぞれ実践領域部会を設けて活動しています。
実践研究推進委員会は、これらの各領域における実践と研究をつなぐ役割を担います。実践に結び付く研究、研究や理論に基づいた実践を推進します。また、実践家と研究者をつなぎ、両者の連携をサポートします。そして、これらを実現するために、実践領域部会の各部会長(池田美樹先生:桜美林大学、一瀬英史先生:Eustress(ユーストレス)株式会社、岡島義先生:東京家政大学、岡村尚昌先生:久留米大学、上地広昭先生:山口大学)の先生方に本委員会の委員となっていただきました。さらに今期は、若手の研究・実践者である田上明日香先生(SOMOIヘルスサポート)と田中裕樹先生(和洋女子大学)にも委員に加わっていただきました。
本委員会は、研修委員会や新設された研究委員会と連携しながら、実践と研究をつなぐという目的の達成に向けて、今期も精一杯取り組んで参ります。どうぞよろしくお願い致します。
三浦 正江(東京家政大学 人文学部)
日本ストレスマネジメント学会実践研究推進委員会規程
2019年8月24日制定
(目的)
第1条 実践研究推進委員会(以下、委員会)は、日本ストレスマネジメント学会(以下、学会)内における、ストレスマネジメントに関わる実践と研究に関わる業務を所管し、本学会の目的達成に寄与することを目的とする。
(業務)
第2条 委員会は、前条の目的を構成するために、次のことを行う。
(1)ストレスマネジメントの実務者と研究者との協働に関すること。
(2)ストレスマネジメントの実践促進に関すること。
(3)その他、ストレスマネジメントの実践的な研究に関すること。
(4)ストレスマネジメントの実践分野を所管すること。
(5)その他、理事会が負託した業務等。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、正会員の委員で組織する。
(1)委員は、委員長の推薦をもとに、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
(2)委員の任期は1期3年とし、再任を妨げない。
(3)委員長1名は、理事の中から理事長が委嘱する。
(4)委員長の任期は、理事の在任期間とする。
(5)委員長指名の副委員長を置くことができる。
(6)委員に欠員が出た際は補欠委員の選任を行うことができる。専任の方法は、本条1号に準ずる。
(改廃)
第4条 本規程の改正は、理事会の承認を得るものとする。
附 則 本規程は、2019年8月25日より施行する。