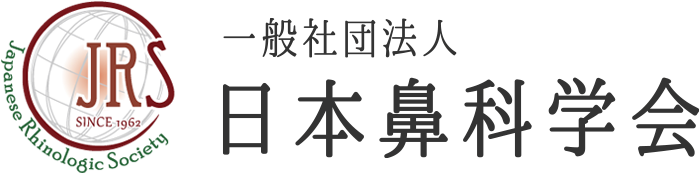ごあいさつ

理事長 春名 眞一
日本鼻科学会理事長3期目にあたって
3期目(令和5〜6年度)の日本鼻科学会理事長を拝命させていただくことになりました。 過去、2期(令和元年〜4年度)は、就任直後からコロナ禍となり、全ての学会関連は非接触を強いられる状況になりました。学会自体の開催も危ぶまれ、会長から開催を延期してほしいとの要望も出され、学会によっては開催を中止し、次年度に延長したところもありました。実際、私自身も開催すべきか悩みましたが、当時の順天堂大学教授池田勝久先生にお願いして、会期を短縮しかつweb形式を取り入れた新しい学会運営で、第59回日本鼻科学会を開催できました。その後、学会運営も多くの会員の参加しやすいようにweb形式が標準になりました。一方、コロナ禍で嗅覚障害の発症が注目をあび、嗅覚異常に対する関心が急上昇しました。嗅粘膜障害をきたすメカニズムの基礎的研究が急進する契機になったと感じます。
日本鼻科学会60周年の記念式典が2021年9月24日に第60回日本鼻科学会(大津市)で開催されました。日耳鼻理事長の村上信五先生のご挨拶や第50回〜59回の会長及び歴代の理事長に対する感謝状の贈呈、欧米の著名な鼻科学の先生(Metin Onerci 、Wytste Fokkens 、Robert Kern 、David Kennedy 先生)からの温かいビデオメーセージも頂きました。今後は、記念誌の発刊を予定しております。
国際交流として従来より親交の厚かった台湾鼻科学会と韓国鼻科学会と間でMOUを締結し、両国の交流がさらに活発化すると期待されます。また、20th ARSR(Asia Research symposium in Rhinology)を第60回日本鼻科学会と同時開催されております。さらに2024年4月には13年ぶりに東京でISIANとIRSが開催される予定であります。
学会刊行物として線毛機能不全症候群の診断の手引きが刊行されました。もう少しで慢性鼻副鼻腔炎の診断の手引きが発刊の予定です。また基礎ハンズオンでは若手の会員の啓蒙のために基礎研究を開始するための様々な手技、動物実験や英語論文の作成などをまとめた基礎ハンズオンテキストが刊行され、多くの会員の鼻科学研究バイブルとなっています。
日本鼻科学会認定手術指導医制度を2020年から開始し、鼻科手術をより安全確実に施行するために術式の標準化を目指し、後進の育成をはかることを目的としました。現在、暫定指導医106名、指導医8名、認可施設128となっており、未だ全ての都道府県までには配置できていません。今年から本格的な指導医認定が開始される予定です。
学会の活性化のために、若手会員の入会を促し積極的に女性医師の会員増を考えており、ダイバーシテイ委員会を活性化し、学会役員やシンポ、パネルなどへの積極的な登用を促す予定です。また積極的に女性医師を代議員や理事に登用することを推進してまいります。本年度は理事に川島佳代子先生が選出されました。今後は、理事に女性枠1名を設置する予定です。
本学会として継続すべき大きな目標は、国際交流や学術及び広報活動の充実、法人としての国民への貢献が挙げられます。60年積み上げられた臨床、研究と教育と国際化企画を前進させるべく、さらなるエビデンスを構築し、break throughとなる新たな基礎及び臨床的な開発を支援していきたいと考えております。鼻科学の主領域である鼻副鼻腔疾患、アレルギーと嗅覚はもちろん、境界領域の頭蓋底や下気道の病態及び治療にも綿密な拡大関連し、より精緻な医療を提供していかなければいけないと考えております。
令和6年元旦には能登半島地震と2日には羽田空港での飛行機追突と想定外な事件が生じ、波乱な年の始まりとなりましたが、会員の皆様には、健康で希望を持った年になることを祈念しております。会員の皆様の期待に応えるように尽力してまいりたいと考えておりますので、ご支援とご理解を何卒よろしく願いいたします。
令和6年1月15日