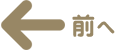がん在宅療養フォーラム 2025 大阪
いつでも頼れるがんの情報と相談先 探す、選ぶ、そして活用する
ディスカッション
| モデレーター: | 渡邊 清高さん、松本 陽子さん |
| パネリスト: | 池山 晴人さん、村上 利枝さん、濱本 満紀さん、伊藤 ゆりさん、佐藤 修さん |

渡邊:では、これからディスカッションに入りたいと思います。会場の方で、今回のテーマについて、何かご意見やご質問がございましたらいただければと思いますが、いかがでしょうか。
では、藤阪先生お願いいたします。
患者さんは不安のなか信じたいものを信じている
藤阪:先生方、本日は非常に貴重な講演、また、大切な情報のご提供をありがとうございました。大阪医科薬科大学の藤阪です。本日の内容を拝聴しながら、あらためて実感いたしましたのは、人というものは、先生方もお話しされていたように、「見たいものを見て、聞きたいものを聞き、そして信じたいものを信じる」という確証バイアスの傾向を強く持っているということです。特に患者さんやそのご家族は、不安や恐怖といった強い感情を抱えた状況にあります。そのような中では、私たちがどれだけ中立的かつ丁寧に情報をお伝えしたとしても、受け手の立場からは異なる解釈がなされることがあります。
実際に、多くの患者さんやご家族は、医療者が提示する客観的な情報と、自らが信じたい情報とのあいだで揺れ動かれます。中には、そのギャップをうまく埋めていかれる方もいらっしゃいますが、すべての方がそうであるとは限りません。ときに、そのギャップを埋めることが非常に難しく感じられる場面もございます。
そうしたとき、私たち医療者としては、伝え方をもう一度考え直したり、もう少し時間をかけてご説明を行ったりする必要があるのではないかと、日々模索しております。
そこで、池山先生にお伺いしたいのですが、先生はこれまでに多くのご経験をお持ちかと存じます。もし、情報を「伝える側」と「受け取る側」とのあいだにギャップが生じた場合、その状況をどのように冷静に受け止め、対応していけばよいのか、ご助言をいただけますと幸いです。
渡邊:池山さんからお話しいただいて、また、ぜひほかのパネリストの方からもお話しいただければと思います。
治療開始までにがん相談支援センターを訪れられるように
池山:ありがとうございます。日々現場で課題と向き合っていますが、患者さんによって状況はさまざまで、簡単に一律の答えを示すことが難しいと感じています。患者さんやご家族の中には、情報をすぐに理解・納得することが難しく、不安や疑問をうまく表現できない方も多くいらっしゃいます。また専門職としては、その気持ちを察知し、適切なサポートを提供する努力が必要だと思います。
国の整備指針(がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 令和4年8月1日)では、『がんの診断から治療開始までの間に、患者さんが少なくとも一度はがん相談支援センターを訪れ、情報を得たり不安を軽減したりする仕組みを整えるように』と推奨しています。ただ実際は、悩みを抱える方が10人いたとしても、実際にがん相談支援センターを訪れることができる方は半数程度にとどまり、その中でも実際に相談室のドアをノックするには心理的なハードルを感じる方も多いでしょう。
ですので、患者さん側にもぜひご自身の不安や疑問を積極的に表明していただきたいと思いますし、私たち専門家側も、相談室のドアを常に開けておくなど、相談しにくい要因を少しずつ取り除き、患者さんがより相談しやすい環境を整えることから始める必要があると感じています。
渡邊:きっかけをつくるのは非常に大切なことだと思っています。科学的に正しかったり、医学的に正しかったりしても、その情報を伝えることが患者さんにとって適切か、時期や内容、伝え方ということについても、結構いろいろとご意見があると思います。ぜひパネリストの皆さまから一言ずつお話しいただければと思うのですが、松本さん、どうですか。
大切なのは十分に理解し納得できるまで繰り返し聞くこと
松本:ご質問ありがとうございます。繰り返しだと思っています。今、例えば担当医が言葉を尽くして説明をしたとしても、今、十分に理解してもらうのは、もしかしたら難しいかもしれないです。「2回目、3回目、何回でも聞けます。僕だけではないです。看護師にも、がん相談支援センターにも、ピアサポーターにも聞けます。あらゆる機会を捉えて、何回でも聞いてください」という言葉掛けがあると違うのかと思っております。
伊藤:最近、苦痛のスクリーニング(課題を抽出するための問診・調査)が、全てのがん患者さんに行われるようになっていて、これを行っている看護師さんに、そのツールとして、そこに患者さんが回答してくれていることを使って、一緒にコミュニケーションできるというお話を伺いました。仕組みの中に患者さんが医療者と対話しやすいようなことを入れていくというのは、一つ大事なことかと思いました。
佐藤:私は、医学的に正しい情報に最初に触れられれば、おそらく一番よいと思います。例えば、若い主婦の方などが、今はYouTubeなどでインパクトのある演出で、まあまあ有名な人のところにいってしまうと、その関連情報だけしか入ってこない世界から抜け出すのが、本当に至難の業になるので、やはりファーストコンタクト(最初の接点)が鍵なのかとは思っております。
村上:ありがとうございます。私はがん患者でやはり不安な時に、そういう情報に惑わされた経験があります。今、オレオレ詐欺も不安な気持ちを利用して、心理作戦で動いているように、やはり不安な時は惑わされやすいと思います。患者さんが不安な時には、まず、「どうしてそこで治療がしたいの?」など、ゆっくりお話を聞くと、ご本人も不安だからその情報に飛びついたということに気がつかれます。まず、お話を聞いて、そして先ほど申し上げたように、きちんとした正しい情報に結び付けてあげることが大事です。これは正しい情報ではないということを、ご本人がおわかりになるように、一緒に勉強してナビゲートしています。
そして、がん相談支援センターでは、また正式な医療的なことをお話ししていただくと、間違った情報だったという理解に、時間はかかりますがたどり着けます。今とても巧妙になっていて、セカンドオピニンを受けたいと思って情報をさがしてみると、そこに違った情報がすり替えられていることもありますので、そこには導いてあげる人たちが必要かと思います。
患者さんは医療者と一緒に治療を決め、治療に臨む
濱本:先ほど対話型AIサービスのことをお話しいたしましたが、皆さん検索なさいますと、最後には必ずといってよいほど定型文のように、「あなたの主治医、医療チームと必ず相談しましょう」というのが付記されています。これは少し前にはなかったことです。今必ず付いているのが、ほっとするところです。
先ほど松本さんがおっしゃいましたように、何度も納得するまで説明を聞いて、そして自分が相談するだけではなく、主体は患者さんだけではなく、医療者と一緒に治療を決めていき、治療に臨んでいくという意味では、何度も繰り返し練り直すという作業が必要だと思います。ですが、それには患者さんがやはり臆してしまうところがあります。ですから、「こういったところで、主治医に確認すればよい」とアドバイスをするわけですが、結局、それは1回で瞬時にAIサービスで調べられたことを、もう一回やり直さないといけないし、がん相談支援センターさんにも行って確かめないといけません。
今はちょうど情報の交差点の黎明期(れいめいき)だと思います。その間は皆さんがそれぞれの相談支援、そして患者支援というものを密にしていただきながら、しばらく「情報の均てん化」というのが、がん対策推進基本計画に盛り込まれていますので、そのさまざまな施策、その検証にもそれが資すると思います。
新しい情報ツールが情報を探すハードルを下げる
渡邊:ありがとうございます。情報というのは声に出さないと伝わらないし、届かないです。「こういったことを聞いたら、担当医の先生が怒ってしまうのではないか」「あきれられてしまうのではないか」というようなことであっても、逆に言うと、医療者は患者さんやご家族から質問がなされることによって、患者さんがどのようなことで不安になっていらっしゃるのか、あるいは自身の説明が十分届いていないということを気付くきっかけになると思います。
そこから、専門の人につないで答えていただいたり、「こういった情報源があるから、自分は専門家ではないですが、もしかしたらお役に立てるかもしれません」と伝えたりすることで、何らかのきっかけにつながると思います。まずは第一歩を踏み出していただくことができるとよいと思いますし、こういったAIツールを使うことで、人には聞けないけれど、一回下調べしてみよういうように、少しでもそのハードルを下げるお手伝いができるのではないかと思いながら伺っていました。
せっかくの機会なので、よろしければもう一つほど、もしご質問があればと思いますが、いかがでしょうか。パネリストの皆さんからもコメントなど、いかがでしょうか。
実はオンラインから、「『ランタン』はSNSなどでシェアしてもよいでしょうか」という大変心強いお声をいただいているのですが、「ランタン」の二次元コードやURLは、シェアしても問題ないですか。佐藤さん、大丈夫ですか。
佐藤:はい。大丈夫です。
渡邊:ご発言にもあったとおり、在宅がん療養財団のホームページからリンクして、利用規約も確認いただけますし、検証事業中ではありますが、ぜひ試験版をお使いいただいて、何かご意見やご感想があれば、財団のホームページに「お問い合わせフォーム」もありますので、そこから寄せていただければと思います。
そうしましたら全部のご質問に答えられていない部分はあるかもしれませんが、本当にいろいろな立場の方から情報を使って、それを活用して、患者さんの支援に届けていくということが非常に大切だというお話をいただきました。
今日は、情報のツールや情報源、相談できる窓口、がん相談支援センター、がん医療ネットワークナビゲーターについてご紹介いただきましたので、ぜひ、使いながら何か困ったことや不安なことなどがあれば、フィードバックしていただけるような仕組みにつながっていくとよいと思っています。
パネリストの皆さま、どうもありがとうございました。以上で第2部を締めさせていただきます。ありがとうございました。