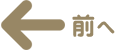がん在宅療養フォーラム 2025 大阪
いつでも頼れるがんの情報と相談先 探す、選ぶ、そして活用する
閉会あいさつ
今日は長い時間どうもありがとうございました。ご講演、ご参加の皆さまには、寒い日にいろいろな遠い所から来ていただいて、やはり顔を合わせて触れると、細かな問題がかなりわかってくる気がいたします。
私どもが情報技術を使ったサービスを開発していますと、情報技術が急に有効になったのは、実はインターネット上での情報が飽和してきたという背景があります。要するに、言葉になるものや文章化されるものには、急激にコンピュータ能力が高まってまいりますと、関心の高い情報に当たるようになりますが、情報技術の専門のほうからいきますと、人工知能はその中身は理解してないです。繰り返し申し上げますが、今、対象の情報が飽和してきたために、「前がこうであれば答えはこうかもしれない」というのを類推できる確率が上がってきました。これが大規模言語モデルなのです。
ところが、人間の感じるところというのは、文章で読む文字だけではないです。皮膚の感じや食べること、触ること、熱かったり、同調したり、嫌いだったり、いろいろな価値や感覚があります。情報技術でまったくできていないのは、生物のように情報を統合して一つの考えにしていくということです。ですから、文字列になった情報の中でもっともらしいものをつくり出す、今のインターネット情報というのは、現実を全部見ているわけではないです。
例えば、人間のその人の価値というのはどこにも触れていません。3人いれば3人別々の価値がありますが、インターネットはそれにはまったく答えません。「今日は何としても退院して孫に会いたい」。そういう場合もあるかもしれません。「生きているうちに会っておきたい人がいれば会っておきたい」。寿命を延ばすか延ばさないかではなしに、その会うことに価値がある場合もあるかもしれません。コロナ禍でそうしたことを山ほど体験させられました。すると、別に正しい情報という価値があるということではなしに、例えば、われわれが医学的情報として、インターネット上での情報提供でできるのは、ニュートラルな情報を淡々と提供することです。
先ほど濱本先生が指摘されていましたように、感情に寄り添うわけではありません。これはむしろ、いろいろ心理学のアドバイザーなどに聞いても、「相手の感情におもねて言うことは、共感を得られない。感情は揺れるものだから、長い間見ていくと、淡々と情報を提供してくれるほうが信頼性としては大事ではないか」ということに従って、感情に対する揺れを抑えて、淡々と情報を提供しています。
そして、一緒に揺れたり、一緒に寄り添ったりというのは、やはり先ほどからお話があったように、人間が入って社会につながらないとできません。それでご質問にあったように、繰り返し質問してくるということですが、繰り返しの質問が変わってくるのは、おそらく現実の少しずつの違いに触れて変わることがあるのではないかと思います。
「ランタン」をつくる時に、大きい見通しなどではなしに今日の足元を照らす、そういう作業が、がんの療養では大事ではないかと思います。ゲノム医療が進んだり、情報技術が進んだり、大きいのはありますが、日々のところでの具体的な問題にやはり寄り添って、人間として一緒に感じてあげる作業がないと、いかに情報提供があっても、納得しないのではないかと思います。
今、私どもが感じておりますのは、地域に根を張ったものと、それから、いわば上での情報提供するようなものを、やはり組み合わせていくような作業が必要だと思います。地域の現実からは、上で言われているものが違うのではないかというふうなことが変わっていく、そういう仕組みをつくるのが大事だと思います。そういう意味で、「ランタン」のプロジェクトも、これで全部が済むとはまったく思っていません。むしろ問題点が多く出てくるような仕組みを、ニュートラルにつくれることが大事なのではないかと思います。
また、私どもが感じている医学の一番の問題は、統計学の問題があり、3人中2人に有効だといっても、自分がほかの1人であれば、この治療をしても「害だけでメリットがない」ということで、これがずっと医学上の問題として残っています。
それに対して、今考えられているのは精密医療というか、細かなデータを多く取って、一人ずつに、「あなたの病気は統計的にこうだ」ではなしに、「メカニズム的にこういう病原体だ」「こういう遺伝子の変異だ」「こういうたばこの害だ」「こういうお酒の問題だ」など、そういうことがわかることによって、解決につながるというような精密なデータになっていくことが大事ではないかと思います。
情報技術がサポートできるのは、おそらく精密に見ていく時の、例えば遺伝子の配列はどうか、経済的な補助制度はどういうものがあるか、その地域でどういうセンターがあるかなど、こういう情報ができてくると進みます。ですから、細かな情報、精密な情報を提供していくことはできますが、それを統合するための人的なサポートというのは別の仕組みが社会の中にないと、人の価値観は決して理解してもらえないし、その問題はやはり個別の一人ずつの生き方の問題としてあるということで、残っていってしまうのではないかと思います。
そうすると、情報技術の一番難しいところはこれから出てきますが、日々の暮らしや、日々の病院、介護施設、緩和ケアの中で出てくる具体的な問題やリスクにどういうふうにきちんと細かく答えられる仕組みができるかということです。それを現実に、今出している答えが本当に実情に合っているか、という修正をできるメカニズムが必要ということで、実は非常に心配しておりますのは、生成AIのことなどをいろいろ語る人はいるのですが、日本で生成AIを自分でプロバイド(供給)しようとしている事例は、ほとんどがんに関係していません。ほとんどあるのはChatGPTやGemini、Claudeを使うものだけで、プロバイドする仕組み、チェックできる仕組みを日本からつくれるかどうかというのは非常に大きな境目に来ています。
ご存じの方もいらっしゃるかもしれません。アメリカでは、グルーポンという会社の創業者が、奥さんががんになったので、株を全部売って4,000億円をかけて、がんのゲノム診断をするTempusという会社をつくっています。Tempusはゲノム診断をしますが、検査と治療方法も、これを推奨するということを、今アメリカの民間保険の半分以上の会社に指示するようなことをしています。そうすると、FDA(Food and Drug Administration:米国食品医薬品局)が何か言うよりも、Tempusがイエス、ノーと言うかどうかのほうが権威を持ってしまうかもしれません。すでにTempusはSB TEMPUSをソフトバンクグループと組んで設立し、ソフトバンクも300億円を投資して、そういう情報の流れをつくり出して進んでいます。
ですから、日本の中で、私が非常に難しくなると思っているのは、がんの療養をやろうとすれば、3つの要素が必要になります。1番目はきちんとした情報です。がんに関わる情報を集めようとすれば、国民皆保険で集める、法的な信頼性のあるもので集める以外にありません。お金で買っても本当の情報は集まりません。これは、例えば日本の国立がん研究センターのC-CAT(Center for Cancer Genomics and Advanced Therapeutics:がんゲノム情報管理センター)では、世界から公平な情報が、きちんと時系列で経過を追って集まるようなものが皆保険の下でつくられつつあります。
それから2番目に、人と施設がなければ、がんの知識がどれほどあっても提供できません。最近私どもも、東大病院で相談に乗っていますと、お金持ちでアメリカから帰ってくる人が非常に多いです。1カ月の入院で、米国の病院で高額の医療費がかかったという方もいました。お金でやる病院にはお金を出しても最高の診療を受けられるという保証がありません。医療の目的がお金になれば、儲かる病院という概念が元々成り立ちません。ですから、きちんとした公的なものとして人と施設がないと、がん診療は成り立たないのではないかと思います。
3番目に、まだいわれていないのですが、がんの診療が高度化した機械や知識が必要になりますと、やはり一国の中にきちんと産業として、例えば薬を提供できる、情報技術を提供できる仕組みがないといけません。現在のところ、例えば日本の貿易収支は、円安でインフレになっていますが、原因を見ると、デジタル赤字が年間6兆円、バイオ医薬品の赤字が年間4兆円です。これでは日本の医療費制度がもつわけありません。ですから、日本の中で、やはり自分たちが必要とする技術や情報をつくり出すことにも努力を払っていくという大事な時になっています。
今日はいろいろな現実のことを教えていただきました。先ほどの5年生存率の見方ひとつから始まって、やはり考え直す問題を多く教えていただきましてありがとうございました。また、このような集いをもって、実際にお会いして交流していくような場も、インターネット情報だけではなしに大事にしたいと思います。
本日は大阪医科薬科大学の方に大変お世話になり、ありがとうございました。在宅がん療養財団のほうからもお礼を申し上げたいと思います。また、ご参加の皆さんには、質疑の時間が取れなくて申し訳なかったのですが、インターネット上でも、それからメールでも引き続き意見を寄せていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。