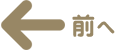がん医療フォーラム 岩手 2016/気仙がんを学ぶ市民講座
【基調講演】気仙の在宅医療の現場から ―退院から看取りまで―

岩渕 正之さん
がんの告知についての考え方
岩渕内科は外来診療と在宅診療をやっています。在宅診療の患者さんは30人前後で推移していて、そのうちがん患者さんは5、6人です。昨年度のがん患者さんの看取りは22件でした。
入院中、あるいは外来で検査を受けて、がんの告知をされます。今は末期がんでも本人に病名を告げるのが一般的です。ご本人がこれから先、何ができるのか、ご家族や友人・知人に伝えておきたいことをどのように伝えるのかを考える時間を持ってもらうためです。病名を告げないと、医療者もご家族も、患者さんに対して嘘をつくことになります。治療が始まると、がんなのだろうとご本人にもわかってしまいます。患者さんにそういう思いをさせないためにも、告知をするのが一般的になっています。
がんになったときに告知してほしいか、というアンケートをとりますと、自分ががんになったときにはだいたい80%の人が「知らせてほしい、残った時間を有効に使いたい」と回答します。一方で、家族ががんになったときにご本人に知らせたいか、という質問に対しては、「知らせたい」という人は40%です。このことから、もう少しがんのことを知っていただかないと、ご家族に対する告知が困難になると感じています。がんの告知をすることで、ご家族、主治医との関係を良好に保つことができます。誰も嘘をつかないということです。
がん告知後の気持ちの変化
告知後1週間以内は「頭が真っ白になった」という患者さんがとても多いです。2週間までは、とてもつらい時間です。苦悩、不安、うつになる方もいて、さまざまな感情が交互に出てきます。2週間を過ぎて1か月から3か月くらいになると、少し気持ちが落ち着いてきます。自分の現在の状況をだんだん理解し始めて、残りの時間を自分はどうするのか、家族とどう過ごすのか、そうしたことを考えられる時期になります。
告知後の精神的な痛みとして、不公平感を抱く人も多いです。なぜ自分ががんになったのか。なぜ、あの人じゃないのか、と思うところまでいく人もいます。そして自分は価値がないと思う方もいらっしゃいます。家族や他人の負担になりたくないと感じたり、治療をしても意味がないという、絶望感を持つ人もいます。誰も自分のことはわかってくれないという孤独感もあります。家族ですら自分の苦悩や不安をわかってくれない。それが痛みよりもつらいとおっしゃる方もいらっしゃいます。自分は何も悪いことはしていないのに、なぜがんになってしまったのかと、刑罰感を抱かれる方もおられます。
ご家族にもさまざまな気持ちの変化があります。大切な家族の病気が治らないことを受け入れるのは、とてもつらいと感じられます。でも、残された時間を自宅でゆっくり過ごせるのならば、本人の願い通りにしてあげたいと思うようになります。
しかし、不安感もあります。家族としてどのように支えていけばいいのか。仕事や家事はどうすればいいのか。患者さんの痛みがだんだん増したり、飲めない、食べられなくなったりしたときに何ができるのか。苦しみに対して何をしてあげられるのかという不安が出てきます。
在宅医療への移行のために
スムーズに在宅に移行していただくために、まず医療側との窓口となるご家族のキーパーソンを決めることが、とても大事です。ご家族で相談して緩和医療を含めた治療方針を決めるだけでなく、遠方にお住まいの親族にその方針を伝えておくことも、意外と大事なことです。
ある患者さんは10人家族で、キーパーソンがお嫁さんでした。末期の方で、だんだん具合が悪くなって、このまま自然に看取りましょうということになりました。ところがその段階になって、今までいらっしゃらなかったご親戚がやって来て「なぜ病院に運ばないのか。病院で死ぬのが当たり前だろう」という話になってしまいました。このときキーパーソンがお嫁さんで立場的に非常に弱かったため、「そう言われると逆らえなかった」とおっしゃっていました。連絡を受けて私が患者さんのお宅に着いたときは、もう救急車で搬送された後でした。その方は救急車の中で亡くなりました。こういったこともあり得るので、遠方のご親戚にも、在宅で療養したい、看取りたいと伝えておくことが大事だと思います。
もう一つとても大事なことは、介護者はひとりで抱え込まないようにすることです。在宅医療に移行するためには、さまざまな手続きや、対応しなければならないこともあります。ひとりで抱え込んでしまうと、たいていの場合、1週間もちません。
在宅療養の準備として、まず環境を整備します。患者さんが寝る部屋を決めて、ベッドなどを用意します。介護保険について、どのようなサービスが利用できるか確認するとよいでしょう。介護保険では1回、認定されるとだいたい1年間適用されることが多いのですが、がんは状態が変わりやすい病気です。状態が変わった場合には区分変更といって、1年以内でも変更することが可能です。
在宅での療養に関わってもらうケアマネジャー、訪問看護師、在宅医を選ぶことも大事です。気仙がん相談支援センターなど、地域の相談窓口がありますので、利用してください。
仮設住宅での在宅療養の困難さ
仮設住宅のがん患者さんの在宅療養は厳しかったです。4人ほど診ましたが、仮設住宅で看取ることができず、最期は入院になりました。仮設住宅は壁が薄いことが、一つの原因でした。がんの患者さんには痛みが伴う人が多いです。夜中に痛いと声をあげる、あるいは言葉に出なくても壁を叩いたりすることがあります。壁が薄いので隣に響いてしまう。看ている人は本人の痛みよりも、隣の人のほうが気になるということで、残念ながら入院しました。また、仮設住宅はたいてい駐車場がすぐそばにあり、部屋の前に車が止まっていたりします。二交代、三交代の仕事をしている人が多いので、夜中に車の出入りがあると、患者さんがやっと寝付いたのに、車の音やドアの音などで目を覚まして、すると痛みが出る、その繰り返しで在宅療養ができなくなってしまう。そういうパターンが多かったです。
在宅療養を始めたあとに起こること
在宅療養では、介護者と患者さんの葛藤がしばしば見られます。介護者は家に帰ってきた患者さんを、どうしても病人として扱ってしまうわけです。患者さんは食べたくないのに、介護者はなんとか食べてほしくて口に入れようとする。そうしているうちに、患者さんは薬も飲みたくない、家族でも自分のつらさを理解してくれないと思うようになります。そうした思いのすれ違いから葛藤が起きます。
がんの患者さんは、だんだん飲めない、食べられない状態になっていきます。がん終末期になってくると、身体が食事をあまり要求しなくなります。でもご家族としては、食べさせよう、飲ませようということで、その結果、誤嚥性の肺炎を起こして入院せざるを得ないということも起こります。
終末期になると、お腹に水が溜まる腹水の症状が出ることも多いです。そうすると食欲が低下してきます。少し前までは、腹水を一気に抜くと身体の循環が変調をきたすといわれていましたが、今では可能な限り抜きます。往診の患者さんにも腹水のある方はいらっしゃって、多い場合は1日3リットルくらい抜きます。これで一時的に楽になって、食事をとることができます。腹水とは別に胸水というのもありますが、こちらは一気に抜いてしまうと循環障害が起きることがあるので、少なくゆっくり抜きます。
患者さんの終末期にどう向き合うか
食べられない、飲めない状態になって、どうしましょうということになります。何もしないで様子をみるというのも一つの考え方です。それを続けていると、だんだんご家族の中に罪悪感が生じてきます。何もしなくていいのか、やろうと思えばやれることがあるのではないかといった疑問が出てくることがあります。脱水で水分が必要な場合は点滴をしますが、普通の点滴はご家族にとっても患者さんにとっても、けっこう負担になります。腕から管が出ているのは邪魔です。ご家族が一晩中、点滴の様子をみているということもあります。血管からの点滴ではなくて、皮下注射による点滴が非常に有効です。出血することもないし、針が抜けても何もすることはありません。ご家族に夜は寝てくださいと言える、こういう点滴をするのも一つの方法です。
がんの痛みを積極的に取る
痛みがひどくなった場合、今は積極的に医療用麻薬を用いています。意識低下を起こさないで痛みを取ることは十分可能です。状態に応じて内服薬、貼り薬、注射薬を使い分けます。飲めない、食べられない方の場合には貼り薬が負担が少ないです。1日1回貼るものから、3日に1度貼るものなどいろいろなタイプの薬があり、これで十分に痛みのコントロールができます。
ところが医療用麻薬に対する誤解があります。中毒になるのではないかと心配をする人がいますが、痛みがある状態での適切な使用では、中毒にはなりません。また「麻薬」という名前の響きが怖いと思われるようです。覚せい剤とか麻薬に絡んだニュースが流れていますので、どうしても印象が悪いかもしれませんが、こういった事件性のある薬物とは、まったく違うものです。医療用麻薬を使ったら眠ってしまって、もう目が覚めないのではないかと思う人も多いですが、適正量で使用すれば眠気は出ません。

講演の様子
看取りの経験から
私の母は80代で、夫とは7年前に死別、長男の私と同居でした。3年前に胃がんで胃の全摘手術を行いました。抗がん剤を服用していましたが、認知症があり飲み忘れやまとめて飲んでしまうようなこともあり、服用をやめました。リンパ節や肝臓などへの転移があらわれました。この時点では食事も自分でつくって食べるなど、生活能力は保たれていました。その後立てない、食べられないといった状態になりました。そうなってから盛岡まで出かけたのが最後の旅行になりました。旅行をさせるために点滴をしたりいろいろ工夫をしましたが、旅行から戻って4日目に亡くなりました。
医療の視点からみれば、最期まで旅行をして寝たきりになったのが1日か2日で亡くなったというのは、経過としては悪くない。ある程度、やり切ったと私も思っていました。しかし四十九日が終わった後に、ふと我に返ってとても悲しくなりました。管が入っていても、意識がなくてもいいから、母には生きていてほしかったという気持ちが出てきたのです。医者ですら、このように迷うのですから、みなさんが迷うのは当たり前だと思います。そうした迷いをひとつひとつ解決していけば、患者さんにとっても、ご家族にとっても、いい看取りになるのではないかと思います。
ひとりで頑張ろうとせずに、いろいろな職種の人たち、医者、歯医者さん、訪問看護師さん、ヘルパーさん、リハビリの方などに相談しながら、ご本人にとって一番いいように、ご家族が一番楽なように在宅医療を進めていければと思っています。