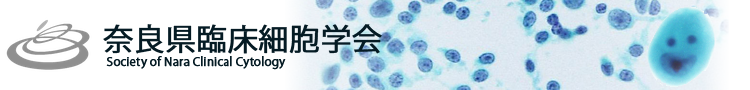奈良県臨床細胞学会
会長挨拶
パパニコロー教授の子宮頚部細胞診の報告からそろそろ100年を迎えるそうです。
当時の提案がほぼ同じかたちでこれほど長く続くとは誰も思っていなかったかと思います。
これから100年後,どうなっているでしょうか。
もう9年も前になりますが, ブー夕ンという国に病理診療応援でーケ月ほど派遺されました。
ブータンはインドと中国に挟まれた小国で, 人口は80万程度, 病理医は当時国全体で3名ほどしかいませんでした。
私は首都の王立病院でお手伝いをしたのですが, その病院の病理検査室は外来も併設し,私が手術材料の切りだしや病理診断をしている隣で70を過ぎたインド人病理医が甲状腺や乳腺の穿刺細胞診を行っていました。
穿刺されたサンプルは次の患者さんの検査を行っている間に技師さんが染色を行い,その医師は穿刺の合間に診断,その場で患者さんに結果を話しておられました。
病院の技師さんからは,ブータンでは医療機関が少なく,違方から来ている患者も多くいるためそうされているとお聞きしました。国情は異なりますが,細胞診の本来的な迅速性,経済性に強く感動しました。何より患者さんが近くに感じられました。
さて, 昨今の細胞診のプレゼンスは大きく変わりつつあると感じています。
子宮頚部細胞診は形態からHPV検査へ,そして細胞診材料を用いたがんゲノム医療への貢献や今後はデジ夕ル化やAIへのシフトが予想されます。
ただこのような大きな変革はあるものの,患者さんの近くで正確で迅速な診断を行うことに変わりありません。
次の時代を見据え,本会が会員の役に立てるよう盛り上げてまいりたいと思います。
会長 吉澤 明彦
Copyright © 奈良県臨床細胞学会 All rights Reserved.