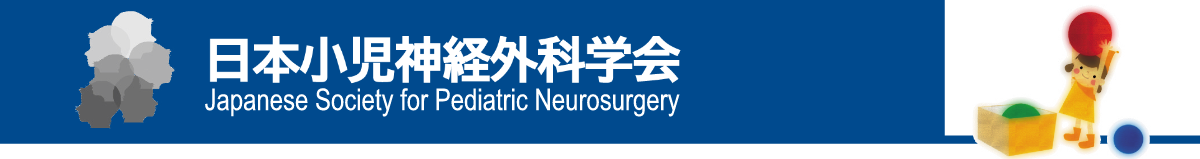

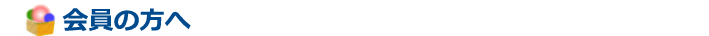
<���m�点�̖ڎ�>
- (2026.02.18) ISPN2026�̂��ē�
- (2026.02.13) TSPN-KSPN-JSPN Joint Meeting �J�×\��̂��m�点
- (2026.01.08) 3rd Global Journal Club�iGJC�j�̂��ē�
- (2025.12.25) 2026�N�x�������w�v���O��������̂��ē�
- (2025.12.02) ��V���]��ᇃJ���t�@�����X�̂��ē�
- (2025.07.24) AASPN2025�̂��ē�
- (2025.05.12) ISPN2025 in Lyon�̂��ē�
- (2024.12.26) 2025�N�x�������w�v���O��������̂��ē�
- (2024.06.19) ��P��Global Journal Club�iGJC�j�iJSPN�AAANS/CNS Peds Section�AISPN�Ƃ̋����J�Áj�̂��ē�
- (2024.02.15) ISPN2024 in Toronto�̂��ē�
- (2024.01.17) KSPN-JSPN Joint Meeting 2024 in Seoul�̂��ē�
- (2024.01.16) 2024�N�x�������w�v���O��������̂��ē�
- (2023.12.26) �V�^�R���i�E�B���X�����ǁiCOVID-19�j�֘A���
- (2023.12.25) BRAF�j�Q�܂����MEK�j�Q�܂̌��\�܂��͌��ʁA�������҂ł̗p�@����їp�ʂ̒lj����F�ɂ���
- (2023.06.16) ��4��A�W�A�E�I�Z�A�j�A�����_�o�O�Ȋw�� �Q���o�^��t�J�n�̂��ē�
- (2023.03.30) ��5��WUPN�̂��ē�
- (2023.01.20) 2023�N���،������w�v���O�����̂��ē�
- (2022.05.31) AACNS 2022�����IFNE inter rim Conference 2022�̂��ē�
- (2022.03.08) �E�N���C�i��Ɋւ��鐺����
- (2021.09.18) �ҒŁE�����nj����U�����c ������������̂��ē�
- (2021.08.23) R3�N�x���{�������������莾�a�̎��a�lj����Ɋւ���p�u���b�N�R�����g���J�i���{�����Ȋw��j�ɂ���
- (2021.08.16) ISPN 2021 Virtual Meeting�ɂ���
- (2021.07.27) �u��K�̓f�[�^�x�[�X��p�������W���D�����������ǂ̓��{�ɂ�������Ԓ����v �Q���o�^�̂��肢
- (2021.07.20) �p�u���b�N�R�����g��W
- (2020.09.07) �ҒŁE�����nj����U�����c ������������̂��ē�
- (2020.05.26) ��48�ۏ����_�o�O�Ȋw��N���w�p�W��iISPN 2020�j�����Ɋւ���d�v�Ȃ��m�点
- (2020.04.17) �V�^�R���i�E�C���X������ (COVID-19) �֘A���
- (2020.04.17) �C�O����̏����_�o�O�Ȋ֘A���
- (2020.04.10) ISPN 2020�̂��ē��@��3��
- (2020.04.10) ESPN�̊J�É����ɂ���
- (2020.04.10) ISPN 2020�̂��ē��@��2��
- (2020.02.07) ISPN 2020�̂��ē�
- (2020.01.29) 2020�N�x ���،������w�v���O�����̂��ē�
- (2020.01.23) �u�������a�Ɋւ���A���P�[�g�v�̂��肢
- (2019.11.26) ���������O���ɂ�����CT�B����̎w�j�E��
- (2019.07.11) ���������O������CT�B����ɂ��Ă̒E�w�j
- (2019.07.11) �l��ΏۂƂ����w�n�����̊w��\��_�����e�ɂ����ď��炷�ׂ��ϗ��w�j�ɂ���
- (2019.01.22) �����������莾�a�Ɋւ��邨�m�点
- (2019.01.22) ���،������w�v���O�����̂��ē�
- (2018.12.20) SEGA�K�C�h���C�����J�̂��m�点
- (2018.09.14) AASPN2019 �J�Â̂��ē�(��R��)
- (2018.09.14) AAACPN 2018 �J�Â̂��ē�
- (2018.09.08) ���{�Ғť�����nj����U�����c���������̌���ɂ���
- (2018.04.23) ���c�����N�f���E�g�̐f�@�}�j���A���̂��ē�
- (2017.07.10) ���{�����_�o�O�Ȋw��F���\�����J�n
- (2014.06.01) �A�Z�^�]���~�h�Ɋւ�����S�����
- (2013.01.01) ���x�Z���`�^���g�p��̒��Ӂi�����j
�@SPN2026�̉��Mohamed El Beltagy�搶����JSPN����֊F�l�փ��b�Z�[�W���͂��܂����B
�@10��7������11���@�J�C���ɂĊJ�Â���܂��B�ߍx�ɂ̓M�U�̃s���~�b�h���N�I�[�v��������G�W�v�g�����ق�����܂��B
�@Beltagy�搶���O�l�A���{�]�_�o�O�ȑ���ɏd�Ȃ�Ȃ��悤���z�����������܂����B����A�����̊F�l�ɂ��Q�����������������ē��\���グ�܂��B�\��m�ۂ����������������B
�@�� �����T�C�g�Fhttps://ispnmeeting.org/
���{�����_�o�O�Ȋw��@���ۈψ���
�S�������F�p�@�i��
�ψ����@�F����@��
�@![]() ����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
�@���̂��сATSPN-KSPN-JSPN Joint Meeting ���A2026�N7���ɑ�p�E�ь��iLinkou�j�ɂĊJ�×\��ƂȂ�܂����̂ŁA����Ƃ��Ă��ē��������܂��B
�@�{��́A����܂Ŋ؍���2�J���ōs���Ă����W���C���g�J���t�@�����X���p�������ď��߂�3�J���ōs�����̂ł��B�����_�Ō��܂��Ă���T�v�͈ȉ��̒ʂ�ł��B
�@�� �J�ÊT�v
�@�@�����F2026�N7��11���i�y�j
�@�@���FChang Gung Memorial Hospital�iLinkou, ��p�j
�@�@�@�@�@�i�������ۋ�`�kTPE�l���玊�߁j
�@�@��FChieh-Tsai Wu �搶
�@�@7��10���i���j��FWelcome Reception
�@�@7��11���i�y�j��FGala Dinner
�@�@��ȃe�[�}�i�\��j�FChiari ��`�A���W�D������������
�@�@���^���i�\��j�@�F2026�N5����
�@�@�@���������\�ɉ����A�|�X�^�[���\�g���݂���\��ł�
�@�Ȃ��A���T���� ��菬���]�_�o�O�Ȉ�����̃g���[�j���O�R�[�X �����×\��̂��߁A�ו��i���ɓ��j���j�ɂ��Ă͍��㒲��������\��������܂����A�{�W���C���g�~�[�e�B���O���̂͏�L�����ł̊J�Â�\�肵�Ă���܂��B
�@�ڍׂ͊m�莟��A���߂Ă��ē��������܂����A���S�̂���搶���́A���Ђ��̓����ł̂��\��m�ۂ����������������B
���{�����_�o�O�Ȋw��@���ۈψ���
�@![]() ����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
�@AANS/CNS Section on Pediatric Neurosurgery��JSPN�Ƃ̋����J�Âł��B
�@�����̂��Q�������҂��\���グ�Ă���܂��B
�@�� �J�ÊT�v
�@�@���@���F2026�N2��8���i���j8�F00�i���{���ԁAJST�j
�@�@�`�@���F�I�����C���i���v���ԁF��1���ԁj
�@�@�e�[�}�FSpasticity Management�i�z�k���Áj
�@�� ���@���@�@�t�c�M�l �搶�i�k����w �]�_�o�O�ȁj
�@�� �u�@�t�@�@�䌴�@�N �搶�i�����s������������ÃZ���^�[ �]�_�o�O�ȁj
�@�@�@�@�@�@�@Robert Keating, MD, Children�fs National Hospital (Washington, D.C., USA)
�@�� Expert Review by
�@ �ERobert Keating, MD, Children�fs National Hospital (Washington, D.C., USA)
�@ �EXiao Bo, MD, Shanghai Children�fs Medical Center (Shanghai, China)
���{�����_�o�O�Ȋw�� ����ψ���
�S�������@���Z�a�F
�ψ����@�@�O�ց@�_
�@![]() ����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
�@�@���{�����_�o�O�Ȋw��iJSPN�j�Ɗ؍������_�o�O�Ȋw��iKSPN�j�̌𗬎��Ƃ̈�Ƃ��āA�����_�o�O�Ȉ�������w�v���O������2016�N�x�����{���Ă���܂��B����܂ł̃v���O�����Q���҂̓̕z�[���y�[�W���������������B
�@2026�N�x�̗��w��]�҂��W�������܂��B
�@�@�@���l���F1��
�@�@�@�����w���ԁF2�`8�T��
�@�@�@��������F2026�N1��31��
�@�@�@�����{�����_�o�O�Ȋw��@�����ǁF jspn@narunia.co.jp
�@�@

�@�@

���{�����_�o�O�Ȋw�� ���ۈψ���
�����@�p �i��
�ψ����@���� ��
�@![]() ����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
�@���N�R���ɊJ�Â���܂���V���]��ᇃJ���t�@�����X�̂��ē��ł��B
�@�F�l�̂��Q�������҂��\���グ�܂��B
�@��7���]��ᇃJ���t�@�����X ���Ԑ��b�l
�@�ޗnj�����ȑ�w �]�_�o�O�ȁ@�p �i��
�@�J�Â̂��ē�

�@�J���F 2026�N3��21��(�y) 14���`�i�\��j
�@�`�@���F Zoom�ɂ��Web�J��
�@�Q����: 2000�~
�@���ʍu��
�@�@1�j�l����ȑ�w�@�]�_�o�O�ȁ@�����@���Z�@�a�F�搶
�@�@�@�@����F�u�O����/�������ɂ�鏬���]��ᇎ�p�v
�@�@2�jSamsung Medical Center, Sungkyunkwan University
�@�@�@ School of Medicine Professor, Department of Pediatrics�@Ji Won Lee�@�搶
�@�@�@�@����F�uCurrent status of pediatric brain tumor management in Korea�v
���{�����_�o�O�Ȋw�� �L��ψ���
�S�������@���� ����q
�ψ����@�q�� �h�j�j
�@![]() ����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
�@AASPN2025(Asian - Australasian Society for Pediatric Neurosurgery)���C���h�l�V�A�@�o������12��11�|14���ɊJ�Â���܂��B
�@Abstract Submission��8��15���܂łƂȂ��Ă���܂��BAbstract�� ���ɕ��������ȂǂȂ��AWord file��Home Page����A�b�v���[�h���Ă��������B
�@2013�N��p�ő�1����J�Â����{�w��́A�o���J�Î��A5��ځA10���N�ɂ�����܂��B
�@�L�O���ׂ��ߖڂ̊J�ÂɂȂ�܂��̂ŁA����A���Q�����������B
�@�܂��AEarly Bird Registration��7��30���ƂȂ��Ă���܂��B�����ӂ��������B
�@�@�@�J���F2025�N12��11���`14��
�@�@�@�J�Òn�F�C���h�l�V�A�@�o����
�@�@�@�����T�C�g�Fhttps://aaspnbali2025.com/
���{�����_�o�O�Ȋw��@���ۈψ���
�@![]() ����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
�@2025�N10���A�t�����X�E�������ɂ� 51st Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN2025)���J�Â���܂��B
�@�@�@�J�Â̂��ē�

�@�@�@�J���F2025�N10��26?30��
�@�@�@�J�Òn�F�t�����X�E�������iLyon�j
�@�@�@�����T�C�g�Fhttps://www.ispnmeeting.org
�@�@�@Regular Abstract Submission Deadline: May 20, 2025�i���ߐ肪�����Ă���܂��B�j
���{�����_�o�O�Ȋw��@���ۈψ���
�@![]() ����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
�@���{�����_�o�O�Ȋw��iJSPN�j�Ɗ؍������_�o�O�Ȋw��iKSPN�j�̌𗬎��Ƃ̈�Ƃ��āA�����_�o�O�Ȉ�������w�v���O������2016�N�x�����{���Ă���܂��B
�@2025�N�x�̗��w��]�҂��W�������܂��B
�@�@���l���F1�����x
�@�@�����w���ԁF2�`8�T�Ԓ��x
�@�@��������F2025�N1��31���܂�
�@�@�����{�����_�o�O�Ȋw��@�����ǁF jspn@narunia.co.jp
�@�@

�@�@

�@�@

���{�����_�o�O�Ȋw��@���ۈψ���
���� �@�p �i��
�ψ����@ ����@��
�@![]() ����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
- �J���F 2024�N7��21���i���j9:00 am JST
- �`�@���F �I�����C���iZoom���g�p�j
 ��Q��i2024.07.08�jAANS/CNS Peds Section���
��Q��i2024.07.08�jAANS/CNS Peds Section��� 
 �ڍ�
�ڍ� 
���{�����_�o�O�Ȋw��@����ψ���
���� �@�����@����q
�ψ����@ ���Z�@�a�F
�@![]() ����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
�@ISPN 2024��2024�N10��13���`17���ɃJ�i�_�̃g�����g�ŊJ�Â���܂��B
�@�i�w��Web�T�C�g�Fhttps://ispnmeeting.org/�Ƀ����N���Ă��������j
�@����̊w���ISPN�ݗ�1972�N�ȗ��A�ߖڂ̑�50��ɂ�����܂��B
�@����The Westin Harbour Castle, Toronto�ŁA�n�[�o�[�t�����g�ɗ��n���Ă��܂��B�I���^���I�Ή����̍`�ŁA�����j���O��U�����y���ނ��Ƃ��ł��A�s���̌e���̏�Ƃ��Ă��l�C�̃G���A�������ł��B
�@�܂����ӂɂ̓i�C�A�K���̑��l�C�T���E�t�B���b�v�X�E�X�N�G�A�Ȃǂ̊ό��X�|�b�g�ɂ��b�܂�Ă��܂��B�i�C�A�K���E�I���U���C�N�̃��C�i���[�ւ̃V���[�g�g���b�v���y���ނ��Ƃ��ł��܂��B
�@���Ђ��̋@��ɐ��E���̏����_�o�O�Ȉ�ƉȊw�I�ȃf�B�X�J�b�V������[�߁A�������w�сA�L���l�b�g���[�N������Ă݂Ă͂������ł��傤���H
�@���݁A����o�^�̒��ߐ肪4��12���ƂȂ��Ă���܂��BJSPN����������̕��X�̂��Q�������肢�v���܂��B
�@�g�����g�E�s�A�\�����ۋ�`����̓��j�I���E�s�A�\���E�G�N�X�v���X�Ƃ�����`�A���S���Ŏs�X��25���قǂŌ���Ă���D�A�N�Z�X�ł��B
�@���̎����̃g�����g�͋C����5�`16�x�قǂł����A���Љ������i�D�ŎQ�����܂��傤�B
���{�����_�o�O�Ȋw��@���ۈψ���
���� �@�p�@�i��
�ψ����@ ����@��
�@![]() ����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
�@��36��؍������_�o�O�Ȋw��iKSPN�j��2024�N5���Ɋ؍��E�\�E���ŊJ�Â���܂��B
�@KSPN��JSPN�͖��N���݂Ɏ�Â��ăW���C���g�J���t�@�����X���s���𗬂�[�߂Ă��܂����B�������N�Ԃ͐��E�I�ȃp���f�~�b�N�̂��ߒ��f����Ă��܂������A����v���Ԃ�Ɍ��n�J�ÂōĊJ����邱�ƂɂȂ�܂����B
�@���\�̃e�[�}�Ȃǂ͎��R�ł����AKSPN�̐搶���ƌ𗬂�[�ߋc�_�ł����ϋM�d�ȋ@��ł��i�ߋ��̎Q����JSPN�̃z�[���y�[�W�ɂ���܂��̂ł��Ђ��Q�Ƃ��������j�B
�@JSPN����̊F�l���̂��Q���Ɖ���̂����\�����肢�\���グ�܂��B
- ����F2024�N5��10���i���j
- ���FHotel Sam Jung

- ��W�l���F����i���Ȃǂ̓s���ɂ��l���ɐ���������܂��B����ґ����̏ꍇ����]�ɓY���Ȃ����Ƃ����������������j
- ������@�F�p�����^�����L�܂ł����肭�������B
�@�@�@�@�@�@�S���F����@��
�@�@�@�@�@�@���[���A�h���X�Fa.muroi@md.tsukuba.ac.jp
�����^�̓^�C�g���A���ҁA�����A�{���i300�P��ȉ��j���܂�word�t�@�C���̌`���ʼnp��ō쐬���Ă��������B - ������ߐ�F2024�N2��29���i�j�������͂���܂���B
���{�����_�o�O�Ȋw��@���ۈψ���
���� �@�p�@�i��
�ψ����@ ����@��
�@![]() ����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
����̕��ւ̂��m�点���j���[�ɖ߂��@
�@���{�����_�o�O�Ȋw��iJSPN�j�Ɗ؍������_�o�O�Ȋw��iKSPN�j�̌𗬎��Ƃ̈�Ƃ��āA�����_�o�O�Ȉ�������w�v���O������2016�N�x�����{���Ă���܂��B
�@2024�N�x�̗��w��]�҂��W�������܂��B
�@�@���l���F1�����x
�@�@�����w���ԁF2�`8�T�Ԓ��x
�@�@��������F2024�N2��29���܂�
�@�@�����{�����_�o�O�Ȋw��@�����ǁF jspn@narunia.co.jp
�@�@

�@�@

�@�@

���{�����_�o�O�Ȋw��@���ۈψ���
���� �@�p�@�i��
�ψ����@ ����@��
- 45th Annual Meeting of The Egyptian Society of Neurological Surgeons in collaboration with The Japan Neurosurgical Society�ɎQ������

��ʌ���������ÃZ���^�[ �]�_�o�O�ȁ@�F���� ���� - 2025�N�x�앣�܁i�p������j��܂̂���

�����s������������ÃZ���^�[ �]�_�o�O�ȁ@���H �^���b - 2025 �N�x�앣��ܘ_���̊T���Ƃ���

�������������a�@ �]�_�o�O�ȔN�@��� �S�� - ��53����{�����_�o�O�Ȋw��Q���L

�F�{��w�a�@ �]�_�o�O�ȁ@���Y �C - �����_�o�O�Ȋw��Q��L

�����w��w��6�N�@�쑺 ���� - ISPN2024 Toronto�Q����

�i2024.103.13�`17�j
���ˎs��������ÃZ���^�[�����]�_�o�O�ȁ@���X�݂Ȃ�
�@2025�N10��13������17���Ƀg�����g�ōs��ꂽISPN2024�ɂ��āA���ˎs��������ÃZ���^�[�̍��X�݂Ȃݐ搶�̃t���b�V���ȕ����������܂����B
�@����͓��{����̔��\�����Ȃ����₵����ۂł����B2025�N��10��26������30���܂Ńt�����X�̃������ŊJ�Â���܂��B
�@�������̓p������TGV�Ŗ�2���ԁA���H�̊X�Ƃ��Ă��m���Ă��܂��B���X�ؐ搶�̕����ǂ݂��������A���`�x�[�V���������߂Ă��ЎQ�������������������B
- JSPN-KSPN exchange program In Seoul National University Children's Hospital for six weeks �L

�i2024.10.21�`2024.11.30�j
�Y�ƈ�ȑ�w�]�_�o�O�ȁ@���� ����
- ��41����{�ҒŌ����� �Q��L

�i2024.7.6�j
�k�C�����q�ǂ�������ÁE�È�Z���^�[�@�g���a�v - ��1��A�W�A�E�I�Z�A�j�A�����_�o�O�Ȋw���R�[�X�F�����o�C�i�C���h�j
�i2024.5.30�`6.1�j
�v���O�����T�v
�L
�k����w�a�@�]�_�o�O�ȁ@�t�c�M�l - ��52����{�����_�o�O�Ȋw���

�x�R��w�@�Ԉ� ��� - ��52�� ���{�����_�o�O�Ȋw��i�x�R�j�ɎQ������

�F�{��w�a�@ �]�_�o�O�ȁ@�A�� �� - ���{�����_�o�O�Ȋw��ɎQ������

�v���đ�w�a�@�Տ��������@���� ���q - �앣�܁i�p������j����܂���

����q��ÃZ���^�[�@���{ �m�� - 2024�N�x�앣��ܘ_���̊T���Ƃ���

�k����w��w���]�_�o�O�ȁ@���c �� - ��4��A�W�A�E�I�Z�A�j�A�����_�o�O�Ȋw��w�p���� ��

��4��A�W�A�E�I�Z�A�j�A�����_�o�O�Ȋw���@���� �瑢�A�t�c �M�l - ��4��A�W�A�E�I�Z�A�j�A�����_�o�O�Ȋw��w�p���� �Q���L

�}�g��w�����a�@�]�_�o�O�ȁ@�c�� ����Y - The 4th Congress of AASPN 2023 �Q���L

�R�`��w�]�_�o�O�ȁ@�ɓ� ���Ȏq - ��4��A�W�A�E�I�Z�A�j�A�����_�o�O�Ȋw��w�p���� (AASPN) �Q���L

���ۈ�Õ�����w��w���]�_�o�O�ȁ@���n �ꏲ ���ۈ�Õ�����w���C��@���� �m���A���c �X�q�A���� �z�ؔT - KSPN-JSPN Joint Meeting 2024 in Seoul�ɎQ�����āF�\�E��(�؍�)

�i2024.5.9�`5.10�j
���ꌧ���암��ÃZ���^�[�E���ǂ���ÃZ���^�[�]�_�o�O�� ���� �� - The 48th Annual Meeting of the International Society for Pediatric�@Neurosurgery�iISPN�j�ɎQ�����āF�V���K�|�[��

�i2022.12.6�`12.10�j
�ޗnj�����ȑ�w �]�_�o�O�� �� �� - ���،������w�v���O���� �\�E����w�����a�@�ł̌��C�F�\�E��(�؍�)

�i2019.11.18�`11.29�j
���Ɍ������ǂ��a�@�]�_�o�O�ȁ@���v�� ��s - The 47th Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery �ɎQ�����āF�o�[�~���K��(�C�M���X)

�i2019.10.20�`10.24�j
����ȑ�w �]�_�o�O�ȁ@�{�c �^�F�q - ���،������w�v���O�����@�\�E����w�����a�@�ł̌��C�F�\�E��(�؍�)

�i2018.8.20�`9.14�j
�k�C�����q�ǂ�������ÁE�È�Z���^�[�@�]�_�o�O�ȁ@��X �`�� - KSPN-JSPN Joint Meeting 2017 in Seoul�ɎQ�����āF�\�E��(�؍�)

�i2017.5.19�j
�k�C�����q�ǂ�������ÁE�È�Z���^�[�@�]�_�o�O�ȁ@��X �`�� - The 17th Inter National Symposium of Pediatric Neuro-Oncology(ISPNO2016) �ɎQ�����āF���o�v�[��(�C�M���X)

�i2016.6.12�`15�j
���Ɍ������ǂ��a�@�]�_�o�O�ȁ@�͑��~ �j - The 41st�@annual meeting of The International Society for Pediatric Neurosurgery �ɎQ�����āF�}�C���c(�h�C�c)

�i2013.9.29�`10.3�j
����������ȑ�w�]�_�o�O�ȁ@���v�� �� - KSPN-JSPN joint meeting �ɎQ�����āF�W�B(�؍�)

�i2013.5.29�j
�ޗnj�����ȑ�w�]�_�o�O�ȁ@�p �i�� - 40th ANNUAL MEETING of the ISPN in SYDNEY�F�V�h�j�[(�I�[�X�g�����A)

�i2012.9.10�`13�j
�����������ی���Ñ����Z���^�[�@�]�_�o�O�ȁ@���� ����q - ��23��d�r�o�m�I�s���F�A���X�e���_��(�I�����_)

�É��������ǂ��a�@�@�]�_�o�O�ȁ@�� ���i
�yESNS-JNS2025�Q�� �L�z
�y2025�N�x�앣��� �L�z
�y��53�� ���{�����_�o�O�Ȋw�� �L�z
�y��52�� ���{�����_�o�O�Ȋw�� �L�z
�y��4��A�W�A�E�I�Z�A�j�A�����_�o�O�Ȋw��w�p���� �L�z
�i2023.12.13�`12.15�j
�@�`���ʐ����W�ό`�ɑ�����{�����_�o�O�Ȋw��̌����`
���{�����_�o�O�Ȋw��
�@���ʐ����W�ό`�َ͑�������������̏_�炩���Y���ɕx���W�̐����Ɋ�Â������W�̕ό`�ł��B���`�ɂ͓����������ԓ���p�����Ƃ邱�ƂŎ����̓��̏d���� ���_�炩�����W���c��ŕό`���邢��������Ȃɂ��ό`�ł����A�o���O��i�q�{����o�����j�ɂ�����l�X�ȓ����ւ̊O�͂����W�ό`�ɉe�����邱�Ƃ��m���Ă��܂��B�䂪���ł͓��ʐ����W�ό`�͂���܂ŗ��ӂ���邱�Ƃ����Ȃ��A���R�o�߂ŊT�ˉ��P������̂ƔF������Ă��܂����B�������Ȃ���A�č��Ő�s���Ă������ʐ����W�ό`�ɑ���w�����b�g�ɂ�鋸�����{�M�ōs����悤�ɂȂ��Ĉȍ~�A�Љ�I�ȔF�m�x���オ���Ă��܂��B
�@�{�w��͓��ʐ����W�ό`�ɑ��Ĉȉ��̂悤�Ȍ����������܂��B
- ���ʐ����W�ό`�̌o��
�@�o������z��܂ł̎����͓��ʐ����W�ό`�����݉����₷�������ł���ƂƂ��ɁA���ʁE�̈ʂ̃|�W�V���j���O�̕ύX�Ȃǂ̐����w���̉���ɂ��ό`�̉��P�����҂ł��鎞���ł��B ���ʐ����W�ό`�͒�o���̏d���E���Y���A�^�����B�̒x��A�Όz�ȂǁA���͂ł̓��ʁE�̈ʂ̕ϊ�������ȏꍇ�ɂ͎��R�y�������҂ł��Ȃ��\��������܂��B�܂��A�ό`�����x�ȏꍇ�͉^�����B�̒x��Ȃǂ��Ȃ��Ă��A���R�y��������ȏꍇ������܂��B
�@���ʐ����W�ό`�͌z��̎����ȍ~�Ɉ�������\���͏��Ȃ��ƍl�����Ă��܂��B���̎����ȍ~�Ɉ������݂���ꍇ�́A���W���D�����������Ȃǂ̎����ɂ��ό`�̉\��������܂��B
�@���ʐ����W�ό`�͎����ł͂Ȃ��A���̔��B�ɉe�����Ȃ��ƍl�����Ă��܂��B�܂����l���ȍ~�̓��퐶���ɂ�����s���v�Ɋւ��ẮA����܂ŗl�X�ȕ͂�����̂́A���e/���e�I�Ȃ��̂��������m�ȕs���v�̏؋��͎�����Ă��܂���B - ���ʐ����W�ό`�Ɠ��W���D������������
�@���ʐ����W�ό`�́A����Ǝ������W�`�Ԃ�悷�铪�W���D�����������ǂƂ̊ӕʂ��d�v�ł��B��҂͎����ł���A��p���K�v�ł��B�������ӕʂ��邽�߂ɂ́A���W���D�����������ǂ̐f�f�ɂ��ăg���[�j���O������t�i���{�����_�o�O�Ȋw��F���A���{���W�{��ʊO�Ȋw�����Ȃǁj�ɂ����I�Ȑf�@���K�v�ł��B - ���ʐ����W�ό`�ւ̑Ή��ɂ���
�@�����������Ōy�x�̏ꍇ�ɂ́A��������镔���̏����A���ʁE�̈ʂ̃|�W�V���j���O�̍H�v�Ȃǂ̐����w�������ő��������P���܂��B����A�����w�������ł͉��P������ȏꍇ�ɂ͔��e/���e�I���P�̊ϓ_����A�w�����b�g�ɂ�鋸���̗L����������Ă��܂��B�w�����b�g�ɂ�鋸���́A���W���}���Ɋg��i�`�Ԃ��ω��j����������O�����ɊJ�n�����ꍇ�ɗL�����������Ƃ���Ă���A�w�����b�g�ɂ�鋸�����s���ꍇ�ɂ͌z��ȍ~�̉y�I�����ɊJ�n���邱�Ƃ��]�܂����ƍl�����Ă��܂��B����A�������i��1�j�ȍ~�ɊJ�n�����ꍇ�ɂ͌��ʂ�����I�ł��邱�Ƃ��m���Ă��邱�Ƃ���A��X�͓������ȍ~�̃w�����b�g�ɂ�鋸�����ÊJ�n�͐������܂���B
�@�w�����b�g�ɂ�鋸���́A��{�I�ɔ��e/���e�̉��P����ړI�Ƃ�������f�Âł���A���̔��f�͌X�̉��l�ςɊ�Â��Č��肳���ׂ����̂ł��B�����_�œ��ʐ����W�ό`�ɑ���w�����b�g�ɂ�鋸���̓K���Ɉ�w�I�ɖ��m�Ȕ��f��͂Ȃ��ƍl�����܂��B
2025�N4��1��
�@���{�����_�o�O�Ȋw��ł͐_�o�Ǖ���Q�̃��X�N�̒ጸ�ւ̎��g�݂Ƃ��ėt�_�ێ�𐄏����鐺�������쐬���܂����̂ŁA�{�z�[���y�[�W�Ō��J���܂��B
2022�N2��14��
�@
�s���n���a�@�]�_�o�O�ȁ@���� ��}
�@�����{�@�̕ω��ɉ����āA2008�N�x�ɉ������ꂽ�V�w�K�w���v�̂ɂ��A2012�N4�����璆�w1�C2�N�̒j���i��240���l�j�ɁA�������h�K�C���h�����B
�@�����i�_���E�����E���o�j�̑I���͊w�Z���Ƃł��邪�A����7�����x���_����I�����Ă���B�o���̗L�����킸�w���͑̈�ȋ��@�ɂ��̂Ō��C������A������̐������i��ł���B
�@�Ƃ��낪�A���ȏȊO�s�c�̂̓��{�X�|�[�c�U���Z���^�[��1983�N����W�v���Ă���u�w�Z�Ǘ����̎��S�E��Q�v������g���āA���w�E���Z�̎��ƁE�����̃X�|�[�c�ɒ��ڂ��ĉ�͂������� �i2010�N�j�ɂ��A�_���ɂ�鎀�S��27�N�Ԃ�110��Ƒ����A���̃X�|�[�c��莀�S�m���������A���̂͏��S�҂ɑ����A�����ɋ}���d�����o���������]�A���������ƂȂǂ����߂Ė��炩�ɂȂ����B
�@2003�N����w���҂⓹��ɒʂ��l��ΏۂƂ����u���Q�⏞�E���������x�v���������Ă����S���{�_���A���̎������g���A �S�_�A��Ȋw�ψ���܂Ƃ߂�������2011�N12������ �u�_���ɂ�����d�Ǔ����O���v�Ƃ��Čf�ڂ���A7�N�Ԃ̐f�f�����m�����������O��30����ڍׂɌ������A ���̃[�����߂��������Ɗ����Ă����B
�@�������Ȃ���A���̌����͎҂ɓ��肵���ł���A���̂��N������������ߒ��Ɍ��y���Ă��Ȃ��B �S�_�A��2011�N6���ɔ��s���A�_�E�����[�h���o����u�_���̈��S�w���v�ɂ́A ���̕�������A�����ɂ͎ҁE���������E �����ꏊ�E�������̏E�֗^�ҁE��̌o�߂Ȃǂ̗�������B
�@�u�֗^�ҁv�͇@�w���҂̒i�ʂ◧���o���N���A���ꑶ�݂̗L���ȂǁA�A����̋Z�ɂ��ɂ́A����̐��ʂ�N��A�i�ʁA�_���o���Ȃǂ��L�ڂ��邱�ƂɂȂ��Ă���B
�@�N��A�̏d���A�_�������l�������g�݂�ւ���A�w���҂̋���҂Ƃ��Ă̎��i�܂Ŋ܂߂����C���K�v�ƍl����B
�@���ہA�]�_�o�O�Ȉ�B�̓X�|�[�c�O���ɂ��}���d��������͂����ɑ�����������Ă��]�A���s�ǂȂ��Ƃ��n�m���Ă���B �����w�H�w���̋{��S��̓f�W�^���E�q���[�}�����f������g���āA��]�������ˋ��Ö���j�]������@������̌����コ��z�肵�A �_���ɂ����Ă͢�g�̊m����������̖h�~�ɂȂ���Ƃ��Ă���B�w���Ɠ���ł̏_�����̂͗ގ��ł͂Ȃ���������Ȃ����A ���̗\�h���l���鎋�_�́A �_���ŗL�̓�����w���̂�����̕��́A�����_�₵������s�҂܂Ŋ܂߂����N�ی�̊ϓ_�A ��w�I�m���̕��y�ȂNJ܂߂āA�]�_�o�O�Ȉ�Ƃ��Ă��s�����Ƃ͑��X����Ǝv����B
Copyright ©JSPN All Rights Reserved.