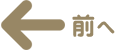気仙がんの在宅療養研修会 2016 岩手
【基調講演】気仙の在宅緩和ケアの現場から

岩渕 正之さん
私の在宅医療の原点と今
30年近く前、東京で勤務医になりたての私が初めて自分でみつけたがんの患者さんは膀胱がんでした。手術のために入院していただきましたが、あちこちに転移していて手術は無理だとわかりました。化学療法を始めたものの副作用のために中止になり、「大学病院としてはもうやることがないから自宅へ帰りましょう」という話になりました。
多発性の骨転移で痛みがとてもひどく、腎臓から2本管が出ていてストーマをつけている状態で、「通院は大変だから往診に来てほしい」という要望がありました。当時の状況では、大学病院から患者さんのところへ往診に行くことは考えにくく、どうしようか思案していたところ、外来の看護師さんに患者さんの住所を渡されて「行って悪いことはないから、行ってきなさいよ」と言われました。それで2週間に1度ずつ通い、管を交換して痛み止めを出していました。
これが教授に知られて、大学病院に医者がいなくなるから、と当初はあまりいい顔はされませんでした。看護師さんが病院の規約に「必要な患者さんには往診すること」という一文があることを見つけてくれました。それを教授に見せてからは何も言われなくなりました。
しかし当時は訪問看護師さんもいない時代で、自分で薬が飲めなかった患者さんの布団をまくると座薬がザーっと出てくるような状態でした。そのときでさえ、私の頭の中には「在宅医療」という考えはありませんでした。なんとかして病院に連れ戻して治療しようと思っていたのです。そのようにして2、3カ月が経ち、意識もなくなって最期が近いというところで、手術後の回復室が1床開いたから入院できるというので救急車で搬送しましたが、その日のうちに亡くなりました。これはとても苦い経験でした。きちんと自宅で看てあげられなかったという大きな後悔が、私の中にありました。この挫折経験が、私の往診と訪問診療の原点になっています。
現在、岩渕病院は岩手県大船渡市で通常の一般外来のほかに往診と訪問診療をやっています。昨年度の看取りは22名で、そのうちがん患者さんは13名でした。肺がん4名、大腸がんと食道がんが各2名、胃がんなどが各1名です。さまざまながん患者さんがいますが、末期になるとみなさんメンタルケアの必要性は同じなので、そちらを中心にやっていくと、だいたい同じような治療で最期を迎えることができました。
当初、治療を拒否していた患者さんの在宅診療
40歳独身の女性の事例をとおして、在宅療養の現場についてお話しします。患者さんは地方都市在住で、ご両親は仮設住宅在住でした。患者さんは特に既往歴はなく、性格は明るくて白黒はっきりさせるタイプで、友人が多いという方でした。
健康診断で肺に影があると指摘され、精査したところ乳がん、多発肺転移、腋窩リンパ節転移の診断がなされました。「治らないのなら治療しても意味がないだろう」と放置され、1年後に頭痛が出現し、検査したところ脳転移がみつかりました。それでも「治療は希望しない」といい、さらに4カ月経ったところで一人暮らしの生活が維持できなくなって、ご両親のところに転居して同じ月に大船渡病院の緩和医療科を受診されました。
緩和医療科の受診時は頭痛と吐き気で顔を上げられない状態でしたが、なんとか会話はできました。CTで多発の脳、脊椎、腸骨そして肝転移が指摘されました。痛みがひどかったのでコントロールするために入院を勧められました。ご家族は入院希望でしたが、ご本人は「どうせ治らないし、お金もない」と拒否され、そのまま帰宅されました。
緩和医療科で訪問診療を勧められて患者さんが同意されたので、初回の往診をしました。真冬なのに仮設住宅で暖房もつけずにマットの上で毛布にくるまっている状態でした。吐き気と頭痛がひどく「動けない、考えがまとまらない、私に何もしないで」と言われました。右を下にして横になっていると少しは楽だという患者さんは、私に背中を向けたままで、この日は顔を見られませんでした。
まず薬剤師さんの介入を要請しました。脳転移のせいで視力が落ちていたために、経口薬はのみ方がわからないというので医療用麻薬の貼り薬に変更して、薬剤師さんによる訪問指導を受けました。薬剤師さんの初回訪問では、視覚障害やテープを貼った後の手洗いといった観点から、お母さんに貼ってもらうよう指導しました。貼り薬の副作用に関しての入浴指導、吐き気や眠気、便秘、痛みがひどくなったときのレスキュー(突発性の強い痛みに対して即効性の薬剤を使うこと)の方法について説明したところ、「薬で不安なことがあればいつでも相談していいのですね、安心です」という言葉をいただきました。
貼り薬とレスキューを使う基本的なやり方で痛みは減退しました。レスキューも1日5回から2~3回に減りました。多少痛みは残っているけれど「ぼーっとするのが嫌なので医療用麻薬はこのくらいでいい、大丈夫です」と言われたときに、初めて笑顔を見せていただきました。最初に訪問してから3週間目には座っていて、初めて顔を正面から見ることができました。それまでは痛みで座れませんでした。
認知行動療法で積極的な姿勢を引き出す
疼痛はまったくないという患者さんと「先生、そんなに薄着で寒くないのですか?」といった会話ができるようになりました。痛みがなくなって精神状態が落ち着いたので、認知行動療法のチャンスと考えて実行しました。
「認知」とはものの受け取り方、考え方をいいます。人間はストレスを感じると悲観的になり、心が問題を解決できない状態になります。認知行動療法は抑うつや不安、非適応的行動、認知の歪みに対して行うものです。現実的でしなやかな心を取り戻し、現在の問題に対処できるようにして、最終的にストレスに対して上手に対応できるようにする。多くの精神障害に適応がありますが、在宅療養の患者さんとそのご家族にとっても非常にいいアプローチだと思います。認知行動療法では短期、長期目標を考えてもらいます。痛みを持っている患者さんは、とにかく現在のことしか考えられません。とにかく今の痛みをとってほしいというのが願いです。
患者さんに短期目標として「一週間後にどうしていたいか」と尋ねると、彼女は「座って食事がしたい」と答えました。そのためには痛みをもっと取ることが必要だと思うというので、MRIやCTの検査を提案すると「やってみようかな」という反応が得られました。それまでは検査も拒否されていました。
次は長期目標です。通常は1年後といった設定ですが、この方の病勢を考えて「1カ月後の目標」を尋ねてみました。「買い物に行きたい、自分で服を手にとって選びたい。あとは競馬。勝ち負けではなくてドキドキしたい、競馬が大好きなんです」と目を輝かせて言いました。化学療法、ホルモン療法について質問が出始めたのがこの頃です。
この後、乳腺外来をお母さんと一緒に受診して放射線治療、ホルモン療法の説明を受けました。ご本人は前向きに考えていましたが、お母さんが「娘に無駄な治療は受けさせたくない」と強く反対されたのです。そこでお母さんにも認知行動療法に基づいた対応をしました。短期目標として、痛みがない笑顔のある生活を想像してもらいました。長期目標として、娘さんが自分らしい人生を送る時間をつくってはどうかという提案をしました。ここで大事なのは、治療の誘導はしていないことです。治療する意味があるかどうかお母さんが考えて、治療するという方向性がはっきりしたところで放射線治療、ホルモン療法でどういうことが起きるのか、副作用をも含めて説明しながら治療に向かっていきました。
ここまで往診初日からだいたい2カ月です。その後、ご家族の入院などがあり、患者さんの治療はすこし間があきましたが、現在は外来で化学療法を受け、私は往診で副作用のチェックをしています。
仮設住宅における在宅療養の問題点
認知行動療法は被災者のみなさんにも効果があります。今の状態でどうしようと、明日のことが考えられなくなっている被災者の方たちは、認知行動療法によって前向きな気持ちになってくれるのではないかと思います。
症例の患者さんも仮設住宅にお住まいですが、そのほか5名の仮設住宅の患者さんを往診しました。仮設住宅の大きな問題として隣との壁が薄いことがあります。せん妄とか不穏を起こして叫んだとき、周りに聞こえているのではないかと家族は生きた心地がしません。実際、聞こえています。せん妄や不穏を起こさないようにしてほしいという要望が多いのですが、ある程度は薬で抑えられても100%抑えることはできません。夜中に騒いでしまい、ご家族が謝って回ることが多かったです。
仮設住宅はそもそも自分の家ではない、なぜここで死ななくてはならないのかという意見もありました。自宅での看取りとは言えないのです。
夜間騒音で眠れないという問題もあります。たいてい仮設住宅の前は駐車場になっています。震災後に仕事をなくした方が新たに就く仕事は2交代、3交代制が多いので、夜中に車で帰ってくる人たちがいます。寝ているがん患者さんは、うちの前に車が止まってドアがバンと閉まった瞬間に目が覚めてせん妄状態になってしまいます。壁をドンドン叩いたり、大声をあげたりするのに対処するご家族は眠れません。
私が往診した仮設住宅はばらばらの地域から入居されていたので、患者さんの様子に目配りしてほしいと頼める人もいなくて、家族が買い物に行くのも困難になります。間取りによっては、玄関のドアを開けると患者さんが寝ているベッドが丸見えです。また室温調節が難しく、夏暑くて冬寒いです。このような問題により、やっと家に帰ってきたのに数日でご家族のほうが疲弊してしまう。仮設住宅のがん患者さん5人は全員、入院になりました。
終末期における医療者と患者家族の感じ方のギャップ
がん患者さんの往診をしていると、最初のうちはご家族と同じような気持ちでいるのですが、終末期に出てくる症状についての受けとめ方にギャップが生じてきます。末期に出てくる下顎呼吸、下あごで呼吸する状態をご家族は呼吸困難と感じます。医療者としては、胸が膨らまなくなってくるのだから首が動いて顎が動くだけで、これは正常な経過だと考えてしまいます。同じようにご家族は呻吟(しんぎん)を痛みなどの苦痛によるうめき声と感じ、喘鳴(ぜんめい)は痰詰まりと感じますが、医療者は死戦期(死に至る直前の状態)の正常な経過だと見ています。
患者さんご家族と感じ方のギャップを生まないために、末期の経過でどのような症状が出るのかについて、ご家族にきちんと説明しておくことがとても大事だと感じています。
使命としての在宅療養
最初にお話しした挫折経験の加えて、私の在宅医療にはもう一つ原点があります。父が亡くなったときに遺品を整理していて、たまたま見つけた原稿にこうありました。「在宅医療を円滑に進めるためには、保健、医療、福祉の連携の下での総合的な在宅支援サービスの充実を図ることが必要である。しかし現在は効率的に運用されているとは言いがたい。疾患の一連の流れの中で中心に存在するのが医療であり、医師が主導しコーディネート役をつとめるのが理想と思われる」。この原稿が書かれたのは20年から25年前で、当時はこのような考え方が提案されても実現しなかったのだと思います。当時勤務していた東京に戻ろうと思っていた私は、この原稿に書かれていることは自分の使命だと思いました。そして大船渡に戻り、父がやろうとしてできなかった在宅療養に取り組むことになり、そして今に至ります。