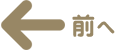がんの在宅療養ガイド 研修会 沖縄 2016
【リレートーク & ワークショップ】がん患者さんが安心してわが家で過ごすために
テーマ2 「最期のとき」に向き合うこと 住み慣れた地域で支えるためには
| コーディネーター: | 宮城 愛子さん(大名訪問看護ステーション 訪問看護認定看護師) |

宮城 愛子さん
「最期を考える」ことに向き合う
第2章のはじめのところから、読み上げてみます。
大切なひとの「最期のとき」を受けとめるのは、決して簡単なことではありません。大切なひとの人生が残りわずかだと知ったとき、そのことを受けとめ、冷静でいられる方は、そう多くないでしょう。ショックやパニックになったり、無気力になったり、何も信じられない気持ちになったり、または怖くなったり、どうしたらいいのかわからなくなったり……。本人だけでなく、家族も、さまざまな思いを1日のなかでめまぐるしく感じることもあるでしょう。これらの感情は、ごく普通に湧き上がってくるものです。
「お別れの時期が近づいている」と認識することは、これからの生き方に大きな変化をもたらします。身近な人の人生が限られているという現実を受けとめられないつらさに加え、これからの生活に関する現実的な不安や悩みが重なり、家族や周りの方々の気持ちは不安定になってしまうかもしれません。
お別れのときを迎えることに対する受けとめ方は、一人ひとり異なります。本人、あるいは家族の気持ちを落ち着かせる特別な方法はありませんが、それでも、本人と家族がお互いに話し合ったり、周囲の方が手を差し伸べたりすることによって、つらさや悲しみをやわらげることができます。本人と同じように、家族の方へのケアも大切と考えられています。
私たち訪問看護師も、ご本人のみならず、ご家族の方もケアの対象者ととらえ、大切に考えるようにしています。
人生の最終段階の時期を過ごす場所はさまざまです。住み慣れたご自宅や施設、病院、福祉施設、いろいろな選択肢があります。ご本人が安心でき、落ち着いて過ごせる場所を、ご本人とご家族とで一緒に話し合い、選択していくことが大切です。在宅での療養においては、本人やご家族が前向きに考えて受け入れられるか、納得して準備をすることができるかどうかで、その後の療養生活の質が変わってきます。
在宅で最期を迎え、看取るということ
私の経験を交えて、事例をお話しします。ずいぶん以前のことですが、初めて在宅で看取りをさせていただいたAさんは、90歳代女性、肺がんの末期でした。沖縄でも最近では珍しい、4世代同居の大家族でした。いよいよ最期かというとき、主治医の往診をお願いしました。「今夜あたりでしょう」と説明されたご家族は、親族の方々に連絡して様子を伝えていました。夕方、「呼吸が荒くなって、足も冷たくなっている」との連絡で訪問すると、おばあのベッドの周りを十数人の親族が隙間なく取り囲み、「おばあ、今までありがとう。もう頑張らなくていいよ」などと口々に語りかけながら、手や足をさすっていました。そばにいた4歳くらいのひ孫さんに「看護師さん、ばあちゃんは天国に行くんでしょ。天国にも看護師さん、行ってくれるの」と無邪気にきかれました。
息子さんが「おばあは病院では先生や看護師さんに気を遣ってかわいそうだから、最期まで家でみたい」といい、自宅での看取りとなった方です。家族や親戚のみなさんに見送られながら、孫やひ孫にも立派な死の教育、デス・エデュケーションをされていかれたと思います。その光景は、私が訪問看護のすばらしさを感じた原点にもなっているように思います。
不安を抱える患者さんとご家族への対応
在宅療養を選んだご家族は、「ずっと自宅で」と最初から強い決意をもって取り組んでいる方ばかりではありません。もう一つの事例は、ご家族が自宅での介護にたいへん不安をもっており、家で介護できるのか、看取りまでできるのか「イメージできない。わからない」と繰り返し話されていたケースです。
Bさんは50歳代女性で、非結核性抗酸菌症、乳がんの術後数年の方でした。ご主人と3人のお子さんがいらっしゃいました。ご本人は予後について明確な告知は受けていなかったようですが、入院中から病棟の看護師に「死ぬのが怖い」と死の恐怖をたびたび訴えていたと聞いています。非結核性抗酸菌症による呼吸状態の心配もあり、病状が安定しているとはいえ、常に呼吸状態の観察などが必要でした。寝たきりになり不安材料はたくさんありましたが、主治医がご家族に「まず、一週間でも自宅に帰ってみましょう。無理ならいつでも病院に戻れるようにしておきます」とおっしゃって、自宅に帰られました。二週間後、外来受診を終えたBさんは「待ち時間が長くて疲れた」といわれました。いつの間にか、すっかり在宅での生活になじんでおられました。「いつでも病院に戻れる」という主治医の言葉が安心感にもつながったのでしょうか。そのままご自宅で最期を迎えることができました。
庭が見渡せる明るいリビングの真ん中に介護用ベッドを置き、即席のカーテンで仕切りをつくり、しっかりとプライバシーも確保しました。常にご主人やお子さんたちがそばにいらして、日々、穏やかに過ごされた印象があります。訪問看護師は24時間態勢を整えました。訪問診療・看護、ケアマネジャー、介護をはじめ、多職種が関わり、カンファレンスも何度か行いました。情報の共有、ケアの内容について、ご家族とたびたび話し合いました。常に訪問診療の先生と連絡を取り合い、ご家族とご本人の安心につながるように支援させていただきました。
在宅療養を支えるチームワーク
在宅療養で大切な支援チームのチームワークを高めるために、忘れられない医師の言葉があります。ご自宅でのカンファレンスの際に、訪問診療の先生が「みなさん、私たちは一つのチームなんです。サッカーのチームのようにね。医者も看護師もヘルパーさんもご家族も、みんなで一つのチームなんですよ。これからは、お母さんの笑顔が少しでも見られるように、みんなで力を合わせていきましょう」とおっしゃいました。そのとき、本当にみんなの心が一つになったような気がしました。
「在宅療養ガイド」第2章の最後には、「穏やかな最期を望む本人を中心にして、家族、在宅支援チームが一緒になって歩くイメージでとらえて」とあります。「本人を中心にして、家族、在宅支援チームが一緒になって歩く」というのは、大切なキーワードだと思います。
チームのあり方について
在宅支援チームとして大切にしたいことに、家族の気持ちを重視しつつ、連絡ノートを活用することが挙げられました。また、情報を共有する際には、相手の顔を見ながら伝えたほうがいいという指摘がありました。特に連絡したい大事なことは、 ステーションなどに立ち寄って、対面して伝えることで、きちんと情報が共有されるのではないかということです。支援チームの一人ひとりがマネージメントの視点と意識をもって関わっていくことも大切だと思います。チームワークということでは、やはり要はケアマネジャーではないかということになりました。
デジタルデバイスを活用した情報共有
看護師を中心として、携帯電話やスマートフォンで患者さんの状態の変化を共有しています。その上で、最後に入った介護者が、その日の状態、食事や介護内容などについて情報を流すことによって、看護も介護も情報が共有できます。リハビリの担当者やケアマネジャーとも情報が共有できることで、一人で患者さん宅に入る訪問看護・介護の担当者は心強く思うところがあります。例えば、昨日はなかった小さな傷があるのはどうしたのか、といったことを確かめることもできます。家族が心配している状況についても、どのように対応したらいいのか相談できます。情報共有によって、患者さんのその日の状況に沿ったケアができるし、チームでの話し合いもできます。その時々の状況を共有することも大切だと思います。
情報の共有はとても大切なことだと思います。臨床倫理士の金城隆展さんもいらしていますので、ご意見をうかがいたいと思います。

金城 隆展さん
金城 隆展さん (琉球大学医学部附属病院地域医療部)
在宅医療を支援する方たちは、たとえれば、山を登山している患者さんの歩みを支える「杖」だと言えると思います。患者さんは病気という重い荷物を持って歩いているわけです。私たち医療従事者、介護者は荷物を代わりに持ってあげることはできないけれど、「杖」として患者さんの登山というきつい行程を、少しだけ和らげてあげる。荷物の重さそのものは感じられませんが、その手を通して、少しだけ共有できるのかもしれません。
患者さんがいらないと思えば「杖」は手から離すこともできます。私たちは、患者さんの生活に入っていくのではなく、受け入れられて、関わっていくのだということからも、「杖」というとらえ方をしています。
今日のテーマの一つに「患者さんの意志を確認することが大事」とあります。その通りだと思います。ただ気をつけなければいけないのは、例えば患者さんから話を聞いて、「これがしたかったんだ、この人がわかった」と思った瞬間、みなさんは落とし穴におちています。それは絶対に避けるようにしてください。患者さんの気持ちは変わりますし、本当に何をしたいのかは、もしかしたら言葉にできないかもしれません。わかったと思わないで、患者さんの思いを探求していく。そして、患者さんの状況を見ながら、専門家の知識を集結して考えていく。そういうチームとして関わっていただけるとよいと思います。