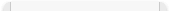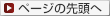近年、薬剤に抵抗性のてんかんに対して外科的な治療が行われる機会が増加しています。外科治療の実際とともに手術適応を決めるにあたって検討すべき事項につき、説明します。
てんかん外科の対象
てんかん外科治療の対象となるのは、難治性で焦点(てんかん発作の引き金となる脳の部位)を特定できるてんかんが主体である。つまりは、この部分を切り取るわけである。
てんかん外科治療のなかで最も早くから、また最も多く行われてきたのが側頭葉てんかんに対する手術である。1886 年にアメリカで行われたてんかん国際会議(ILAE)での集計では、1985年以前には3400例のてんかん手術が行われたとされているのに対し、その後1992年の集計では1986年から1990年のわずか5年間に実に8000例以上のてんかん手術が行われ、急増していることが分かる。
そのうちの60%が内側側頭葉てんかんに対するものである。この形のてんかんは、海馬・扁桃核切徐を行うことによって高率に発作を抑えることができる点で他の部位に焦点を持つてんかんとは一線を画している。
対象となる部位
てんかん原性のある部位と病変部とは必ずしも一致しないことは古くから指摘されていた。Ludersらは、てんかん焦点に関して明確な概念を提唱した[1]。つまり、irritative zone、ictal onset zone, epileptogenic lesion, symptomatogenic zone, functional defict zone, epileptogenic zonedeの6つである。 irritative zoneは発作間欠期に脳波で棘波を引き起こす部位である。一般的に脳波所見で発作の焦点という場合はこれをさす。しかしこの部分は比較的広く、すべてが切徐対象になるわけではない。epileptogenic lesionは発作の原因病変をさす。腫瘍や瘢痕、あるいは形成異常などの器質性病変で、発作の起始に関与するが、焦点がその近傍に完成してからはこの部位を摘出しただけでは発作は抑制できない。また、術前の検査では把握できない症例も多い。Ictal onset zone は発作起始時に発作波が開始する部位で、頭蓋内脳波記録ではじめて確認できる。Epileptogenic zone は切除することにより発作を抑制することのできる部位を指し、まさに切除手術の目標そのものである。術前検査の多くの部分はこの同定のために行われる。多くの場合、ictal onset zone はこの中に含まれ、irritative zone はこれよりも広い範囲である。 epileptogenic lesion はepileptogenic zone の近傍あるいは合併して存在することが多いが、離れて存在する場合もある。さて、症候学的なとらえかたであるが、 symptomatogenic zoneは発作の起始には直接関与する必要はなく、その部位に発作が波及してきた場合に前面にでて発作症状を引き起こす部位をさす。たとえば、頭頂葉焦点例で、焦点そのものが発作を起こしている時点では症状をきたさず発作が、第一次運動領に波及して初めて痙攣発作が見られる場合、第一次運動領がsymptomatogenic zoneにあたる。また、functional deficit zone は発作以外の神経症状を引き起こしている部位をさす。後二者は切徐の対象ではない。
このような観点で焦点周囲の脳組織の役割を論理的に理解し、後述する術前検査の結果を評価する努力により、切徐外科の治療成績は次第に向上している。
てんかん外科の術前診断
まず、外科治療の適応を決定するにあたっては、その症例が難治性てんかんであることを確認する必要がある。みせかけの薬剤抵抗性を除外すること、つまり、患者側の問題点として怠薬をしていないか、医師側の問題点として適切な薬剤が適切な量投与されているか、などを厳密に検討することが重要である。そして、外科的治療の対象となるのは、発作が患者の社会的・精神的活動に大きな障害になっている場合である。われわれは、手術適応となる発作回数のおおよその目安は年間5回以上と考えている。
上記の条件が満たされた場合は、焦点の同定を行う。手術を前提とした焦点診断は、焦点の部位、大きさ、切徐部位の生理的機能分布などを正確に確定する必要があり、薬剤療法を目的とする診断とは趣を異にする。
術前診断は大まかに2つのphaseに分けることができる。
phase1は非観血的な検査であり、MRI,CT,SPECT,MEG、頭皮上脳波、蝶形骨誘導脳波などで、ことに脳波とビデオを組み合わせた持続モニタリングによって発作の様子を観察することが最も信頼性のあるデータと考えられている。モニタリングは、3回以上の発作が捉えられるまで続けるが、通常は7-10日間を要することが多い。また、われわれは近年では近赤外線マッピングをphase1のひとつに加えるようにしている。
phase1で明らかにてんかん発作であることが証明され、かつphase 1の情報だけでは焦点の同定ができない場合、あるいはphase1の検査の間で互いに矛盾した所見が得られた場合には観血的なphase 2に進む。頭蓋内に記録電極を留置して、脳波ビデオ持続モニタリングを行うことが主である。海馬に対しては針電極を定位的に刺入し、新皮質の焦点に対しては硬膜下電極を設置する。これにより、発作時の脳局所の脳波活動を捉え、発作の起始部位を正確に同定する。施設により、また時代によりその割合は変化するが、phase 2まで行う症例は側頭葉内側焦点例で6割程度、その他の新皮質焦点例ではほぼ全例であることが多い。また、われわれは、海馬に刺入された記録電極を用いて脳深部電気刺激を行い、記憶機能の診断も試みている。術前から非焦点側の海馬に機能低下がある症例では、焦点側を切除したのみで記憶低下となる場合があるが、このような症例では焦点側の電気刺激で学習機能の低下がみられることが判ってきた。この検査によって記憶機能低下を予知できる可能性がある。
頭蓋内電極法
頭蓋内電極法は手術を前提とする場合にのみ行われるのでここで詳細を解説する。
深部電極
われわれは図1Aのような4接点を持つ直径1.5mmのポリエチレン被服電極を用いている。定位脳手術フレームを用いて定位的にMRIあるいはCT誘導下に両側の海馬に1本ずつ刺入する。皮下を通して外部に誘導し、強い伸展時に離脱するようコネクターを介して、脳波計に接続する。
硬膜下電極
脳表の焦点発作活動を記録するためには、硬膜下電極を用いる。これは、シリコンのシートでステンレス電極をはさんだもので、電極間距離は10-15mmで、一列のみのストリップ電極(図1B)や、30−50極のグリッド電極(図2)がよく用いられる。図1Cと図4はその例である。頭皮上脳波モニタリングや画像診断などで焦点の部位が推定された場合、1)焦点を同定し、2)切徐後の機能欠損を予測するための機能マッピングを行うために設置する。焦点は発作に先立って発作波が出現する部位であることがその診断基準である。機能マッピングは、電極間双極で高頻度電気刺激することにより、一時的に見られる機能脱失(negative response)あるいは機能活性化(positive response)を指標として行う。刺激は50Hz、5-10mAの矩形はあるいは正弦波が用いられる。この検査は、第1次運動領、言語野、視覚野など重篤な機能欠損が予測される部位に対しては不可欠な検査である。
機能画像診断
焦点の診断は、上述のように脳波が中心であり、頭蓋内電極を用いた脳波モニタリングが最も信頼できる方法とされている。しかし、頭蓋内電極法は侵襲的であり、脳全体をカバーすることができないなどが欠点である。このため、侵襲がより少く、脳全体の俯瞰ができるマッピング法が必要とされている。1980年ころから、発作間欠期にPETで焦点が低代謝領域として観察されることが知られるようになり、てんかん診断における非侵襲マッピング法の先駆けとなった。その後、同様の低代謝・低灌流がSPECTでも観察されることが知られるようになり、より一般化した。一方発作間欠期に低代謝を示さない症例も30%弱に見られる。そこで、発作時には焦点部位で局所脳血流が増加することを利用して、発作時のSPECTが盛んにつかわれるようになっている[11,12,20,12,20]。あるいは、この両者を組み合わせることにより、診断率が向上する。しかし、発作時SPECTは、非常に動的な発作起始時のある一時点のみを切り取って観察するため、観察の時点を誤ると、正しい診断ができない場合がある[19,20]。近赤外線マッピング法(NIRS)は、脳局所血液量の変化を非侵襲かつ経時的に観察できるマッピング法であり[1,5,1418]、てんかん発作時のように急激に変化する血行動態の観察には最適な手法と思われる。ここでは、発作時SPECTとNIRSについて概説する。
NIRSによる発作計測
NIRSの装置は図3Aに示すように、半導体レーザ、受光部、コンピュータで構成されている。頭部に置いたプローベは図3Cに示す。近赤外領域の光線を半導体レーザで発生し、光ファイバーで頭皮上に置かれた入射プローベに導く。赤外線は図3Bに示すように皮膚、頭蓋骨は良く透過するので、そのまま乱反射を繰り返して脳組織に広がってゆく。入射プローベから3cm離 れた頭皮上に受光プローベを置くと、脳組織を通過してきた反射光を捉えることができる。赤外線は脳組織を通過する間にヘモグロビンで吸収されるので、反射光を計測すると脳組織内のヘモグロビン濃度の変化を調べることができる。我々が使用したのは780nmと820nmの2波長である。オキシヘモグロビンとデオキシヘモグロビンは、この2波長でそれぞれ異なった吸収係数を持つので、それぞれの吸光度を調べると、オキシとデオキシそれぞれのヘモグロビンの濃度変化を求めることができる。プローブ間距離が3cmのとき計測できるのはプローベの中点の下2cmを中心とするバナナ形の組織であるとされている[7]。この値は、頭皮上から直下の脳組織を計測する場合至適と思われる。このような入射と受光プローブのペアで1チャンネルと考え、24チャンネル分を頭皮上に配置して計測を行う。プローブは、熱形成樹脂を用いて被験者各々の頭部に密着するようにヘルメットを作成し、これに孔を開けて固定する。あるいは、一般的な頭部形状に成形した面型のホルダーにプローベを固定することもできる。各計測点はナビゲータを用いて各個のMRI上に投射する。13人の難治性てんかん(側頭葉てんかん11人・頭頂葉てんかん2人)につき、一側4あるいは12チャンネルづつ左右対称にNIRの受光及び照射プローベを配置した[22]。11例では、脳波モニターのもとでbemegrideを100-200mg静注して発作を誘発し、発作がおこると同時にHMPAOあるいはECDを静注した。二次性全般化した場合は速やかにdiazepamを静注し、発作が治まった後SPECTを撮像した。また、2症例では、4-6時間にわたってNIRSとEEGのモニターを続け、自然発作を捕らえることができた。Bemegrideで誘発を行った全例で発作が誘発され、脳波上発作波は、自然発作時と同様の部位から起始していることが確認された。同時に行った発作時SPECTでは13例のうち9例で脳波上の焦点部位を中心に血流増加が観察され、NIRSによる血流計測では、全症例で脳波上の発作開始から5〜10秒以内に焦点側血流の急峻な増加が観察された。側頭葉てんかんの症例での計測例を図5に示した.また、自然発作を捕らえることができた2症例はいずれも深部電極法によって側頭葉内側型と診断された症例であるが、2例とも最終診断に一致した側の側頭葉でNIRSによって血液量の増加を認めることができた。
手術法
皮質焦点切除
新皮質に焦点が同定された場合には、これを中心に切除が行われる。この場合、切除範囲が大きな問題となる。切除の対象となるのはepileptogenic zoneとirritative zoneであり、epileptogenic lesionに関してはこれのみの切除では発作を抑制できない。また、臨床症状にとらわれてsymptomatogenic zoneを切除対象とする事を避けなければならない。切徐対象が決まった後、硬膜下電極による刺激や、機能マッピングのデータとの重畳法などによって、eloquent areaを避けて、術後の神経脱落を防止する必要がある。
MST
前項のように、新皮質てんかんでは焦点を決定し、これを切除することが基本である。しかし、焦点が言語野や第一次運動野、第一次感覚野などいわゆるeloquent areaを含んでいる場合、これを切除することは、術後の重篤な機能障害を意味するために十分な切除ができないことがある。このような症例に対して、Morrellが開発した手法がMST(multiple subpial transection)である[1]。焦点を含む皮質の全域を脳回にそって5mmの間隔で軟膜下に挿入した鉤型の切磋具で多数の切除を行うことによって発作の伝播を防ごうとするものである。
この手法の有効性は以下の2点で理論付けられている。1つは、Jacsonian marchと呼ばれるてんかんの進展は、主として皮質を横方向につなぐ神経繊維によって伝達されて行くという実験的な事実である[9]。第2は新皮質の細胞構築はカラム構造の機能単位で構成され、神経機能は主として表面に対して縦方向の繊維で支えられているという事実である。この考えはMountcastle[10]により提唱され、視覚野においてHubelとWiesel[3]が実験的に証明したことで有名である。一方Sperryは[14]皮質に直角に雲母片を多数差し込み、横方向の繊維連絡を遮断しても、神経機能に大きな以上をきたさないという実験を報告している。これらの実験結果は、神経機能を温存しつつてんかんの進展を食い止める方法としてMSTが有用であることの論理的な裏づけとなっている。
選択的切除術海馬扁桃核
焦点切除外科の一形ではあるが、その頻度が多いこと、比較的定型的切徐術が功を奏する点で特殊な存在である。側頭葉てんかんは内側型と外側型とに大別できる。外側型は側頭葉新皮質に焦点のあるもので基本的には他の新皮質に焦点のあるてんかんと同様に皮質焦点切除術が行われる。内側型は海馬あるいは扁桃核にてんかん原性があるものが圧倒的に多く、特異な疾患群を形成し、図6Aのように海馬・扁桃核が切除の対象となる。Penfieldは内側構造とともに、側頭葉の外側部まで切除する側頭葉切除術を行い、これが有効であることを証明した。従来は側頭葉の先端部分のみを切除した後、内側構造を切除する方法が行われてきた。しかし、その後切除範囲、特に上側頭回の切徐範囲を極力小さくする努力が続けられた。その代表的な到達法を頭6Bに示した。まず、Niemeyerは中側頭回においた小さな皮質切除から海馬・扁桃核を切除する手法を報告した。また、Yasargil[9]は外側皮質を切裁せず海馬扁桃核だけを選択的に切除する経シルビウス法が考案した。わが国では真柳[5]が経シルビウス法をさらに前方から到達するよう改良し、堀ら[1]が、側頭葉下面から内側構造のみを切除する方法を開発している。
手術成績
術後の成績を評価するために標準的に用いられているのはEngelの分類である。ClassIは発作がまったくない、ClassIIは発作がごくたまにみられる、ClassIIIは発作頻度が有意に減少、ClassIVは発作頻度不変である。この分類にしたがって焦点の部位別に成績を比較すると、側頭葉てんかんではclassI,IIが68%,classIIIが23%,classIVが9%と、手術の効果の見られた症例が90%いじょうであった。それに反し、新皮質に焦点のある症例では、classI,IIが45%,classIIIが35%、classIVが19%であり、有効率は80%とやや低い値となった。新皮質てんかんの外科治療の困難さをうかがわせる数値である。
側頭葉てんかんの側頭葉切除術に関してSalanovaらは術後の経年的な発作頻度を報告している[14]。これによると、まったく発作の見られなくなったclass Iは術後1年で66%、5年で60%で、わずかながらも術後遅発性に再発を起こすものが認められている。しかし、術後2年までに発作をおこさなかった症例の92%はその後も発作をみていないことから、術後早期の発作頻度が長期的な予後を決定するものと考えられる。
ここで、われわれの施設での成績を示す。1978年から1999年までに外科手術適応として脳波の長期モニターを行った症例は142例である。このうち外科的治療を行ったのは100例で、他の42例は手術にいたらなかった。その理由としては、モニターの結果、①焦点が確定できなかった、②発作中の記録が得られなかった、③刺激試験の結果焦点の切除が記銘力障害や運動麻痺などを惹起すると考えられた場合などである。100例の手術例のうち側頭葉てんかんが70例、新皮質焦点が20例、全般てんかんでdrop attackが前面に立つため脳梁離断を行った症例が10例である。側頭葉てんかんの術後成績はEngelのClassI,IIが87%、IIIが7%であり、94%に良好な結果が得られた。一方同じ焦点切除手術であっても新皮質てんかんでは、ClassI,IIが75%、IIIが10であり、やや成績に差が見られた。術後の合併症としては、3%に一過性の運動麻痺、2%に記銘力障害,精神障害が9%であった。
術後の支援
今後のてんかん外科
海馬に関してはanterior temporal approach, transsylvian approach(Yasargil), trans T2 approach, trans-T1 sulcal approach、subtemporal approach など,枚挙に暇がないが、手術手技的には成熟した分野である。言語野、運動野など、切除手術で重篤な後遺症を起こす領域にある焦点に対しての治療法の開発が必要である。
また、最も進歩が期待され、患者の福祉に役立つと思われるのは、如何に患者の肉体的精神的負担を軽減させて正確に焦点診断がおこなわれるかという点であるかと思われる。