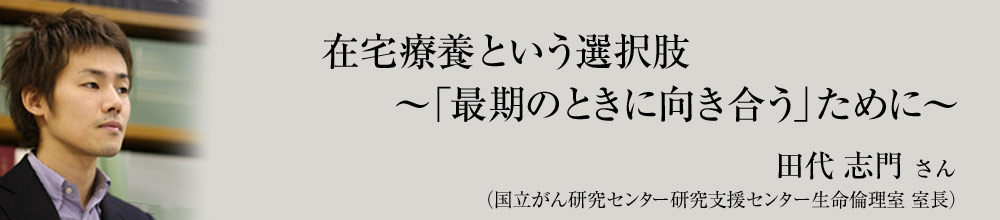「最期のときに向き合う」ことの新しさ
現在の終末期医療の「難しさ」の背景として、往々にして「現代人は死を忘れてしまった」「昔の人はもっと死を受け入れていた」といったことが語られがちです。確かに伝統的な社会では、さまざまな宗教や儀礼が死を受け止めるうえで大きな力を持っていたのかもしれません。それに対して、現代社会ではそういったものの力が段々と失われていっているように思えます。その意味では、それによって人々は死を受け入れにくくなっている、という側面もあるのかもしれません。しかし私は、こうした「昔は良かった」的な話はちょっと疑ってかかる必要があると思います。
だってそもそも、こんなに人が長く生きるようになったのはごく最近のことですよね。この半世紀に医療技術が急速に発展し、次第に医師は正確な診断ができ、ある程度は亡くなるまでの経過が予想できるようになってきました。つまり、今日本が直面している終末期医療に関する「難しさ」は、医療制度が十分に発展し、人々が医療技術の助けを借りて長く生きるようになったことを前提として初めて出てきたものなのです。その意味で、私たちは過去とはまた違う形で「最期のとき」に向き合わざるをえない時代を生きている、と考えた方が良いのではないでしょうか。
告知されるようになって何が変わったのか
特にここ20年くらいで大きく変わったのが、いわゆる「告知」の問題です。1990年ころから日本では議論になり、2000年代以降は、かなりはっきりと方向が変わりました。特にがん専門病院では、1990年代のどこかで「原則伝えない」から「原則伝える」へと大きく舵が切られ、この動きが2000年代に他の病院へも波及していったと考えられています。さらに最近では、病名に関する「告知」以外にも、治る見込みがないことや具体的な余命の予測といった、予後に関わる情報まで患者さんに伝えられるようになってきました。
もちろんこれには良し悪しがありますし、そうした情報を一方的に伝えられて深く傷ついている患者さんや家族がいることを忘れてはいけません。しかし、ここで確認しておきたいのは「最期のときに向き合う」ことに伴う困難は、こうした変化を前提にしている、ということです。実際、一昔前の医療現場での「困難」の代表例は、どのようにして本人に悪い情報が伝わらないようにするかを工夫する、ということでした。これは日本だけではなく、例えば1960年代のアメリカの病院での「告知」の様子を研究した本を見ても、もっぱら「いかに情報を隠すか」ということが主題になっています。
これに対して、予後も含めて悪い情報が本人に伝わるようになってくると、ずいぶんと状況が変わってくるわけです。例えば、現代の緩和ケア病棟で働く看護師の研究を読むと、そこには「人間は死んだらどこにいくのか」といった問いを投げかけられて答えに窮する、といった場面が描かれています。これは悪い情報が伝わらないように苦心する、という困難とはずいぶん違いますよね。
そういう意味では、日本で「最期のときに向き合う」ということが正面切って話題になってきたのは、たかだかここ10年くらいのことなのです。だから私たちは過去を懐かしんでも仕方がなく、これから皆で新たに「最期のときに向き合う」ための知恵や仕組みを考えていかなければならないのだと思います。
病院死の時代を超えて
一般市民の側からすると、急に医療者の考え方が変わって厳しい「告知」を突き付けられても、ぜんぜん準備ができないよ、ということがあるわけです。特に日本では、1976年以降、病院で亡くなる人が在宅で亡くなる人を上回るようになり、その後も現在に至るまで、約8割が病院で最期を迎えています。つまり、「最期は病院で医師に看取られる」ということが「ノーマルな死に方」になっているわけです。
最近でこそ、いわゆる老人ホームなどの福祉施設で最期を迎える人も出てくるようになってきましたが、まだまだ少数ですし、ましてや在宅となると、といった感があります。その良し悪しはともかくとして、これほど長い間、病院死の割合がほとんど下がらないまま推移してきたのは、日本の特徴ともいえます。こうした状況は国民が望んだことという側面もあるとは思いますが、逆に言えば、医療者が積極的にその役割を引き受けてきた、とも言えるわけです。
もちろん、人によっては「自分は絶対に病院で死にたい」という希望を持つこともあるでしょうし、それはそれで尊重されるべきだと思います。海外の状況を見ても、病院死がゼロになることはなく、それなりに福祉施設や在宅ケアの体制が整ってきても、やはり病院死は一定の割合で残ります。ただ、日本全体で見ると、そもそも病院で亡くなること以外の選択肢が十分に育っていないので、本当の意味での選択にはなりえていない、ということがあるわけです。
また先ほども述べたように、そもそも病院で医師に看取られることが「常識」とされている世界では、在宅での看取りを選択する、ということ自体、心理的にも高いハードルが課せられることになります。テレビドラマでも人が亡くなるときには医師が心電図を見て、時計を確認して、という場面が繰り返し放送されていますから、私たちにとってはやはりあれが「馴染みのある」死の風景になっているのでしょう。
実際、私がお話しさせていただいている在宅の先生たちからも、家で亡くなること自体を親族や近所の方が受け入れられず、対応に苦慮する場合があると聞いています。「いくら本人が望んでも、こんな状態の悪い人を家に置いておくべきではない」という考え方は、私たちのここ数十年間の体験に根差していますから、そう簡単には変わらないでしょう。
在宅療養ガイドの役割
そうした状況のなかで、この「ご家族のための がん患者さんとご家族をつなぐ在宅療養ガイド」(2024年に新版を発行しました)が、具体的な選択肢としての在宅療養を考えるきっかけになってくれれば、と思います。ガイドの一つのメッセージは、「自宅で最期を迎えることは、決して特別なことではない」ということです。
もちろんこのガイドには、在宅ケアの専門家や実際にそれを利用したご家族たちの「知恵」が詰まっていますから、そういう意味では高度に「専門的」な内容も含まれています。しかしその多くは何も医療専門職のみができる特別な技術ではなく、ある種の日常的なサポートに近いものだと思います。これは終末期のケアの本質がその人の暮らしを支えることにあることを思えば、ある意味で当たり前のことかもしれません。
在宅療養を阻害する要因はさまざまにありますが、その一つは心理的なバリアです。何度か述べたように、私たちの社会では、ここ数十年の間、病院で亡くなることを「ノーマル」と考えてきたために、在宅で看取ることが過大に考えられがちです。本人が特別強い意志をもっており、ご家族の献身的なサポートがあって初めて成り立つ特別なケア、という印象もまだ根強くあります。
しかし、あらゆる命に限りがあるように、人が亡くなるのは、いわば自然なことです。病院で医師や看護師がいるから、人が最期を迎えられるわけではありません。その意味では、この「ガイド」を読んで関係者が在宅療養のプロセスを具体的にイメージできるようになることで、日本で在宅ケアが当たり前の選択肢の一つとして育つことに少しでもつながれば、と願っています。