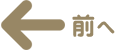がん在宅療養フォーラム 2025 東京
いつでも頼れるがんの情報と相談先 探す、選ぶ、そして活用する
閉会あいさつ
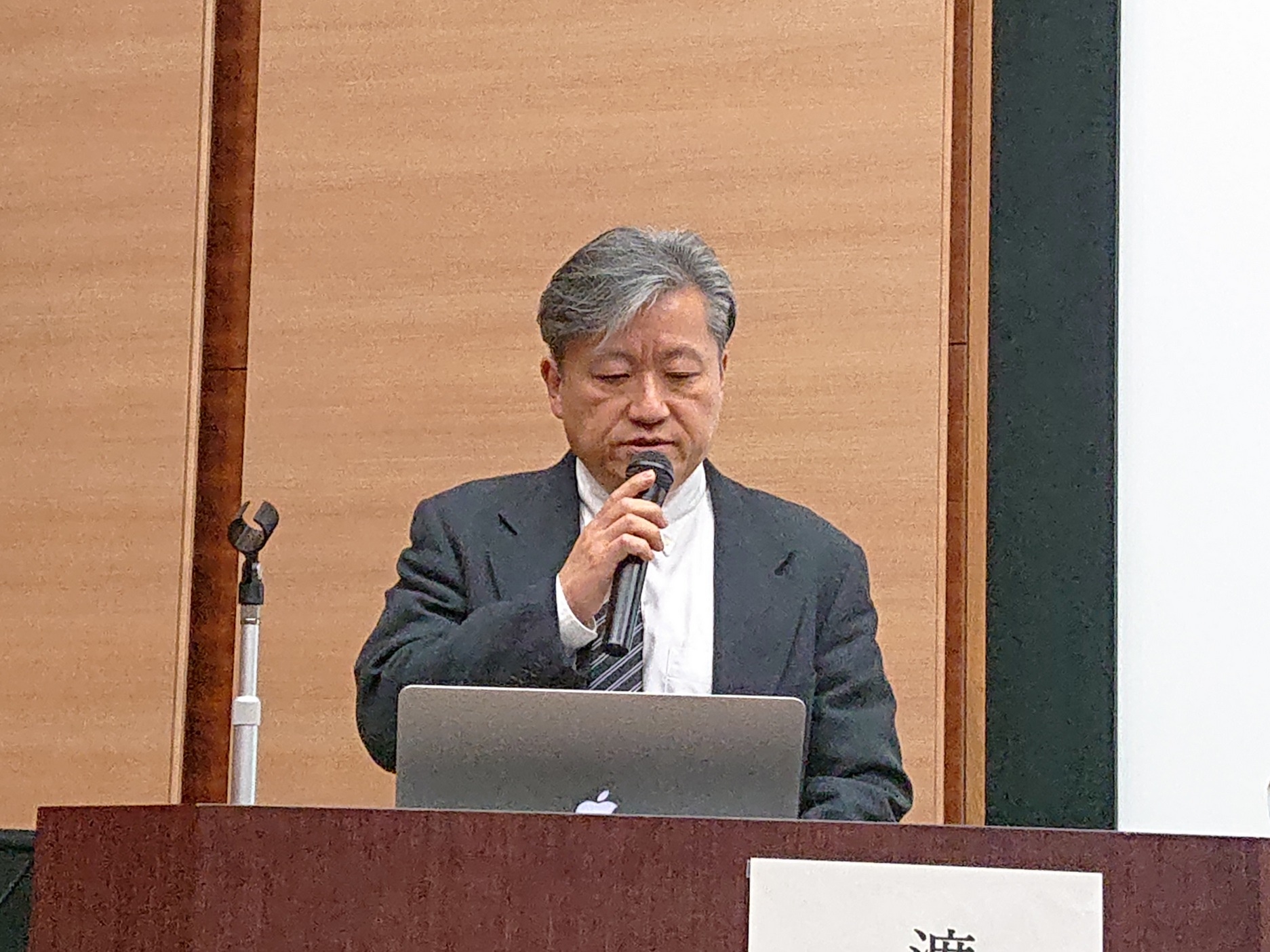
筆宝 義隆さん
皆さん、長らくお付き合いいただきまして、ありがとうございました。千葉県がんセンターの研究所長の筆宝と申します。本財団の評議員会の会長を拝命しておりまして、最後に一言、ごあいさつを申し上げたいと思います。
本日のフォーラムでは、がんの患者さんがある日突然、がんと診断されて、それから情報を集めなくてはいけないということで、急にそういう立場になった時にどうやって情報を集めたらよいか、皆さん、苦労されているというお話がありました。
本日の登壇いただいた先生方はご自身がサバイバーだったり、あるいはご家族の立場や、その患者さんの支援をしている現場の立場だったり、いろいろな現場の問題点や課題などをご紹介いただいたと思います。
また、それに対応する対策として、当財団では「ランタン」というAIを使ったシステムで、うまくそれを技術的に乗り越えられないかと努力をしているところでございます。
もちろん正確な情報を集めるというのは、非常に大事ですが、私も実は医学部を卒業して何年か臨床したのですが、その時に、やはり同じような局面がありまして、「こういう治療法はこういうメリットがあって、デメリットがあります」「こっちの治療法はこういうのがあります」というふうな話をするのですが、「結局、どうしたらよいのですか」「どれがよいのですか」と必ず聞かれました。それで、「あなたが選んでください」と突き放したような言い方をするのが、当時は何となく欧米流の自己決定権の考え方なのかと思ったのですが、結局、患者さんから求められているのは「先生、信頼するから、お薦めを教えてください」ということなのです。ですので、途中から「もしあなたが私の父親だったら、こういうふうなのをお薦めします」と、つまり医学的にこちらのほうがよいか悪いかという話とは別に、個別性を大事にすることにしました。
おそらく、少し今日のお話にもありましたが、「ランタン」の進むべき方向としても、将来はそういうそれぞれの患者さんの人生観や、大事にする価値観など、そういったものも踏まえて、お答えして最適な選択肢を勧められるとよいのかと思います。また、それに「『ランタン』がそう言うならそうだな」というふうに思っていただけるような信頼を獲得していくということが大事かと思いながら、今日、話を拝聴しておりました。
私自身はChatGPTも含めて生成系AIが、非常に技術的に大きな期待も高まっていて、もちろん問題もあると思うのですが、基本的に私は、楽観的でして、技術的な進歩でかなりの問題が乗り越えられるだろうと思っています。一方で、やはり医療というのは、人間対人間のアクティビティーなので、最後は、やはり人間の温かさというか、人間が一枚かんであげるということで、よいものにできたらと思いながら、今日、いろいろな議論を拝聴しておりました。
本日は、多数の方に参加していただいて、非常に私自身も勉強になりましたし、それからご視聴いただいた方も非常にいろいろな問題点、あるいは可能性を感じていただいたのではないかと思います。
全体をオーガナイズしていただいた渡邊先生、それから財団の会長の児玉先生をはじめ、関係の諸先生方、非常にありがとうございました。今後とも財団の支援を、皆さま、よろしくお願いいたします。最後の締めのごあいさつにさせていただきます。ありがとうございました。