ICFは、専門分野や機関を超えた「共通言語」と言われますが、実際の違いはどこにあるのでしょうか。確かに、分類やコードが共通化されていれば便利でしょう。UWDBプロジェクトでは私も、ICFコードを使い倒しました。
しかし、共通言語としてのICFには、ICIDHとは全く違った、共通認識の伝達の「違い」を出せることが分かってきて、それこそ、共通言語の最重点ではないかと考えるようになっています。
障害のある人の障害や「生活機能」の情報を企業や他の支援者等に伝達するときは、十分に注意して、総合的な情報を伝えることが極めて重要です。多くの場合、情報の受け手には障害や疾患についての先入観をもっています。また、情報の発信者からも、知らず知らずのうちに、意図とは全く逆の、非常に強い否定的なメッセージを伝えてしまうことがあります。
ICFを使っていても、実際の説明の中では、相変わらず、障害の「できないこと」を説明し、環境面の影響については、様々な支援の必要性を説明し、個人因子についても、相当の個人の努力を強調したりすることがあります。これでは、ICIDHの概念枠組に、環境因子や個人因子が単に追加されたものに過ぎません。その結果は、他人には、障害によって「できないこと」、プラス、支援の負担、本人の努力の必要性、と、非常に否定的な情報ばかりになってしまいます。
ICFを使うからには、様々な要素の相互作用のダイナミックさを反映させた説明を行うべきです。適切な支援や本人の取組によって様々な問題が解決すること、適切な支援計画によれば、決して支援は負担にならないこと等を明確にする必要があります。その方が、現実を正確に反映した描写になります。実際、障害のある人の多くは、一般就労で職業人として活躍していますし、職場からも評価されています。また、職場での配慮は決して企業にとって過大な負担ではありません。「障害者雇用は難しく、企業の負担」というのは、しばしば机上の空論にすぎません。
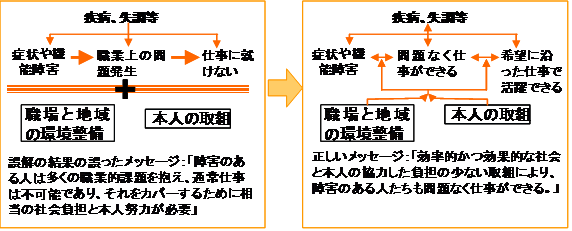
同一人物の描写でも、従来の「障害」中心の描写と、ICFの「生活機能」の描写では全く異なり、雇用を検討する企業側への説明の効果も全く異なってくることを実例で示します。
分断された情報の伝達の場合
「Aさんは重度の知的障害者で、施設の中でも最も手がかかります。みんなと同じ作業は無理で、奇声をいつも発していて、すぐにどこかに行こうとします。年齢も30歳代後半で、体力的にも衰えてきています。雇用管理の負担も大きく、企業では対応は無理だと思います。就労は無理だと思います」
― 支援者自身が十分な就労支援の検討なしに、短絡的な判断をしてしまっています。これでは企業を説得することはできません。
総合的な情報の伝達の場合
「Aさんは、手袋をはめて洗い物をするのが大好きです。施設の職員と一緒に食器洗いや片付けをうまくできます。御社の給食サービスで、きっとお役に立てると思います。制度を活用できますし、お困りの際も、地域でバックアップがあります。ジョブコーチと一緒に実習をさせていただき仕事ぶりをご覧下さい」
分断された情報の伝達の場合
「彼は重症筋無力症患者です。難病に指定されていて、神経伝達の障害があります。外見からは分かり難いのですが障害があり、疲れやすく、突然休むこともあります。力作業は無理です。定期的な通院の必要があり、入院の可能性もあります。障害者雇用率にはカウントされませんが、難病を理解して雇用をお願いします」
― 就業継続には雇用する企業の理解が不可欠であるとの認識から「正直に」説明していますが、意図とは逆の結果になりやすい説明です。
総合的な情報の伝達の場合
「彼は、大学ではデザインを学んで、前職ではホームページ制作も経験しました。御社のニーズに100%応えられる人材です。持病がありますが、適切な休憩があれば問題ないとの医師の手紙もあります。御社にはフレックスタイムもあります。その他ご相談等ありましたら、いつでも無料の支援が提供されます」
分断された情報の伝達の場合
「彼は元気で明るく、仕事にもまじめにコツコツと取り組みます。はめを外した場合には、厳しく注意して下さい。雇っていただければ仕事はどんなものでも結構です。障害の詳しいことはお話できませんので、本人に聞いていただければと思います」
― 就職のために、障害やできないことよりも、本人のアピール点を強調していますが、企業の不安は解消されず、職場配置や配慮等についての企業や本人の取組も保障されません。
総合的な情報の伝達の場合
「彼の能力は職場実習でお分かりと思います。本人もこの仕事がとても気に入っているようです。雇用後も、従業員の方たちとの関係づくりを含めて支援させていただきます。体調面での不安につきましては、月一回の通院ができるようにしていただければ大丈夫だと医師からの意見書もあり、就業・生活支援センターの方でもバックアップします」
ICFは、「プラスを見る」という特徴があると言われます。その意味は、「障害」だけでなく「生活機能」を見るということで、様々な要因を総合的に検討するということが含まれます。上記ケース3のように、「障害」を隠して、よいところだけをアピールするというものとは違います。
むしろ、疾患や障害のマイナスの影響についても直視しつつも、それを職場の悪影響につなげない方法を検討し、一人ひとりの生活イメージを再構築していくという、ケースマネジメントの取組が不可欠であることを強調すべきでしょう。