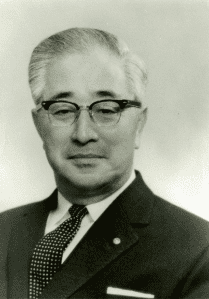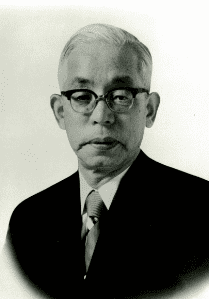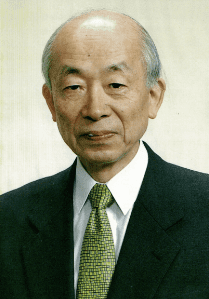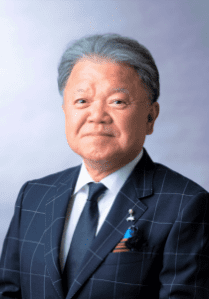名古屋市立大学は昭和25年4月に名古屋女子医科大学と名古屋薬科大学が統合して設立された。医学部のルーツはさらに古く、昭和6年7月に開設された名古屋市立市民病院にさかのぼり、初代耳鼻咽喉科部長は田中芳次郎先生であった。昭和9年9月に第二代部長に松田豪一先生が就任され、以後、松田先生は名古屋市立女子高等医学専門学校教授、名古屋女子医科大学教授を歴任、昭和25年には名古屋市立大学耳鼻咽喉科初代教授に就任され、教室が発展する基礎を築いた。
第二代教授 高須 照男
昭和38年4月~昭和51年5月
第二代教授には、昭和38年4月には高須照男先生が就任された。高須教授は、耳鼻咽喉科領域の感染症に対する化学療法の研究に従事され、昭和40年に第1回国際鼻科学会(Extraordinary Meeting of International Rhinologic Society, Kyoto) を、昭和42年に第19回日本気管食道科学会を会長として主催した。退任後は昭和50年に藤田保健衛生大学耳鼻咽喉科の初代教授に就任され活躍された。
第三代教授 馬場 駿吉
昭和51年6月~平成10年9月
第三代教授は、昭和51年6月に馬場駿吉先生が就任された。馬場教授は、感染やアレルギーなどの生体防御反応を研究し、昭和62年に第88回日本耳鼻咽喉科学会総会で「上気道細菌感染の成立機序とその臨床」と題した宿題報告を発表した。平成3年に第10回ISIAN (10th International Symposium on Infection and Allergy of the Nose)、平成4年に第93回日本耳鼻咽喉科学会、平成7年に日本口腔・咽頭科学会を主催した。また、俳人・美術家としても活躍され、退任後の平成18年より名古屋ボストン美術館館長に就任し活躍された。
第四代教授 村上 信五
平成10年10月~ 平成31年3月
第四代教授には、平成10年10月に村上信五先生が就任された。村上教授は、早くから顔面神経の研究を主題とし、その成果を平成27年に第116回日本耳鼻咽喉科学会総会にて「ウイルス性顔面神経麻痺―病態と後遺症克服のための新たな治療―」と題して宿題報告を発表した。また、聴神経腫瘍の発生と手術治療、耳管開放症のメカニズムと治療についても研究成果をあげた。平成19年に第20回日本口腔咽頭科学会、平成24年に第22回日本耳科学会、平成25年に第25回日本頭蓋底外科学会、平成28年に第117回日本耳鼻咽喉科学会を主催した。また、学会活動としては平成25年より日本顔面神経学会の理事長、平成28年より日本耳科学会の理事長、平成30年より日本耳鼻咽喉科学会副理事長、令和2年より日本耳鼻咽喉科学会理事長として活躍されている。
大学の方では、平成30年より名古屋市東部医療センター院長として、新型コロナウイルス感染症の第一線治療病院として尽力された後、令和3年より名古屋市立大学医学部附属東部医療センター・高次ウイルス感染症センター センター長、また名古屋市立大学医学部特任教授・学長補佐として活躍されている。