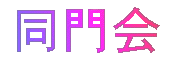芸術のなかの“痛み” 連載3
およねの肩凝り
先日、図書館の女性係長が、以前とはうって変わった笑みをたたえながら訪ねてきた。この人は、それまで頸肩腕症候群の治療のために休暇をとっていたのだ。「よくなってよかったですね」「はい。でも退職することに決めました。辞めると決心したとたん、肩の凝りがさっと引いて、気分が楽になりました」。確かに彼女の肩凝りはなくなっていた。
凝りを英訳すればstiffnessとなる。“肩が凝る”は“My shoulders are stiff.”または“I have stiff shoulders.”だ。ドイツ語でも“Meine Schultern sind steif.”という。
わが国では、夏目漱石の「門」で、肩が“凝る”という言葉がはじめて使われたそうだ。それまでは肩が張るといっていたらしい。
「門」は、すでに安井という婚約者があったおよねと人情の必然に押されて結びついた宗助が、社会の片隅で、お互いに互いだけを頼りとして生きる生活を続ける話だ。罪の重荷を背負いながら、寂しくて、暗い、じめじめした生活を送る。そうこうするうちに、満州にいた安井が帰ってくる。安井に対する背負いきれない負い目から、宗助は動揺する。参禅して、宗助を脅かす安井の影から逃れようとするのだが、それを果たせず、腹痛に悩まされる。
この小説の中で肩凝りが出てくるのは次の部分だ。
《その日ははっきり土に映らない空が、朝から重なり合って、重い寒さが終日人の頭を押さえ付けていた。御米は前の晩にまた寝られないで、休ませ損なった頭を抱えながら、辛抱して働きだしたが、起ったり動いたりするたびに、多少脳に応える苦痛はあっても、比較的明るい外界の刺戟に紛れた為か、凝りと寝ていながら、頭丈が冴えて痛むよりは、却って凌ぎ易かった。兎角して夫を送り出す迄は、しばらくしたら又何時もの様に折り合って来ることと思って我慢していた。所が宗助がいなくなって、自分の義務に一段落が着いたという気の緩みが出ると等しく、濁った天気がそろそろ御米の頭を攻め始めた。空をみると凍っている様であるし、家の中にいると、陰気な障子の紙を透して、寒さが浸み込んでくるかと思はれる位だのに、御米の頭はしきりに熱って来た。仕方がないから、今朝あげた布団を又出してきて、座敷へ延べたまま横になった。夫でも堪えられないので、清に濡手拭を絞らして頭へ乗せた。それが直生温くなるので、枕元に金盥を取り寄せて時々絞り易へた。
2時頃になって、御米は漸っとの事、とろとろと眠ったが、眼が覚めたら額を捲いた濡れ手拭いが殆ど乾くぐらい暖かになっていた。其代わり頭の方は少し楽になった。ただ肩から脊筋へかけて全体に重苦しいような感じが新しく加はった。御米は何でも精を付けなくては毒だといふ考えから、1人で起きて遅い午飯を軽く食べた。
「御気分は如何で御座います」と清が御給仕をしながら、しきりに聞いた。御米は大分可い様だったので、床を上げて貰って、火鉢に倚ったなり、宗助の帰りを待ち受けた。
宗助は例刻に帰ってきた。神田の通りで、門並旗を立てて、もう暮れの売出しを始めた事だの、勧工場で紅白の幕を張って楽隊に景気を付けさしている事だのを話した末、「賑やかだよ。一寸行って御覧。なに電車に乗って行けば訳はない」と勧めた。さうして自分は寒さに腐蝕されたように赤い顔をしていた。
御米はかう宗助から労はられた時、何だか自分の体の悪い事を訴へるに忍びない心持がした。実際又夫程苦しくもなかった。それで何時もの通り何気ない顔をして、夫に着物を着換えさしたり、洋服を畳んだりして夜に入った。
所が9時近くになって、突然宗助に向かって、少し加減が悪いから先へ寝たいと云い出した。今迄平生の通り機嫌よく話していただけに、宗助はこの言葉を聞いて一寸驚いたが、大した事でもないと云う御米の保証に、漸く安心してすぐ休む支度をさせた。
御米が床へ這込ってから、約20分許の間、宗助は耳の傍に鐵瓶の音を聞きながら、静かな夜を丸心の洋燈に照らしていた。
其時座敷で「貴方一寸」と云う御米の苦しさうな声が聞こえたので、我知らず立ち上がった。
座敷へ来てみると、御米は眉を寄せて、右の手で自分の肩を抑えながら、胸迄布団の外へ乗り出していた。宗助は殆ど器械的に、同じ所へ手を出した。さうして御米の抑えている上から、固く骨の角を攫んだ。「もう少し後ろの方」と御米の思う所へ落ち付く迄には、二度も三度も其所此所と位置を易えなければならなかった。指で圧してみると、頸と肩の継ぎ目の少し脊中へ寄った局部が、石のように凝っていた。御米は男の力一杯にそれを抑えて呉れと頼んだ。宗助の額からは汗が煮染み出した。それでも御米の満足する程は力が出なかった。》
ここで医者の往診を仰ぐのだが、医者は首と肩を芥子で湿布四手か、氷嚢で額を冷やし、足を湿布で温めて、小一時間様子をみる。症状が少し治まったのを見とどけてから立ち去り、一回分の頓服を出す。それは睡眠薬であった。およねは翌日の午後までぐっすり寝て、苦しみから解放された。
肩凝りは、普通、僧帽筋に現れる。僧帽筋は下行部、横行部および上行部の3部に分けられる。下行部は上項線、外後頭隆起および項靭帯から起こり、鎖骨の外側1/3に終わる。横行部はC7〜T3(棘突起と棘上靭帯)から起こり、鎖骨の肩峰端、肩峰および肩甲棘の一部に達する。上行部はT3〜T12から起こり、棘三角またはそれに続く肩甲棘に停止する。各部にしこりを伴う発痛点(Trigger point)の好発部位がある。下行部と横行部の発痛点を刺激したときの関連痛は、頭、頸部に現れる。上行部の発痛点刺激による関連痛は、肩から首にかけて現れる。およねの肩凝りは、僧帽筋上行部にあったようだ。
およねは常々不眠症に悩まされていた。当時ごく普通にみられた肺結核症の疑いもあるが、臨床診断は多分、僧帽筋の筋・筋膜痛症候群で、睡眠不足が発症促進因子になっていたように思われる。
「門」は明治の末期、朝日新聞に連載された。その頃の漱石は胃の病に苦しんでいた。「門」を書き終えると直ちに胃腸病院で診察を受け、胃潰瘍を宣告される。そこに2カ月近く入院してから修善寺に転地するが、その2週間後に大吐血して、人事不省に陥る。胃に爆弾をかかえながら「門」を書いていたわけだ。「門」は確かに肩の凝るsolid readingだ。