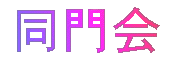芸術のなかの“痛み” 連載2
洗濯女と生理学
19世紀にパリで活躍した芸術家たちにとって、洗濯女は極めて現代的な、トレンディーな主題であった。エドモンド・ゴンクールは、1867年に出版された「マネット・サロモン」の中で「洗濯女と踊り子の二つの職業こそが、当代のもっとも画趣豊かなモデルを芸術家に提供する」と書いている。これを実行に移したのがドガで、洗濯女と踊り子の連作を描いた。その中に欠伸をする女と力を込めてアイロンをかける女との組み合わせを描いたものが4点あって、その一つをパサデナのノートン・サイモン美術館が収蔵している。この絵で特に注目したいのは欠伸をする女の方で、魔術的な光を浴びた疲労と倦怠がよく表現されている。顔の表情や左手の動きから察すると、この女は肩に凝りか痛みをもっているように見える。この女のように力を入れてアイロンをかける仕事を毎日続けていると、慢性筋肉痛に苦しむようになる。凝った筋肉痛にしこりがあって、それをつまむと飛び上がるほど痛むならば、それは病的な状態で、筋・筋膜痛症候群、あるいは頚肩腕症候群と診断されるだろう。
洗濯女で思い出されるのが、エミール・ゾラの小説「居酒屋」L'Assimmoirに出てくるジェルヴェールだ。この小説は多分にドガの洗濯女とかかわりをもっていて、ゾラ自身がドガに向かって「私は自分自身の著作の中であなたの絵のいくつかを描写しただけです」と語ったそうだ。まだ10代のジェルヴェールは、同棲していたランチェと共に南仏の田舎町を逃れ、2人の子どもを連れてパリに上る。ランチェはパリにきてから女遊びを覚え、金づかいが荒くなる。そのあげく女を作って蒸発してしまう。こんな仕打ちに耐え、子どものために洗濯女をしてかいがいしく働くジェルヴェールに感心した板金工のクーポーが彼女に結婚を申し込む。ジェルヴェールはこの申し込みをこばみ続けるのだが、ついに結婚に同意する。2人はまじめに働いて、そこばくの貯えをもつようになる。ジェルヴェールはこの貯えで洗濯屋を開きたいと夢みるのだが、仕事で屋根から転げ落ちたクーポーが大怪我を負って貯えを使い果たしてしまう。これを知った隣人の青年グジェはジェルヴェールに好意を抱いたこともあって、彼女の夢をかなえてやる。この援助で洗濯屋を開店できたジェルヴェールは、よく働いて近所の人々からも信頼され、店は繁盛して3人の女子従業員を雇うまでになる。しかし幸せはそこまでで、やがて不幸がしのびよる。夫のクーポーは回復期の怠け癖から抜け切れず、あれほどきらっていた酒におぼれるようになって、店の稼ぎを酒につぎ込んでしまう。さらに悪いことに彼女を捨てたはずのランチェがもどってきて奇妙な共同生活が始まる。こうして2人ののらくら男と放縦な生活を始めたジェルヴェールは、転落の一途をたどる。その後の筋の運びは残忍で、読むに耐えないほどだ。
ゾラは、当代の自然化学、とりわけ生物学、生理学と深いかかわりをもっていた。1862年には、彼自身がダーウィンの「種の起源」を仏訳した。また大生理学者ベルナール(1865)が書いた「実験医学序説」をよく読んでいた。創作の面では、下層社会の風物や病的な愛欲のもたらす荒廃の医学を探求したゴンクール兄弟(1865)の「ジェルミニー・ラセルトウー」にならって、「テレーズ・ラカン」(1867)を書き、生理学、心理学的な人間の探求を開始する。そして数年、ベルナールの「実験医学序説」から着想を得て「実験小説論」を書く。それは駄目な祖先の血を引いたある人間を、ある環境においたときどうなるかを決定論的な見方でとらえ、生理学的、社会的に探求して、客観的に描くというもので、科学の方法をどこまで押し広げられるか、いかにこれから学ぶかを、原理にまでさかのぼって追及しようとした。
ゾラがベルナールの「実験医学序説」から学んだことの一つに、現実に直面してもたじろがぬ不敵の精神があった。このことが現実を現実として冷酷にとらえる態度につながり、ジェルヴェールの転落を戦慄すべき克明さで最後まで描くもとになるのだが、作品の中で痛みや苦しみを描いた部分についても同様なことがいえる。その一つを紹介しよう。
「若妻がお産をしたのは4月の最後の日だった。午後の4時ごろ、フォーコニエ婦人の店で一組のカーテンにアイロンをかけていると、陣痛がはじまった。彼女は椅子の上で身体をよじりながらもそこに踏み止まり、痛みが少し鎮まるとまたアイロンをかけはじめて、すぐに帰ろうとはしなかった。カーテンは急いでいたので、それを仕上げてしまおうとがんばった。そしてたぶん腹痛にすぎないだろう、腹痛ぐらいで自分勝手なまねはできない、男のワイシャツにかかろうかと話していると、突然真っ青になった。それで身体を二つに折り曲げ、壁にすがりながら仕事場をでて、通りを横切っていった。仲間のひとりがついてゆこうとしたが彼女はそれを断り、そのかわりシャルボール街の産婆の家までいってくれるよう頼んだ。むろん家に火はないが、この痛みは一晩中続くだろうから、家へ帰ったらクーポーの夕食ぐらいはなんとかしよう。それがすんだら衣服を脱ぐなんてことをしないで、ちょっと寝台に横になってみよう。だが階段でひどい激痛に襲われた。そのため階段の途中で座り込まねばならなかった。彼女は声をたてないようにと、両方のこぶしを口におしつけた。声を聞いてあがってきた男たちにそんな姿を見られるのが恥ずかしかったからだ。苦痛が去った。ほっとして、きっと思い違いだったのだと考えながら家の扉口をあけることができた。夕食には羊の脇肉の上部を使ってシチューをこしらえるつもりだった。じゃがいもの皮をむいている間は、まだうまくいっていた。だが、脇肉が小鍋の中で半煮えになった時分に、陣痛がまたおこってびっしょり汗をかいた。大粒の涙で目が見えなくなっても、竈の前で足踏みしながらバターソースをかき回した。たとえお産がはじまっても、クーポーを食べさせないでおく理由にはならない。とうとうシチューは灰をかぶせた火の上でぐつぐつ煮えた。彼女は居間に帰った。食卓の端にひとり分の食器を置くだけのひまはあると思った。だが大急ぎでワインの瓶を下に置かねがならなかった。するともう寝台までたどりつく力がなくなり、床のマットの上にたおれて、そこでお産をした。15分ばかりたって産婆がくると、産婆はその場所で臍の緒を切った。」
マジャンディーに始まり、ベルナールに受け継がれた19世紀のフランス生理学が自然主義文学のよりどころになっていたのは意義深いことだ。