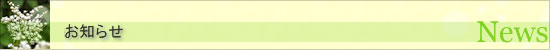同時接種について
庵原 俊昭(国立病院機構三重病院小児科、予防接種感染症委員会委員長)
アメリカ小児科学会(AAP)の同時接種に対する見解は、①生ワクチンと不活化ワクチンを同時に接種しても、単独接種時と免疫原性は変わらず、副反応の増加もないこと、②人の免疫力にはゆとりがあり、一度に多くの抗原が入っても対応する能力があること、③接種するワクチンの数には制限はないが、接種数は柔軟に対応すること、④それぞれのワクチンが必要とする接種回数を接種すること、⑤それぞれのワクチンのブースタ接種は1期初回の最後の接種が終了してから6か月後以降に接種すること、としている。
2010年度末から子宮頸がん等ワクチン推進接種事業が開始され、1歳未満に接種するワクチンの種類が増加した。各ワクチンの接種時期は、副反応と定期接種の期間からBCGは3か月から6か月未満に接種すること、ポリオ麻痺を予防するためには経口ポリオワクチン(OPV)は移行抗体が残存している期間で、接種が許可されている3か月から早い時期に接種すること、百日咳の流行している地区では3か月から早い時期にDPTワクチンを接種すること、侵襲性Hib感染症および侵襲性肺炎球菌感染症は生後6ヶ月以降から増加するため、Hibワクチンと肺炎球菌結合型ワクチン(PCV)を生後6か月までに少なくとも2回、可能ならば3回接種することが求められる。これらの条件を満たすためには単独接種だけでは困難であり、日本小児科学会は同時接種を推奨した。
しかし、2011年3月始めにHibワクチンおよびPCVを含むワクチンの同時接種により、接種後24時間以内に死亡する症例が4例報告されたため、HibワクチンとPCVの接種一時接種差し控えが厚生労働省から通知された。3月8日から24日までの調査で、同時接種を行ったワクチンのエンドトキシン量はあわせても日本の基準を満たすこと、ワクチン後の死亡例6例の死亡原因は、乳幼児突然死症候群3例、誤嚥1例、メタニューモウイルス感染1例、基礎疾患の悪化が疑われるもの1例と、ワクチンとの直接の因果関係が認められなかったこと、HibワクチンおよびPCV10万接種あたりの死亡率はいずれも0.2と、海外の報告率(0.1~1.0/10万接種)と同様であること、などによりHibワクチンおよびPCVを含むワクチンの同時接種の安全性が確認され、同時に死亡者数が急に増加した要因として、2月に入り接種数が急激に増加したこと、子宮頚がん等ワクチン接種推進事業ではワクチンとの因果会計に関係なく有害事象は全数報告であること、などが関与しているとまとめられた。
3月24日に発表された厚生労働省の今後の接種対策は、同時接種と単独接種とがあることを説明し、保護者にどちらの方式で接種するか選択を促すことであり、同時接種を否定したものでない。したがって、医療関係者がワクチン接種を希望して来院した保護者に単独接種を推奨するのは厚生労働省から出された接種対策への過剰対応と判断される。