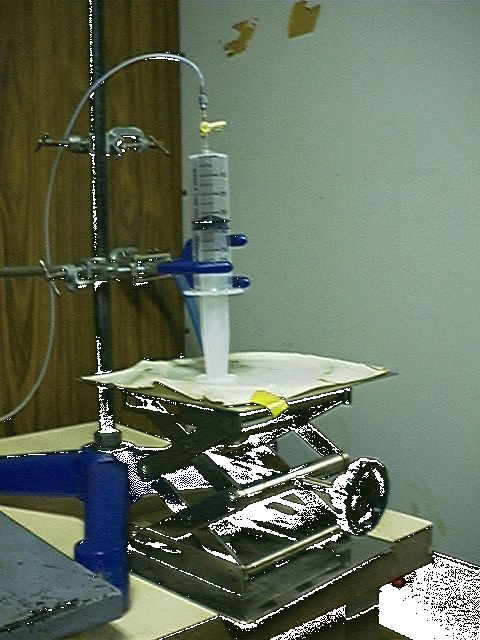(実習3)DNA微量注入による形質転換
担当:古賀誠人
テキスト:前年(石原健)のを改変
injectionのやり方は各研究室、各人によって色々なのでここでは我々が行っている方法を紹介する。
1.原理
a. 概略
線虫への外来DNAの導入は、通常成虫(雌雄同体)の生殖巣にDNA溶液をマイクロイ
ンジェクションすることにより行う。成虫の生殖巣は多核であるので、前後の生殖巣
(gonad)に一度づつマイクロインジェクションすれば、外来DNAを持った形質転換し
たこども(F1)が多数得られる。しかし、こうして得られたF1の内、形質転換したこど
も(F2)を生じるものは約10%程度である。このような形質転換株は、多数の外来DNAが
組換えを起こしてできた直鎖上のextrachromosomal arrayと呼ばれるDNA断片をもつ
。このextrachromosomal arrayは、free duplicationの様に振る舞い半安定的に子孫
に遺伝する(子孫の数〜数十%が形質転換体)。これを安定化するには、UV・γ線を
照射して染色体に挿入されたものを単離する必要がある。(→解説7、三谷)
このほかに、卵母細胞の核に注入したり、生殖巣に一本鎖DNAとともに導入するこ
とにより染色体に直接外来DNAが挿入されたという報告があるが、効率が低いので
あまり行われていない。
b.マーカー
extrachromosomal arrayが、マイクロインジェクションしたDNAが多数連結して構
成されていることを利用して、形質転換のマーカーとなるDNAを同時に注入すること
により形質転換株を見分けられる。
○rol-6(su1006)
優性の変異をもつrol-6(コラーゲン)遺伝子DNAで、これをもつ
線虫は、L3以降Rol表現型を示す。このマーカーは、injectionする線虫に制限がない
ので、injectionによるrescue実験などに使われることが多い。また、このDNAととも
にinjectionするとGFPやlacZの発現が強いらしい。しかし、Rol表現型を示すので、m
aleが交尾しないなどの欠点もある。
○lin-15 (wt)
lin-15(n769ts)は、許容温度(15℃)では野生型だが、制限温度(22
℃以上)ではMuv(Multi Vulva)でUncの表現型を示す。野生型のlin-15遺伝子を含むDN
Aを、許容温度で飼育したlin-15(n769ts)にマイクロインジェクションしたのち、制
限温度で飼育すると形質転換株は野生型を示すのでMuvを示す形質転換していない線
虫と区別できる。染色体に導入するとモザイクにならない。表現型が野生型のためma
leが使えるなどの利点があるが、実体顕微鏡では成虫にならないと区別できない。
○dpy-20 (wt)
野生型のdpy-20遺伝子を含むDNAを、dpy-20にマイクロインジェクシ
ョンしたのち、飼育すると形質転換株は野生型を示す(L2以降で判別可能)。表現型
が野生型のためmaleが使えるなどの利点があるが、染色体に導入しても表現型がモザ
イクになりやすいらしい。また、dpyにinjectionするのが少しやりにくい。
○GFP融合遺伝子(mec7-GFP, ttx3-GFP その他いろいろ)
蛍光装置のついた実体顕微
鏡下で観察し、光る虫を取る。Dominant マーカーなのでホストとなる線虫に制限が
ない。光ること以外特に表現形を出すわけではないので、広く色々な用途に使えると
思われる。ただ、たくさんいれると転写因子をくって表現形がでる場合もあるらしい
。
lacZやGFPなどを用いて発現を調べる際には、用いるマーカーの発現部位がGFPの発
現に影響を与える(たとえばrol-6を使うと下皮で発現するなど)ことがある。
2. 実験装置
ニードルプラー ナリシゲPB-7

b. 顕微鏡 Nikon TE300、微分干渉;Zeiss Axiovert 135、微分干渉、回転ステージ
Zeiss Axiovert 10 (桂研)、Zeiss Axiovert 35 (大島研)、回転ステージ、対物レ
ンズ プランネオフルアール 5x, 40x 微分干渉
c. マニピュレーター
ナリシゲMMN-1, MO-202;Eppendorf 5171, 5246
(大島研) ナリシゲ 三次元マニピュレーターMNー2、ジョイスティック油圧マイ
クロマニピュレーターMO-202、ボールジョイントB8ーB、ステンレスインジェクション
フォルダーHI-6
(桂研) ナリシゲ MJ-2 (それ程精度が高いものでなくてよい。)
(C.elegans news
group(http://www.bio.net:80/hypermail/CELEGANS/9506/0033.html)ではナリシゲMN
-151が薦められていた。)
d. 除震台 実験台の上に硬式テニスボールを置き、そのうえに鉄板をおいて使って
いる(大島研)。
e. その他 マニピュレーターに圧力をかけるための50mlプラスチック注射器、三方
コック、ラボジャッキなど
圧力をかける装置
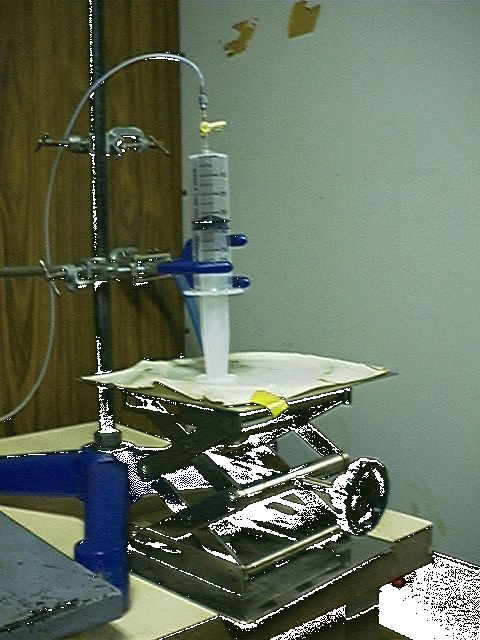
3. 実験方法
a. DNA溶液
プラスミドの精製
DNAの純度が高いことが再現性よく形質転換株を得るためには重要である。
CsCl平衡密度超遠心法やQiagenカラム、Wizardキットなどを用いて精製したものが望
ましい。我々が行っている方法をいくつか紹介する。
A (桂研)
1. プラスミドを保持する大腸菌を3mlのLBにて一晩培養する。
2. Qiagen plasmid mini kitを用いてプラスミドを精製し、プロトコールに従ってイ
ソプロパノール沈殿を行う。
3. 得られたDNAを0.1xTEもしくは滅菌水200μlに溶解した後、15,000rpm5分間遠心
し、上清に1/10容の1M酢酸カリウム(pH7.4)と2容のエタノールを加えエタノール沈殿
を行う。
4. 得られた沈殿を10μlの滅菌水に溶解する。
B (大島研)
1.プラスミドを保持する大腸菌を200mlのLBにて一晩培養する。
2.アルカリ法で粗精製した後Wizardレジン(プロメガ社)で精製。
3. TEで溶出したものを一部0.1μg/μlになるようにTEで薄めて用いる。
C (大島研)
1.プラスミドを保持する大腸菌の一晩培養液1.5mlよりBoiling法(TELT法)によりmini
-prep、50μlのTEに溶解する。
2. Centriflex-MPカートリッジ(エムエスエクノシステムズ社)に1回通し、それをそ
のまま用いる。
b. injection溶液の調製
DNA溶液は、DNAの最終濃度が合計0.1mg/ml程度になるように調製する。マーカーとin
jectionしたいDNAとの量比は1:200から200:1程度まで変えられるので、各々の実験に
よって使い分ける。たとえば、rescue実験の時にはうすく、GFPやlacZの発現実験の
ときは濃いほうが望ましい。
injection溶液中に粒子があるとinjectionする際に針が詰まる原因になるので遠心
または濾過によって取り除く。また、Na+イオンが微量でもあるとうまく形質転換株
が得られないという報告もある。(TE中のNa+イオンが阻害するという説があるが、T
Eのまま問題なくinjectionできている人もいます。)
A(桂研) 20μlのDNA溶液を1xinjection bufferにて作製した後、ミリポアの0.1μm
のフィルター(ウルトラフリーC3)で濾過して用いている。
10xinjection buffer
20 %ポリエチレングリコール, molecular weight 6000-8000
200 mM リン酸カリウム pH 7.5
30 mM クエン酸カリウム pH 7.5
フィルター滅菌
B(大島研) TEに溶解したDNAをSUPREC-01(TAKARA社のアガロースゲルからのDNA回
収用のスピンフィルター)を通したものを用いる。
c.アガロースパッド
線虫を固定するために用いる乾燥したアガロース。
作り方
1. 電気泳動用のアガロースを用いて、2%のアガロース液をつくる。
2. スライドガラスを5枚程度並べ、アルコールで拭く。その上に2%アガロース液
を一滴たらしては素早く、60x24のカバーグラス(IWAKI 2918 cover 24-60)を上から
のせる。この操作を5枚について連続して行う。0.5から1mm厚程度のアガロースの板
がガラスの間にできる。
3. 60x24のカバーグラスをそーっとスライドさせて、アガロースの板を付着させたま
まスライドガラスより外す。アガロースを上にして平たい缶(クッキーやかにせんべ
いの空き缶など)の上に重ならないように並べる。
4. 2、3を繰り返し欲しいだけ作る。
5. 缶ごと乾熱器に入れ100℃で20分乾燥させる。その後、適当な入れ物に入れて保存
しておく。重ねても良い。(半永久的に保存可能)
d.針の作り方
針はニードルプラーで引いた後、先を折ったり、うすいHFで溶かしたりして、先を太
くして使う。もしくは先が太くなるように引いてそのまま用いている。
1.
A(桂研)
芯入りガラス管(ナリシゲGDC-1)をニードルプラーを用いてひく。下側の針を使って
いる。針は以下のようにして引いている。
おもり: おもりなしと軽いおもり1個との間で調節する(おもりが軽いほど大き
い穴になる)。ヒーター: 800〜850目盛りの間で調節する。
針の先端の太さはアガロースパッドにつけたときにでる溶液のでかたで決める。
(針に圧力をかけてアガロースパッドにつけたときに液の水たまりができる程度
。油の中で液が出ているのが見えるようだと太すぎる。)
B(大島研)
芯入り硝子管(ナリシゲGDー1)をニードルプラー(ナリシゲPBー7)で引く。重りは
4個、HeaterADJ No.1を49に固定、No.2を850-750の間で調整し、すーっと伸びて鋭く
尖った針ができるようにする。値が大きいと針の先端が細く長く伸びて鋭く尖らない
ようになる。また値が小さいとお化けのQ太郎の頭にゲゲゲの鬼太郎の妖怪アンテナ
を立てたような寸詰まりの針になる。
2. 50μlのマイクロキャピラリーピペットを炎であぶって細く引き、マイクロキャピ
ラリーを作製する。
3. 2.で作製したマイクロキャピラリーをマウスピースに装着する。DNA溶液中に先端
を入れゆっくり吸って数μl装填する。1.で作製した針の後端からキャピラリーの先
端を差し込む。針の先端付近まで差し込んでもよいし、途中まで、あるいはちょっと
差し込んだだけでもよい。マウスピースをゆっくり吹いてDNA溶液を1-2μl出す。溶
液は毛細管現象によって針の先端まではいって行く。キャピラリーを針の先端まで入
れると泡が入りやすい傾向にあるようだ。針のDNA液中に空気の泡があるとinjection
しにくいので、その時はしばらく針先を下にして泡を除く。
e.injectionの仕方
1. starveしていないプレート(3日か4日前に一匹から数匹程度おとなの虫を6センチ
プレートで飼ってF1を出したものを使うようにしている)からyoung adult(卵を数
個ぐらいもつもの)を大腸菌の塗っていないNGMプレートに移して数分はわせ、まわ
りについている大腸菌などを除く。(育てるプレートや大腸菌を除くためのプレート
が乾きすぎていると、アガロースパッドに線虫をのせたときにすぐ乾いてしまうこと
がある。)
2. アガーロースパッドにinjection用のoilを置き、そこに1.の虫を数匹から15匹程
度やさしく傷つかないように並べる。オイルの量はイエローチップで1滴程度か。好
みによる。5μl程度を薄く虫がぎりぎり浸る程度に塗ると虫が3次元的に暴れられな
いのでアガーパッドに着きやすい。虫の乾きも早い。虫はオイルを絡めたピッカーで
取ると傷つけることが少なくやりやすい。虫は乾燥に弱いのでピッカーに乗せたまま
もたもたしない。オイルを絡めておくと乾燥を防げる。虫をパッドに置くときは押し
つけてはいけない。ピッカーからはみ出ている体の一部をパッドに触れさせると水分
を取られてそこがパッドに着くので、そしたらそっとピッカーを抜く感じで虫を置い
て行く。先の細いピッカーで1匹ずつおいていってもよいし、先の平たいピッカーで
まとめてとってパッド上のオイルの中までもって行き先の細いピッカーでそーっと降
ろして行く感じで置いていくと効率が良い。虫は互いが接触しないように直径7mm
程度の円形に並べる。一旦パッドに着いてしまったら無理に移動させようとすると潰
してしまうことが多いので、そのままにする。
3. アガロースパッドが線虫の水分を吸収して、線虫が乾いてくるのを待つ(数分程
度)。顕微鏡(対物x5)でみて、線虫が動かなくなったらinjectionする。インジェク
ションしている間にもどんどんパッドに水分をとられて乾いていく。体がほとんど透
明で卵が黒々と見えるようになったら、それはもう乾きすぎである。そうなる前に打
ち終わるようにする。
4. 針をマニピュレーターにセットする。50mlの注射器を25ml程度まで押して、針内
の圧力が1.5〜2気圧になるように圧力を調節する。
5. ステージを回転させ、injectionの針の向きと線虫の向きとの角度が30〜45度にな
るようにする。虫と針先を視野の中央に持ってくる。
6. 対物レンズをx40に変え、針先と線虫の生殖巣(gonad)の中央部分とが同じ焦点
面になるように高さを調節する。distal gonadは、核が周囲にあって中央が細胞質(
核が見えない部分)になっている。この細胞質にinjectionする。(下図参照)
7. ステージを動かして線虫を針にさす(針は動かさない)。針が線虫に触れると液
がではじめるので、すばやく針をgonadにさすのがよい。DNA溶液が出ないときは
キムワイプを毛羽立たせた先で、針先を先端に向かって軽くこすり、また虫に射して
みる。折れたか折れないかわからないくらいで、液がどーっと出るというのができれ
ばよい。
8. 液がgonadにはいりgonadが膨らんだことを確認した後、針を抜く。(針内の圧力
をさげてから抜くとgonadの中身が出にくい。)あまりDNA液を多く入れるとgonadが
パンクする。
9. 前後のgonadに一度づつinjectionする。
針が詰まったら、毛羽立たせたキムワイプの先でそーっと液が出るようになるまで
撫でる。針先が太く折れすぎたら針を変える。アガロースパッドの上を少しこすると
、再び液が出るようになることもある。
10. 全ての線虫にinjectionしたら即座に、S basalまたはM9 bufferを100μl程度オ
イルの上から線虫にかける。虫はすぐにアガロースパッドから離れ浮いてくる。えさ
のぬってあるNGMプレートに移す。すぐに移してもよいし、インジェクションが一段
落するまで1時間程度放置しておいてからでもよい。ピッカーで1匹ずつ移しても良い
が、M9とともにペッペとNGMプレートに振り落とすと簡単である。
11. F1が出るまで飼育する。線虫が乾きすぎたり、injectionの時の傷が深いと生き
返らない。
f. 形質転換株の分離
1. injectionしてから3〜4日目に、形質転換体(F1)を一匹づつ新しいプレートに移す
(injectionした線虫1匹あたり0から10匹程度の形質転換したF1が得られる。)
2. その3〜4日後にF2を観察し、F2に形質転換体がいれば、その虫を新しいプレート
に移す。F2に形質転換体がいれば、半安定的に外来DNAを保持する形質転換株として
植え継ぐことができるが、発現がモザイクになっていることに注意する必要がある。
(形質転換したF1の5〜20%から、形質転換したF2が得られる。)
g. 形質転換株が得られない場合
1. injectionした外来DNAの発現が、線虫に毒性を持つ場合がある。この場合は外来
DNAのマーカーとの量比を1:200ぐらいまでうすめてやりなおしてみる。
2. 外来DNAの純度が低い場合も形質転換株が得られないことがある。DNAを取り直し
てやり直してみる。
3. injectionする部屋の温度が高いとうまくいかないという説もあるので、部屋の
温度をできるだけ下げる(少なくとも25℃以下)。
参考文献
Fire, A. (1986) Integrative transformation of C. elegans. EMBO Journal 5:
2673-2680.
Mello C.C., Kramer J.M., Stinchcomb D., and Ambros V. (1992) Efficient gene
transfer in C. elegans: Extrachromosomal maintenance andintegration of
transforming sequences. EMBO Journal 10: 3959-3970
Mello C. and Fire A. (1995) DNA transformation. "Methods in Cell Biology.
Caenorhabditis elegans: Modern Biological Analysis of an Organism." H.F.
Epstein and D.C.Shakes (eds), Academic Press, Inc., San Diego. 48: 451-482
この他に
Ambros Lab Comprehensive Protocol Collection
http://www.dartmouth.edu/artsci/bio/ambros/protocols.html
�