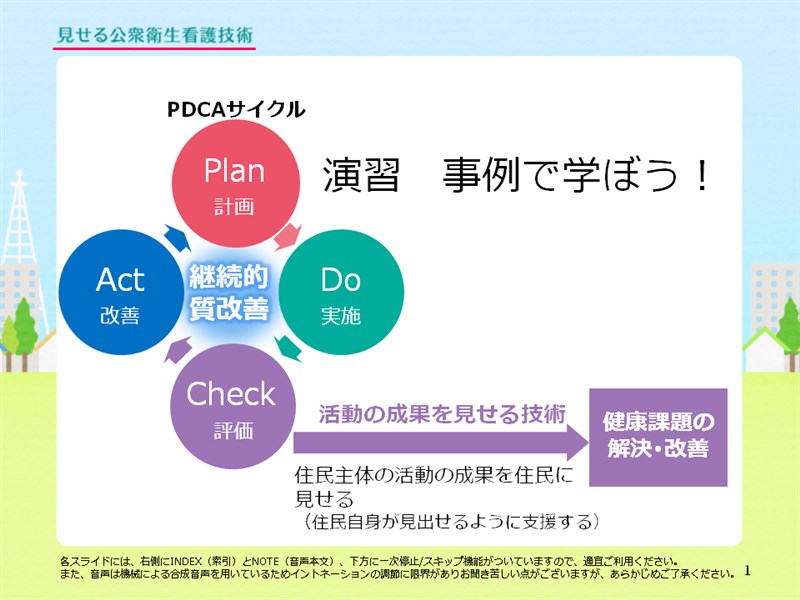【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。
【ノート】
ステップ4はいよいよ評価計画の立案です。
1回目の会議終了後、野の花保健師は、具体的にどのように評価を進めるのか、2回目の会議に向けて評価計画案を作成しようと考えました。ここが専門職としての支援のしどころと意欲的に取り組みました。
会議で出た意見を整理して、わからない部分はワーキングチームのメンバーの先輩保健師に相談しながら、ご覧のようなアウトカム・アウトプット・プロセス・構造を枠組みとする表に評価項目を書き出しました。
さて、ここで考えてみましょう。
あなたなら、これらの評価項目について、どのような評価方法、どのような評価指標を用いて評価を実施しますか?
一時停止して、あなたの考えをワークシートに記入してみましょう。
記入が終わったら、再生ボタンをクリックしてください。
野の花保健師は、 アウトカム評価としては、まず活動の目的である「子育ての孤立化を防ぐ」を何で評価するかを考えました。単純に考えると 「子育てに孤立する親子が減ること」ですが、地域の中で誰が孤立しているかを特定することが難しいことから、これについては、V市が5年毎に市民を対象に実施している健やか親子21の実態調査の一項目 「子育てに対する親の孤立感の程度」の結果を用いて、市全体の動向として見せようと考えました。その調査はタイミングよく、ちょうど今年2015年に実施されたところです。
目標(1)については、今年度の乳幼児健診の問診票の記入内容を用いて、 子育てサロンに参加している人と、そうでない人の、育児仲間のいる割合に違いがあるかを調べてはどうかと考えました。問診票で聞いている項目、ここ半年で子育てサロンに参加した回数と、育児仲間の有無を問うた質問をデータ化し、 子育てサロン参加あり群となし群の、育児仲間がいる人の割合に違いがあるかどうかを調べて、子育てサロン参加が孤立化防止に効果がある可能性を見せたいと考えました。
目標(2)については、 子育てサロン参加者と地域の住民とのつながりが強くなった割合を、 2016年に子育てサロンに新規に参加した人を対象に、初回参加時にベースラインのアンケートを取り、継続して参加した方を対象におよそ1年後にもう一度アンケートをとり、その変化を見てはどうかと考えました。
アウトプットとしては、 事業実施量を表す 実施回数や参加者数の実績をまとめればよいと思いました。
プロセス評価として、 活動の経過については、 活動記録を読み直して、年度単位、あるいは季節単位で、工夫した点や学んだこと、成長したと思うこと、および困った点をピックアップして整理することで、意義や改善点が見えてくると考えました。 子育てサロンのプログラムの妥当性については、 同じく活動記録から、各回の内容や方法が、参加者のニーズと合っていたのかどうかについて、参加者の反応などから読み取り、 子育てサロンへの参加を通しての満足感は、 参加者とスタッフを対象としたアンケート調査で把握できると考えました。
構造評価として、まず、 活動に費やした人員と予算の適切性をあげ、 スタッフや、手遊びなどの協力者の実人員と延べ人数、および収支の状況から分析できると考えました。 活動場所の適切性は、 使用している施設や設備の広さや安全性、アクセスなどの状況から、また 活動の運営体制や関係機関との連携体制の適切性は、 それらの実際の状況から判断していけると考えました。
また、ワーキングチームの1回目の会議では、評価を共同で実施していくことと、それぞれの評価項目については主な担当を決めて進めることに合意していました。そこで、野の花保健師は、それぞれの評価項目について、データ収集や整理、結果のまとめと解釈を行う 主な実施者と時期についても欄を設けました。ただし、2回目の会議にはここは空欄にして、話し合って分担を決めていこうと考えていました。
評価に用いるデータには量的データと質的データがあります。特にプロセス評価では、質的データを活用する場合が多く、この事例でも活動記録の読み取りがそれにあたります。
ひとつの事例を評価するにも、表に示したように、 多くの評価項目に渡って多様な評価方法・評価指標を用いることがお分かりいただけたでしょうか。