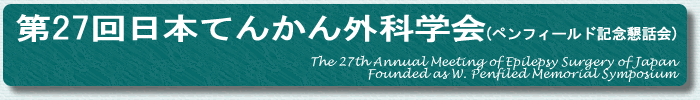
 |
第27回日本てんかん外科学会
会長 星田 徹 |
| わが国の神経疾患の中でてんかんは、日常遭遇することの多い疾患であり、てんかんに対する治療は格段の発展進歩を遂げています。新しい抗けいれん剤の治験が進んでいる一方、てんかんに対する外科治療にも著しい進歩が認められています。日本てんかん外科学会は昭和53年にペンフィールド記念懇話会として発足してから、先達のご尽力の基に今回で第27回を迎えることになりました。奈良県立医科大学脳神経外科
榊寿右教授が本会をお世話させていただいてから丁度10年になります。10年前に主題としました「側頭葉外てんかんの手術と小児てんかんへの展望」は、今なおわれわれが取り組みを続けているテーマであります。この間、MSTの手術法とともに迷走神経刺激術、ガンマナイフ治療、さらに脳深部刺激療法などが新たな治療法として確立しつつあります。 しかしながら、てんかん外科手術に関わる諸問題が解決されているでしょうか。例えば側頭葉てんかんの手術で、標準的な側頭葉前部切除術や選択的扁桃体海馬切除術が行われ、様々な手術アプローチが報告されていますが、側頭葉皮質切除の範囲や海馬切除の長さはいかにして決定しているのでしょうか?どのようにすれば手術を安全に行うことができるのでしょうか?側頭葉以外のてんかん手術ではどうでしょうか?これからてんかん外科をめざす若い先生方のためにも、さまざまな手術方法について各施設のノウハウをもっと論議すべきではないでしょうか?切除中および切除後の皮質脳波はどのように活用しているのでしょうか?その場合、どのような麻酔がてんかん焦点同定に有用になるのでしょうか?てんかん焦点の病理で認められるmicrodysgenesisとはいかなる所見でしょうか?所見としてのコンセンサスは得られているのでしょうか?様々な疑問が残っています。これらの疑問点を少しでも解決して、てんかん外科を始めたばかりやこれから始めようとしている先生方のみならず、十分にてんかん外科の鍛練を積まれた先生方にも、再度新たな眼で振り返っていただくのはいかがでしょうか。そこで第27回日本てんかん外科学会のテーマを「てんかん外科治療法の確立をめざして」に致しました。 今回から本学会は日本定位・機能神経外科学会とともに日本脳神経外科学会総会から分離し、平成16年4月に奈良の地でお世話させていただくことになりました。小生にとりまして大変名誉なことであり、関係各位のご尽力に深謝申し上げます。4月22日の午後からは、第43回日本定位・機能神経外科学会会長の榊寿右教授とともに、合同シンポジウム「脳を刺激する」を企画致しました。わが国における機能的脳神経外科をさらに「刺激」するために、この分野の第一人者に講演をお願いいたしました。前回の第26回てんかん外科学会から開催までの期日が半年間という短い期間でありますが、奈良公園の鹿が皆様のお越しをお待ち申し上げています。先生方に多数ご参加いただき、ご支援とご協力のもとに開催できればと願っております。実り多いてんかん外科学会となりますよう、何卒宜しくお願い致します。 |
|
奈良県立医科大学 脳神経外科
〒634-8522 奈良県橿原市四条町840
TEL:0744-29-8867 FAX:0744-24-1466
E-mail:essj-gakkai@umin.ac.jp