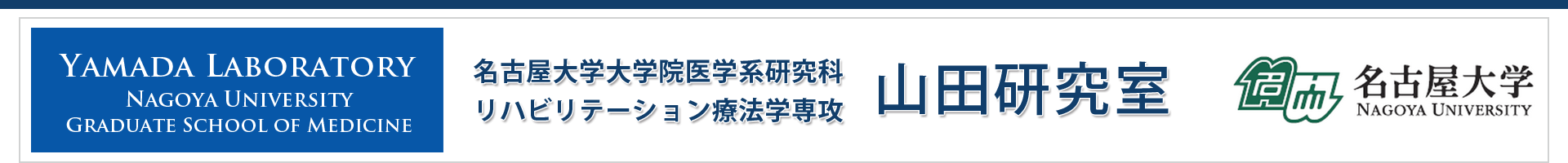アテローム血栓症の重症化予防
軽症脳梗塞再発予防研究
軽症脳梗塞患者におけるライフスタイル介入による再発予防効果‐ランダム化比較試験‐
本邦の非心原性脳梗塞患者は、麻痺が軽度な軽症脳梗塞患者が約6割を占める。この対象は退院後3年で約30%が動脈硬化性疾患を再発しており、さらに再発には身体活動(運動)と減塩が関係する。これまでに研究室で示した結果は、ライフスタイル介入により動脈硬化性疾患の再発が予防できることを強く示唆しているが、これまでに軽症脳梗塞患者を対象としてライフスタイル介入と動脈硬化性疾患の因果関係は検証されていない。そこで我々は非心原性軽症脳梗塞患者を対象に運動・減塩・栄養指導を組み込んだライフスタイル介入を実施し、動脈硬化性疾患の再発抑制効果を検証した。
対象はmodified Rankin Scaleが0-1の軽症脳梗塞患者とした。初回評価後介入群と対照群にランダムに割り付けし、6ヶ月間の運動・塩分を中心とするライフスタイル介入を実施した。研究期間内に70例取り込み、各群に35例ずつ振り分けた。ライフスタイル介入群では身体活動量の増加(6250歩→8422歩、P=0.012)、中等度活動時間の増加(23.2分→31.5分、P=0.033)、塩分摂取量の減少(10.1g→8.8g、P<0.001)を認め、対照群と有意差を認めた。またライフスタイル介入群において収縮期血圧(136mmHg→125mmHg、P<0.001)、HDL-C(54.4mg/dl→62.6mg/dl、P=0.018)に有意な改善を示したが、対照群では変化を示さず、群間の検討では収縮期血圧とHDL-Cに有意差を認めた。その後平均2.9年の追跡調査後、対照群で12名(34.3%:脳卒中再発5名、冠動脈疾患発症7名)、ライフスタイル介入群で1名(2.8%:冠動脈疾患発症)のアウトカム発生を認めた。Kaplan-Meier再発曲線の検討では、ライフスタイル介入群で有意なイベント抑制効果が示された(図)。
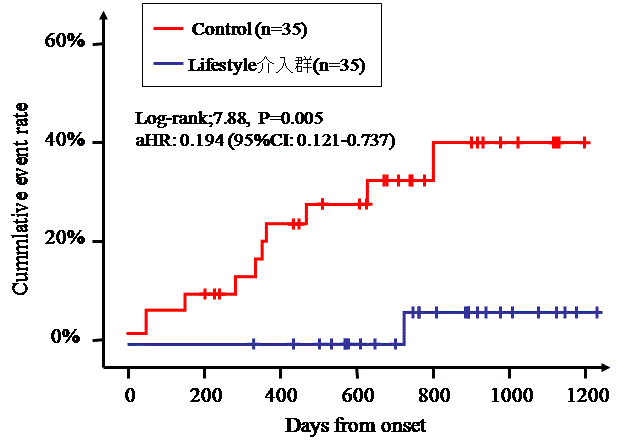
関連文献
- Kono Y, et al. Predictive impact of daily physical activity new vascular events in patients with mild ischemic stroke. International Journal of stroke, 2015; 10: 219-223.
- Kono Y, et al. Secondary prevention of new vascular events with lifestyle intervention in patients with mild ischemic stroke - A Single-Center Randomized Controlled Trial -, Cerebrovascular Diseases, 2013; 36:88-97.
- Kono Y, et al. Recurrence risk after noncardioembolic mild ischemic stroke in a Japanese population, Cerebrovasc Dis, 2011; 31:365-372.
研究助成
- 平成21-22年度挑戦的萌芽研究:課題番号:21650135 (研究者代表者:山田純生)
- 平成23-24年度挑戦的萌芽研究:課題番号:23650322 (研究者代表者:山田純生)
軽症脳梗塞に対するライフスタイル介入は脳血流量を改善するのか
先行調査より、軽症脳梗塞患者の約40%に軽度の認知機能低下(MMSE<27点)が認められた。認知機能低下は脳血流の低下と関連しており、脳血流の低下は脳の血管内皮機能障害の影響が大きく動脈硬化が進展した脳に特徴的である。脳血管内皮機能と末梢血管内皮機能との関連は未だ一致した見解はないが、脳梗塞患者は脳と末梢の血管内皮機能はともに低下していることが報告されている。さらに、末梢の血管内皮機能は運動により改善することが報告されている。
そこで本研究では、脳血流量測定の再現性を確認した後、軽症脳梗塞患者を対象として脳血流量と末梢の血管内皮機能の関連を検討する。次に、6ヶ月間のライフスタイル介入で末梢の血管内皮機能の改善に脳血流量の改善が伴うか否かを検討する。血管内皮機能の指標には、血流依存性血管拡張反応(FMD)を、脳血流量の測定はMR灌流画像のArterial Spin Labeling法を用いる。本研究により、認知機能低下予防における新しい可能性を提示することが期待される。
研究助成
- 平成22-24年度挑戦的萌芽研究:課題番号:22300186 (研究者代表者:山田純生)
軽症脳梗塞患者における無呼吸低呼吸指数および夜間血圧動態の実態調査
本研究室では先行調査にて本邦の非心原性脳梗塞患者の約60%を占める軽症脳梗塞患者の再発率は3年で約30%と高く、また再発とともに身体運動麻痺が重度化する実態を報告した。脳梗塞の再発の危険因子として高血圧は最大の危険因子であるが、最近は24時間にわたる血圧測定が可能になったことで、血圧日内変動に注目が集まっている。夜間血圧は日中に比べ10~20%低下することが明らかとなっているが、この夜間血圧低下が障害されたものでは心血管イベント発症との関連が報告されている。睡眠時無呼吸症候群(SAS)は夜間高血圧の要因のひとつであり、脳卒中発症・再発の独立した危険因子である。SASや夜間血圧動態は脳梗塞患者の再発、予後悪化の危険因子の一つとなっているが、本邦の脳梗塞患者の大部分を占める軽症例ではSASおよび夜間血圧の実態を報告したものはなく、その詳細は明らかとなっていない。そこで本検討では軽症脳梗塞患者における夜間呼吸障害の有病率および夜間血圧動態の実態と、両者の関連性を横断的調査研究により検討した。
インターネットを用いたライフスタイル変容プログラム
脳梗塞や虚血性心疾患は、不適切な生活習慣などに起因する動脈硬化の進行を背景とし、両者はアテローム性動脈硬化疾患として捉えることができる。軽症脳梗塞患者や血行再建術後の虚血性心疾患患者では、日常生活機能は維持されており早期の社会復帰が可能な反面、その後の再発予防のための生活習慣是正が非常に重要である。しかしアテローム性動脈硬化疾患患者を対象とした生活習慣の変容支援を提供する場は少なく、患者本人の自己管理に任せられているところが現状である。
そこで我々はインターネットを用いたオンラインライフスタイル変容プログラムを構築した。このプログラムにより、患者は時間や場所に拘束されずに適切な指導を受けながらライフスタイル変容に取り組むことが可能になる。本プログラムの特徴は、腕時計型脈拍計を用いることで客観的指標に基づいた運動指導を可能とし、行動変容理論に基づく指導プログラムを実施している点が挙げられる。虚血性心疾患11例を対象とした予備検討では8-12週間の介入によって、冠危険因子是正、運動耐容能改善が期待できる結果であった1)。
本プログラムはアテローム性動脈硬化疾患患者のライフスタイル変容を支援することで、その再発予防に寄与できるものであると考えている。今後はさらに対象を拡大し本プログラムの効果検証を実施していきたい。

関連文献
- 萩原悠太 他.脈拍監視装置を用いたオンライン心臓リハビリテーションの運動耐容能改善ならびに冠危険因子是正効果に関する予備的研究, 心臓リハビリテーション, 2013; 18:111-118.