
研究紹介
進行中のプロジェクト
 |
研究紹介 |
疾病予防 遺伝疫学 生活習慣病 ホームに戻る 生活基盤安全 医療事故 環境保健
| I. 生活基盤安全プロジェクト |
| (a)医療事故対策プロジェクト | 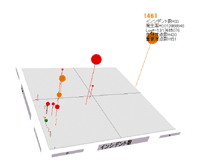 |
|
医療従事者の作業態様を産業衛生学的視点から分析し、医療事故予防対策を研究をしています。共同研究病院 (全国数施設) で業務量調査を行い、インシデントレポートの提出を受け、それぞれの病院での個々の業務のFailure rate (失敗する確率) を算出し、業務のリスク評価に基づき対策を立案するシステムを構築し、看護業務リスク管理ソフトウェアを開発しました。また看護師の労働様態の特性である3交替制勤務に注目し、血糖と認知能力の関連について研究しています。 |
||
| (b)環境保健プロジェクト | ||
|
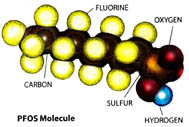 |
|
| (2)長期環境プロジェクト: 京都大学国際融合創造センター創造部門(バイオ電子システム:井出研)をはじめ多くの考古学者との共同研究 縄文人から現代人までの歯のエナメル質を用い、我々の祖先が発育期に曝露した重金属の曝露環境を再現するプロジェクトです。分析には高速加速器Spring 8を用いています。 |
 |
|
| II. 疾病予防 |
(a) 遺伝的感受性素因からの疾病予防 1)脳動脈瘤多発家系における感受性遺伝子検索プロジェクト
京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座(脳神経外科学)との共同
家族性脳動脈瘤の遺伝疫学を行っています。脳動脈瘤は日本人に多く、その破裂によるくも膜下出血の発症は、年間10万人当たり15人、死亡率は約50%です。一方MRIなどの進歩により早期発見、早期治療が可能となりました。しかし、脳ドッグなどを利用した一般人口への検診プログラムは医療経済的には現実的ではありません。我々は脳動脈瘤の原因解明と、予防体制の確立にむけ、感受性遺伝子の研究をしています。
[共同研究機関リスト]2)のう胞腎の新たな遺伝子検索プロジェクト
のう胞腎は、常染色体優性遺伝形式をとる疾患で、現在2つの関与遺伝子が知られていますが、我々の研究している家系では新しい遺伝子の関与が推定されました。この研究は疾患の早期発見と早期介入による腎不全の予後の改善を目指しています。
3)その他の遺伝疫学プロジェクト
小児の低身長に関わる遺伝子の検索、内分泌撹乱物質で注目される家族性甲状腺腫の原因遺伝子の検索などを行っています。
(b) 生活習慣病の予防 京都大学再生医科学研究所生体機能学研究部門(細胞機能調節学分野:永田研)との共同研究 糖尿病は先進国における主要な生活習慣病の一つです。我々の開発したAkita Mouse は、insulin のA7cysteineがtyrosineに変異したマウスであり、proinsulinのfolding 異常により糖尿病を発症します。しかし凝集体などの形成は無く、糖尿病発症メカニズムは不明です。proinsulinのタンパク構造と生体反応を研究しています。[動物モデルからヒト糖尿病の予防への展開の可能性ー新しい糖尿病モデルAkita-mouseを例にー}
(第8回東北動物実験研究会(平成10年1月23日 東北大学医学部))
[糖尿病モデルマウス-秋田マウスの特性]
(第81回関西実験動物研究会 平成 16年 3月 5日(金) 於:京大会館)
Akita Mouse