‘و‚Pڈحپ@گE‹ئڈم‚ج‰ًŒˆ‚·‚ׂ«‰غ‘è‚ئ‚µ‚ؤ‚جڈلٹQ
ICF‚جپuگ¶ٹˆ‹@”\‚ئڈلٹQپv‚جƒtƒŒپ[ƒ€ƒڈپ[ƒN‚إ‚حپAگE‹ئ“Iژ‹“_‚©‚ç‚ف‚½ڈلٹQ‚ئ‚حپA‘½—l‚بگE‹ئڈê–ت‚ة‚¨‚¯‚錒چN–â‘è‚ةٹضکA‚µ‚½ٹˆ“®گ§Œہ‚ئژQ‰ءگ§–ٌ‚ب‚ا‚جچ\‘¢“I‚ب”cˆ¬‚ھ•K—v‚إ‚ ‚éپB
پuڈلٹQژزپv‚ئ‚¢‚¤‚ئپA‚ـ‚¾‘½‚‚جگl‚ھپA“ء’è‚جƒXƒeƒŒƒIƒ^ƒCƒv‚بƒCƒپپ[ƒW‚إ‘¨‚¦‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚±‚ئ‚ھ‘½‚¢‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB‚آ‚ـ‚èپA•پ’ت‚جگl‚ئ‚حˆل‚¤ˆê’è‚جڈگ”‚جگl‚½‚؟‚ھ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤Œë‰ً‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µپAژہچغ‚ة‚حپA“ء’è‚جپuڈلٹQژزپv‚ھ‚¢‚é‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢پB‚±‚ê‚ـ‚إ‚جپuڈلٹQپv‚جچl‚¦•û‚ةژْ‚ي‚ꂸپAگE‹ئ‚ةٹضکA‚·‚é‰غ‘è‚»‚ج‚à‚ج‚ً‚ ‚è‚ج‚ـ‚ـ‚ة‘¨‚¦‚邱‚ئ‚ھپA‘S‚ؤŒں“¢‚جڈo”“_‚إ‚ ‚éپB
—ل‚¦‚خپAچ‘‚ة‚و‚ء‚ؤپA‚ا‚ج”حˆح‚ًڈلٹQ‚ئ‚ف‚ب‚·‚©‚ة‚ح‘ه‚«‚بچ·‚ھ‚ ‚éپB—ل‚¦‚خپA”DگP‚ة”؛‚¤ٹˆ“®گ§Œہ‚âژذ‰ï“Iگ§–ٌپAٹwڈKٹˆ“®‚جگ§ŒہپAکV‰»‚ة”؛‚¤گSگg‹@”\’ل‰؛‚ب‚ا‚حپA‚ي‚ھچ‘‚إ‚حڈلٹQ‚ئ‚ح‚ف‚ب‚³‚ê‚ب‚¢ڈêچ‡‚ھ‘½‚¢‚ھپA‚±‚ê‚ç‚ًڈلٹQ‚ئ”F‚ك‚éچ‘‚à‚ ‚é‚ب‚اپAڈلٹQ”F’è‚ج”حˆح‚حٹeچ‘پE’nˆو‚جگچô‚â‹K”ح‚ب‚ا‚ةˆث‘¶‚µ‚ؤ‚¢‚éپiڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[,1999پjپB‚ـ‚½پAپuڈلٹQژزپv‚ئ‚¢‚¤ˆêŒQ‚جگl‚½‚؟‚ھ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤چl‚¦‚إ‚حپAپuڈلٹQژزپv‚ح“ْڈيگ¶ٹˆ‚إ‚àپAٹwچZگ¶ٹˆ‚إ‚àپAگE‹ئگ¶ٹˆ‚إ‚à“¯‚¶‚–â‘è‚ھ‚ ‚éگl‚½‚؟‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚ھ‚؟‚إ‚ ‚é‚ھپAŒ»ژہ‚ة‚حپAگE‹ئگ¶ٹˆ‚ة‚¨‚¯‚é–â‘è‚حپA“ْڈيگ¶ٹˆڈم‚ج–â‘è‚ئ‚حˆظ‚ب‚邵پAٹwچZگ¶ٹˆ‚ة‚¨‚¯‚é–â‘è‚ئ‚àˆظ‚ب‚é‚ئ‚¢‚¤—ل‚ح‘½‚‚ ‚éپi—ل‚¦‚خپAڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[,2001aپjپB
پuڈلٹQژز‚جŒظ—p‚ج‘£گi“™‚ةٹض‚·‚é–@—¥پv‚إ‚حپAڈلٹQژز‚ًپu‡@گg‘ج–”‚حگ¸گ_‚ةڈلٹQ‚ھ‚ ‚邽‚كپA’·ٹْ‚ة‚ي‚½‚èپA‡AگE‹ئگ¶ٹˆ‚ة‘ٹ“–‚جگ§Œہ‚ًژَ‚¯پA–”‚ح‡BگE‹ئگ¶ٹˆ‚ً‰c‚ق‚±‚ئ‚ھ’ک‚µ‚چ¢“ï‚بژزپv‚ئ‚µ‚ؤپAگE‹ئ‚ئ‚¢‚¤ڈê–ت‚ةڈلٹQ‚ًŒہ’肵‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚ج‚و‚¤‚ةپAژہچغ‚جگE‹ئ“I‚ب‰غ‘è‚ًٹîڈ€‚ة‚·‚ê‚خپAٹب’P‚ةپuگE‹ئ“Iژ‹“_‚©‚ç‚ف‚½ڈلٹQپv‚ج–â‘è‚ح’è‹`‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ةژv‚¦‚éپB‚µ‚©‚µپA‚±‚ê‚ح‚»‚¤’Pڈƒ‚ة‚ح‚¢‚©‚ب‚¢پA‚±‚ê‚ح’·‚¢ٹش‹cک_‚ج‚ ‚ء‚½–â‘è‚إ‚ ‚éپB
Œ»ژہ‚ة‚حپAگg‘ج–”‚حگ¸گ_‚ةڈلٹQ‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚àپAگEڈê‚إ‚ج“Kگط‚ب”z—¶پiڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[,1998aپj‚ة‚و‚ء‚ؤپAگE‹ئگ¶ٹˆ‚ة‘S‚گ§Œہ‚à‚ب‚¢‚µپA–â‘è‚ج‚ب‚¢گl‚½‚؟‚ھ‚¢‚éپBˆê•ûپA’·ٹْ‚ة‚ي‚½‚ء‚ؤڈAگE‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢“ï•a‚جگl‚ھگg‘ج–”‚حگ¸گ_‚جڈلٹQ‚ھ‚ب‚¢‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é—ل‚à‚ ‚éپiڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[,1998bپjپBŒ»چف‚ج’è‹`‚إ‚حپA‚»‚ê‚ً‚»‚ج‚ـ‚ـ‚ة“K—p‚·‚é‚ئپAŒ»ژہ‚ةگE‹ئ“I‚ب–â‘è‚ھ‚ ‚èژx‰‡‚ً•K—v‚ئ‚·‚éگl‚ً”rڈœ‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚à‚ج‚ة‚ب‚è‚©‚ث‚ب‚¢پB‚و‚èگ®چ‡گ«‚ھ‚ ‚èپAŒ»ژہ‚ج–â‘è‚ة“Kگط‚ة‘خ‰‚إ‚«‚éپAپuگE‹ئ“Iژ‹“_‚©‚ç‚ف‚½ڈلٹQپv‚ج‘¨‚¦•û‚ھ•K—v‚إ‚ ‚éپB
‚±‚ج‘و‚Pڈح‚إ‚حپAپuگE‹ئ“Iژ‹“_‚©‚ç‚ف‚½ڈلٹQپv‚ًچl‚¦‚éڈo”“_‚ئ‚µ‚ؤپAپuڈلٹQپv‚جŒ©•û‚»‚êژ©‘ج‚ج‘ه‚«‚ب“]ٹ·‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپBڈ]—ˆپAپuڈلٹQژزپv‚ئ‚¢‚¤ˆêŒQ‚جگl‚ھ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‘O’ٌ‚إپA‚»‚جگl‚½‚؟‚جپuگE‹ئ“I‚ب–â‘èپv‚ًچl‚¦‚é‚ئ‚¢‚¤Œ©•û‚ھ‚³‚ê‚邱‚ئ‚ھ‘½‚©‚ء‚½پB‚آ‚ـ‚èپAپuڈلٹQپv‚ئپuگE‹ئ“I‚ب–â‘èپv‚ح•ت‚ج–â‘è‚ئ‚¢‚¤‘¨‚¦•û‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µپA‰نپX‚حپAŒ©•û‚ً‹t“]‚³‚¹‚ؤپAپuگE‹ئ“I‚ب–â‘è‚»‚êژ©‘ج‚ھڈلٹQپv‚ئ‚¢‚¤‘¨‚¦•û‚ً‘S‚ؤ‚جŒں“¢‚جٹî‘b‚ئ‚·‚éپB‚±‚ج‚و‚¤‚بگ¶ٹˆڈم‚ج‹@”\‚جگ§Œہ‚âگ§–ٌ‚»‚êژ©‘ج‚ًڈلٹQ‚ئ‚·‚éچl‚¦•û‚حŒˆ‚µ‚ؤگV‚µ‚¢‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢پBٹù‚ة1980”N‚جICIDH‚ة‚¨‚¢‚ؤژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپA‚»‚ج‰ü’è‚إ‚ ‚é2001”N‚جICF‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚و‚è–¾ٹm‚ةژ¦‚³‚ꂽپuڈلٹQپv‚جچ‘چغ“I‚بƒRƒ“ƒZƒ“ƒTƒX‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپB‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپA–{ڈح‚إ‚حICF‚جٹT”Oکg‘g‚ة‰ˆ‚ء‚ؤگE‹ئڈم‚ج–â‘è‚ًڈ‡”ش‚ة•ھ—ق‚µپA‚»‚ج–â‘è‚جٹش‚ج‘ٹŒفٹضŒWگ«‚ً•ھگح‚µپA‚³‚ç‚ةپAگE‹ئڈم‚ج–â‘è‚إ‚ح‚ ‚ء‚ؤ‚àپuڈلٹQپv‚ة‚حٹـ‚ك‚ب‚¢‚à‚ج‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚à–¾ٹm‚ة‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
l ‘و‚Pگكپ@گE‹ئڈم‚ج–â‘è‚ج•ھ—قپFپ@ICF‚جڈلٹQ‚ئگ¶ٹˆ‹@”\‚جچ\گ¬—v‘f‚ة‰ˆ‚ء‚ؤپAگE‹ئڈê–ت‚إ‚ج—lپX‚بژ‹“_‚ة‚و‚é–â‘è‚â‰غ‘è‚ً•ھ—ق‚إ‚«‚éپB
l ‘و‚Qگكپ@ڈلٹQپ^گ¶ٹˆ‹@”\‚ج—v‘fٹش‚جٹضŒWگ«پFپ@ژ¾ٹ³‚ئڈلٹQ‚جٹضŒW‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حٹù‚ة‘½‚‚جگM—ٹ‚إ‚«‚éƒfپ[ƒ^‚ھ‚ ‚éˆê•û‚إپA‚»‚ج‘¼‚جپAڈلٹQ‚جˆِ‰ت“™‚ةٹضŒW‚·‚é—v‘fپE—vˆِٹش‚ج‘ٹŒفٹضŒW‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حŒآ•ت‚ج•ھگحژ–—ل‚ھگد‚فڈd‚ث‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é’iٹK‚إ‚ ‚éپB
l ‘و‚Rگكپ@ڈلٹQ‚ئڈلٹQ‚إ‚ب‚¢‚à‚جپFپ@ژ¸‹ئ‚âچ·•ت‚â‘س‚¯‚ب‚ا‚ة‚و‚éˆê”ت“I‚بگE‹ئ“Iچ¢“ïگ«‚â–â‘è‚ئ‹و•ت‚µ‚ؤپAپuگE‹ئ“Iژ‹“_‚©‚ç‚ف‚½ڈلٹQپv‚ً“Kگط‚ة”cˆ¬‚·‚邽‚ك‚ة‚حپAپuŒ’چNڈَ‘شپv‚ئ‚جٹضکA‚ً‘O’ٌ‚ة‚·‚邱‚ئ‚ھ“Kگط‚إ‚ ‚éپB
‘و‚Pگكپ@گE‹ئڈم‚ج–â‘è‚ج•ھ—ق
گE‹ئڈê–ت‚إ‚ج–â‘è‚â‰غ‘è‚ة‚حپAٹض‚ي‚éگl‚ج—§ڈê‚ة‚و‚葽—l‚بژ‹“_‚ھ‚ ‚èپAŒ»چs‚ج‹@”\ڈلٹQ‚ةٹî‚أ‚–¾ٹm‚ب”F’èٹîڈ€‚ة”ن‚ׂؤپA‚ح‚é‚©‚ة•،ژG‚إپA‚ ‚¢‚ـ‚¢‚ب–â‘è”cˆ¬‚ج•û–@‚ة‚ف‚¦‚éپB
—ل‚ئ‚µ‚ؤپAژ‹ٹoڈلٹQ‚ً‚ف‚ؤ‚ف‚و‚¤پBŒ»چs‚ج”F’è‚إ‚حپAژ‹—حƒeƒXƒg‚ةٹî‚أ‚¢‚ؤ–¾ٹm‚ة’è‹`‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤپAژ‹ٹoڈلٹQ‚ة‚و‚éگE‹ئڈê–ت‚إ‚ج–â‘è‚â‰غ‘è‚ة‚حٹب’P‚ة‚ح”cˆ¬‚µ“ï‚¢‘½–ت“I‚بژ‹“_‚â—v‘f‚ھ‚ ‚éپBژہچغ‚جگEڈê‚إ‚ج–â‘è‚ئ‚µ‚ؤ‚حپAŒ©‚و‚¤Œ©‚ـ‚ث‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢‚ئ‚©پAƒeƒLƒXƒg‚âƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹‚ھ“ا‚ك‚ب‚¢‚ئ‚¢‚ء‚½‹Z”\ڈK“¾پAگEڈê“àٹO‚إ‚جˆع“®پA’ت‹خپA‘خگlٹضŒWپAڈ‘—ق‚ج“ا‚فڈ‘‚«پAŒ’چNٹا—‚ب‚ا—lپX‚ب‚±‚ئ‚ة–â‘è‚ھ‚ ‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB‚à‚؟‚ë‚ٌپA‚±‚ê‚ح“¯‚¶گl‚إ‚àگEڈê‚ھ•د‚ي‚ê‚خ‘ه‚«‚•د‚ي‚肤‚éپB‚ ‚é‚¢‚حپAژہچغ‚ةژdژ–‚ةڈA‚¯‚ؤ‚¢‚é‚ب‚ç‚ـ‚¾‚و‚‚ؤپAژdژ–‚ةڈA‚¯‚ب‚¢‚±‚ئ‚ھ–{“–‚ج–â‘è‚ئ‚¢‚¤ژ‹“_‚à‚ ‚邾‚낤پB‚ ‚é‚¢‚حپA‚ح‚èپE‚ ‚ٌ‚ـپEƒ}ƒbƒTپ[ƒW‚جژdژ–‚ب‚ç‚ ‚é‚ھپA‚»‚êˆبٹO‚جژdژ–‚ةڈA‚¯‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ–â‘è‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB‚ ‚é‚¢‚حپAٹé‹ئ‚ج—§ڈê‚©‚ç‚·‚é‚ئپAڈلٹQژزŒظ—p‚جŒoچد“I•‰’S‚ً‰غ‘è‚ئ‚·‚éژ‹“_‚à‚ ‚邾‚낤پB‚ـ‚½پA–{گl‚حپA‚ق‚µ‚ëپA“¯—»‚ج‘ش“x‚ة–â‘è‚â‰غ‘è‚ًٹ´‚¶‚ؤ‚¢‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB
‚±‚ج‚و‚¤‚ب•،ژG‚بژہ‘ش‚ً‚à‚آپAگE‹ئڈê–ت‚إ‚ج–â‘è‚â‰غ‘è‚ً‚ا‚ج‚و‚¤‚ةگ®—‚·‚ê‚خ‚و‚¢‚©پEپEپEپB
‚±‚ê‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAٹù‚ةپAICF‚ة‚و‚ء‚ؤٹî–{“I‚ب‰ًŒˆ‚ھژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپBICF‚ھچ‘چغپu•ھ—قپv‚إ‚ ‚é‚ج‚àپA‚ـ‚³‚ةپA‚±‚ج‚و‚¤‚ب•،ژG‚ب“à—e‚ً•ھ—ق‚·‚邽‚ك‚ج‚à‚ج‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپB
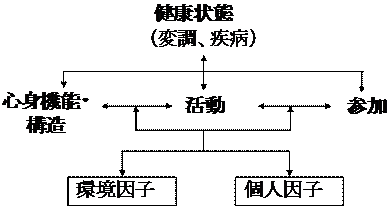 |
ICF‚إ‚حپAپuڈلٹQپv‚ًپAگl‚ھگ¶‚«‚ؤپAگ¶ٹˆپiگE‹ئگ¶ٹˆ‚ًٹـ‚قپj‚µپAگlگ¶‚ً‰c‚ق‚±‚ئپiپپپuگ¶ٹˆ‹@”\پiFunctioning)پvپj‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ج”غ’è“I‚ب‘¤–ت‚ئ‘¨‚¦پA‚»‚ê‚ç‚ًŒف‚¢‚ةٹضکA‚µ‚ ‚¤‚T‚آ‚جچ\گ¬—v‘f[1]‚ة‚و‚葨‚¦‚ؤ‚¢‚éپB
‚»‚ê‚ç‚حپAگ¶ٹˆ‹@”\‚ج‚R‚آ‚ج—v‘f‚إ‚ ‚éپuگSگg‹@”\پvپuٹˆ“®پvپuژQ‰ءپvپA‚»‚µ‚ؤپA‚±‚ê‚ç‚ئ‘ٹŒفچى—p‚·‚é”wŒiˆِژq‚ئ‚µ‚ؤ‚جپuٹآ‹«ˆِژqپv‚ئپuŒآگlˆِژqپv‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚ةپAڈلٹQ‚ج‘O’ٌ‚ئ‚ب‚鉽‚ç‚©‚جپuŒ’چNڈَ‘شپv‚ً‰ء‚¦‚邱‚ئ‚إپAگE‹ئ“Iژ‹“_‚©‚ç‚ف‚½ڈلٹQ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ج—lپX‚بژ‹“_‚حپA‘S‚ؤ‚±‚ج‚U‚آ‚ج—v‘f‚ة•ھ—ق‚إ‚«‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚ب‚¨پAŒ»چفŒں“¢’†‚ج—v‘f‚إ‚ ‚éپuژهٹد“IژںŒ³پv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جچlژ@‚à‚±‚جگك‚إچs‚¤‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‚Pپ@پuگ¶ٹˆ‹@”\پiFunctioningپjپv
ŒآپX‚ج—v‘f‚ة‚آ‚¢‚ؤŒں“¢‚·‚é‘O‚ةپAپuڈلٹQپv‚ئپuگ¶ٹˆ‹@”\پiFunctioning)پvپj‚جٹضŒW‚ة‚آ‚¢‚ؤٹب’P‚ة‚ـ‚ئ‚ك‚éپB
’تڈيژg‚ي‚ê‚éˆس–،‚إ‚جپuڈلٹQپv‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚ة‚حپA‰؟’lٹد‚ھگF”Z‚”½‰f‚³‚ê‚ؤ‚¢‚邽‚كپA‚»‚ج•پ•ص“I‚©‚آ‹qٹد“I‚ب’è‹`‚ح‚»‚ê‚ظ‚اٹب’P‚ب‚±‚ئ‚إ‚ح‚ب‚¢پBڈلٹQ”F’è‚ج”حˆح‚حٹeچ‘پE’nˆو‚جگچô‚â‹K”ح‚ب‚ا‚ةˆث‘¶‚·‚é‚à‚ج‚إپA•پ•صگ«‚ح‚ب‚¢پB‚»‚ê‚إ‚حپAگE‹ئڈم‚إ‚ج–â‘è‚ئ‚حپA‰½‚ًٹîڈ€‚ة‚·‚ê‚خ‚و‚¢‚¾‚낤‚©پB
ICF‚إ‚حپAگlٹش‚ھگ¶‚«‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ةٹض‚·‚éپuگ¶ٹˆ‹@”\پv‚ج•½‹د‚©‚ç‚ج“Œv“I‚ب‚ ‚é’ِ“xˆبڈم‚ج•دˆت‚ًپuڈلٹQپv‚ئ’è‹`‚µ‚ؤ‚¢‚éپBپuگ¶ٹˆ‹@”\پv‚ئ‚حگlٹش‚ھگ¶‚«‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ةٹضŒW‚·‚é‘S‚ؤ‚ً–ش—…‚·‚éگV‚µ‚¢ٹT”O‚إ‚ ‚éپBگEƒٹƒn‚جگ¢ٹE‚إ‚حٹµڈK“I‚ةپuگ¶ٹˆ‚ئگE‹ئپv‚ئ‚¢‚ء‚½‘خ—§ٹT”O‚ھ‚ ‚èپA“ْ–{Œê–َ‚جپuگ¶ٹˆ‹@”\پv‚إ‚حگE‹ئ‹@”\‚ھڈœ‚©‚ê‚éˆَڈغ‚ھ‚ ‚é‚ھپA‚±‚±‚إ‚¢‚¤پuگ¶ٹˆ‹@”\پv‚ة‚حگE‹ئڈê–ت‚إ‚ج‚±‚ئ‚à‚à‚؟‚ë‚ٌ‘S‚ؤٹـ‚ٌ‚إ‚¢‚éپB‚±‚ج‚و‚¤‚بICF‚جپuڈلٹQپv‚جٹT”O‚جگ®—‚حپAڈلٹQ‚ً‚à‚ح‚âƒ}ƒCƒmƒٹƒeƒB‚ج–â‘è‚إ‚ح‚ب‚پA’N‚ة‚إ‚à‚ ‚ؤ‚ح‚ـ‚é•پ•ص“I‚ب–â‘è‚ئ‚µ‚ؤˆت’u•t‚¯‚ؤ‚¢‚éپB‚½‚¾‚µپAپuڈلٹQپv‚ًژ¸‹ئ–â‘èپAگ«چ·•تپAگlژيچ·•ت‚ب‚ا‚ئچ¬“¯‚µ‚ب‚¢‚½‚ك‚ةپA‘و‚Qگك‚إڈq‚ׂé‚و‚¤‚ةپuŒ’چNڈَ‘شپv‚ئ‚جٹضکA‚ًڈًŒڈ‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
‚±‚ج‚و‚¤‚ة•چL‚پuڈلٹQپv‚ج”حˆح‚ً‘¨‚¦‚邱‚ئ‚حپAژذ‰ï’ت”O‚ئ–µڈ‚‚·‚é‚ئ‚¢‚¤–â‘è‚ھ‚ ‚éپBپuڈلٹQپv‚ھ–¢‚¾”غ’è“I‚بƒ‰ƒxƒٹƒ“ƒO‚إ‚ ‚é‚ي‚ھچ‘‚إ‚حپA“ï•a‚جگl‚½‚؟پA‚ـ‚½پAٹwڈKڈلٹQ‚ھ‚ ‚éگl‚½‚؟‚ب‚اپAگE‹ئگ¶ٹˆڈم–¾‚ç‚©‚ة–â‘è‚ھ‚ ‚èپAژx‰‡‚ھ•K—v‚إ‚ ‚é‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پAژ©•ھ‚ًپuڈلٹQژزپv‚ئ‚حŒ©‚ç‚ꂽ‚‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤ڈêچ‡‚ھ‚ ‚éپiڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[,1997; 1998bپjپBپuڈلٹQپv‚ھ‚ ‚éژي‚ج‰؟’lٹد‚ًگF”Z‚”½‰f‚µ‚½ƒ‰ƒxƒٹƒ“ƒO‚إ‚ ‚邱‚ئ‚حژ–ژہ‚إ‚ ‚èپA‚±‚جڈلٹQ‚ج’è‹`‚ھپuڈلٹQژزپv‚ئ‚µ‚ؤ‚جƒ‰ƒxƒٹƒ“ƒO‚ئ‚µ‚ؤژg‚ي‚ê‚é‚ׂ«‚إ‚ب‚¢‚±‚ئ‚âپA–œچ‘‚ة‹¤’ت‚·‚éڈلٹQگچô‚ج‘خڈغ”حˆح‚ًŒˆ‚ك‚é‚à‚ج‚إ‚à‚ب‚¢‚±‚ئ‚ح‚ ‚炽‚ك‚ؤ‹’²‚·‚é•K—v‚ھ‚ ‚낤پiڈعچׂحICF•tک^5‚ًژQڈئپjپB‚±‚ê‚حپA‚ ‚‚ـ‚إ‚àپA–â‘è‚ً‚ ‚è‚ج‚ـ‚ـ‚ة—‰ً‚·‚邽‚ك‚ج’è‹`‚إ‚ ‚éپB
گچô“I‚ب’è‹`‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAŒ»ژہ‚ج–â‘è”cˆ¬‚ً“¥‚ـ‚¦‚ؤ•ت‚ةŒں“¢‚·‚é•K—v‚ھ‚ ‚낤پB•ؤچ‘‚ب‚اپA‹@‰ï‹د“™‚ھ•غڈل‚³‚ê‚é”حˆح‚ئ‚µ‚ؤپuڈلٹQپv‚ً’è‹`‚·‚éچ‘‚إ‚حˆê”ت‚ة‚»‚ج”حˆح‚حچL‚پA”N‹à“™‚جژذ‰ï•غڈل‚ج“K—p”حˆح‚ئ‚µ‚ؤپuڈلٹQپv‚ً’è‹`‚·‚éچ‘‚إ‚ح‚و‚èŒہ’è“I‚إ‚ ‚éپiڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[,2001bپjپB‚ـ‚½پA•ؤچ‘‚إپuƒAƒ‹ƒRپ[ƒ‹‚â–ٍ•¨ˆث‘¶پv“™‚ج”½ژذ‰ï“I‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚حپuڈلٹQپv‚ةٹـ‚ك‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ب‚اپAگچô“I‚بپuڈلٹQپv‚ج”حˆح‚ح•د‰»‚µ‚¤‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
‚Qپ@Œ’چNڈَ‘شپiHealth Conditionپj
‚»‚جگl‚جˆمٹw“I‚بڈَ‘ش‚حپAٹî–{“I‚ةپAپuŒ’چNڈَ‘شپv‚ئ‚µ‚ؤچl‚¦‚ç‚ê‚éپB“TŒ^“I‚ة‚حچ‘چغژ¾•a•ھ—قپiICD-10; WHO, 1994پj‚إ•ھ—ق‚³‚êپAƒRپ[ƒfƒBƒ“ƒO‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ب“à—e‚إ‚ ‚éپB—ل‚¦‚خپA‚»‚جگl‚ج‘®گ«‚ئ‚µ‚ؤ‚جڈلٹQژي—قپE“™‹‰پA’m“IڈلٹQ‚âگ¸گ_ڈلٹQپA—lپX‚ب”’BڈلٹQپA“ï•aپA”DگP‚ب‚ا‚جڈَ‘ش‚حپAپuŒ’چNڈَ‘شپv‚ةˆت’u•t‚¯‚ç‚ê‚éپB
ڈلٹQژي—قپE“™‹‰‚حپAپu‹@”\ڈلٹQپv‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚邱‚ئ‚à‘½‚¢‚ھپAژہچغ‚حپA‹@”\ڈلٹQ‚جڈَ‘ش‚âٹˆ“®گ§Œہ‚ب‚ا‚ً‘½–ت“I‚ة•]‰؟‚µ‚½Œ‹‰ت“¾‚ç‚ê‚éˆêژي‚جگf’f‚إ‚ ‚èپA‘½‚‚ھICD-10‚ة‚à•ھ—ق‚³‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚©‚çپuŒ’چNڈَ‘شپv‚ئ‚µ‚ؤ‚جˆت’u•t‚¯‚à‰آ”\‚إ‚ ‚éپB
ڈ]—ˆپA–{—ˆ‚حˆمٹw“I‚بگf’f–¼‚إ‚ ‚é‚à‚ج‚ًپA‚ ‚¦‚ؤپu‹@”\ڈلٹQپv‚âپuٹˆ“®گ§Œہپv‚ئ‚µ‚ؤˆت’u‚أ‚¯‚و‚¤‚ئ‚µ‚ؤٹT”Oڈم‚جچ¬—گ‚ھ‚ف‚ç‚ê‚éپi—ل‚¦‚خپAپuگ¸گ_’x‘طپvپiŒ’چNڈَ‘شپj‚ئپu’m“IڈلٹQپvپi‹@”\ڈلٹQپjپAپu“ءˆظ“I”’BڈلٹQپvپiŒ’چNڈَ‘شپj‚ئپuٹwڈKڈلٹQپvپiٹˆ“®گ§Œہپj‚ب‚اپB‚ب‚¨پA‚±‚ê‚ç‚حˆê‘خˆê‚جٹضŒW‚إ‚ح‚ب‚پA—ل‚¦‚خپAپu’m“IڈلٹQپvپi‹@”\ڈلٹQپj‚حپuƒ_ƒEƒ“ڈاŒَŒQپvپiŒ’چNڈَ‘شپj‚ة‚و‚ء‚ؤ‚à‹N‚±‚éپBپjپB‚µ‚©‚µپA‚±‚ê‚حپA–{—ˆپA”r‘¼“I‚ب‚ا‚؟‚ç‚©ˆê•û‚ج–¼‘O‚إŒؤ‚خ‚ب‚¯‚ê‚خ‚¢‚¯‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚پAˆمٹw“Iگf’f‚ةٹî‚أ‚‚à‚ج‚حپuŒ’چNڈَ‘شپv‚ةˆت’u‚أ‚¯پA‚»‚ê‚ة‚و‚éڈلٹQ‚ح•ت‚ج–â‘è‚ئ‚µ‚ؤˆµ‚¤‚±‚ئ‚ھ•K—v‚إ‚ ‚éپB
‚Rپ@‹@”\ڈلٹQپiImpairmentپj
پu‹@”\ڈلٹQپv‚ئ‚حپAگ¶—ٹw“IپAگS—ٹw“I‚ب‘¤–ت‚إ‚ ‚éپuگSگg‹@”\پvپA‹y‚رپA‰ً–Uٹw“I‚ب‘¤–ت‚إ‚ ‚éپuگg‘جچ\‘¢پv‚ج‰½‚ç‚©‚جˆظڈي‚â•د’²پA‹@”\’ل‰؛‚ب‚ا‚ج”غ’è“I‚بڈَ‘ش‚ًژ¦‚·‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB
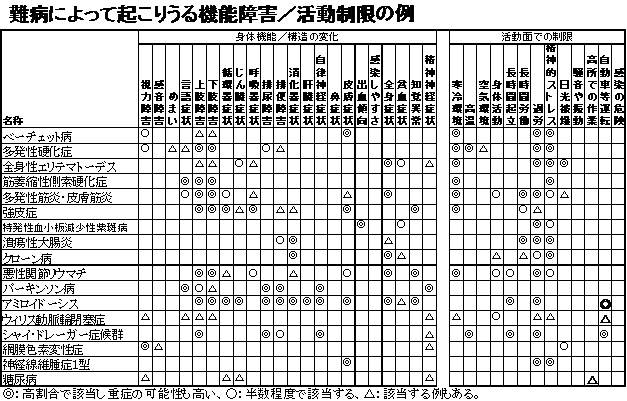 |
‚±‚ê‚حپuŒ’چNڈَ‘شپv‚ئ–§گع‚ةٹضکA‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‘S‚ˆظ‚ب‚郌ƒxƒ‹‚ج–â‘è‚إ‚ ‚éپBگg‘جڈلٹQ”F’èٹîڈ€‚إپAڈلٹQژي—ق‚ً•ھ‚¯‚ؤ‚¢‚éٹد“_‚حپA‚ـ‚³‚ةپA‚±‚ج‹@”\ڈلٹQ‚جٹد“_‚إ‚ ‚éپB‚±‚ê‚ة‚و‚ء‚ؤپA‹@”\ڈلٹQ‚جŒ´ˆِ‚ة‚©‚©‚ي‚炸ڈلٹQ‚ً”cˆ¬‚µ‚ؤ‚¢‚éپB“ï•a‚ج—ل‚ًژ¦‚·‚ئپA‚و‚è–¾ٹm‚ةپAپuŒ’چNڈَ‘شپv‚ئپu‹@”\ڈلٹQپv‚ھ•تپX‚ج–â‘è‚إ‚ ‚邱‚ئ‚âپA‘ٹŒف‚ة“ء—L‚جٹضکAگ«‚ھ‚ ‚邱‚ئ‚ھ—‰ً‚إ‚«‚éپi•\پGڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[,1998b‚و‚èپjپB‚ب‚¨پAŒ»چفپA‚±‚ê‚ç“ï•a‚ج‚ ‚éگl‚½‚؟‚ة‚حپAژهڈلٹQ‚ج”F’è–¼‚إ•ھ—ق‚³‚ê‚éگl‚à‚¢‚é‚ھپA‘½‚‚جڈêچ‡‚±‚جگl‚½‚؟‚ج‹@”\ڈلٹQ‚ح‚»‚ꂾ‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢‚±‚ئ‚ة’چˆس‚ھ•K—v‚إ‚ ‚éپB
‚ـ‚½پAژں‚ج—ل‚ج‚و‚¤‚ةپAŒ»چف‚جڈلٹQ”F’è‚ة‚©‚©‚é‹@”\ڈلٹQ‚جژي—ق‚ھڈ\•ھ‚إ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ب‚اپAڈلٹQ”F’èڈم‚ج–â‘è‚à‚ ‚éپB
l ’m“IڈلٹQپAگ¸گ_ڈلٹQپAٹwڈKڈلٹQپAژ©•آڈاپAچ‚ژں”]‹@”\ڈلٹQ‚ب‚ا‚ة‚حپAŒآ•ت“I‚بگ¸گ_‹@”\پiپپ’چˆسپA‹L‰¯“™پj‚ة‚¨‚¢‚ؤ‹¤’ت‚·‚é‹@”\ڈلٹQ‚à‘½‚¢‚ھپA‚±‚ج‚و‚¤‚بگ¸گ_‹@”\‚ج‹@”\ڈلٹQ‚ج”F’èچ€–ع‚ح‚ب‚¢پB—ل‚¦‚خپA’m“IڈلٹQ‚ب‚ç‚خپu’m“I‹@”\پvپAپu‘S”ت“IگS—ژذ‰ï“I‹@”\پvپAپu‚»‚ج‘¼Œآ•ت“Iگ¸گ_‹@”\پv‚ج‹@”\ڈلٹQ‚ھ‚ ‚邾‚낤‚ھپA‚±‚ê‚ç‚جˆل‚¢‚حچl—¶‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB
l ‚ـ‚½پAپuچ‚ژں”]‹@”\ڈلٹQپv‚ئ‚¢‚¤ڈلٹQ‚ج“ءژꂳ‚àژw“E‚µ‚ؤ‚¨‚«‚½‚¢پB‚»‚جŒ´ˆِ‚ح”]ٹOڈپA”]‘²’†پAƒ‚ƒ„ƒ‚ƒ„•a“™پA—lپX‚إ‚ ‚ء‚ؤپAICD-10‚إ‚حپuچ‚ژں”]‹@”\ڈلٹQپv‚ة‘ٹ“–‚·‚é•ھ—ق‚ھ‚ب‚¢‚ب‚اپA–¾‚ç‚©‚ةپuŒ’چNڈَ‘شپv‚ئ‚µ‚ؤˆت’u•t‚¯‚µ“ï‚¢ڈلٹQ–¼‚إ‚ ‚éپB‚±‚ê‚حپAڈƒگˆ‚ةپu‹@”\ڈلٹQپv‚ة‚و‚ء‚ؤ•ھ—ق‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپA‘½—l‚بژ¾ٹ³‚âڈٹQ‚ة‚و‚éگ¸گ_“I‚بپu‹@”\ڈلٹQپv‚ئ‚µ‚ؤپAICF‚إŒ¾‚¦‚خپA’چˆس‹@”\پA‹L‰¯‹@”\پAچ‚ژں”F’m‹@”\پiپuگ‹چsپv‹@”\پjپAŒ¾Œê‚ةٹض‚·‚éگ¸گ_‹@”\پiژ¸ŒêپjپA•،ژG‚ب‰^“®‚ًڈ‡ڈک—§‚ؤ‚ؤچs‚¤گ¸گ_‹@”\پiژ¸چsپj‚ب‚ا‚ً•ھ—ق‚µ‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µپA‚±‚ج‚و‚¤‚بپu‹@”\ڈلٹQپv‚حŒ»چs‚إ‚حڈلٹQ”F’肳‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB
l پu‹@”\ڈلٹQپv‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚àپAŒ»چs‚جگ§“x‚إڈلٹQ”F’肳‚ê‚ب‚¢ڈêچ‡‚حپA‘¼‚ة‚à‘½‚‚ ‚éپBٹج‘ں‹@”\ڈلٹQپA‚·‚¢‘ں‹@”\ڈلٹQپA”畆‹@”\ڈلٹQپAژ©—¥گ_Œo‹@”\ڈلٹQپA“™پAگE‹ئگ¶ٹˆ‚ة‘ه‚«‚ب‰e‹؟‚ً‹y‚ع‚µ‚¤‚é‹@”\ڈلٹQ‚إپAڈلٹQ”F’肳‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚à‚ج‚حڈ‚ب‚‚ب‚¢‚ج‚إ‚ ‚éپB‚ـ‚½پAگE‹ئگ¶ٹˆ‚ة‚ح‚ ‚ـ‚è‰e‹؟‚µ‚ب‚¢‚ئژv‚ي‚ê‚é‚و‚¤‚بپAڑkٹo‚â–،ٹo‚ج‹@”\ڈلٹQپA‹Cژ؟‚âگ«ٹi‚ج‹@”\ڈلٹQ‚àپAگEژي‚ة‚و‚ء‚ؤ‚ح‘ه‚«‚ب‰e‹؟‚ھ‚ ‚邱‚ئ‚à‚ ‚éپB
‚Sپ@ٹˆ“®گ§ŒہپiActivity limitationپj
پuٹˆ“®گ§Œہپv‚ئ‚حپAŒآگl‚ھٹˆ“®‚ًچs‚¤ژ‚ةگ¶‚¶‚é“‚³‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپBپuٹˆ“®پv‚ئ‚حپA‰غ‘è‚âچsˆ×‚جŒآگl‚ة‚و‚éگ‹چs‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپBICF‚جپuٹˆ“®پv•ھ—ق‚حپA•چL‚پA‚©‚آڈعچׂةگlٹش‚ج‘S‚ؤ‚جٹˆ“®‚ئژQ‰ء‚جچ€–ع‚ً•ھ—ق‚µ‚ؤ‚¨‚èپAپuٹwڈK‚ئ’mژ¯‚ج‰—pپvپAپu’Pˆê‰غ‘è‚جگ‹چsپvپAپu•،گ”‰غ‘è‚جگ‹چsپvپAپu“ْ‰غ‚جگ‹چsپvپAپuƒXƒgƒŒƒX“™‚ض‚ج‘خڈˆپvپAپuƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“پvپAپuژpگ¨‚ج•دٹ·‚â•غژپvپAپu•¨‚ج‰^”ہپEˆع“®پE‘€چىپvپAپu•àچs‚ئˆع“®پvپAپuŒً’ت‹@ٹض‚âژè’i‚ً—ک—p‚µ‚ؤ‚جˆع“®پvپAپuƒZƒ‹ƒtƒPƒAپvپAپu‰ئ’ëگ¶ٹˆپvپAپu‘خگlٹضŒWپv‚ب‚ا‚ج—جˆو‚ًƒJƒoپ[‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
گE‹ئڈم‚جژہچغ‚ج‰غ‘è‚ج‘½‚‚حپA‚±‚جپuٹˆ“®گ§Œہپv‚ئ‚µ‚ؤˆت’u•t‚¯‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚邾‚낤پB‚ب‚؛‚ب‚çپAگE–±گ‹چs‚â–ˆ“ْ‚جگE‹ئگ¶ٹˆ‚جˆغژ‚ج‚½‚ك‚ة‚حپA‚±‚ê‚ç‚ج•K—v‚ب‰غ‘è‚âچsˆ×‚ھ‚إ‚«‚é‚©پA‚إ‚«‚ب‚¢‚©‚ھŒˆ’è“I‚ةڈd—v‚¾‚©‚ç‚إ‚ ‚éپBژہچغ‚جگE‹ئگ¶ٹˆڈم‚ج–â‘è”گ¶‚âگ¶ژYگ«‚ج’ل‰؛‚ئ‚¢‚ء‚½–â‘è‚حپA‘S‚ؤپuٹˆ“®گ§Œہپv‚ةˆت’u•t‚¯‚ç‚ê‚éپB
‚±‚جپuٹˆ“®گ§Œہپv‚حپAژہچغ‚جگE‹ئڈم‚ج–â‘è‚ة’¼Œ‹‚µ‚ؤ‚¨‚èپA‚³‚ç‚ةپAICIDH‚©‚ç20”N‚ًŒo‚ؤپAچׂ©‚¢ٹT”Oگ®—‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é—جˆو‚إ‚à‚ ‚é‚ج‚إپAˆب‰؛‚ةپA“ء‚ةپAپuگE‹ئ“Iژ‹“_‚©‚ç‚جڈلٹQپv‚ج”Fژ¯‚ةژہچغڈم‚ج‰e‹؟‚ً‹y‚ع‚·ڈd—v‚ب“_‚ة‚آ‚¢‚ؤپAگ®—‚µ‚ؤ‚¨‚پB
پi‚PپjŒ´ˆِ‚ة‚و‚ç‚ب‚¢–â‘è”cˆ¬
پuٹˆ“®گ§Œہپv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚àپA‘¼‚جپu‹@”\ڈلٹQپv‚ئ“¯‚¶‚پAŒ´ˆِ‚ة‚و‚炸‚ة”cˆ¬‚³‚ê‚é‚ׂ«‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB
‰نپX‚ج’²چ¸پiژ‘—؟ƒVƒٹپ[ƒYNo.27 ‘و‚Rڈحپj‚إ‚à–¾‚ç‚©‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚إ‚ ‚é‚ھپA’®ٹoڈلٹQ‚ج‚ ‚éگl‚حپAپuƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“پvڈلٹQ‚خ‚©‚è‚ھ’چ–ع‚³‚ê‚é‚ھپAژہ‚حپAپuٹwڈK‚ئ’mژ¯‚ج‰—pپvپAپu’Pˆê‰غ‘è‚جگ‹چsپvپAپu•،گ”‰غ‘è‚جگ‹چsپvپAپu“ْ‰غ‚جگ‹چsپvپAپuƒXƒgƒŒƒX“™‚ض‚ج‘خڈˆپvپAپu‘خگlٹضŒWپv‚ب‚ا‚جٹˆ“®گ§Œہ‚ھ‹N‚±‚肤‚éپiچى‹ئژwژ¦‚ھŒû“ھ‚¾‚¯‚إ‚ب‚³‚ê‚éڈêچ‡‚ب‚ا‚ج‚±‚ئ‚ًچl‚¦‚é‚ئ‚و‚¢پBپjپBژ‹ٹoڈلٹQ‚ج‚ ‚éگl‚ة‚àپAپuٹwڈK‚ئ’mژ¯‚ج‰—pپvپAپuƒXƒgƒŒƒX“™‚ض‚ج‘خڈˆپvپAپu•¨‚ج‰^”ہپEˆع“®پE‘€چىپvپAپu•àچs‚ئˆع“®پvپAپuŒً’ت‹@ٹض‚âژè’i‚ً—ک—p‚µ‚ؤ‚جˆع“®پvپAپuƒZƒ‹ƒtƒPƒAپvپAپu‘خگlٹضŒWپv‚ب‚ا‘½—l‚بٹˆ“®گ§Œہ‚ھ‚ ‚肤‚éپB
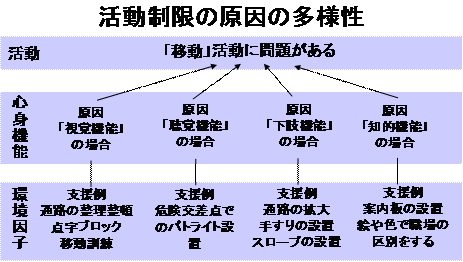 |
پuٹˆ“®گ§Œہپv‚حپAگE‹ئگ‹چsڈم‚جژہچغ‚ج–â‘è‚ً•\‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚©‚çپAپuگE‹ئ“Iژ‹“_‚©‚ç‚ف‚½ڈلٹQپv‚ة‚¨‚¢‚ؤڈd—v‚ب—v‘f‚إ‚ ‚é‚ھپAڈم‹L‚ة‚àژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ةپA“¯‚¶پuٹˆ“®گ§Œہپv‚ھ‘½—l‚بŒ´ˆِ‚©‚ç‚ھگ¶‚¶‚ؤ‚‚邱‚ئ‚ة’چˆس‚ھ•K—v‚إ‚ ‚éپB—ل‚¦‚خپAپuˆع“®پvٹˆ“®گ§Œہ‚ھ‚ ‚éگl‚ئ‚¢‚¤‚ئپA‘S‚Œ´ˆِ‚ح–â‚ي‚ب‚¢‚ج‚إپA‰؛ژˆڈلٹQ‚ح‚à‚؟‚ë‚ٌپAژ‹ٹoڈلٹQپA’®ٹoڈلٹQپA’m“IڈلٹQپA“™پA‘½‚‚جڈلٹQ‚ھ‚»‚ê‚ةٹY“–‚µ‚¤‚éپB‚µ‚©‚µپA“¯‚¶پuˆع“®پvڈم‚جٹˆ“®گ§Œہ‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚àپA‚»‚جŒ´ˆِ‚ة‚و‚ء‚ؤپAگ«ژ؟‚àپAژx‰‡‚جژd•û‚àˆظ‚ب‚肤‚éپB‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپAپuٹˆ“®گ§Œہپv‚ج—v‘f‚¾‚¯‚إپuگE‹ئ“Iژ‹“_‚©‚ç‚ف‚½ڈلٹQپv‚ً‘¨‚¦‚邱‚ئ‚ح‚إ‚«‚¸پA‚ ‚‚ـ‚إ‚àپA‘¼‚ج—v‘f‚ئ‚جٹضکA‚إ‘¨‚¦‚邱‚ئ‚ھڈd—v‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB
پuٹwڈKڈلٹQپv‚ج–â‘è‚ج‘¨‚¦•û‚ج”“W‚حپAپuٹˆ“®گ§Œہپv‚ً’†گS‚ئ‚µ‚ؤ‘¼‚ج—v‘f‚ئ‚جٹضکAگ«‚ھ•K—v‚ئ‚ب‚邱‚ئ‚ج‚و‚¢—ل‚إ‚ ‚éپB‚±‚جٹT”O‚حپA‚à‚ئ‚à‚ئپA’m“IڈلٹQˆبٹO‚إ‰½‚ç‚©‚جگ¸گ_“I‚ب—vˆِ‚ة‚و‚èپAژه‚ةٹwچZ‹³ˆç‚جڈê‚إ‚جپuٹwڈKپv‚جٹˆ“®گ§Œہ‚ھ‚ ‚éگlپA‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µپA‚»‚ج‹ï‘ج“I‚ب“à—e‚ًŒں“¢‚µ‚ؤ‚¢‚‚ة‚آ‚êپAŒ´ˆِ‚ئ‚µ‚ؤ‚جپuŒ’چNڈَ‘شپv‚ئ‚µ‚ؤپAپu’چˆسŒ‡ٹב½“®گ«ڈلٹQپiADHD)پvپAپuژ©•آڈاپvپAپuٹwڈK”\—ح‚ج“ءˆظ“I”’BڈلٹQپv‚ب‚ا‚ھٹـ‚ـ‚ê‚邱‚ئ‚ھ–¾‚ç‚©‚ئ‚ب‚ء‚½‚èپA’è‹`ڈمپAژ‹ٹoڈلٹQپA’®ٹoڈلٹQپA’m“IڈلٹQ“™‚ة‚و‚é‚à‚ج‚ًڈœ‚•K—v‚ھگ¶‚¶‚½‚è‚ئ‚¢‚¤پu‹@”\ڈلٹQپvڈم‚جٹضŒWگ«‚ً–¾ٹm‚ة‚·‚é•K—v‚ھگ¶‚¶‚ؤ‚¢‚éپiڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[پA2004پjپB
پi‚Qپj‹@”\ڈلٹQ‚ئٹˆ“®گ§Œہ‚ج‹و•ت
گSگg‹@”\‚ح‚ ‚‚ـ‚إ‚àپAگ¶—پEگS—“I‹@”\پi—لپFژ‹ٹoپj‚ًˆس–،‚µپAٹˆ“®“à—eپi—لپFŒ©‚邱‚ئپA“ا‚ق‚±‚ئ‚ب‚اپj‚ئ‚ح‹و•ت‚·‚邱‚ئ‚ھڈd—v‚إ‚ ‚éپBژdژ–‚ج—vŒڈ‚ًŒˆ‚ك‚éڈêچ‡‚ب‚اپA’¼گعپAگSگg‹@”\‚ةٹض‚·‚é—vŒڈ‚ًژw’è‚·‚邱‚ئ‚ح‹ة—ح”ً‚¯پAژdژ–‚ج‚â‚è•û‚ح–â‚ي‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‘O’ٌ‚إگE–±ڈمچs‚¤•K—v‚ھ‚ ‚éٹˆ“®‚ًژw’è‚·‚é‚و‚¤‚ة‚·‚ê‚خپAڈلٹQ‚ج‚ ‚éگl‚ج–â‘è‚ج‘¨‚¦•û‚ھژہچغ‚ة‘ه‚«‚•د‚ي‚肤‚éپB
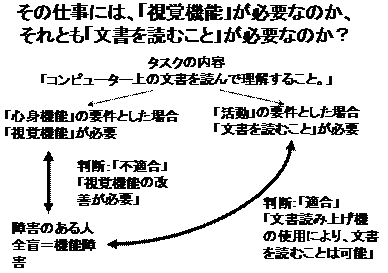 |
—ل‚¦‚خپAپuژ‹ٹo‚ھ•K—v‚إ‚ ‚éپv‚ئ‚¢‚¤گSگg‹@”\—vŒڈ‚إ‚ح‚ب‚پAپuƒRƒ“ƒsƒ…پ[ƒ^پ[‚جƒfƒBƒXƒvƒŒƒC‚ج“à—e‚ً“ا‚قپv‚±‚ئ‚ًٹˆ“®—vŒڈ‚ئ‚µ‚ؤŒں“¢‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپAژ‹ٹoڈلٹQ‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚àپAٹg‘ه“اڈ‘ٹي‚≹گ؛“ا‚فڈم‚°‹@‚ة‚و‚ء‚ؤپA—vŒڈ‚ً–‚½‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚éپB‚±‚جڈêچ‡پAپu‹@”\ڈلٹQپv‚إ‚ ‚éپuژ‹ٹo‹@”\ڈلٹQپv‚ح‚ ‚ء‚ؤ‚àپAپuƒRƒ“ƒsƒ…پ[ƒ^پ[‚جƒfƒBƒXƒvƒŒƒC‚ج“à—e‚ً“ا‚قپv‚ئ‚¢‚¤پuٹˆ“®گ§Œہپv‚ح‚ب‚¢‚ج‚إ‚ ‚éپB
پi‚Rپjٹˆ“®گ§Œہ‚ج‚Q‚آ‚ج‘¤–تپFپu”\—حپv‚ئپuژہچsڈَ‹µپv
‘Oچ€‚إپAژx‰‡‹@ٹي‚ًژg‚¤‚±‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپuٹˆ“®گ§Œہپv‚ھ‚ب‚‚ب‚ء‚½—ل‚ًژ¦‚µ‚½‚ھپA‚±‚ê‚ة‚آ‚¢‚ؤڈd—v‚بک_“_‚ھ‚ ‚éپB‚»‚ê‚حپAپuٹˆ“®گ§Œہپv‚ة‚حپAژx‰‡‹@ٹي‚ب‚ا‚ج“±“ü‚ة‚و‚ء‚ؤ•د‚ي‚ç‚ب‚¢پu”\—حپv‚ئپA‚±‚ج‚و‚¤‚ةژہچغ‚جڈَ‹µ‚ً–â‘è‚ة‚·‚éپuژہچsڈَ‹µپv‚ئ‚¢‚¤‹و•ت‚·‚ׂ«‚Q‘¤–ت‚ھ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB
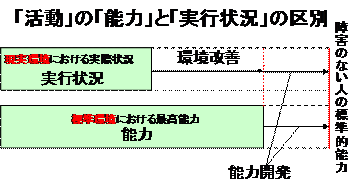 |
پu”\—حپv‚ئ‚حپAٹآ‹«ڈًŒڈ‚ًˆê’è‚ة‚µ‚½‚¤‚¦‚إ•]‰؟‚â‘ھ’è‚ًچs‚¤‚à‚ج‚إ‚ ‚èپAٹآ‹«‚©‚ç“ئ—§‚µ‚½Œآگl‚ج”\—ح‚ًژ¦‚·‚à‚ج‚إ‚ ‚éپBƒڈپ[ƒNƒTƒ“ƒvƒ‹–@‚ب‚ا‚ة‚و‚é•]‰؟Œ‹‰ت‚حپA‚±‚ê‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚éپBˆê•ûپAپuژہچsڈَ‹µپv‚حپAڈل•ا‚â‘£گiˆِژq‚ھ‚ ‚éژہچغ‚جگEڈê‚إ‚جڈَ‹µ‚ًژ¦‚·‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚±‚ج—¼ژز‚ح‘ه‚«‚ˆظ‚ب‚é‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚é‚ج‚إپA–â‘è‚ً”cˆ¬‚·‚éچغ‚ة‚حپA‚±‚ج—¼ژز‚جٹT”O‚ً‹و•ت‚·‚é•K—v‚ھ‚ ‚éپB‚آ‚ـ‚èپA‚ ‚éگl‚جپu”\—حپv‚ً‚¢‚¤ڈêچ‡‚ة‚حپA‚»‚ê‚ھˆê’è‚ج•Wڈ€‰»‚³‚ꂽٹآ‹«‚إچs‚ي‚ꂽ•]‰؟‚ب‚ج‚©پA•]‰؟‚جچغ‚ج‹ï‘ج“I‚بٹآ‹«‚جڈَ‹µ‚ح‚ا‚¤‚¾‚ء‚½‚©پA‚ً”cˆ¬‚µ‚ؤ‚¨‚•K—v‚ھ‚ ‚éپB
‚ـ‚½پAپu”\—حپv‚ئپuژہچsڈَ‹µپv‚ج‹و•ت‚ھ‚ ‚¢‚ـ‚¢‚إ‚ ‚é‚ئپAژv‚¢‚ھ‚¯‚¸”\—ح”»’è‚ًچs‚¤‹@ٹض‚ھپAڈAکJژx‰‡‚جڈل•ا‚»‚ج‚à‚ج‚ة‚ب‚éٹ댯گ«‚ھ‚ ‚邱‚ئ‚àژw“E‚µ‚ؤ‚¨‚«‚½‚¢پBڈلٹQژزŒظ—p‚جŒoŒ±‚ھ–L•x‚إ‘½—l‚ب‘£گiˆِژq‚ھ‚ ‚邽‚كپA‘½ڈ‚ج‹@”\ڈلٹQ‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚àپAپuژہچsڈَ‹µپv‚ئ‚µ‚ؤ‚جپuٹˆ“®گ§Œہپv‚ح‹N‚±‚è‚ة‚‚¢‚ئ‚¢‚¤گEڈê‚ھچإ‹ك‘‚¦‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚éپB‚µ‚©‚µپA•]‰؟‹@ٹض‚ھ‚©‚ب‚èگج‚جژ–‹ئڈٹ‚جٹآ‹«گ…ڈ€‚ً‘O’ٌ‚ةپu”\—حپv•]‰؟‚ًچs‚¤‚ئپAژdژ–ڈم‚جٹˆ“®گ§Œہ‚حŒ»ژہ‚و‚è‚à‘½‚‚جٹˆ“®گ§Œہ‚ھ‚ ‚é‚à‚ج‚ئ—\‘z‚³‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢پAڈAگE‚ح–³—‚ئ‚¢‚¤Œë‚ء‚½”»’è‚ً‰؛‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
ژہ‚حپA‚±‚جپu”\—حپv‚ئپuژہچsڈَ‹µپv‚ج‹و•ت‚ة‚حپA•Wڈ€ٹآ‹«‚ج’è‹`‚ئ‚¢‚¤پA‚و‚è‘ه‚«‚ب–â‘è‚ھ”wŒم‚ة‚ ‚邽‚كپAڈعچׂة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‘و‚Qڈح‚إ‚³‚ç‚ةگ®—‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
پi‚SپjگEژي‚â“‚«•û‚ج‘½—lگ«‚ج‰e‹؟
گE‹ئڈê–ت‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAگEژي‚â“‚«•û‚ة‚و‚ء‚ؤپA–â‘è‚ھ‹N‚±‚ء‚½‚è‹N‚±‚ç‚ب‚©‚ء‚½‚è‚·‚éپB—ل‚¦‚خپAژش‚¢‚·‚ًژg‚ء‚ؤ‚¢‚éگl‚ھپAˆê”ت‹خ–±‚ً‚µ‚و‚¤‚ئ‚µ‚½ژ‚ة‚ح’ت‹خ‚ج–â‘è‚ھ‚ ‚ء‚½‚ھپAچف‘î‹خ–±‚¾‚ئ’ت‹خ‚ج–â‘è‚ھ‚ب‚‚ب‚ء‚½پB‘S–س‚جگl‚إ‘½‚‚جژdژ–‚ھ‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½‚ھپA“dکbƒIƒyƒŒپ[ƒ^پ[‚إ‚ح–â‘è‚ب‚ژdژ–‚ھ‚إ‚«‚½پA‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB‚±‚ê‚ًپA‚ا‚¤چl‚¦‚é‚©پB
ICF‚إ‚حپAپuڈلٹQپv‚ًŒآگl‚ج‘®گ«‚ئ‚µ‚ؤ‚إ‚ح‚ب‚پA‚ ‚è‚ج‚ـ‚ـ‚ج–â‘è”cˆ¬‚ًچs‚¤‚¾‚¯‚ب‚ج‚إپAگEژي‚â“‚«•û‚ھ•د‚ي‚ê‚خٹˆ“®گ§Œہ‚ح•د‚ي‚ء‚ؤ“–‘R‚إ‚ ‚éپB‚»‚جگEژيپA‚»‚ج“‚«•û‚إپA‚»‚à‚»‚à“–ٹY—جˆو‚جپuٹˆ“®پv‚ھ‚ب‚©‚ء‚½‚è—vŒڈƒŒƒxƒ‹‚ھ’ل‚©‚ء‚½‚è‚·‚éڈêچ‡‚ة‚حپAپuژہچsڈَ‹µپv‚ئ‚µ‚ؤ‚جپuٹˆ“®گ§Œہپv‚حپu”ٌٹY“–پv‚ئ‚µ‚ؤˆµ‚¤پA‚»‚ꂾ‚¯‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB
‚±‚ج‚و‚¤‚ةپAپuٹˆ“®گ§Œہپv‚ھگEژي‚â“‚«•û‚ة‰e‹؟‚ًژَ‚¯‚邱‚ئ‚حپAپuگE‹ئ“Iژ‹“_‚©‚ç‚ف‚½ڈلٹQپv‚ج‘ه‚«‚ب“ء’¥‚إ‚ ‚é‚ج‚إپAڈعچׂة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‘و‚Rڈح‚إ‚³‚ç‚ةگ®—‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‚Tپ@ژQ‰ءگ§–ٌپiParticipation restrictionپj
ژQ‰ءگ§–ٌ‚ئ‚حپAŒآگl‚ھ‰½‚ç‚©‚جگ¶ٹˆپEگlگ¶ڈê–ت‚ةٹض‚ي‚é‚ئ‚«‚ةŒoŒ±‚·‚é“‚³‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپBگE‹ئڈê–ت‚إ‚¢‚¦‚خپAپuŒ©ڈKŒ¤ڈCپiگE‹ئڈ€”ُپjپvپuژdژ–‚جٹl“¾پEˆغژپEڈI—¹پvپu•ٌڈV‚ً”؛‚¤ژdژ–پvپu–³•ٌڈV‚جژdژ–پv‚ب‚ا‚ھICF‚ة‚و‚ء‚ؤ•ھ—ق‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éچ€–ع‚إ‚ ‚éپB
‰نپX‚حپAپuŒآگl‚ھگlگ¶ڈê–ت‚ةٹض‚ي‚éپv‚ئ‚¢‚¤پuژQ‰ءپv‚جƒŒƒxƒ‹‚ج“ء’¥‚ً“¥‚ـ‚¦‚ؤپAژں‚ج‚R‚آ‚جƒŒƒxƒ‹‚ج“‚‚±‚ئ‚ةٹض‚·‚é‘I‘ً‚âژہŒ»‰آ”\گ«‚ج–â‘è‚ًپuژQ‰ءگ§–ٌپv‚ئ‚µ‚ؤ•ھ—ق‚·‚邱‚ئ‚ئ‚µ‚½پB
l “‚‚±‚ئ‚ج‘I‘ًپFپ@ژه—v‚بگ¶ٹˆ—جˆو‚ئ‚µ‚ؤپA•ںژƒژ{گف‚جگ¶ٹˆ‚â“ü‰@گ¶ٹˆپA‚ ‚é‚¢‚ح–³گE‚جچف‘îگ¶ٹˆ‚إ‚ب‚پA—ل‚¦‚خŒظ—p‚³‚ê‚ؤ“‚‚±‚ئ‚ً‘I‘ً‚µ‚»‚ê‚ًژہŒ»‚إ‚«‚é‚©پH
l “‚«•û‚ج‘I‘ًپFپ@’تڈي‚ج‹خ–±‚¾‚¯‚إ‚ب‚پAچف‘î‹خ–±‚â’Zژٹش‹خ–±پA“ء—لژq‰ïژذ‚إ‚ج‹خ–±پAگEڈZ‹كگع‚ب‚ا‚ج‘½—l‚ب“‚«•û‚ً‘I‘ً‚µ‚»‚ê‚ًژہŒ»‚إ‚«‚é‚©پH
l گEژي‚ج‘I‘ًپFپ@‘½—l‚بگEژي‚ج’†‚©‚çپAژ©•ھ‚ج‹»–،‚â‹‚ف‚ب‚ا‚ةٹî‚أ‚¢‚ؤپAڈA‚«‚½‚¢گEژي‚ً‘I‘ً‚µ‚»‚ê‚ًژہŒ»‚إ‚«‚é‚©پH
ڈلٹQژزŒظ—p—¦پAگEˆوگ§Œہ‚⌇ٹiڈًچ€پAڈAگEچ·•ت‚ئ‚¢‚ء‚½–â‘è‚حپA‚±‚جچ\گ¬—v‘f‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚éپB‚ـ‚½پAگE‹ئڈ€”ُ‚جڈê–تپA‹پگl‚ض‚ج‰•ه‚جڈê–تپA–تگع‚جڈê–تپA“üگEژ‚جڈê–تپAŒ¤ڈC‚جڈê–تپAژdژ–Œp‘±‚جڈê–تپAڈ¸گi‚جڈê–تپA‹xگE‚âگEڈê•œ‹A‚جڈê–تپA‘قگE‚جڈê–تپA“™پX‚ج‘ه‚«‚بڈê–ت‚حپA‚±‚جپuژQ‰ءپv‚ئ‚µ‚ؤ‘¨‚¦‚é‚ׂ«‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚³‚ç‚ةپA‰نپX‚حپA‚±‚جپuژQ‰ءگ§–ٌپv‚ج“ء’¥‚ئ‚µ‚ؤپA‚ ‚éگl‚جگlگ¶‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚جˆس‹`‚ة‚و‚ء‚ؤ‹ï‘ج“I‚ب—جˆو‚ح‚©‚ب‚è‘ٹ‘خ“I‚ة‚ب‚邱‚ئ‚âپAژہچغڈم‚ج–â‘肾‚¯‚إ‚ب‚‰آ”\گ«‚ًٹـ‚ك‚½‚à‚ج‚à–â‘è‚ة‚·‚é•K—v‚ھ‚ ‚é‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚éپB
پi‚Pپjپuٹˆ“®پv‚ئپuژQ‰ءپv‚ج‘ٹ‘خگ«
ICF‚ة‚¨‚¯‚éپuٹˆ“®پv‚ئپuژQ‰ءپv‚ج‹و•ت‚ح‚©‚ب‚è‘ٹ‘خ“I‚ب‚à‚ج‚إ‚ ‚éپBژہچغپA•ھ—قƒٹƒXƒg‚حپuٹˆ“®‚ئژQ‰ءپv‚ئ‚¢‚¤‹¤’ت‚ج‚à‚ج‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
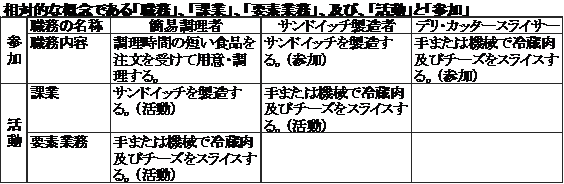 |
ICF‚إ‚حپA‚»‚ج‹و•ت‚حچ‘‚â’nˆو•ت‚ج”»’f‚ة”C‚³‚ꂽٹiچD‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‰نپX‚حپAگE‹ئڈê–ت‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAپuٹˆ“®پv‚ئپuژQ‰ءپv‚ًŒآگl‚جƒŒƒxƒ‹‚إ‘ٹ‘خ“I‚بٹT”O‚ئ‚µ‚ؤ‘¨‚¦‚邱‚ئ‚ھ“Kگط‚إ‚ ‚é‚ئچl‚¦‚éپB‚±‚ê‚حپAگE–±•ھگحڈم‚جٹT”O‚ئ‚µ‚ؤڈ]—ˆ‚©‚ç‚ ‚éپuگE–±پvپ|پu‰غ‹ئپvپ|پu—v‘fچى‹ئپv‚ج‘ٹ‘خگ«‚ئ‚µ‚ؤ‚جگ®—‚ةڈ€‚¸‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚éپiU.S. Department of Labor, 1991.پjپB‚آ‚ـ‚èپA—ل‚¦‚خپAپuژ©“®ژش‚ج‰^“]پv‚ح‚ ‚éگl‚جڈêچ‡پAژذ‰ïژQ‰ء‚»‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚èپAپuژQ‰ءپv‚ةˆت’u‚أ‚¯‚ç‚ê‚é‚ھپA‘î”z•ض‚جƒhƒ‰ƒCƒoپ[‚ةڈAگE‚µ‚و‚¤‚ئ‚·‚éگl‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚حپAپu‘î”z•ض‚جƒhƒ‰ƒCƒoپ[‚ض‚جڈAگEپv‚ئ‚¢‚¤پuژQ‰ءپv‚جˆê‚آ‚ج—vŒڈ‚ئ‚µ‚ؤ‚جپuٹˆ“®پv“à—e‚ةˆت’u‚أ‚¯‚ç‚ê‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
پ@‚±‚ê‚ة”؛‚ء‚ؤپA‰نپX‚حپAپuژQ‰ءپv‚ً•،گ”‚جپuٹˆ“®پv“à—e‚©‚ç‚ب‚éٹK‘w“I‚بچ\‘¢‚ئ‚µ‚ؤ—‰ً‚·‚é‚ئ‚¢‚¤گ®—‚جژd•û‚ً’ٌˆؤ‚µ‚½‚¢پB‚±‚ج‚و‚¤‚بگ®—‚جژd•û‚ة‚و‚ء‚ؤپAٹeگEژي‚â“‚«•ûپiپپپuژQ‰ءپvپj•ت‚ةپA—vŒڈپiپپپuٹˆ“®پvپj‚ھˆل‚¤‚ئ‚¢‚¤ژ–ژہ‚ھگ®—‚إ‚«‚é‚©‚ç‚إ‚ ‚éپB‚ب‚¨پA‚±‚جگ®—‚جژd•û‚ج‘أ“–گ«‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‘و‚Rڈح‚جگEژي‚â“‚«•û‚ة‚و‚éپuگE‹ئ“Iژ‹“_‚©‚ç‚ف‚½ڈلٹQپv‚جŒآ•تگ«‚جŒں“¢‚âپA‘و‡V•”‚ة‚¨‚¯‚éڈî•ٌƒcپ[ƒ‹‚جٹJ”‚ة‚¨‚¯‚郂ƒfƒ‹‚جژہ—pگ«‚جٹد“_‚ً“¥‚ـ‚¦‚ؤŒں“¢‚·‚邱‚ئ‚ئ‚µ‚½‚¢پB
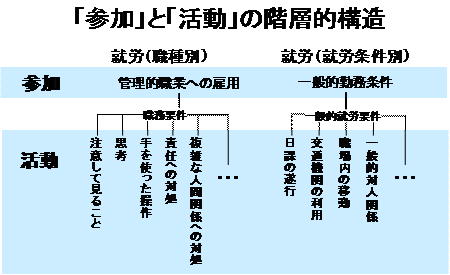 |
پi‚Qپjٹm—¦“I‚ب—\‘ھ‚ئ‚µ‚ؤ‚جپuژQ‰ءگ§–ٌپv
‚ ‚‚ـ‚إŒآ•ت‚ة‚ف‚邵‚©ˆس–،‚ج‚ب‚¢پuٹˆ“®پv‚ئ‚حˆل‚ء‚ؤپAپuژQ‰ءپv‚ة‚حپAپu‘I‘ًپv‚ئ‚¢‚¤ٹد“_‚©‚çپAڈW’c‘S‘ج‚ئ‚µ‚ؤ–â‘è‚ً‚ف‚ؤپAٹm—¦‚ئ‚µ‚ؤ–â‘è‚ھ‹N‚±‚é‚©‚ا‚¤‚©‚ًک_‚¶‚邱‚ئ‚ةˆس–،‚ھ‚ب‚¢‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢پB—ل‚¦‚خپA‘½‚‚جŒ»ژہ‚جگEژي‚ً’²‚ׂé‚ئپAگE–±گ‹چsڈمپAژ‹—ح‚ھ•Kگ{‚ئ‚¢‚¤گEژي‚ھ‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ب‚ج‚ة‘خ‚µ‚ؤپA’®—ح‚ھ•Kگ{‚ئ‚¢‚¤گEژي‚ح”نٹr“Iڈ‚ب‚¢پB‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپAژ‹—ح‚ھ‘S‚ڈلٹQ‚³‚ꂽڈêچ‡‚ئپA’®—ح‚ھ‘S‚ڈلٹQ‚³‚ꂽڈêچ‡‚إ‚حپAگEˆوگ§Œہ‚حپAژ‹—ح‚جڈلٹQ‚ج•û‚ھ‘ه‚«‚‚ب‚éپB‚ـ‚½پA‘½‚‚ج“à•”ڈلٹQ‚إ‚ح‘S”ت“I‘ج—ح’ل‰؛‚ھٹˆ“®گ§Œہ‚ج‘ه‚«‚ب—vˆِ‚إ‚ ‚邱‚ئ‚©‚çپAچ،ŒمپA“÷‘جکJ“‚ھŒ¸ڈ‚µƒfƒXƒNƒڈپ[ƒN‚ھ‘‰ء‚·‚é‚ئپA‘½‚‚ج“à•”ڈلٹQژز‚جگEˆو‚حٹg‘ه‚·‚邾‚낤پB
‚±‚ج‚و‚¤‚ة‚µ‚ؤپAگE‹ئ‘I‘ً‚ة‚¨‚¯‚éگ§–ٌ‚ج’ِ“x‚ًگ„’è‚إ‚«‚é‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚éپBƒIƒ‰ƒ“ƒ_‚إ‚حژہچغپA1992”N‚©‚ç’nˆو•ت‚جگE‹ئ•ھ•z‚âگE‹ئ•ت‚جڈٹ“¾‚جƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒX‚ًپA9,800گEژي‚جگE–±•ھگحƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒX‚ئ‘g‚فچ‡‚ي‚¹‚ؤپAڈلٹQژè“–‚ج‹àٹz‚جŒˆ’è‚ة—p‚¢‚ؤ‚¢‚é(Function Information System; FIS: ƒIƒ‰ƒ“ƒ_’†‰›ژذ‰ï•غڈل‹¦‰ï, 1997)پB‚±‚جƒVƒXƒeƒ€‚حڈd“xڈلٹQژز‚جˆê”تŒظ—p‚ج‰آ”\گ«‚ًژ¦‚·‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚پAڈd“xڈلٹQژز‚ة•غŒىŒظ—p‚â”N‹àگ¶ٹˆ‚ً’ٌ‹ں‚·‚邽‚ك‚ج”»’è‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚ةژهٹل‚ھ’u‚©‚ê‚ؤ‚¢‚éپBگ„Œv‚إ‚ ‚é‚ھپAڈلٹQ‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚à‰½‚ج‘مڈ‘خچô‚à‚ب‚“‚¯‚éژdژ–‚ھŒ»‘¶‚·‚éژdژ–‘S‘ج‚ج‚Tپ“ˆب‰؛‚إ‚ ‚éڈلٹQ‚ئ‚µ‚ؤ‚حپAڈd“x’m“IڈلٹQژزپAژ‹ٹoڈلٹQژز‚PپA‚Q‹‰پA—¼ڈمژˆ‚ج‘S”p‚ ‚é‚¢‚ح’ک‚µ‚¢‹@”\ڈلٹQپA”]گ«–ƒلƒ‚PپA‚Q‹‰‚ب‚ا‚ھ‚ ‚èپAŒoŒ±ڈم‚جگE‹ئ“Iڈd“xڈلٹQ‚ج”حˆح‚ة‘ٹ“–‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚جŒ¤‹†‚à‚ ‚éپiڈt–¼پA1997پjپB
‚½‚¾‚µپA‚±‚ج‚و‚¤‚ةپA‰½‚ج‘مڈ‘خچô‚à‚ب‚“‚¯‚éژdژ–‚ة‚و‚ء‚ؤژQ‰ءگ§–ٌ‚ج’ِ“x‚ًگ„Œv‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‘O’ٌ‚حپA‚©‚ب‚è”ٌŒ»ژہ“I‚إ‚ ‚èپA—د—“I‚ة‚à–â‘è‚ھ‚ ‚éپB‚±‚¤‚µ‚½“_‚àٹـ‚كپA‘مڈ‘خچô‚âژx‰‡‚ھچإ‘هŒہ’ٌ‹ں‚³‚ê‚邱‚ئ‚ً‘O’ٌ‚ئ‚µ‚ؤپA‘½—l‚بگEژي‚ةڈAکJ‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚éڈêچ‡‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جŒ»ژہ“I‚بŒں“¢‚ح‘و‚Rڈح‚إچs‚¤‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپB
پi‚Rپj—lپX‚بگE‹ئ“Iڈê–ت‚ة‚¨‚¯‚éپuژQ‰ءگ§–ٌپv
گE‹ئ“I‚ب–â‘è‚حپAپuگe‚àژüˆح‚àژdژ–‚ح–³—‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚ؤ‹پگEٹˆ“®‚جژd•û‚ھ‚ي‚©‚ç‚ب‚¢پBپv‚ب‚ا‚ج‹پگEٹˆ“®‚جڈê–تپAپuگE‚ة‰•ه‚µ‚ؤ‚à—ڑ—ًڈ‘‚ة•a–¼‚ًڈ‘‚‚ئ—ژ‚ئ‚³‚ê‚éپBپvپu–تگع‚âچج—pژژŒ±‚إ‰ïڈê‚ةژش‚¢‚·‚إƒAƒNƒZƒX‚إ‚«‚ب‚¢پ^ژèکb’ت–َ‚ھ—ک—p‚إ‚«‚ب‚¢پBپv‚ئ‚¢‚ء‚½‹پگEڈê–ت‚ب‚اپAژہچغ‚ةگE‚ةڈA‚¢‚ؤ‚©‚ç‚جگEڈêŒp‘±ڈم‚ج–â‘è‚âڈ¸گi‚âڈˆ‹ِ‚ج–â‘è‚ب‚اپAڈê–ت‚ة‚و‚ء‚ؤ‘ه‚«‚ˆظ‚ب‚èپA‚»‚ꂼ‚ê‚جڈê–ت‚ة‚¨‚¯‚é‰غ‘è‚ً•تپX‚ةŒں“¢‚·‚邱‚ئ‚ھ•K—v‚إ‚ ‚éپB•ؤچ‘‚ج—ل‚إ‚حپAگE‚ةڈA‚¢‚ؤ‚©‚çŒp‘±“I‚ةژèکb’ت–َ‚ً”z’u‚·‚邱‚ئ‚ح–³—‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚é‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA–تگعژ‚ةˆêژ“I‚ةژèکb’ت–َ‚ً”z’u‚·‚邱‚ئ‚ھ‹پ‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
‚½‚¾‚µپAپuٹˆ“®پv‚ئپuژQ‰ءپv‚ح‘ٹ‘خ“I‚إ‚ ‚èپA“ü‚êژq“I‚بچ\‘¢‚ً‚à‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‘ه‚«‚پuŒظ—p‚ئگE‹ئپv‚جژQ‰ء‚ئ‚µ‚ؤ‚‚‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¦‚خپA‚±‚ê‚ç‚à‚ـ‚½‚»‚ê‚ًچ\گ¬‚·‚é•”•ھ‚ئ‚µ‚ؤ‚جپuٹˆ“®پv‚ئ‚µ‚ؤˆت’u‚أ‚¯‚邱‚ئ‚à‰آ”\‚إ‚ ‚éپB
‚Uپ@ٹآ‹«ˆِژqپiEnvironmental factorپj
ڈلٹQ‚ج‚ ‚éگl‚جڈAکJ‚ةٹضŒW‚µ‚ؤپA—lپX‚بٹآ‹«–ت‚ج•دچX‚ج•K—v‚ھگ¶‚¶‚½‚èپA‚»‚ê‚ة”؛‚ء‚ؤپAٹآ‹«گ®”ُ‚ةٹض‚·‚镉’S‚âژہچs‰آ”\گ«‚ب‚ا‚ج‰غ‘è‚ھگ¶‚¶‚½‚è‚·‚éپB‚±‚ê‚ç‚ج‰غ‘è‚حپAپuٹآ‹«ˆِژqپv‚ئٹضکA‚µ‚ؤ•ھ—ق‚إ‚«‚éپBٹآ‹«ˆِژq‚ئ‚حپAگlپX‚ھگ¶ٹˆ‚µپAگlگ¶‚ً‘—‚ء‚ؤ‚¢‚镨“I‚بٹآ‹«‚âژذ‰ï“Iٹآ‹«پAگlپX‚جژذ‰ï“I‘ش“x‚ة‚و‚éٹآ‹«‚ًچ\گ¬‚·‚éˆِژq‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB‚±‚ê‚ة‚حپAڈلٹQ‚ج‚ ‚éگl‚ة‚ئ‚ء‚ؤ—L—ک‚بپu‘£گiˆِژqپv‚ئپA•s—ک‚بپu‘jٹQˆِژqپiڈل•اپjپv‚ج‚Q‘¤–ت‚ھ‚ ‚éپB‚±‚ê‚ة‚حپA‹ï‘ج“I‚ة‚حپuگ¶ژY•i‚ئ—p‹ïپvپuژ©‘Rٹآ‹«‚ئگlٹش‚ھ‚à‚½‚炵‚½ٹآ‹«•د‰»پvپuژx‰‡‚ئٹضŒWپvپu‘ش“xپvپuƒTپ[ƒrƒXپEگ§“xپEگچôپv‚ئ‚¢‚¤—جˆو‚ھ‚ ‚éپB
پuٹآ‹«ˆِژqپv‚ة‚آ‚¢‚ؤپAڈلٹQژز“–ژ–ژز’c‘ج‚ب‚ا‚جڈلٹQ‚جچl‚¦•û‚إ‚حپuژذ‰ï‚جڈل•اپپڈلٹQپv‚ئ‚¢‚¤Œ¾‚¢•û‚ھ‚³‚ê‚邱‚ئ‚à‚ ‚é‚ھپAICF‚إ‚حپAڈلٹQ‚ة‰e‹؟‚·‚éپu”wŒiˆِژqپv‚جˆê‚آ‚إ‚ ‚ء‚ؤپAڈلٹQ‚»‚ج‚à‚ج‚ًچ\گ¬‚·‚é‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپBپuٹآ‹«ˆِژqپv‚حپAڈلٹQ‚ًژذ‰ï“I‰غ‘è‚ئ‚µ‚ؤ‘¨‚¦‚éچغ‚ةڈd—v‚ئ‚ب‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚èپA‚»‚ج‹ï‘ج—ل‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‘و‚Qڈح‚إڈعچׂةŒں“¢‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‚Vپ@ŒآگlˆِژqپiPersonal factorپj
پuŒآگlˆِژqپv‚ئ‚حپAŒآگl‚جگlگ¶‚âگ¶ٹˆ‚ج“ء•ت‚ب”wŒi‚إ‚ ‚èپAŒ’چNڈَ‘ش‚⌒چNڈَ‹µˆبٹO‚ج‚»‚جگl‚ج“ء’¥‚©‚ç‚ب‚éپB‚±‚ê‚حپAڈلٹQ‚إ‚ح‚ب‚¢‚ھپA‚µ‚خ‚µ‚خپAڈلٹQ‚ئچ¬—گ‚³‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پB—ل‚¦‚خپAگE‹ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤچl‚¦‚½‚±‚ئ‚à‚ب‚¢پA’xچڈ‚¹‚¸‚ةڈo‹خ‚·‚éڈKٹµ‚ھ‚ب‚¢پAژdژ–‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جچl‚¦•û‚ھٹأ‚¢پA‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚ب–{گl‚جگE‹ئڈم‚ج–â‘è‚ًپAپu‚Qژں“IڈلٹQپv‚âپuڈلٹQ“ءگ«پv‚ئ‚µ‚ؤ‘¨‚¦‚邱‚ئ‚à‘½‚¢پB‚µ‚©‚µپAڈلٹQ‚ة‚و‚ء‚ؤپA‚±‚ج‚و‚¤‚ب“ءگ«‚ھگ¶‚¶‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح•خŒ©‚ة‹ك‚¢‚à‚ج‚ھ‚ ‚éپB‚ق‚µ‚ëپA‚±‚ê‚ç‚حٹî–{“I‚ةڈلٹQ‚»‚ج‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢پuŒآگlˆِژqپv‚ئ‚µ‚ؤˆµ‚¢پA‚»‚ê‚ھڈلٹQ‚ئ‘ٹŒفچى—p‚·‚é‚ئ‚¢‚¤ٹد“_‚ھ•K—v‚إ‚ ‚é‚ئچl‚¦‚éپB
‚ـ‚½پA‹t‚ةپAپuڈلٹQ‚ج‚ ‚éگl‚جگlگ¶ŒoŒ±‚ح‹Mڈd‚¾پBپv‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚بƒvƒ‰ƒX‚ج•]‰؟‚à‚ ‚肤‚é‚ھپA‚±‚ê‚àڈلٹQ‚ئ‚حٹضŒW‚ج‚ب‚¢پuŒآگlˆِژqپv‚ةˆت’u•t‚¯‚ç‚ê‚é‚ׂ«‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚³‚ç‚ةپAژش‚¢‚·‚جگl‚ھچف‘î‹خ–±‚ً‘O’ٌ‚ئ‚µ‚ؤپA—ل‚¦‚خƒEƒFƒuƒfƒUƒCƒiپ[‚ئ‚µ‚ؤ‚جگE‹ئ”\—ح‚ًŒں“¢‚µ‚½ڈêچ‡‚ةپA•K—v‚ب’mژ¯‚â‹Z”\‚ھ‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤–â‘è‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚àپAڈلٹQ‚ئ‚حٹضŒW‚ج‚ب‚¢Œآگlˆِژq‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ج–â‘è‚إ‚ ‚éپB
‚Wپ@ژهٹد“IژںŒ³پiSubjective dimensionپj
چإŒم‚ةپAICF‚جٹJ”’†‚©‚猻چف‚àŒں“¢‚ھŒp‘±‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپuژهٹد“IژںŒ³پv‚جڈلٹQ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚àگG‚ê‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB‚±‚ê‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپAŒ»چف‚جICF‚جٹT”Oکg‘g‚ة‚حٹـ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢•ت‚جژںŒ³‚إ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤چl‚¦‚ج‘¼‚ةپAپuژQ‰ءپv‚âپuŒآگlˆِژqپv‚ج“à—e‚ئ‚µ‚ؤٹـ‚ـ‚ê‚é‚ׂ«‚à‚جپA‚ئ‚¢‚ء‚½‚و‚¤‚ب—lپX‚ب‹cک_‚ھ‚ ‚é(Ueda & Okawa, 2003)پB‚±‚ê‚ة‚آ‚¢‚ؤپAˆê•”ٹضکA‚·‚éژ–چ€‚ة‚آ‚¢‚ؤگ®—‚µ‚ؤ‚¨‚پB
گE‹ئپi“‚‚±‚ئپj‚حپAژ©Œب‚جˆسژv‚ئگس”C‚ةٹî‚أ‚¢‚ؤگ¶ٹˆ‚جˆغژ‚ً‰آ”\‚ئ‚µپAژه‘ج“I‚بژذ‰ïژQ‰ء‚جچإ‚à–]‚ـ‚µ‚¢Œ`‘ش‚إ‚ ‚èپA‘S‚ؤ‚جگl‚جگ¶ٹˆ‚ج‰غ‘è‚إ‚ ‚éپB‚±‚ê‚ھگ§–ٌ‚³‚ê‚邱‚ئ‚حپAگ[چڈ‚بژهٹد“I‚ب–â‘è‚ًˆّ‚«‹N‚±‚·پBڈAکJ‚ة‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا–â‘è‚ھ‚ب‚¢‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚بژشˆضژqژg—pژز‚إ‚ ‚ء‚ؤ‚àپAژَڈ’¼Œم‚ة‚حگlگ¶‚ً”كٹد‚µ‚ؤگE‹ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤچl‚¦‚ç‚ê‚ب‚‚ب‚邱‚ئ‚ھ‚ ‚éپBژَڈ‚ة‚و‚èژ©ŒبƒCƒپپ[ƒW‚ج’ل‰؛‚ة‚آ‚ب‚ھ‚èپA‚³‚ç‚ةپAژذ‰ï“Iژx‰‡‚ج‰آ”\گ«‚ة–³’m‚إ‚ ‚é‚ب‚ا‚µ‚ؤپA–{گl‚ھگE‹ئ“I–ع•W‚ًŒ©ژ¸‚¤‚±‚ئ‚ح‘½‚¢پB—ل‚¦‚خپAٹOڈگ«”]‘¹ڈ‚ب‚ا‚àٹـ‚كپAژَڈ’¼Œم‚جژٹْ‚ةگع‚·‚邱‚ئ‚ھ‘½‚¢ˆم—أ‚â•ںژƒ‚جگê–هگE‚ھپA–{گl‚جژ©ŒبƒCƒپپ[ƒW‚ج‰ٌ•œ‚âگE‹ئ‚ًٹـ‚ك‚½–ع•W‚جچؤگف’è‚ًژèڈ•‚¯‚·‚é–ًٹ„‚ح‘ه‚«‚¢پB‚±‚ê‚حپuŒآگlˆِژqپv‚ة‚و‚ء‚ؤ‚àچ¶‰E‚³‚ê‚éپAژهٹد“I‚ب–â‘è‚جڈd—vگ«‚ًژ¦‚·‚à‚ج‚إ‚ ‚낤پB
‚ـ‚½پAڈلٹQ‚ة‚و‚ء‚ؤژ©•ھ‚ج”\—ح‚ًٹm”F‚إ‚«‚éŒoŒ±‹@‰ï‚جگ§–ٌ‚ب‚ا‚ھگ¶‚¶‚â‚·‚‚ب‚ء‚½‚èپA‰ئ‘°‚âگEڈê‚â’nˆوژذ‰ï‚جگl‚½‚؟‚ج‘ش“x‚ة‚و‚ء‚ؤ‚حژ©Œب‚ً”غ’è“I‚ة‘¨‚¦‚ھ‚؟‚ة‚ب‚ء‚½‚è‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚èپAگE‹ئڈ€”ُگ«‚ج’ل‰؛‚ة‚آ‚ب‚ھ‚邱‚ئ‚ھ‚ ‚éپB‚±‚ê‚حپuŒآگlˆِژqپv‚جٹض—^‚ئ‚µ‚ؤ—‰ً‚·‚邱‚ئ‚à‰آ”\‚إ‚ ‚낤‚ھپA‚»‚جژهٹد“I‚بگ«ژ؟‚©‚ç‚حپAژهٹد“IڈلٹQ‚جˆê‚آ‚جŒ`‘ش‚ئ‚µ‚ؤ—‰ً‚إ‚«‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB
‚ـ‚½پAژهٹد“IڈلٹQ‚ً–‘«“x‚ئٹضکA‚أ‚¯‚邱‚ئ‚à‰آ”\‚إ‚ ‚낤پB‰نپX‚حپAٹé‹ئ‚إ“‚¢‚ؤ‚¢‚éڈلٹQ‚ج‚ ‚éگl‚جگE‹ئگ¶ٹˆ‚ج–‘«“x‚ج’²چ¸‚ًچs‚¢پAگEڈê‚إ‚جڈلٹQڈَ‹µ‚ھڈd‚ٹé‹ئ‘¤‚©‚ç‚ج”z—¶‚ھ‘ه‚«‚¢ڈêچ‡‚ة–‘«“x‚ھچ‚‚‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپA‚»‚ê‚حپA”z—¶‚ة‚و‚é‹qٹد“I‚ب–â‘è‰ًŒˆ‚ئ‚حٹضŒW‚ھ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ً–¾‚ç‚©‚ة‚µ‚½پiژ‘—؟ƒVƒٹپ[ƒYNo.27‘و‚UڈحپjپB‚آ‚ـ‚èپA–‘«“x‚ئ‚¢‚¤ٹد“_‚©‚çژهٹد“IڈلٹQ‚ً‘¨‚¦‚é‚ئپA‹qٹد“I‚بڈلٹQڈَ‹µ‚ئ‚ح“ئ—§‚µ‚½‰½‚©‚إ‚ ‚邱‚ئ‚حٹm‚©‚إ‚ ‚é‚ھپA‚±‚جŒّ‰ت‚حپA‚ ‚‚ـ‚إ‚àژ–‹ئژه‚ة‚و‚é‹qٹد“I–â‘è‚ض‚جژو‚è‘g‚ف‚جŒ‹‰ت‚ئ‚µ‚ؤ‘¨‚¦‚é‚ׂ«‚à‚ج‚إ‚ ‚èپA’P‚ة–‘«“x‚ًڈم‚°‚邽‚ك‚ة–{—ˆپA‹پ‚ك‚ç‚ê‚é‚ׂ«Œّ‰ت‚ج—L–³“™‚ة‚©‚©‚ي‚炸‚»‚¤‚µ‚½پuژx‰‡پv‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚ح–{––“]“|‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚éپB‚±‚ê‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‘و‚Sڈح‚إچؤ‚رگG‚ê‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‚ـ‚½پA‹ك”NپAƒJƒEƒ“ƒZƒٹƒ“ƒO‚âگS——أ–@‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚àپAپuڈلٹQژَ—eپv‚ة‚آ‚¢‚ؤپA‹ك”NڈلٹQ‚ج‚ ‚éگl‚جپuژ©Œبژَ—eپv‚جچl‚¦•û‚ھچs‚«‰ك‚¬‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ض‚ج”ل”»‚ئ‚ئ‚à‚ةپAژذ‰ï‘¤‚ھڈلٹQ‚ج‚ ‚éگl‚ًژَ‚¯“ü‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤پuژذ‰ïژَ—eپv‚±‚»‚ھڈلٹQژَ—e‚ج–{ژ؟‚إ‚ ‚é‚ئ‚ج‹cک_‚ھ‚ ‚éپi“ى‰_پA2004پjپB‚±‚ê‚حپAپuژQ‰ءپvگ§–ٌ‚ج–â‘è‚ھژهٹد“IƒŒƒxƒ‹‚ج–â‘è‚ئٹضکA‚أ‚¯‚ç‚ê‚·‚¬‚é‚ئپA‹qٹد“I‚بپuژQ‰ءگ§–ٌپv‚ض‚ج‘خ‰‚ً“ف‚点‚é‚ئ‚¢‚¤ٹ댯گ«‚ًژ¦چ´‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚¢‚¦‚é‚إ‚ ‚낤پB‚±‚ê‚حپAڈلٹQ‚ج‚ ‚éگl‚ةڈAکJ‹@‰ï‚ھ‹ة‚ك‚ؤŒہ‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‘O’ٌ‚إپAژهٹد“I‚ب–‘«‚جŒ¹گٍ‚إ‚ ‚éژdژ–‚ج‹@‰ï‚ً’ٌ‹ں‚·‚é‚ئ‚¢‚¤•ںژƒچHڈê‚âژِژYژ{گف‚âڈ¬‹K–حچى‹ئڈٹ‚ب‚ا‚جˆس‹`‚ج‹cک_پiڈ¼ˆ×, 2001پj‚ة‚àٹضŒW‚·‚é‚ئژv‚ي‚ê‚éپB
ژهٹد“IڈلٹQ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAگE‹ئڈê–ت‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚àڈd—v‚بˆس‹`‚ھ‚ ‚é‚ھپA“¯ژ‚ة‹qٹد“I‚ب‰غ‘è‚ً‰B•ء‚·‚é‚و‚¤‚بŒë‚ء‚½”Fژ¯‚ً‚³‚ê‚éٹ댯گ«‚à‚ ‚éپBچ،ŒمپAژهٹد“IڈلٹQ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جچ‘چغ“I‹cک_‚ً“¥‚ـ‚¦‚ؤپA‚و‚èŒں“¢‚ًگ[‚ك‚é•K—v‚ھ‚ ‚낤پB
‘و‚Qگكپ@ڈلٹQپ^گ¶ٹˆ‹@”\‚ج—v‘fٹش‚جٹضŒWگ«
ڈم‹L‚إپAگE‹ئڈم‚ج‘½—l‚ب–â‘è‚ًپAICF‚جٹeچ\گ¬—v‘f‚ة•ھ—ق‚µ‚ؤگà–¾‚µ‚½‚ھپA‚±‚ê‚ç‚ج–â‘è‚ج‘ٹŒفٹضŒW‚ً–¾‚ç‚©‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ھڈd—v‚إ‚ ‚éپBICF‚جٹT”Oکg‘gژ©‘ج‚حپA‘½—l‚ب‘ٹŒفچى—p‚ھ‚ ‚肤‚éپA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ًژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚邾‚¯‚إ‚ ‚ء‚ؤپA‘ٹŒفچى—p‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAچ،Œم‚جژہڈط“I‚بŒ¤‹†‚ج‘خڈغ‚إ‚ ‚é‚ئˆت’u‚أ‚¯‚ؤ‚¢‚éپB
‚»‚±‚إپA‰نپX‚حپA‚ـ‚¸پA‚±‚ê‚ç‚جچ\گ¬—v‘fٹش‚جٹضŒW‚ة‚حپA‚ا‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚ھٹù‚ة–¾‚ç‚©‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©پA‚ا‚ج‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ً–¾‚ç‚©‚ة‚·‚é•K—v‚ھ‚ ‚é‚©‚ًŒں“¢‚µ‚½پB‚»‚جŒ‹‰تپAپuŒ’چNڈَ‘شپv‚©‚çپu‹@”\ڈلٹQپv‚âپuٹˆ“®گ§Œہپv‚ض‚جٹضŒWگ«‚حپAژ¾ٹ³‚ئڈلٹQ‚جٹضŒW‚ئ‚µ‚ؤپAٹù‚ة‘½‚‚جگM—ٹ‚إ‚«‚éƒfپ[ƒ^‚ھ‚ ‚éˆê•û‚إپA‚»‚ج‘¼‚جٹضŒWگ«‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حŒآ•ت‚ج•ھگحژ–—ل‚ھگد‚فڈd‚ث‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é’iٹK‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ھ–¾‚ç‚©‚ئ‚ب‚ء‚½پB‚±‚ج‚و‚¤‚بٹضŒWگ«‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‚±‚±‚إ‚ح‚»‚جٹT—v‚ة‚آ‚¢‚ؤŒں“¢‚µپA‚و‚è‹ï‘ج“I‚بٹضŒWگ«‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‘و‡V•”‘و‚Vڈح‚ة‚¨‚¢‚ؤپA‘½—l‚بٹضکAڈî•ٌ‚ًICF‚جٹT”Oکg‘g‚إƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒX‰»‚·‚éچغ‚ةڈq‚ׂ邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‚Pپ@ژ¾ٹ³پiDiseaseپj‚ئڈلٹQپiDisabilityپj‚جٹضŒW
ژ¾ٹ³‚©‚çڈلٹQ‚ھگ¶‚¶‚é‚ب‚ا‚جٹضŒWگ«‚ح–¾‚ç‚©‚إ‚ح‚ ‚é‚ھپAڈ]—ˆ‚حژ¾ٹ³‚جپuڈاڈَپv“™‚ج•tگڈ“I‚بˆت’u‚أ‚¯‚إ‚ ‚èپAڈلٹQژ©‘ج‚ً–â‘è‚ئ‚·‚é‚ئ‚¢‚¤ٹد“_‚حپA”نٹr“IگV‚µ‚¢‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚±‚ج‚و‚¤‚بٹد“_‚©‚çپA‚±‚ê‚ـ‚إ‚جˆمٹw“™‚ج•ھ–ى‚إ’~گد‚³‚ꂽڈî•ٌ‚ة‚آ‚¢‚ؤپAگV‚½‚ب—ک—p‰؟’l‚ھگ¶‚¶‚éپB
 |
WHO‚ة‚¨‚¢‚ؤپA‚±‚ê‚ـ‚إ150”Nˆبڈم‚ج—ًژj‚ً‚à‚آچ‘چغژ¾•a•ھ—قICD-10‚ة‰ء‚¦‚ؤپAچ‘چغگ¶ٹˆ‹@”\•ھ—قICF‚ًگV‚½‚ةٹJ”‚µ‚½–ع“I‚حپAژ¾ٹ³‚جژ‹“_‚ئ‚حˆظ‚ب‚éڈلٹQ‚جژ‹“_‚ًڈdژ‹‚·‚é•K—v‚ھ‚ ‚ء‚½‚©‚ç‚إ‚ ‚éپB‚آ‚ـ‚èپAICF‚ج–ع“I‚حپAپuICD-10‚ة‚و‚éژ¾•a‚جگf’f‚ةٹض‚·‚éڈî•ٌ‚ةگ¶ٹˆ‹@”\‚جڈî•ٌ‚ً‰ء‚¦‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپAŒ’چN‚ةٹض‚·‚é•چL‚¢ڈî•ٌ‚ًƒRپ[ƒfƒBƒ“ƒO‚·‚邽‚ك‚جŒ¾Œê‚ً’ٌ‹ں‚µپAŒ’چN‚ئ•غŒ’ƒPƒA‚ةٹض‚·‚éڈ”گê–ه•ھ–ىپE‰بٹw‚ة‚ـ‚½‚ھ‚éچ‘چغ“I‚بڈî•ٌŒًٹ·‚ً‰آ”\‚ئ‚·‚é‚و‚¤‚ب•Wڈ€“I‹¤’تŒ¾Œê‚ً’ٌ‹ں‚·‚邱‚ئپiICFڈکک_پjپv‚ة‚ ‚éپB
ˆمٹw‚âˆم—أ‚جٹد“_‚©‚çگ®—‚³‚ꂽڈî•ٌ‚ة‚حپAٹù‚ةپAژ¾ٹ³‚ئڈلٹQ‚جٹضŒW‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ج‘½‚‚جڈî•ٌ‚ھ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µپAˆمٹw‚âˆم—أ‚جٹد“_‚حپAƒٹƒnƒrƒٹƒeپ[ƒVƒ‡ƒ“‚جٹد“_‚ئ‚ح‘ه‚«‚ˆظ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ة’چˆس‚ھ•K—v‚إ‚ ‚éپiڈم“cپE‘هگى, 1998پjپB‚آ‚ـ‚èپA‚±‚ê‚ç‚جڈî•ٌ‚إ‚حپAپuڈلٹQپv‚ح‚ ‚‚ـ‚إ‚àپuڈاڈَپv‚âپuگf’fٹîڈ€پv‚ئ‚µ‚ؤˆت’u‚أ‚¯‚ç‚êپA‚»‚جچھ–{‚ة‚ ‚éپuŒ’چNڈَ‘شپv‚ًگf’f‚µ‚½‚è”F’肵‚½‚è‚·‚éژè‚ھ‚©‚è‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپB‚ب‚؛‚ب‚çپAˆمٹw“Iژ‹“_‚©‚ç‚حپAŒآگl‚ج‘S‘ج‘œ‚ًˆê‚آ‚جگf’f–¼‚ئ‚µ‚ؤٹm’è‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپA•aˆِپAڈاڈَپA•a—‚ً–¾‚ç‚©‚ة‚µپA—\–hپA‘پٹْ”Œ©پAژ،—أپAچؤ”–hژ~پAŒمˆâڈاٹا—‚ب‚ا‚ج‘خچô‚ً‚ئ‚邱‚ئ‚ھڈd—v‚¾‚©‚ç‚إ‚ ‚éپBˆê•ûپAƒٹƒnƒrƒٹƒeپ[ƒVƒ‡ƒ“‚جٹد“_‚إ‚حپA‹@”\ڈلٹQپAٹˆ“®گ§ŒہپAژQ‰ءگ§–ٌ‚حپAڈاڈَ‚âگf’fٹîڈ€‚إ‚ح‚ب‚پA‚»‚êژ©‘ج‚ھژx‰‡‚ج‘خڈغ‚إ‚ ‚éپB—ل‚¦‚خپA“ï•a‚ة‚ح‘½—l‚بژ¾ٹ³ژي—ق‚ھ‚ ‚èپA‚»‚ꂼ‚ê‚جژ¾ٹ³‚ح“ء’¥‚ج‚ ‚éڈلٹQ‚جƒpƒ^پ[ƒ“‚ً—L‚µ‚ؤ‚¨‚èپAŒآپX‚جڈلٹQ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ف‚é‚ئڈلٹQ“à—e‚ة‚ح‹¤’ت‚·‚é‚à‚ج‚ھ‚ف‚ç‚ê‚éپBˆم—أ‚جٹد“_‚©‚ç‚ح‚±‚ê‚ç‚جڈلٹQڈَ‹µ‚ح’P‚ب‚éگf’fٹîڈ€‚إ‚ ‚èپAڈاڈَ‚ة‹¤’ت“_‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚àپAگf’f‚âژ،—أ–@‚ة‚ح‚ ‚ـ‚èˆس–،‚ح‚ب‚¢پB‚µ‚©‚µپAƒٹƒnƒrƒٹƒeپ[ƒVƒ‡ƒ“‚جٹد“_‚إ‚حپA‚±‚ê‚ç‚جڈلٹQ‚ج‹¤’ت“_‚حڈd—v‚بˆس–،‚ً‚à‚آپB—ل‚¦‚خپAƒxپ[ƒ`ƒFƒbƒg•a‚ئ–ش–ŒگF‘f•دگ«ڈا‚ح‘S‚ˆظ‚ب‚éژ¾ٹ³‚¾‚ھپA‚»‚ê‚ة‚و‚ء‚ؤگ¶‚¶‚éژ‹—حڈلٹQ‚جŒ‹‰ت‚ح“¯‚¶‚إ‚ ‚éپB‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپA‚»‚ê‚ة‚و‚éٹˆ“®گ§Œہ‚ة‚ح‚ ‚é’ِ“x‚جٹضکAگ«‚ھ‚ف‚ç‚êپA•K—v‚بژx‰‡‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚àˆê•”‚ح‹¤’ت‚µ‚¤‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
‚Qپ@ڈلٹQپ^گ¶ٹˆ‹@”\‚جچ\گ¬—v‘fٹش‚جٹضŒWگ«
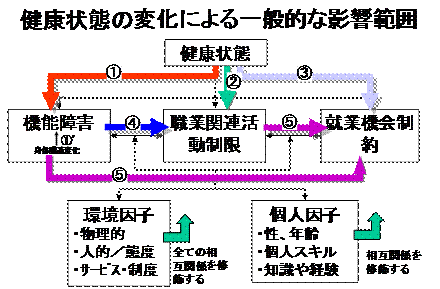 |
پuŒ’چNڈَ‘شپv‚©‚çگE‹ئ“I‚ب–â‘è‚ة‚ا‚ج‚و‚¤‚ةٹضکA‚·‚é‚©‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‘½—l‚ب–â‘è‚ًٹـ‚ف‘½‚‚جŒں“¢‚ً•K—v‚ئ‚·‚éپBگ¸گ_ڈلٹQ“™‚ة‚¨‚¯‚éژ{گفڈا‚â”p—pگ«ڈاŒَŒQ‚ج‚و‚¤‚ةژQ‰ءگ§–ٌ‚âٹˆ“®گ§Œہ‚©‚ç‹@”\ڈلٹQ‚⌒چNڈَ‘ش‚جˆ«‰»‚ھگ¶‚¶‚éڈêچ‡‚à‚ ‚é‚ھپA‚ ‚‚ـ‚إ‚à‚Qژں“I‚بٹضŒWگ«‚إ‚ ‚邽‚كپA‚±‚±‚إ‚حپA–â‘è‚ج’Pڈƒ‰»‚ج‚½‚ك‚ةپAپuŒ’چNڈَ‘شپv‚©‚ç‚جٹضŒWگ«‚ج—¬‚ê‚ج‘م•\“I‚ب‚à‚ج‚ًگ®—‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
l ‡@پuŒ’چNڈَ‘شپv‚©‚çپu‹@”\ڈلٹQپiگg‘جچ\‘¢•د‰»‚ًٹـ‚قپjپv‚ھگ¶‚¶‚éپi‚»‚جٹش‚ة”wŒiˆِژq‚ة‚و‚éڈCڈü‚ھ‚ ‚éپBپjپBپGپ@ƒxپ[ƒ`ƒFƒbƒg•a‚ة‚و‚èژ‹ٹoڈلٹQ‚âژˆ‘ج•sژ©—R‚ھگ¶‚¶‚éپAگ¸گ_’x‘ط‚ة‚و‚è’m“IڈلٹQ‚ھگ¶‚¶‚éپA‚ب‚اپB
l ‡@پfپuگg‘جچ\‘¢پv•د‰»‚©‚çپu‹@”\ڈلٹQپv‚ھگ¶‚¶‚éپBپGپ@‘O“ھ—t‚ج‘¹ڈ‚ة‚و‚èچ‚ژں”F’m‹@”\ڈلٹQ‚ھگ¶‚¶‚éپA‚ب‚اپB
l ‡AپuŒ’چNڈَ‘شپv‚©‚çپuٹˆ“®گ§Œہپv‚ھگ¶‚¶‚éپi‚»‚جٹش‚ة”wŒiˆِژq‚ة‚و‚éڈCڈü‚ھ‚ ‚éپBپjپBپGپ@•a‹C‚ة‚و‚ء‚ؤˆمژt‚©‚çپuƒXƒgƒŒƒXپv‚ً”ً‚¯‚é‚و‚¤‚ةŒ¾‚ي‚ê‚邱‚ئپA‚ب‚اپBپ@
l ‡BپuŒ’چNڈَ‘شپv‚©‚ç’¼گع‚ةپuژQ‰ءگ§–ٌپv‚ھگ¶‚¶‚éپi‚»‚جٹش‚ة”wŒiˆِژq‚ة‚و‚éڈCڈü‚ھ‚ ‚éپBپjپBپFپ@—ڑ—ًڈ‘‚ة•a–¼‚ً‹Lچع‚µ‚½‚ئ‚±‚ëپAژdژ–‚ً‚·‚é”\—ح‚ة‚ح–â‘è‚ھ‚ب‚¢‚ة‚àٹض‚ي‚炸Œظ—p‚³‚ê‚ب‚¢پA‚ب‚اپB
l ‡Cپu‹@”\ڈلٹQپiگg‘جچ\‘¢•د‰»‚ًٹـ‚قپjپv‚©‚çپuٹˆ“®گ§Œہپv‚ھگ¶‚¶‚éپi‚»‚جٹش‚ة”wŒiˆِژq‚ة‚و‚éڈCڈü‚ھ‚ ‚éپBپjپBپFپ@ژ‹ٹoڈلٹQ‚ة‚و‚èپAٹwڈKپAˆع“®پAگlٹشٹضŒW“™‚ة–â‘è‚ھگ¶‚¶‚éپA‚ب‚اپB
l ‡Dپu‹@”\ڈلٹQپiگg‘جچ\‘¢•د‰»‚ًٹـ‚قپjپv–”‚حپuٹˆ“®گ§Œہپv‚ة‚و‚ء‚ؤپuژQ‰ءگ§–ٌپv‚ھگ¶‚¶‚éپBپFپ@ژdژ–‚ة•K—v‚ب—vŒڈ‚ً–‚½‚¹‚ب‚¢‚½‚كپAڈAگE‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢پA‚ب‚اپB
‘و‚Rگكپ@ڈلٹQ‚ئڈلٹQ‚إ‚ب‚¢‚à‚ج
–{ڈح‚إ‚حپA‚ي‚ھچ‘‚جŒ»چs‚جپuڈلٹQپv‚جچl‚¦•û‚ةچS‚炸پAICF‚جٹد“_‚©‚çپuگE‹ئڈم‚ج–â‘èپv‚ةٹضکA‚·‚é‚à‚ج‚ً’†گS‚ئ‚µ‚ؤ‰غ‘è‚ًگ®—‚µ‚ؤ‚«‚½پB‚µ‚©‚µپA‚½‚¾’P‚ةژ¸‹ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éگl‚ًپAپuگE‹ئ“Iژ‹“_‚©‚ç‚ف‚½ڈلٹQپv‚ھ‚ ‚éگl‚ئ‚حŒ¾‚¦‚ب‚¢‚إ‚ ‚낤پBپuگE‹ئ“Iژ‹“_‚©‚ç‚ف‚½ڈلٹQپv‚ًپAŒ»ژہ‚جگE‹ئ“I‰غ‘è‚ئ‚µ‚ؤ”cˆ¬‚·‚邽‚ك‚ة‚حپA‚»‚جˆê•û‚إپAژ¸‹ئ‚âچ·•ت‚â‘س‚¯‚ب‚ا‚ة‚و‚éˆê”ت“I‚بگE‹ئ“Iچ¢“ïگ«‚â–â‘è‚ًپAڈلٹQ‚ئ‹و•ت‚·‚éٹîڈ€‚ھ•K—v‚إ‚ ‚éپB
ICF‚جٹد“_‚إ‚àپAژہ‚حپuگE‹ئڈم‚ج–â‘èپv‚»‚êژ©‘ج‚ًپuڈلٹQپv‚ئ‚·‚é‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢پB‚±‚جˆل‚¢‚حپA‚»‚جگE‹ئ“I‚ب‰غ‘è‚ھپAICF‚ج‚¢‚¤پuŒ’چNڈَ‘شپv‚ةٹضکA‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©‚ا‚¤‚©‚ة‚و‚éپB‚±‚ج‚و‚¤‚بٹîڈ€‚ة‚و‚ء‚ؤ‚ح‚¶‚ك‚ؤپAڈلٹQ‚إ‚ح‚ب‚¢گE‹ئڈم‚ج–â‘è‚ئپAŒ»چs‚إ‚حپuڈلٹQپv‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸گ^‚جپuگE‹ئ“Iژ‹“_‚©‚ç‚ف‚½ڈلٹQپv‚إ‚ ‚é‚à‚ج‚ً‹و•ت‚إ‚«‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
‚Pپ@ڈلٹQ‚إ‚ح‚ب‚¢گE‹ئ“Iچ¢“ïگ«
ڈلٹQ‚ح‚ ‚‚ـ‚إ‚àپAŒ’ڈيژز‚ًٹîڈ€‚ة‚µ‚½”غ’è“I‘¤–ت‚إ‚ ‚ء‚ؤپAˆê”ت“I‚ةپAŒ’ڈيژزƒŒƒxƒ‹ˆبڈم‚جŒ’چNڈَ‘ش‚ةٹضکA‚µ‚½گE–±—vŒڈ‚ًŒآگl‚جٹˆ“®”\—ح‚âگSگg‹@”\‚ھ–‚½‚¹‚ب‚¢ڈêچ‡‚ب‚ا‚حپAگ¶ٹˆ‹@”\‚جˆê”ت“I‚بƒ~ƒXƒ}ƒbƒ`‚ئ‚µ‚ؤˆت’u•t‚¯پAڈلٹQ‚ئ‚حŒ©‚ب‚³‚ê‚ب‚¢پB‚»‚ج‘¼پAŒ’چNڈَ‘ش‚ةٹضکA‚µ‚ب‚¢گE–±—vŒڈ‚ةٹضکA‚·‚éŒآگl‚ج“ءگ«‚حڈلٹQ‚âگ¶ٹˆ‹@”\‚إ‚ح‚ب‚پAپuŒآگlˆِژqپv‚ئ‚µ‚ؤˆµ‚¤پB
—ل‚¦‚خپA’P‚ةگE‹ئ‹Z”\‚ج–¢ڈn‚âگ«پA”N—îپAگlژي“™‚جچ·•ت‚ب‚ا‚ة‚و‚éگ§Œہ‚âگ§–ٌ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپuڈلٹQپv‚ة‚ح‚ ‚½‚ç‚ب‚¢‚à‚ج‚إ‚ ‚èپA‚ ‚‚ـ‚إ‚àŒ’چN–â‘è‚ةٹضکA‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھپuڈلٹQپv‚ئŒؤ‚شڈًŒڈ‚ئ‚ب‚éپB
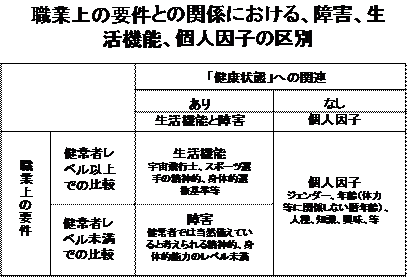 |
‚Qپ@‹@”\ڈلٹQ‚ئ‚جٹضکAپ@vs. Œ’چNڈَ‘ش‚ئ‚جٹضکA
ICF‚إ‚حپAڈلٹQ‚ئڈلٹQ‚إ‚ب‚¢‚à‚ج‚ج‹و•ت‚ًپAپuŒ’چNڈَ‘شپv‚ئ‚جٹضکAگ«‚ج—L–³‚ة‚و‚é‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚ê‚حپA•ؤچ‘‚جڈلٹQ‚ج‚ ‚éƒAƒپƒٹƒJگl–@پiADAپj‚ة‚و‚éڈلٹQ‚ج”حˆح‚ھپAپuˆمٹw“Iگf’fپv‚ئگE‹ئ“I‚ب‰غ‘è‚ئ‚جٹضکAگ«‚ة‚و‚é‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ئ“¯‚¶‚إ‚ ‚éپB‚±‚ê‚ة‚و‚èپAڈيژ¯“I‚ة‚¢‚ء‚ؤپAڈلٹQ‚ئ‚ح”F‚ك‚ç‚ê‚ب‚¢گE‹ئ“Iچ¢“ï‚ً—L‚·‚éگl‚ة‚آ‚¢‚ؤپAپuڈلٹQپv”F’è‚·‚邱‚ئ‚ً”ً‚¯‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éپB
‚µ‚©‚µپAˆê•û‚إپA‚±‚ê‚ًپuŒ’چNڈَ‘شپv‚ئ‚جٹضŒW‚ج”حˆح‚ئ‚·‚é‚ظ‚¤‚ھ‚و‚¢‚©پA‚»‚ê‚ئ‚àپAپu‹@”\ڈلٹQپv‚ئ‚جٹضŒW‚ج”حˆح‚ة‚·‚é‚©‚ح‹cک_‚ھ‚ ‚é‚ئ‚±‚ë‚إ‚ ‚낤پB‚ي‚ھچ‘‚إ‚حپAپuگg‘ج–”‚حگ¸گ_‚ةڈلٹQ‚ھ‚ ‚邽‚كپEپEپEپv‚ئپu‹@”\ڈلٹQپv‚ئ‚جٹضکA‚ً‹پ‚ك‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µپAŒ»ژہ‚ة‚حپAپu‹@”\ڈلٹQپv‚ح‚ب‚¢‚ھپAپuŒ’چNڈَ‘شپv‚ةٹضکA‚µ‚ؤپAگE‹ئڈم‚ج–â‘è‚إ‚ ‚éپuٹˆ“®گ§Œہپv‚âپuژQ‰ءگ§–ٌپv‚ھ‹N‚±‚肤‚é—ل‚ھچ،Œم‚à‘‰ء‚·‚邱‚ئ‚ھŒ©چ‚ـ‚ê‚邽‚كپA‚â‚ح‚èپAپuŒ’چNڈَ‘شپv‚ئ‚جٹضکA‚ج”حˆح‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ھ•K—v‚إ‚ ‚낤پB
پi‚Pپj‹@”\ڈلٹQ‚ً”؛‚ي‚ب‚¢ڈلٹQ‚ج‘¶چف
‹ك”NپAڈلٹQ‚ً–â‘è‚ة‚·‚é•K—v‚ھگ¶‚¶‚ؤ‚¢‚éژ¾ٹ³‚ة‚حپAHIVٹ´گُڈاپAگ¸گ_ڈلٹQپA“ï•a‚ب‚ا‚ھ‚ ‚°‚ç‚ê‚éپB‚±‚ج‚و‚¤‚بپuژ¾ٹ³پv‚إ‚à‚ ‚éپuڈلٹQپv‚حپAڈ]—ˆپAژ¾ٹ³‚ھژ،–ü‚µ‚½Œم‚جŒمˆâڈاٹا—‚ئ‚µ‚ؤ‚جƒٹƒnƒrƒٹƒeپ[ƒVƒ‡ƒ“‚ً’†گS‚ئ‚·‚é‚ي‚ھچ‘‚جڈلٹQژز‘خچô‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپA—لٹO“I‚ب‚à‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پB‚µ‚©‚µپAچ،Œم‚حپA‚±‚ج‚و‚¤‚بژ¾ٹ³‚ة‚و‚éگE‹ئ“I–â‘è‚ًپAپuگE‹ئ“Iژ‹“_‚©‚ç‚ف‚½ڈلٹQپv‚ج‘خڈغ‚ئ‚µ‚ؤ–¾ٹm‚ةˆت’u‚أ‚¯‚é•K—v‚ھ‚ ‚èپA‚»‚ê‚ة”؛‚ء‚ؤپA‹@”\ڈلٹQ‚ً‘O’ٌ‚ئ‚µ‚ب‚¢ڈلٹQ‚ج‘¨‚¦•û‚ھ•s‰آŒ‡‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
—ل‚¦‚خپAHIVٹ´گُڈا‚حپA‘پٹْ”Œ©‚µ‚ؤژ،—أ‚ًٹJژn‚·‚ê‚خپA–ئ‰u‹@”\‚جڈلٹQ‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ب‚¢ƒŒƒxƒ‹‚ةƒRƒ“ƒgƒچپ[ƒ‹‚ھ‰آ”\‚إ‚ ‚èپA‘پٹْ”Œ©‘پٹْژ،—أ‚ةگ¬Œ÷‚µ‚½ڈêچ‡پAŒ»چs‚جڈلٹQ”F’èٹîڈ€‚ةٹY“–‚µ‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µپA‹@”\ڈلٹQ‚ح‚ب‚‚ؤ‚àپA–ˆ“ْژdژ–’†‚ة‚à•–ٍ‚ًŒ‡‚©‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½‚èپAƒXƒgƒŒƒX‚â‰كکJ‚ً”ً‚¯‚é•K—v‚ھ‚ ‚ء‚½‚è‚ب‚ا‚جپuٹˆ“®گ§Œہپv‚ھ‚ ‚èپA‚ـ‚½پA•a–¼‚ً—ڑ—ًڈ‘‚ةڈ‘‚‚ئچج—p‚ھ’f‚ç‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤چ·•ت‚ة‚و‚éپuژQ‰ءگ§–ٌپv‚ئ‚¢‚ء‚½–â‘è‚ح‹N‚±‚肤‚éپiڈt–¼, 1999پjپB‚±‚ê‚حپAگ¸گ_ڈلٹQ‚إ‚à“¯—l‚بڈَ‹µ‚ح‹N‚±‚肤‚邵پA“œ”A•a‚ب‚ا‚ج–گ«ژ¾ٹ³‚إ‚à‚ ‚肤‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پi‚QپjڈلٹQ‚جŒ´ˆِ‚ج‘S”ت“I•د‰»
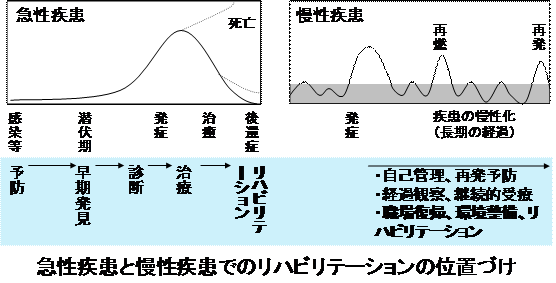 |
‚ي‚ھچ‘‚ًٹـ‚ك‚ؤگوگiچ‘‚إ‚حپAڈلٹQ‚ھ”گ¶‚·‚錴ˆِ‚جچھ–{“I‚بچ\‘¢‚ھ‘ه‚«‚•د‰»‚µ‚ؤ–گ«“I‚بŒo‰ك‚ً‚ئ‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¨‚èپA‚±‚ج‚و‚¤‚ب–گ«“I‚بŒo‰ك‚ً‚ئ‚éژ¾ٹ³‚ة‘خ‚µ‚ؤ‚حˆم—أ‚¾‚¯‚إ‚ح‚ب‚پAگE‹ئگ¶ٹˆ‚ًٹـ‚ك‚½ژذ‰ï‘S‘ج‚ة‚و‚éژو‚è‘g‚ف‚ھ•s‰آŒ‡‚ئ‚ب‚éپB‹}گ«ژ¾ٹ³‚جڈêچ‡پA•a‹C‚حٹ´گُ“™‚©‚çگِ•ڑٹْ‚ًŒo‚ؤ”ڈا‚µپAژ،—أ‚ة‚و‚ء‚ؤپAژ،–ü‚·‚é‚©پAژ€–S‚·‚é‚©پAŒمˆâڈا‚ًژc‚·‚©پA‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھˆê”ت“I‚بŒo‰ك‚إ‚ ‚èپAƒٹƒnƒrƒٹƒeپ[ƒVƒ‡ƒ“‚ج‘خڈغ‚حپAŒمˆâڈا‚إ‚ ‚é‹@”\ڈلٹQ‚ً‚ف‚ê‚خ‚و‚©‚ء‚½پB‚µ‚©‚µپA–گ«ژ¾ٹ³‚حپA‚±‚ê‚ئ‚ح‘S‚ژ¾ٹ³‚جŒo‰ك‚ھˆظ‚ب‚éپBHIVٹ´گُڈا‚âگ¸گ_ڈلٹQ‚إ‚حپA–ٍ•¨—أ–@‚ب‚ا‚ھŒp‘±‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپA‚±‚ê‚ة‚و‚èپAڈاڈَ‚ھƒRƒ“ƒgƒچپ[ƒ‹‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éڈَ‘ش‚ب‚ج‚إ‚ ‚ء‚ؤپAژ،–ü‚µ‚½‚ي‚¯‚إ‚àپAŒمˆâڈا‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚邾‚¯‚جڈَ‘ش‚إ‚à‚ب‚¢پB“Kگط‚بژ،—أ‚ھ’†’f‚³‚ê‚ê‚خڈاڈَ‚ھˆ«‰»‚·‚éپA‚ـ‚³‚ةژ،—أ’†‚جڈَ‘ش‚ھگ¶ٹU‚ة‚ي‚½‚è’·ٹْ‚ة‘±‚‚ج‚إ‚ ‚éپB
“ï•a‚ج‚ ‚éگl‚ھŒِ‹¤گE‹ئˆہ’èڈٹ‚ةچs‚‚ئپAپu•a‹C‚ھژ،‚ء‚ؤ‚©‚ç—ˆ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پBپv‚ئ‚¢‚ي‚ꂽ‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚à‚ ‚ء‚½‚炵‚¢پiڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[, 1998bپjپB‚µ‚©‚µپA“ï•a‚حˆê”ت‚ةٹ®ژ،‚·‚邱‚ئ“‚پAگ¶ٹU‚ة‚ي‚½‚è’·ٹْ‚ةژ،—أ‚ً‘±‚¯‚é•K—v‚ھ‚ ‚é•a‹C‚إ‚ ‚éپB‚»‚جˆê•û‚إپAژ،—أ‚³‚¦‘±‚¯‚ؤ‚¢‚ê‚خ–â‘è‚ب‚ژdژ–‚ھ‚إ‚«‚éڈêچ‡‚à‘‚¦‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚àژ–ژہ‚إ‚ ‚éپB–گ«ژ¾ٹ³‚ج“ء’¥‚ً“¥‚ـ‚¦‚é‚ئپAگE‹ئ“Iژ‹“_‚©‚ç‚ف‚½ڈلٹQ‚ج”حˆح‚ئ‚µ‚ؤ‚حپAژ،—أ’†‚إ‚ ‚é‚©‚ا‚¤‚©‚ة‚©‚©‚ي‚炸پAگE‹ئگ¶ٹˆڈم‚ج‰غ‘è‚ً”cˆ¬‚µ‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ھڈd—v‚إ‚ ‚낤پB
پi‚RپjڈلٹQ‚جژ‘±‚·‚éٹْٹش
‚ي‚ھچ‘‚إ‚حپAپuڈلٹQپv‚ئ‚ح•s‰آ‹t‚إگ¶ٹU‚ة‚ي‚½‚èŒp‘±‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚·‚éچl‚¦‚ھ‹‚¢پBڈلٹQ”N‹àژَ‹‹ژ‘ٹi‚جٹîڈ€‚ب‚ا‚إ‚حپA‚±‚ج‚و‚¤‚بڈًŒڈ‚حڈd—v‚إ‚ ‚낤پBڈ”ٹOچ‘‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚àپAˆê’èٹْٹش‚حŒp‘±‚·‚é‚à‚ج‚¾‚¯‚ًپuڈلٹQپv‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é—ل‚ح‘½‚¢پB‚µ‚©‚µپA‚±‚ج‚و‚¤‚بŒہ’èژ–چ€‚àپAژx‰‡“à—e‚âژx‰‡’ٌ‹ں‚ج‰آ”\گ«‚ةˆث‘¶‚·‚é‘ٹ‘خ“I‚ب‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB
—ل‚¦‚خپAچإ‹ك•ؤچ‘‚إ‚حپA‹}گ«“I‚إˆêژ“I‚بگE‹ئڈم‚ج•sژ©—R‚إ‚ ‚ء‚ؤ‚àپA•K—v‚بٹْٹش‚حژx‰‡‚ًچs‚¤‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚جڈî•ٌ‚ً“¾‚ؤ‚¢‚éپi‘و‚Uڈح‚إچؤ“xگG‚ê‚éپBپjپB—ل‚¦‚خپAŒغ–Œ‚ً‘¹ڈ‚µ‚ؤ’®—ح‚ًژ¸‚ء‚½ڈêچ‡پAŒغ–Œ‚ھچؤگ¶‚·‚é‚ـ‚إ‚جٹش‚ح•â’®ٹي‚ً‚آ‚¯‚ç‚ê‚ب‚¢‚½‚كپA‚»‚جٹش‚حگE‹ئڈم‚ج‘ه‚«‚بگ§Œہ‚ھگ¶‚¶‚éپB‚±‚ج‚و‚¤‚بˆêژ“I‚بƒjپ[ƒY‚ة‘خ‚µ‚ؤ‚àپAƒ^ƒCƒ€ƒٹپ[‚ةژx‰‡’ٌ‹ں‚إ‚«‚éگv‘¬‚بƒTپ[ƒrƒX‚ھ‰آ”\‚إ‚ ‚ê‚خپA‚±‚ج‚و‚¤‚بژx‰‡‚ً•s•K—v‚ئچl‚¦‚éچھ‹’‚ح‚ب‚¢پB
Œ‹‹اپAپuگE‹ئ“Iژ‹“_‚©‚ç‚ف‚½ڈلٹQپv‚ج”حˆح‚حپAˆمٹw“I‚بگf’f‚ھ‚ ‚ê‚خپA‚±‚ئ‚³‚ç‚ة‹}گ«ژ¾ٹ³‚جŒمˆâڈا‚ئ–گ«ژ¾ٹ³‚ةŒہ‚é•K—v‚à‚ب‚پA‚ـ‚½پAژ،—أ’†‚إ‚ ‚é‚©‚ا‚¤‚©‚ة‚©‚©‚ي‚炸پAگE‹ئگ¶ٹˆڈم‚ج‰غ‘è‚ً”cˆ¬‚·‚ê‚خ‚و‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB
‚ـ‚ئ‚ك
–{ڈح‚إ‚حپAڈ]—ˆ‚جپuڈلٹQپv‚جچl‚¦•û‚ة‚ئ‚ç‚ي‚ꂸپAICF‚جٹT”Oکg‘g‚ف‚ة‚»‚ء‚ؤپAگE‹ئڈم‚جژہچغ‚ج–â‘è‚ً–ش—…‚إ‚«‚é‚و‚¤‚بگ®—‚ًچs‚ء‚½پB‚½‚¾‚µپA‚±‚ꂾ‚¯‚جگ®—‚إ‚حپA‹ï‘ج“I‚بژx‰‡‚ة‚آ‚ب‚ھ‚é•ïٹ‡“I‚بƒ‚ƒfƒ‹‚ة‚ح‚آ‚ب‚ھ‚ç‚ب‚¢پB‚»‚ê‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‘±‚‘و‚Qڈح‚ئ‘و‚Rڈح‚ج‰غ‘è‚إ‚ ‚éپB
‚ب‚¨پAŒ»چs‚جپuڈلٹQپv‚جچl‚¦•û‚ئ‚جٹضکA‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‘S‚ؤ‚ج–â‘è‚ًگ®—‚µ‚½Œم‚ةچs‚¤‚±‚ئ‚ئ‚µ‚½‚¢پB
•¶Œ£
ڈt–¼—RˆêکYپFHIV‚ة‚و‚é–ئ‰u‹@”\ڈلٹQ‚جگ³‚µ‚¢—‰ً‚ئŒظ—pژx‰‡‚ج‰غ‘è‚ة‚آ‚¢‚ؤپAگEƒٹƒnƒlƒbƒgƒڈپ[ƒN 44, 30-34, 1999.
ڈt–¼—RˆêکYپwڈلٹQژز‚جگE‹ئ“Iچ¢“ïگ«‚جƒVƒ~ƒ…ƒŒپ[ƒVƒ‡ƒ“ژژˆؤپxپAگEƒٹƒnƒlƒbƒgƒڈپ[ƒN 35, 32-35, 1997.
ڈ¼ˆ×گM—YپFڈلٹQژز‚جŒظ—p‘£گi‚ئ•ںژƒ‚جکAŒgپ|ƒٹƒnƒrƒٹƒeپ[ƒVƒ‡ƒ“‚ًژ‹“_‚ئ‚µ‚ؤپ|, ‹Gٹ§ژذ‰ï•غڈلŒ¤‹† 37(3), 218-227, 2001.
“ى‰_’¼“ٌپFڈلٹQژَ—e‚ئکAŒgپAƒٹƒnƒrƒٹƒeپ[ƒVƒ‡ƒ“کAŒg‰بٹw 5(1), 182-187, 2004.
ƒIƒ‰ƒ“ƒ_’†‰›ژذ‰ï•غڈل‹¦‰ï: گE–±ڈî•ٌٹا—ƒVƒXƒeƒ€پFFISپAƒIƒ‰ƒ“ƒ_’†‰›ژذ‰ï•غڈل‹¦‰ïپAƒAƒ€ƒXƒeƒ‹ƒ_ƒ€پA1997.
ڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[پFپuٹwڈKڈلٹQپv‚ًژه‘i‚ئ‚·‚éژز‚جڈAکJژx‰‡‚ج‰غ‘è‚ةٹض‚·‚錤‹†پi‚»‚ج‚QپjپCڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[’²چ¸Œ¤‹†•ٌچگڈ‘No.56پC2004.
ڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[پF’m“IڈلٹQژز‚جٹwچZ‚©‚çگE‹ئ‚ض‚جˆعچs‰غ‘è‚ةٹض‚·‚錤‹†پAڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[’²چ¸Œ¤‹†•ٌچگڈ‘No.42پC2001a.
ڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[پFڈ”ٹOچ‘‚ة‚¨‚¯‚éڈلٹQژزŒظ—p‘خچôپAڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[ژ‘—؟ƒVƒٹپ[ƒYNo.24پC2001b.
ڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[پFڈ”ٹOچ‘‚ة‚¨‚¯‚éگE‹ئڈم‚جڈلٹQ‚ةٹض‚·‚éڈî•ٌپCڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[ژ‘—؟ƒVƒٹپ[ƒYNo.20پC1999.
ڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[پGڈلٹQپEگE‹ئ•تپuڈA‹ئڈم‚ج”z—¶ژ–چ€پvپ|ٹé‹ئ‚جŒoŒ±12,000ژ–—ل‚©‚çپ|پCژ‘—؟ƒVƒٹپ[ƒYNo.19پC1998a.
ڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[پw“ï•a“™–گ«ژ¾ٹ³ژز‚جڈAکJژہ‘ش‚ئڈAکJژx‰‡ڈم‚ج‰غ‘è پxپDڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[’²چ¸Œ¤‹†•ٌچگڈ‘No. 30پA1998bپD
ڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[پw’nˆوڈلٹQژزگE‹ئƒZƒ“ƒ^پ[‚ج‹ئ–±“Œvڈمپg‚»‚ج‘¼پh‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éڈلٹQژز‚جڈA‹ئڈم‚ج–â‘è پxپDڈلٹQژزگE‹ئ‘چچ‡ƒZƒ“ƒ^پ[’²چ¸Œ¤‹†•ٌچگڈ‘No. 21پA1997.
U.S. Department of Labor. Revised Handbook of Analyzing Jobs, 1991.
Ueda S & Y Okawa. The subjective dimension of functioning and disability: what is it and what is it for? Disability and Rehabilitation25(11-12), 596-601, 2003.
ڈم“c•qپA‘هگى–يگ¶پFƒٹƒnƒrƒٹƒeپ[ƒVƒ‡ƒ“ˆمٹw‚ة‚¨‚¯‚éڈلٹQک_‚ج—صڈ°“Iˆس‹`پAڈلٹQژز–â‘茤‹† 26(1), 4-15, 1998.
WHO: International classification of functioning, disability and health: ICF., 2001.پi“ْ–{Œê”إپFICFپ@چ‘چغگ¶ٹˆ‹@”\•ھ—قپ|چ‘چغڈلٹQ•ھ—ق‰ü’ù”إپ|پA’†‰›–@‹Kڈo”إپA2002پj
WHO. International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. Geneva, 1980.پi“ْ–{Œê–َپFŒْگ¶ڈب‘هگbٹ¯–[“Œvڈî•ٌ•”پGWHOچ‘چغڈلٹQ•ھ—قژژˆؤپi‰¼–َپjپC1985پj
WHO: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision, Vols. 1-3. Geneva, 1992-1994.پi“ْ–{Œê”إپFŒْگ¶ڈب‘هگbٹ¯–[“Œvڈî•ٌ•”•زپAژ¾•aپAڈٹQ‚¨‚و‚رژ€ˆِ“Œv•ھ—ق’ٌ—v<ICD10ڈ€‹’>پAŒْگ¶“Œv‹¦‰ïپA1993-1996.پj